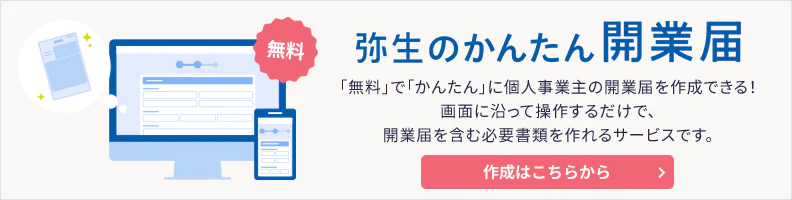制作への熱意と行動力が鍵!切り絵作家に見る、アーティストの生存戦略
執筆者: 二木 繁美
更新

アーティストが集まる京都の長屋「あじき路地」を拠点に、切り絵作家として活動する望月めぐみさん。和をモチーフにした切り絵で、京都の初夏の風物詩である「鴨川をどり」のポスター原画を手掛けたり、切り絵が盛んなスイスで展覧会を企画したりするなど、国内外で活躍されています。
そこで今回は、コネもなく手探りの状態から活動をスタートしたという望月さんに、アーティストとして、そして個人事業主として生活していくために実践したことをうかがいました。
- ※この取材はオンライン会議ツールを使用し、リモートでインタビューしたものです
望月 めぐみ(もちづき めぐみ)
1978年神奈川県生まれ。京都市在住。東京学芸大学在籍中に切り絵と出会い、2003年から切り絵作家として活動を開始。イベントでの展示や雑誌イラストレーションのほか、京都先斗町第182回「鴨川をどり」ポスター、京都・知恩院での個展など、多方面で活躍。著書に『平安絵巻の素敵な切り絵』(PHP研究所)がある。
http://www.mochime.com

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
期限は10年。アルバイトをしながら制作を続けた日々
幼い頃から絵が好きで、6歳から絵を習っていたという望月さん。美術系の大学に進学し、所属していた演劇サークルで公演用チラシのビジュアルイメージを探しているときに、はじめて切り絵に出会います。
「切り絵を見たとき、あっ、これだ!と。自分にピタッときたんです。それまでいろいろな画材で絵を描いてきましたが、あんなにピッタリくる感覚はありませんでした」

そのまま切り絵にハマり、大学在学中から作家活動を開始。最初は趣味として切り絵を続けるつもりでしたが、就職活動はせずに切り絵で身を立てる道を選びます。
「当時は就職活動が本当に大変で。同じ苦労をするなら、自分が一番好きなことにチャレンジしようと思ったんです。でも、ズルズル続けても仕方ないので、10年で芽が出なければあきらめようと考えていました。10年というと長く思えますが、逆に短い、あと10年しかないと思っていました」
切り絵作品のポートフォリオを作成して出版社に直接売り込みをかけた結果、すぐに集英社『non-no』の占い特集ページでイラストを描くことになり、商業作家としてのデビューを果たします。

「実際の仕事につながったことで、可能性はゼロではないと確信できました。ただ、作品づくりを優先したかったので、その後は売り込みはせず、先方のオーダーありきで販売するスタイルをとっていたんです。ギャラリーやデパートの企画展で原画販売もしていましたが、それだけで食べていくことはできなくて、絵画教室でアルバイトもしていました」
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
人とのつながりを自ら広げ、チャンスをつかむ
切り絵だけで身を立てたいと思っていた望月さんにとって、売り込みを優先して制作時間が削られるのは不本意なこと。切り絵に集中するため、作品づくり以外のことで負担がかからないようにしていたといいます。
売り込みをせず、アルバイトとの併行で収入のバランスをとっていたのもそのひとつ。そんななか、趣味と学びを兼ねたギャラリー巡りが作品の売上につながっていきます。

Photo:Studio MacCa
「ギャラリーで絵を眺めているとき、そこのオーナーに『何か作っているの?』と声をかけていただいたんです。切り絵の作品を見せたら、うちで販売しないかという話になって。ギャラリー在廊中に仲良くなったお客さんから、別のギャラリーを紹介していただくこともありました」
仕事につながる出会いは、いつ訪れるかわからないもの。自分の作品をいつでも見せられるように準備しておくことは、作家にとって重要な営業戦略のひとつです。そして、積極的にいろいろな場所に出向き、人とのつながりを自分自身の力で広げていくのも大切なこと。
「いろいろな所に顔を出していると、お誘いを受ける機会も多くなります。さすがに全部は出られませんが、ひとりでも会いたい人がいる場所にはできるだけ行くようにしています」
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
アーティスト活動をさらに後押しした京都への移住
転機が訪れたのは、30代の頃。都会での生活から一変、のどかな田園風景が広がる京都の大原へ移住することになりました。
「京都大原里づくり協会の理事長さんの家が空き家になるので、作家活動をしながら管理する人を募集していると知人に教えてもらって。行きたい!と思って、すぐに応募しました」
望月さんの和をモチーフにした切り絵作品は、京都の風情にまさにぴったり。実際に、京都に移住してから、仕事の規模が格段に大きくなったといいます。これだ!と思ったら躊躇せず挑戦する行動力も、望月さんが持つ強みのひとつです。
「大原では、周りの方とのお付き合いを大切にしながら3年暮らして、徐々にフィールドを広げていきました。期間満了で引っ越すことになったときも、あじき路地で入居者を募集していることを知人が教えてくれたんです」

京都の東山にあるあじき路地は、若手作家の住居兼工房が集まる場所。入居時には審査が必要で、雑誌やウェブで紹介されて認知度が高く、住むことが作家としての名刺代わりにもなります。基本的に同じジャンルの作家は住めないルールがあるため、自分とは異なる作品を生み出す仲間との交流を通して刺激を受けたり、作品づくりのヒントをもらったりもしているのだそう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
作品のみの販売から、プロジェクト全体を請け負う働き方にシフト
京都への移住後もいろいろな場所に足を運んで研鑽を重ね、そこで得た情報をもとに、現在のポジションにもつながる大きな一歩を踏み出します。
「京都には大学が多く、社会人向けの講座も充実しています。私も美大の社会人講座に参加して、そこでアート系プロジェクトの公募チラシを入手して応募するようになって。作品を作って売る形式ではなく、作品の制作を含めたプロジェクト全体に関わる事業に興味を持って、この頃から動き方を大きく変えていきました。
最初に採用されたのは、イギリスの『アーティスト・イン・レジデンス(Artist-in-residence)』で、36歳のときでした。アーティスト・イン・レジデンスは、一定期間アーティストを招聘してそこでの制作活動を支援する事業のことで、その採用をきっかけに国内外のさまざまなプロジェクトに参加しはじめました。

プロジェクトによって異なりますが、企画書を作って応募して、採用されると予算がつく形式が多いですね。制作費はそれで確保できるので、制作した作品が売れれば収入になります」
作った原画を販売しているときは、売れなければもちろん赤字。一方で、プロジェクトでは基本的に制作費を確保できるため、予算内におさまれば作品の売上はそのまま作家の収入になります。加えて、プロジェクトには多くの人が関わるので、出会いの機会が増え、その地域とのつながりも生まれます。実際に、そうしたつながりから次の仕事を得ることもあるようです。

「2016年に、奈良県の明日香村で開催された『飛鳥アートヴィレッジ』の展覧会に参加したときもそうでしたね。現地で作品を見た方からのご依頼で、翌年の文化イベント『飛鳥光の回廊』で『飛鳥大仏切り絵コラボレーション』という大きなプロジェクトに携わることができました。
こうしたプロジェクトへの参加は、自分の作品というパーソナルなものに社会的な役割を見出す貴重な機会ともなります。応募するだけでも、新たな発見や学びがあると思いますよ」
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
自分だけのスイッチを持つことで、制作時の集中力を高める
写真撮影でアトリエを訪れたときはNirvana、インタビュー時はThe WhoのTシャツを着ていた望月さん。和風の作品を多く手掛けていますが、意外にも仕事中に聞く音楽はロック・ミュージックとのこと。
「ロックにハマったのは20代の後半頃から。ザ・クロマニヨンズが好きで、ライブにもよく行きます。ロックは作業中のBGMというか、私にとっては労働歌ですね。切り絵の制作時は、120分を1コマ、1日に4コマ行うのが作業ルーティンで、CDアルバムは1枚でだいたい40分。3枚聞いたら120分で1コマ分になります」
なんとなく作業するのではなく、1日の作業時間を4コマに区切って進めることで、集中力が増すのだといいます。

「基本はThe BeatlesやThe Whoなどのブリティッシュ・ロックで、なにか怒っているときにはNirvana。ロックに込められたパッションに刺激を受けて、作業がはかどるんです。ロックを聞くとスイッチが入って、自然に仕事モードになりますね。自分だけのスイッチがあると集中しやすくなるので、作家を目指す方にはオススメです」
このロック好きが、実際の仕事につながったというエピソードも出ました。
「Twitterで好きなバンドの事務所アカウントをフォローしていたら、事務所の社長からダイレクトメッセージが届いたんです。当時は切り絵作品をアイコンにしていたので、それを見て興味を持ってもらえたみたいで。そこから、バンドのCDジャケットの仕事につながりました。彼はいま、私の切り絵のマネージャーもしてくれているんですよ」
自分の得意なことや好きなことを積極的に発信していく。いまはそれができるプラットフォームがたくさんあります。アーティストとして生き残っていくうえで、これらを利用しない手はありません。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
ネガティブな気持ちも原動力に。失敗を恐れず行動することが大切

順風満帆にも思える作家生活ですが、コンペに落ち続けて全然うまくいかない時期もあったといいます。それでも続けられたのはなぜなのでしょうか。
「落ち込んだり怒りを感じたりしたときは、その気持ちを次の作品制作の原動力にしています。私はもともと強い人間ではありませんが、ネガティブな感情に固執しないようにして、自ら強くあることを選んでいるんです。強く『なる』のは無理でも、強く『ある』ことを選ぶのは、望めばきっと誰でもできることだと思います。
何かにチャレンジするときも、私は失敗を恐れません。興味を持ったらすぐ調べてみる。とりあえずアクションを起こすことが大事なんです。そして、決めたからには全力で取り組む。例えうまくいかなくても、全力を尽くせば悔いは残りません。失敗しても別の出会いや発見があったりして、ちゃんと次につながっていきますから」
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
この記事の執筆者二木 繁美
愛媛県出身のパンダ好きフリーライター。グラフィックデザイナーを経て、ライター・イラストレーターとして独立。トラベル系の取材記事や企業オウンドメディアのコンテンツ作成、インタビュー記事の執筆を得意としている。