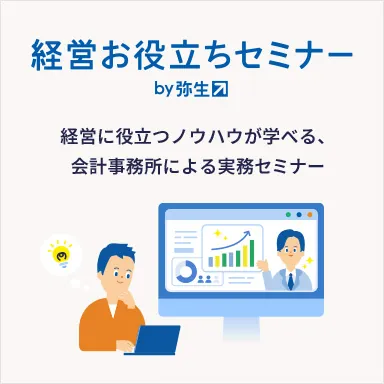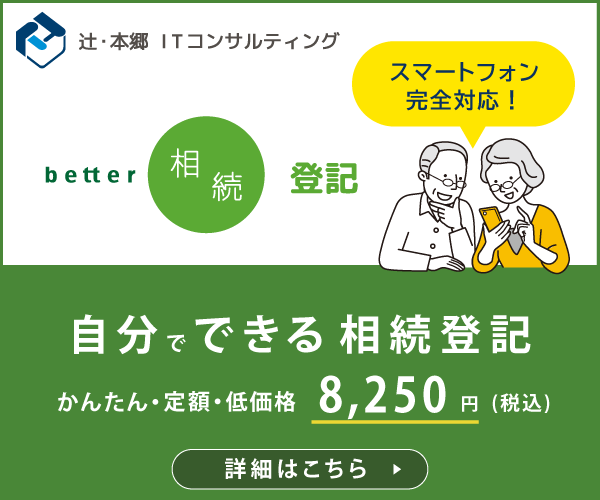不動産会社を買収する際に知っておくべき課題やM&Aにおける留意点
更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら
土地や建物を扱う不動産業界には、不動産売買、不動産仲介、不動産開発、不動産管理、不動産賃貸といった業種があります。
ここでは、買手が知っておくべき不動産業界の課題や、不動産関連の企業を買収する際の留意点について解説します。
不動産業界の概況
公益財団法人不動産流通推進センターの「2022不動産業統計集(3月期改訂) 」(2022年)によると、不動産業を営む法人は、ここ20年ほど右肩上がりで増え続けており、2020年時点で35万社を超えました。そのうち、資本金1,000万円未満の企業は不動産業界全体の約69%、資本金5,000万円未満の企業は全体の約97%で、大部分は中小企業が占めています。
不動産業界の特徴
不動産業界は、取引の対象である土地や建物の価格が高いため、大きな市場規模であることが特徴の1つです。国土交通省「不動産ビジョン2030~令和時代の『不動産最適活用』に向けて~ 」(2019年4月)によると、2017年時点での不動産業界の市場規模は売上高43.4兆円、法人・個人・公的セクターが所有する不動産ストックの総額は約2,606兆円で、国民資産の23.9%に達しています。
不動産業界のもう1つの特徴は、景気や社会情勢の影響を受けやすいことです。2010年代の不動産市場はほぼ一貫して成長を続けていましたが、財務省「年次別法人企業統計調査(令和2年度) 」(2021年9月)によると、2019年は45.3兆円、2020年は44.3兆円とここ2年ほどは縮小傾向にあります。主な要因としては、新型コロナウイルス感染症の拡大による一時期取引減少の他、東京五輪関連の開発終了やオフィスや店舗の平均賃料下落などが考えられます。
なお、コロナ禍の不動産業界への影響で顕著なのは、オフィスビルの空室率の上昇です。三鬼商事株式会社のWebサイトで公開している「オフィスマーケット 」によると、主要都市のオフィスビル空室率は以下の表のとおりです。新型コロナウイルス感染症の拡大後、平均空室率は軒並み上がっており、コロナ禍がオフィスビルの所有やテナント経営に深刻な影響をもたらしたことがうかがえます。
| 2019年12月 | 2022年6月 | |
|---|---|---|
| 東京ビジネス地区 | 1.55% | 6.39% |
| 大阪ビジネス地区 | 1.82% | 5.01% |
| 名古屋ビジネス地区 | 1.92% | 5.85% |
| 札幌ビジネス地区 | 1.91% | 2.33% |
コロナ禍の影響は少ない堅実な業界との見方もある
公益財団法人東日本不動産流通機構「季報 Market Watchサマリーレポート2022年4~6月期 」によると、首都圏の中古マンション・中古一戸建て成約件数は、初めて緊急事態宣言が出された2020年4月は買い控えなどでいったん大きく落ち込んだものの、2020年7月には回復し、ほぼコロナ禍以前の水準を維持しています。むしろ、テレワークの浸透による郊外物件への移転やその後の都心への回帰など新しいニーズが生まれたことで、時期によっては成約件数の増加につながった面もありました。
不動産業界は、生活の基盤である住居を取り扱うだけに、堅実な業界であると評価される傾向もあります。
不動産業界の課題
市場規模も大きく、生活の基盤を支える不動産を扱うという強みを持つ不動産業界ですが、課題がないわけではありません。不動産業界の主な課題として、以下の3つが挙げられます。
人口減少、少子高齢化による需要の変化
国内では、人口の減少や高齢者層の増加により、住宅余りや家族向けより単身者向け住宅が求められるなど、不動産の需要に変化が起こっています。需要の変化に対しては、リフォーム事業者との協業によるリフォーム部門の強化や在留外国人への対応強化などの対策が必要です。具体的には、ファミリー向けの物件を単身者向けにリノベーションして売り出す、在留外国人が利用しやすいように諸外国語への対応を進めるといったことが考えられます。
IT活用の遅れ
不動産業界は内見や契約など対面を前提としたやり取りが多いため、ITの活用が遅れていることも課題の1つです。法改正により2022年5月からは、紙のやり取りが必要であった書類の電子交付が可能になりましたが、まだ対応していない不動産業者も少なくありません。業務効率化の達成や顧客の利便性アップのためには、オンライン内見や契約業務の電子化への対応などが求められています。
後継者不足
株式会社帝国データバンクの「特別企画:全国社長年齢分析 」(2021年2月)によると、不動産業界の経営者の平均年齢は62.2歳と全業種の中で最も高くなっており、不動産業界では後継者不足も課題の1つに挙げられます。また、公益財団法人不動産流通推進センターの「2021不動産業統計集(9月期改訂)
」で不動産仲介を手掛ける宅地建物取引業者の推移を見てみると、法人・個人の業者を合わせた全体数としては、ここ10年で3,000件ほど増加しています。一方で、個人事業者は2011年には2万181件でしたが、2020年には1万4,738件まで減少しました。法人事業者は増える中、個人事業者は年々減少していることから、後継者不足などから廃業や売却を選ぶ個人事業者が出ていると推察されます。
不動産業界のM&Aの目的
不動産業界でM&Aを行う場合、主に2つの目的が考えられます。ここでは、不動産業界のM&Aの目的についてご紹介します。
事業領域の拡大
M&Aの目的の1つに、中規模・大規模の不動産業者がさらなる事業領域の拡大を目指して、小規模な同業他社を買収することが挙げられます。また、物件売買や土地開発を行う事業者が、仲介専門の事業者を買収することなどもあります。買収によって、市場におけるシェアの拡大やサプライチェーンの強化の他、仲介から売買まで一気通貫の体制で業務の効率化を図れることから、競争力を強化することが可能です。
人材確保
M&Aによって人材を確保できることもM&Aの目的の1つです。国土交通省の「不動産ビジョン2030 参考資料集 」(2019年)によると、2015年時点で不動産業界の従業員のうち20~29歳は6.7%にすぎず、全産業の約15%に比べて低い数字となっています。不動産業界では今後も若手の人手不足が課題となることが予想されるため、M&Aによって人材を確保することは課題解決にもつながります。
M&Aのメリットや買収を成功させるポイントについては別の記事で解説していますので、参考にしてください。
不動産業界のM&Aの留意点
不動産業界のM&Aを行う際には留意点があります。特に、不動産事業者の中でも宅地建物取引業者である不動産仲介事業者を買収する場合は、以下のような点に確認が必要です。
宅地建物取引士の人数
不動産仲介業は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた「宅地建物取引業者(宅建業者)」でなければ営むことができません。宅建業者は、宅地建物取引業法と国土交通省令によって、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置することが義務付けられています。宅建士の人数が不足してしまうと、事業を営むことができませんので注意が必要です。
個人の事業所や小規模な事業所では、経営者が宅建士である場合も多くあります。宅建士が経営者のみであれば、せっかく買収したのに宅建士不足で営業ができなくなることがあるため、事前に売手の従業員の人数を確認すると共に、宅建士の数や継続して雇用できるかを確認しておくことが大切です。
宅地建物取引業者の免許更新回数
宅地建物取引業の免許は、都道府県をまたいで営業する事業者は国土交通大臣発行の免許、1つの都道府県内で営業する事業者は都道府県知事発行のものとなり、どちらも5年ごとの更新制です。国土交通大臣発行のものは「国土交通大臣(1)第◯◯◯◯◯号」、例えば東京都だけで営業する場合は「東京都知事(1)第◯◯◯◯◯号」と表記された宅建業免許が発行され、宅建業者は発行された免許を事業所内に掲示することが義務付けられています。
免許の()の中の数字は更新回数を表しており、この数字は、M&Aにより買収しても変わりません。更新回数の数字が大きいと、業績が長く信用に値する会社だという評価を得やすい傾向がありますので、この数字は買収先の事業者を選ぶ要素の1つです。
なお、個人事業者が法人成りした際や、都道府県知事免許を国土交通大臣免許に切り替えた際などは数字が(1)に戻るため、更新回数と事業年数が合わないこともありますので確認が必要です。
不動産業界のM&A事例
不動産業界のM&Aでは、事業の拡大や人手不足の解消を目的として小規模事業者を買収することがありますが、ここでは実際に行われたM&Aの事例をご紹介します。
従業員10人程度の小規模な不動産賃貸管理・仲介会社が、M&Aによる第三者承継を選択したというケースです。創業社長が高齢となり後継者も決まらない中、病気になったのをきっかけに第三者承継を検討し始めました。
同社は小規模ながら歴史は長く、その堅実な仕事ぶりで、地域では高い知名度と顧客である管理物件オーナーからの信頼を得ている会社です。その知名度と信頼は魅力的で、人材を確保しつつその地域での事業拡大を考えていた買手の目的とマッチし買収に至りました。
このように、売手が抱えていた課題と地域での事業拡大を目指したいという買手のニーズがマッチすれば、買収しやすくなります。
M&A案件を探す方法
M&Aでは、買手のニーズとマッチした売手を探すことや、交渉力に加えて財務、税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となります。すべての手続きを自力で進めるのは困難ですので、マッチングサービスをうまく活用していきましょう。これから事業を始めたい個人の方や、事業を拡大したい方、事業の多角化を目指したい方にもぴったりです。
まずは、専門家に相談してみよう
不動産業界のM&Aでは、同業の小規模事業者を買収することで、事業や市場の拡大、人材獲得といった課題を解消することにつながります。不動産業界のM&Aを検討するなら、まずは「M&A・事業承継相談窓口 by BATONZ」で相談してみましょう。