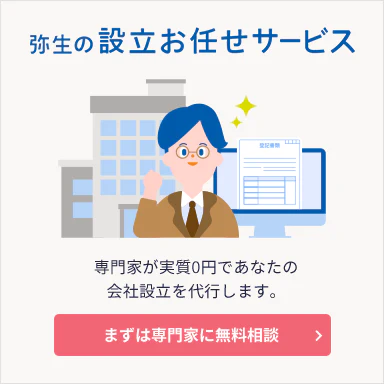シェアオフィスとは?レンタルオフィスとの違いやメリットを解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

テレワークなど働き方の多様化が進む中、シェアオフィスを利用する事業者も増加傾向にあります。
シェアオフィスは、法人でも個人事業主でも利用できます。また、登記可能なシェアオフィスも増えているため、起業にあたってシェアオフィスが選ばれるケースも少なくありません。シェアオフィスを利用する際には、特徴を理解しておきましょう。
本記事では、シェアオフィス概要やシェアオフィスを利用するメリットのほか、シェアオフィスを選ぶ際のポイントなどについて解説します。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
シェアオフィスは複数の事業者が共同で利用するオフィスのこと
シェアオフィスとは、複数の事業者が共同で利用するオフィスのことを指します。
例えば、アクセスの良い駅ビルの中にある広々とした1つのスペースを複数の事業者で共有するタイプや会議室や談話室が用意されているもの、電話応対サービスが付帯しているものといった、さまざまな形態のシェアオフィスがあります。全国に展開しているシェアオフィスもあるため、出張の際や拠点を広げたい場合などにも活用が可能です。
また、設置されている机や椅子、プリンター(複合機)などは、オフィス内に設置されているため、自分で購入する必要がありません。
なお、シェアオフィスによっては、利用者同士が交流を図れるようなイベントやセミナーなどが開催されていることもあるため、人脈づくりを検討している方は利用を検討してみてください。
シェアオフィスでできること
シェアオフィスでは一般的には固定席はなく、設置されたデスクの好きな場所を使って仕事ができます。電気や水道、インターネット回線(Wi-Fi)なども、自由に利用可能です。
また、シェアオフィスによっては、次のような機能・設備を備えていることもあります。利用にあたって有料のオプション契約が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
シェアオフィスで主にできること
- 会議室やミーティングルームの利用
- ドリンクサービス
- コピー機やプリンター、FAX、シュレッダー、ロッカーなどの利用
- 来客対応
- 電話代行や郵便物の受け取り
- 法人登記や名刺などへの住所利用
- 個室や半個室など専用スペースの利用
シェアオフィスと似ている4つのオフィスとの違い
シェアオフィスと混同されやすいものに、レンタルオフィスやコワーキングスペース、サテライトオフィス、バーチャルオフィスといった4つのオフィス形態があります。それぞれの違いを確認し、自社のニーズに合うか検討してみましょう。
レンタルオフィスとの違い
シェアオフィスとレンタルオフィスの違いは、使用できるスペースです。
シェアオフィスの中には個室契約ができるものもありますが、基本的には1つのスペースを複数の事業者が共同で使うため、個人や小規模な事業者の利用に向いています。
それに対して、レンタルオフィスは、一般的に専用の個室ブースを貸し出す形態を指します。レンタルオフィスでは専用スペースを確保できるので、固定電話を引いたり個人の備品を保管したりすることも可能なため、個人よりも中小規模の事業者にとって使いやすいといえるでしょう。
コワーキングスペースとの違い
シェアオフィスとコワーキングスペースの違いは、人との交流を重視しているかどうかです。
どちらも1つのスペースを複数の事業者が共同で利用する点は同じですが、シェアオフィスに比べてコワーキングスペースでは、利用者同士のコミュニケーションを促進するような仕組みづくりが活発に行われている傾向があるため、人脈を作りながらビジネスを成長させていきたい事業者の利用に最適です。
サテライトオフィスとの違い
シェアオフィスとサテライトオフィスの違いは、本拠地が別にあるかどうかです。
サテライトオフィスとは、satellite(衛星)という名称が示すように、本社などの本拠地から離れた場所に設置されたオフィスのこと。複数の企業で共同利用型のサテライトオフィスを設置することもありますが、必ずそれぞれに本拠地が存在します。それに対してシェアオフィスは、本拠地の有無は関係ありません。
サテライトオフィスがあることで、従業員は通勤時間を削減しつつ集中して仕事に取り組む環境を得られ、企業は本社などの本拠地を小規模なスペースに削減することができます。
バーチャルオフィスとの違い
シェアオフィスとバーチャルオフィスの違いは、オフィスの実体がないことです。
バーチャルオフィスとは、実際に入居はできませんが、事業上の住所として設定し、オフィスに必要な電話番号やFAX番号の貸し出しの他、郵便物の受け取りや転送などのサービスを提供するものです。シェアオフィスのように、物理的な作業スペースを提供することはありません。
オフィス機能は必要ないので、法人の登記するための住所が欲しいという事業者は、バーチャルオフィスの利用を検討してみてください。
- ※バーチャルオフィスついては以下の記事を併せてご覧ください
シェアオフィスを利用するメリット
シェアオフィスを利用すると、コスト削減以外にもさまざまなメリットがあります。自分が行いたい事業との相性も判断しやすいため、事前に確認しておきましょう。
シェアオフィスを利用するメリット
- 初期費用を抑えられる
- ランニングコストを抑えられる
- オフィスの拡大や縮小を容易にできる
- 好立地にオフィスを構えられる
初期費用を抑えられる
シェアオフィスのメリットは、通常のオフィスに比べて初期費用を抑えられることです。
シェアオフィスでは、一般的なテナント契約のような敷金や礼金、保証金は不要です。仕事に必要な設備もひととおり揃っているので、内装工事を行ったり、家具やOA機器を購入したりする必要もありません。基本的にはノートパソコンさえあれば、契約後すぐに業務を開始できます。
ランニングコストを抑えられる
シェアオフィスのメリットは、ランニングコストを抑えられることです。
シェアオフィスの月額利用料金は、一般的なオフィスの家賃に比べて非常に低額なうえ、光熱費や通信費などは基本料金に含まれています。会議室やミーティングルームなどの共用設備を効果的に利用すれば、大規模なオフィスを構える必要もないため、毎月の固定費を削減できるでしょう。
オフィスの拡大や縮小を容易にできる
シェアオフィスのメリットは、オフィスの拡大や縮小を容易にできることです。
例えば、一般的なオフィスの場合、従業員の数が増えてスペースが手狭になれば、広いオフィスへの移転を考えなければなりません。そのような場合も、シェアオフィスであれば、利用人数に応じた金額を支払うだけで済みます。
好立地にオフィスを構えられる
シェアオフィスのメリットは、好立地にオフィスを構えられることです。
実際に、主要駅の近くやビジネス街など、アクセスの良い場所に設けられていることがほとんどです。毎日通うのにも便利ですし、取引先との打ち合わせなども行いやすいでしょう。
知名度や利便性の高い場所でも安価な料金で利用できるため、ブランディングに有利に働くこともあります。
シェアオフィスを利用する際の注意点
メリットの多いシェアオフィスですが、注意点もあります。利用してから後悔しないよう、あらかじめ知っておきましょう。
シェアオフィス利用する際の注意点
- 他者の視線や雑音により集中できない場合がある
- 情報の漏えいや機密情報の取り扱いに注意が必要
- 小規模の施設では満席になる場合がある
- 法人登記をする場合は住所記載に配慮が必要
他人の視線や雑音により集中できない場合がある
シェアオフィスを利用する際の注意点は、他人の視線や雑音により集中できない場合があることです。
シェアオフィスの中には、複数の人が同じスペースで仕事をするため、会話や飲食禁止のエリアを設けている施設もあります。人の声や物音が聞こえると集中できないという場合には、そのようなシェアオフィスを選ぶと良いでしょう。
情報の漏えいや機密情報の取り扱いに配慮が必要
シェアオフィスを利用する際の注意点は、情報の漏えいや機密情報の取り扱いに配慮が必要なことです。
複数の事業者が利用するシェアオフィスでは、セキュリティに注意しなければなりません。特に、ドロップイン(一時利用)に対応しているシェアオフィスは、不特定多数の人が出入りすることになります。
機密情報が記載された文書などの管理はもちろん、共同スペースにパソコンを置いたまま離席しないようにする、PCの画面が他人から見えないようにするといった配慮も必要です。
小規模の施設では満席になる場合がある
シェアオフィスを利用する際の注意点は、小規模の施設では満席になる場合があることです。シェアオフィスの契約前には見学や内覧をして、混雑具合を確かめておきましょう。好きなタイミングで確実に利用したい場合には、専用スペースを契約できるシェアオフィスを選ぶのも1つの方法です。
法人登記をする場合は住所記載に配慮が必要
シェアオフィスを利用する際の注意点は、法人登記をする場合には住所の記載に配慮が必要なことです。
法人登記にあたって登録する本店所在地は、ビル名や部屋番号は省略できます。そのため、将来、フロアを移動する可能性がありそうな場合には、登記申請の際に住所記載を番地までにとどめておくと、ビル内での移転があっても変更登記を行わずに済みます。
なお、同一住所に同一の商号がある場合は、登記ができません。シェアオフィスでの法人登記を考えている場合には、利用者の中に重複している社名の企業がないかを事前に確認しておきましょう。
シェアオフィスを選ぶ際のポイント
シェアオフィスごとに、機能や条件はそれぞれ異なります。シェアオフィスを選ぶ際には、次のようなポイントを意識すると良いでしょう。
シェアオフィスを選ぶポイント
- 立地条件
- 利用料金
- 設備、機能、サービス
- セキュリティ
立地条件
シェアオフィスを選ぶポイントには、立地条件があります。立地条件は、シェアオフィスの使いやすさも左右されます。取引先への訪問や来客が多くなりそうな場合には、アクセスの良い主要駅の近くなどがおすすめです。その一方で、自分の作業だけに利用するのであれば、自宅から通いやすい場所を選ぶと良いでしょう。
また、オフィスの立地は、会社のイメージにもつながります。事業内容にもよりますが、立地条件の良い場所であれば顧客にも好印象を与え、従業員を募集する際に応募が集まりやすくなるため、立地を選ぶ際には考慮するようにしてください。
利用料金
シェアオフィスを選ぶポイントには、利用料金もあります。
シェアオフィスの多くは月額の利用料金が決められていますが、中には、スポット利用が可能な時間制の料金プランを設けているところもあります。
どのように利用するかを想定し、自分の望む使用パターンに一番適した料金体系を選びましょう。
シェアオフィスの料金体系は、主に時間による従量課金制と月額での定額課金制の2種類です。シェアオフィスを毎日使うわけではない方は、スポットで時間単位の料金プランを選ぶと無駄がありません。
また、シェアオフィスによっては、荷物の受け取りや書類のコピーなど、利用するサービスに応じてオプション料金が発生する場合もあります。シェアオフィスの利用頻度とともに利用予定のサービスも考慮して、トータルで見たときにお得になる月額での料金プランの契約を検討するようにしてください。
設備、機能、サービス
シェアオフィスを選ぶポイントには、設備や機能、サービスがあります。
利用可能時間や土・日・祝日の利用の可否、会議室や複合機の利用の可否といった、サービスの種類や利用条件の確認が必要です。
シェアオフィスによっては、Web会議ができる専用ブースを設けていたり、全国の系列オフィスを無料または割引料金で利用できたりすることもあります。
例えば、会議を行うことが多ければ専用ブースがあるところ、全国展開を考えているなら全国の系列オフィスを利用できるといった、自社が必要とする機能が揃ったシェアオフィスを選びましょう。
規模の大きさ
シェアオフィスを選ぶポイントには、規模の大きさもあります。
規模が大きく共有スペースに余裕のあるシェアオフィスなら、満席で利用できないという心配が少なくなるはずです。それに対して、小規模なオフィスは、利用できる設備が限られますが、その分、料金が安く設定されていることがあります。利用料金とのバランスも考えながら、自分のニーズに合った規模のシェアオフィスを選びましょう。同時に、会議室などの数や広さについても確認が必要です。
セキュリティ対策
シェアオフィスを選ぶポイントには、セキュリティ対策もあります。
シェアオフィスを利用するうえで、施設のセキュリティ対策は重視すべきポイントの1つです。入退室がどのように管理されているか、インターネットのセキュリティ対策はどうなっているかといった点について、必ず確認しておきましょう。
シェアオフォスでは、文書を印刷するときにパスワードを設定できたり、PCのモニター画面が他人から見えづらいようなデスク配置にしたりといった、セキュリティリスクを低減させる仕組みを採用しているところもあります。特にセキュリティに注意したい事業では、そういった仕組みを採用しているシェアオフォスを選ぶのも1つの方法です。
- ※個人事業主の開業については以下の記事を併せてご確認ください
ビジネスに必要な環境を手軽に揃える方法
起業直後は、オフィスの準備以外にも、やらなければいけないことがたくさんあります。事業準備にかかる手間を減らしたいときにおすすめなのが、会社設立直後に必要なツールや環境が揃えられる起業支援パッケージ「起業・開業応援パック」です。
「起業・開業応援パック」は、会社設立直後に必要になるモノやサービスが特典付きでご利用いただけるサービス。シェアオフィスやバーチャルオフィスを優待価格で利用できる他、会計ソフトや固定電話などのバックオフィスツール、法人口座の開設、パソコンをはじめとするIT機器、Webサイト・事業計画書の作成など、起業時に発生する事務手続きや設備環境の準備などを効率化し、すぐに本業に集中できる環境づくりを後押しします。
シェアオフィスのメリットを知って、上手に活用しよう
シェアオフィスは、複数の企業や個人事業主が共同で利用するオフィスです。初期費用や固定費を抑えられ、立地条件の良い場所でも手軽に利用できるため、シェアオフィスのニーズは高まってきています。
その一方で、シェアオフィスを利用する際には、設備や機能、料金、セキュリティなど、いくつか確認すべきポイントがあります。特に、シェアオフィスで起業を考えている場合は、登記が可能か、同じシェアオフィス内に重複している社名の会社がないかといったことを、必ず確認しておいてください。
まずはシェアオフィスで起業し、事業拡大のタイミングで自社オフィスを構えるという方法もあります。シェアオフィスの特徴を把握したうえで、ビジネスに賢く活用して行きましょう。
また、会社の設立における手続きをかんたんに済ませたい場合には、「起業・開業応援パック」の利用もご検討ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。