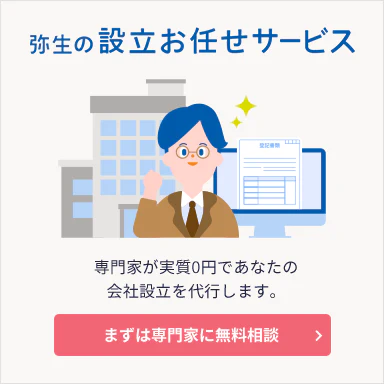バーチャルオフィスで起業・登記はできる?メリット・デメリットを解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

バーチャルオフィスは、作業スペースや事務所を借りるのではなく、住所や電話・FAX番号をレンタルするサービスです。オフィスを賃貸で借りるのに比べてコストがかからないため、起業にあたりバーチャルオフィスも選択肢となり得ます。
本記事では、バーチャルオフィスの利用例や、バーチャルオフィスで起業するメリット・デメリットの他、バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントなどについて解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
バーチャルオフィスで起業の際に登記ができる
起業する際には、バーチャルオフィスでも法人登記が可能です。
会社を設立するには必ず本店所在地の登記が必要ですが、商業登記法では本店所在地の住所に関する制限はないからです。
そのため、バーチャルオフィスのように業務実態のない場所を本店所在地として登記しても法的に問題はなく、実態としてのオフィスを必要としていない方には登記するうえでの選択肢となるでしょう。
バーチャルオフィスを利用するかどうかは利用例をもとに検討してみる
バーチャルオフィスでの起業を考えているなら、自分の起業ニーズと合っているのか、バーチャルオフィスの利用例を確認しておきましょう。バーチャルオフィスを活用できるのは、実際の業務を行う必要はないけれど、業務上の住所や電話番号だけを利用したいという場合です。
バーチャルオフィスの利用例
- 法人登記
- 名刺・パンフレット・Webサイトへの住所の記載
- オンラインでの商品販売
- 許認可や事業の届出
法人登記
バーチャルオフィスの利用例には、法人登記が挙げられます。
実際には自宅で仕事をするが自宅住所を登記したくないという場合や、決まった場所で仕事をしないという場合、バーチャルオフィスを利用すれば、コストをかけず登記に必要な住所を借りることができます。
- ※法人の登記については以下の記事を併せてご確認ください
名刺・パンフレット・Webサイトへの住所の記載
バーチャルオフィスの利用例には、名刺・パンフレット・Webサイトへの住所の記載が挙げられます。
事業上の連絡先として、名刺やパンフレット、Webサイトに、バーチャルオフィスの住所や電話番号を記載することができます。ビジネス街や主要駅の近く、知名度の高い場所などの住所を利用できれば、ブランディングにも役立つでしょう。
オンラインでの商品販売
バーチャルオフィスの利用例には、オンラインでの商品販売が挙げられます。
バーチャルオフィスは、ネットショップを運営する事業者にも多く選ばれています。オンラインでの商品販売においては、特定商取引法により、販売者の氏名や住所、電話番号を記載することが義務付けられているため、自宅の住所や電話番号を公開したくない場合は、バーチャルオフィスの利用が便利といえるでしょう。
許認可や事業の届出
バーチャルオフィスの利用例には、許認可や事業の届出が挙げられます。
法人登記だけでなく、許認可申請においてもバーチャルオフィスの利用が認められる場合があります。ただし、バーチャルオフィスの住所では許認可が受けられない業種もあるため、事前に条件を確認するようにしてください。
- ※許認可の手続きについては以下の記事を併せてご覧ください
バーチャルオフィスで登記できない場合もある
バーチャルオフィスでの起業は原則として可能ではあるものの、場合によっては登記ができないことがあります。設立準備を進んでしまってから慌てることのないように、どのようなケースで法人登記ができないのかを知っておきましょう。
同一住所・同一名称が法人登記されているため
同一住所に同一商号(社名)の会社がある場合は、法人登記ができません。また、まったく同じ商号でなくても、同一住所に類似した商号の法人登記は認められないことがあります。
バーチャルオフィスは複数の会社が同じ住所を利用できるため、同一または類似した社名の企業が契約していないか、事前に確認しておくことが必要です。
既に登記されている会社名を調べる際には、登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」や法務局の専用端末の他、独立行政法人工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat
」を確認してみましょう。
バーチャルオフィスでは法人登記ができない業種であるため
事業所の確保が許認可の要件になっているなど、バーチャルオフィスでは事業を行えない業種があります。
バーチャルオフィスでは法人登記ができない業種の例としては、主に以下のようなものが挙げられます。
バーチャルオフィスでは法人登記ができない主な業種
- 古物商許可が必要な業種(リサイクルショップ、古本屋、古着屋など)
- 士業(税理士・弁護士・司法書士など)
- 職業紹介業
- 人材派遣業
- 建設業
- 不動産業
- 探偵業
自分の起業したい業種が当てはまる場合には、バーチャルオフィス以外のオフィス形態を検討するようにしてください。
バーチャルオフィスで起業するメリット
バーチャルオフィスで起業するメリットには、以下のような点もあります。バーチャルオフィスでの起業を検討している方は、参考にしてください。
バーチャルオフィスで起業するメリット
- 費用を抑えられる
- プライバシーを守れる
- ブランディングができる
- すぐに住所を借りられる
費用を抑えられる
バーチャルオフィスで起業するメリットは、オフィスにかかる費用を抑えられることです。
バーチャルオフィスの利用料金は、一般的なオフィスの賃料に比べて格安です。さらに、実際にオフィスを借りる必要がないため、レンタルオフィスやシェアオフィスよりも安い料金で住所を利用できます。敷金や礼金、保証金なども不要なので、初期費用と固定費の両方を削減できるでしょう。
プライバシーを守れる
バーチャルオフィスで起業するメリットは、自宅を仕事場にしている場合、プライバシーを守れることです。
法人の本店所在地は、登記事項として一般に公開されます。また、法人の住所や電話番号は、名刺やWebサイト、封筒などにも記載することになるでしょう。
しかし、防犯やプライバシー保護の観点から、自宅住所の開示に抵抗がある人は少なくありません。バーチャルオフィスで起業すれば、不特定多数の人に自宅住所を公開せずに済みます。
ブランディングができる
バーチャルオフィスで起業するメリットは、ブランディングができることです。
一般的なオフィスを借りるには家賃が高額になる都心部やビジネス街、知名度の高い場所などでも、バーチャルオフィスなら他のオフィス形態よりも安価で利用が可能です。特に、イメージ戦略が重要な業種にとってはメリットになるでしょう。
すぐに住所を借りられる
バーチャルオフィスで起業するメリットは、すぐに住所を借りられることです。
一般的なオフィスを借りようとすると、物件選びから内見、審査、契約と、入居するまでに1~2か月かかることも珍しくありません。バーチャルオフィスなら、スピーディーに契約が完了するため、会社設立にかかる時間を短縮できるはずです。
バーチャルオフィスで起業するデメリット
バーチャルオフィスにはメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。バーチャルオフィスの利用を検討する際には、借りてから後悔をしないよう、デメリットも把握して比較検討するようにしましょう。
バーチャルオフィスで起業するデメリット
- 信用を得にくい場合がある
- 職種によっては会社住所として登録できない
- 他会社と住所が重複することがある
- 法人口座の開設が難しい場合がある
信用を得にくい場合がある
バーチャルオフィスで起業するデメリットは、信用を得にくい場合があることです。
オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスは、コスト面から見れば費用がかからずメリットになりますが、取引先からの信用という意味ではデメリットにもなり得ます。取引先によっては、業務実態のないバーチャルオフィスを会社の住所としていることで、不信感を抱かれる場合もあります。
そのような場合は、来客対応や電話受付が可能なバーチャルオフィスを選ぶといった工夫が必要になるでしょう。
職種によっては会社住所として登録できない
バーチャルオフィスで起業するデメリットは、職種によっては会社住所として登録できないことです。
例えば、宅地建物取引業では、他の法人と同一の住所を本店所在地とすることは認められていません。また、建設業の許可申請にあたっては、実際に事業を営む営業所などの画像提出が求められます。許認可が受けられなければ、事業を行うことができません。許認可が必要な業種に該当する場合は、十分注意が必要です。
他の会社と住所が重複することがある
バーチャルオフィスで起業するデメリットは、他の会社と住所が重複することです。
バーチャルオフィスで起業した場合、オフィスを提供する会社が用意できる本店所在地となる住所は限られるため、自社の他にも複数の会社が同じ住所で本店所在地を登記している可能性が高いといえます。同一または類似した商号でなければ、登記するうえでの問題はありません。
ただ、インターネットで検索をすると、同一の住所なのに、多数の会社のWebサイトがヒットすることになります。その結果、取引先に混同されたり不信感を持たれたりする可能性があるため、注意しましょう。
法人口座の開設が難しい場合がある
バーチャルオフィスで起業するデメリットは、法人口座の開設が難しい場合があることです。
バーチャルオフィスを本店所在地とした場合、登記はできても、法人口座の開設が難しくなる可能性があります。これは、マネーロンダリング(資金洗浄)や振り込め詐欺などの犯罪防止の観点から、金融機関の審査が厳しくなっているためです。
審査基準は金融機関によって異なり、バーチャルオフィスでも問題なく法人口座を開設できるケースもありますが、念のため確認しておくようにしてください。
バーチャルオフィスの選び方のポイント
一口にバーチャルオフィスといっても、立地条件や料金、利用できるサービスにはそれぞれ違いがあります。バーチャルオフィスで起業しようと考えている場合は、次のようなポイントに注目して選ぶと良いでしょう。
バーチャルオフィスの選び方のポイント
- 法人登記の可否
- 住所や電話番号
- 基本機能や追加オプション
- 契約形態
- 立地やアクセス
法人登記の可否
バーチャルオフィスの選び方のポイントには、法人登記の可否が挙げられます。
バーチャルオフィスで起業する場合、法人登記ができることは第一条件になるでしょう。そもそもバーチャルオフィスでの起業ができない事業もありますし、バーチャルオフィス自体も運営会社によっては登記が認められていないこともあります。個人事業主としての開業ではなく、会社設立を考えているなら、法人登記ができるかどうかを確認するようにしてください。
住所
バーチャルオフィスの選び方のポイントには、住所が挙げられます。
契約を検討しているバーチャルオフィスの住所や電話番号を確認し、ビジネスで利用するうえで問題がないかチェックが必要です。
例えば、歓楽街や清潔感のない雑居ビル、過去に犯罪やトラブルが起こった住所などを利用すると、事業そのものの信用低下につながるリスクがあります。
反対に、洗練されたイメージのある街や、都内一等地の高層ビル、顧客が多く存在するエリアの住所などで登記すれば、企業のイメージアップにつなげることができるでしょう。
基本機能や追加オプション
バーチャルオフィスの選び方のポイントには、基本機能や追加オプションが挙げられます。
バーチャルオフィスによっては、住所や電話番号のレンタルといった基本機能に加えて、私書箱や郵便物転送、急な来客対応、エントランスへの社名表示、会議室・シェアオフィスの利用といったオプションサービスが用意されていることもあります。
住所や電話番号を借りるだけで良いのか、他のサービスも利用したいのかを考え、自社のニーズに合ったバーチャルオフィスを選ぶようにしましょう。
契約形態
バーチャルオフィスの選び方のポイントには、契約形態が挙げられます。
バーチャルオフィスの中には1年契約のところもあり、解約時に残りの期間の分を全て支払わないといけないこともあります。そのような場合、事業拡大によって通常の賃貸オフィスに移転を考えたとき、余計な支払いが発生してしまうかもしれません。
他にも、入会金などの初期費用が必要かどうか、最低契約期間の有無、1か月単位での契約の可否、解約条件なども、バーチャルオフィスを選ぶ判断材料になります。
立地やアクセス
バーチャルオフィスの選び方のポイントには、立地やアクセスが挙げられます。
バーチャルオフィスの中には、会議室やシェアオフィスなどの利用ができるものもあります。オフィス利用や来客の可能性がある場合は、立地やアクセスといった条件もバーチャルオフィス選びのポイントになります。
また、打ち合わせなどで訪れる取引先の利便性も考え、最寄り駅からの距離や周辺環境、ビルの外観の印象などもチェックしておきましょう。
会社設立の手続きを手軽に行う方法
会社を設立する際には、オフィスの契約以外にもさまざまな手続きがあります。会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」です。
「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。
また、「弥生の設立お任せサービス」は、会社設立に関わる手続きを、起業に強い専門家に丸ごと代行してもらえるサービスです。電子定款や登記書類作成、公証役場への定款認証、法務局への登記書類提出などの各種手続きを依頼できるので、事業の準備で忙しくても確実かつスピーディーな会社設立が可能です。
起業する際は自社のニーズに合わせたオフィス形態を選ぼう
バーチャルオフィスの住所でも、法人登記は可能です。特に、オフィスにかかるコストを削減したい場合や、自宅住所を公開したくない場合、バーチャルオフィスでの起業にはメリットがあります。ただし、バーチャルオフィスでは登記ができない業種がある他、法人口座の開設が難しくなる可能性があるため注意が必要です。
オフィスを構える費用を抑えて起業するには、バーチャルオフィスの他に、シェアオフィスやレンタルオフィスを利用する方法もあります。それぞれの特徴を把握し、自社のニーズに合ったオフィス形態を選びましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。