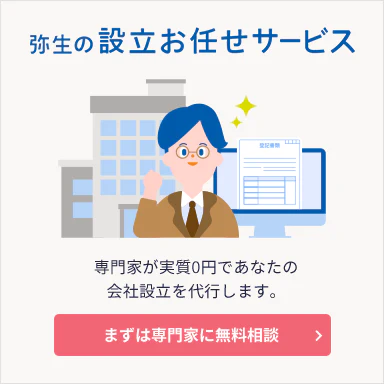フリーランスとは?代表的な仕事や準備・手続きをわかりやすく解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

働き方の多様化が進む中、企業や団体などの組織に属さずに「フリーランス」として働くスタイルが広がりを見せています。現在は会社員として働いていても、いずれフリーランスとして働きたい、副業でフリーランスとして働きたいと考える方もいることでしょう。
組織に所属せずに個人で仕事をするフリーランスは、会社員とは働き方が異なります。
本記事では、フリーランスで働くメリット・デメリットや、フリーランスの代表的な職種の他、フリーランスになるために必要な準備と手続きについて解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
フリーランスは個人で仕事を請け負って収入を得る働き方
フリーランスとは、企業や特定の団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方のことです。最近ではさまざまな分野で、フリーランスとして働く人が増えてきました。
例えば、企業に属さず働くWebライターやイラストレーターといった職種では、これまで通りフリーランスが多くいますし、最近ではコンサルタントといった職種でもフリーランスという方はいます。
ただ、フリーランスは法律上の用語ではなく、フリーランスになるにあたって必要な資格や実績などもありません。誰でもいつからでもフリーランスと名乗ることができます。
また、会社員であっても、副業でフリーランスとして働くことは可能であることも知っておきましょう。
副業でフリーランスとして働く場合について、詳しくは以下の記事も参照してください。
フリーランスの定義はさまざまなので、多様な働き方を選べる
フリーランスという呼び方に法的な根拠はなく、定義もさまざまです。ただ、国が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」においては、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義しています。
フリーランス協会の「フリーランス白書2023」によると、フリーランスは、全体の89.4%を占める独立系フリーランスと、9.0%の割合の副業系フリーランスに分けられます。
企業や組織に属さず雇用関係を持たない独立系フリーランスには、法人経営者(法人成りしている人)、個人事業主、すきまワーカー(開業届未提出の個人)がおり、基本的に主となる企業や組織に雇用されつつすきま時間で仕事をしている副業系フリーランスには、1社に雇用されながら起業する人、1社に雇用されながら他の組織や個人と契約を結ぶ人、2社以上に雇用される人がいるなど、フリーランスは多様な働き方を選べることがわかります。
フリーランスが増加した背景を知っておくと情勢に合わせられる
国内のフリーランス人口は、年々増加傾向にあるため、増加した背景について知っておくと、今後の情勢にも合わせていきやすいといえます。フリーランスとして働く人が増えている背景には、働き方の多様化や副業解禁、リモートワークの普及などが挙げられます。
また、クラウドソーシングやエージェントサービスの発展により、個人で仕事を獲得する方法が広がったことも要因の1つといえるでしょう。
このような流れや、副業を解禁する会社が増えつつあることを考えると、今後もフリーランス人口は増加していくと予想されています。
そのため、2021年9月から労災保険の特別加入の対象が拡大し、フリーランスも加入が可能になるなど、国もフリーランスという新しい働き方のためにさまざまな制度を整えつつあるのです。
また、2024年11月1日から施行されたフリーランス新法(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法))についても知っておきましょう。
フリーランス新法(フリーランス保護法)について詳しくは、以下の記事をあわせてご覧ください。
個人事業主との違い
個人事業主は、フリーランスと混同されやすい言葉といえます。フリーランスも個人事業主も、特定の団体に所属せずに個人で仕事をしている点では同じです。
しかし、フリーランスが働き方を指す言葉であるのに対して、個人事業主は税法上の区分であることが違いとなります。
個人事業主は、税務署に開業届を提出し、個人で継続して事業を営んでいる人を指します。つまり、フリーランスが開業届を出せば個人事業主になりますし、開業の届出にかかわらず、スキルを活用して1人で仕事をしている人がフリーランスということです。
なお、開業届を出しているかどうかにかかわらず、フリーランスとして一定以上の所得があれば、確定申告が必要となります。
- ※個人事業主の開業については以下の記事を併せてご覧ください
フリーランスで働くメリット
フリーランスの特徴は、仕事内容や仕事の進め方などを全て自分で決められることです。会社員のように会社の指示に従う必要はなく、自分のやり方で仕事を進めることができます。メリットを確認しておくことで、自分がフリーランスに向いているか向かないかを知ることができるでしょう。
フリーランスとして働くメリット
- 自由な働き方ができる
- 自分に合う仕事を選べる
- スキルや成果によって高い報酬を得られる
自由な働き方ができる
フリーランスとして働くメリットは、自由な働き方ができることです。
フリーランスは組織に所属しないため、働く場所、時間、休日、ペース配分などを、全て自分でコントロールができます。例えば、土日に仕事をして平日に休んでも、カフェや旅先で仕事をしても、依頼された業務さえやり遂げれば問題はありません。
フリーランス協会の「フリーランス白書2023」からも、「今の働き方に対する満足度」として、働く時間や場所などの「就業環境」は、70%以上の満足度を得ていることがわかります。
なお、フリーランスは基本的には出勤不要ですが、請け負う仕事内容によっては、クライアントに常駐する必要があったり、働く場所や時間を指定されたりすることもあります。
自分に合う仕事を選べる
フリーランスとして働くメリットは、自分に合う仕事を選べることです。
原則としてフリーランスは、単発の案件ごとに契約を結んで業務にあたります。依頼された案件を受けるかどうかは自分の判断で決められるので、苦手な仕事を断ったり、条件について交渉したりすることも可能です。
反対に、自分のスキルアップにつながる仕事や、チャレンジしてみたい分野の仕事を選ぶこともできます。組織の目的に従って指示された仕事をこなさなければいけない会社員とは、異なる点といえるでしょう。
スキルや成果によって高い報酬を得られる
フリーランスとして働くメリットは、スキルや成果によって高い報酬を得られることです。
フリーランスは、自分の行動が収入に直結します。スキルを磨き、高い成果を上げれば、その分報酬額も上がっていくでしょう。クライアントと価格交渉をして単価を上げる、仕事量を増やして年収アップを目指すなど、自分の努力次第で大きな収入を得ることも可能です。
フリーランスで働くデメリット
自由度の高いフリーランスですが、メリットばかりではありません。自由に働けるということは、裏を返せば、業務にまつわる全てを自分1人で決めなければいけないということです。
また、自由に仕事を選べるといっても、選り好みばかりしていては依頼がなくなり、収入が途絶えてしまう可能性もあります。フリーランスとして働くなら、あらかじめデメリットについても知っておきましょう。
フリーランスとして働くデメリット
- 収入が不安定になりやすい
- 確定申告や保険の手続きが大変
- 他者と関わる機会が減り孤独を感じやすい
収入が不安定になりやすい
フリーランスとして働くデメリットは、収入が不安定になりやすいことです。
個人の成果にかかわらず給与が支給される会社員とは異なり、フリーランスは仕事をしなければ収入はありません。たとえ現在順調に収入を得られていても、それが継続する保証はどこにもないといえます。
また、案件ごとに報酬額が決まるため、収入の波が大きくなりやすいという特徴もあります。
フリーランス協会の「フリーランス白書2023」によると、「フリーランスとしての働き方を始めてから資金調達が必要だと感じた経験」が「ある」と回答したのは27.1%に上り、「資金調達経験者が調達した資金の用途」としては「生活費」が最多の37.8%でした。生活に必要な資金を外部から調達する必要がある人の割合を考えると、フリーランスは収入を安定させることが難しいといえるでしょう。
確定申告や社会保険の手続きが煩雑
フリーランスとして働くデメリットは、確定申告や保険の手続きが煩雑なことです。
個人で働くフリーランスは、事業にまつわる全てのことを自分で行う必要があります。例えば、会社員なら勤務先が処理してくれる税金や社会保険の手続きや帳簿付けなどの会計業務も、自分自身で行わなければなりません。会社員のような年末調整はないので、年に1度の確定申告も必要になります。
他者と関わる機会が減り孤独を感じやすい
フリーランスとして働くデメリットは、他者と関わる機会が減り孤独を感じやすいことです。
クライアントへの常駐やチームでプロジェクトに携わるケースなどを除き、フリーランスは基本的には単独で仕事をします。
会社員であれば仕事で迷ったり困ったりしたことは上司や同僚に相談できますが、フリーランスは全て自分で判断して答えを出さなければなりません。他人と関わる機会が少なくなり、孤独を感じるフリーランスも多いようです。
- ※フリーランスの営業については以下の記事を併せてご覧ください
フリーランスの代表的な職種例10種の仕事内容
フリーランスとして代表的な職種には、下記のようなものが挙げられます。
なお、フリーランス協会の「フリーランス白書2023」の調査では、フリーランスの主な職種として上位5位が、「クリエイティブ・Web・フォト系」26.6%、「エンジニア・技術開発系」14.8%、「出版・メディア系」9.9%、「コンサルティング系」7.9%、「通訳翻訳系」7.3%となっています。
フリーランスの代表的な職種例
- ライター
- デザイナー
- エンジニア
- イラストレーター
- コンサルタント
- マーケター
- アフィリエイター
- 動画クリエイター
- カメラマン
- 編集者
- 美容師
- ヘアメイク
- 講師
フリーランスの職種は多種多様ですが、共通するのは、スキルや経験を活かして収入を得ていること。職種によって、企業との取引がメインになる場合もあれば、一般消費者を対象にした事業形態もあります。自分がフリーランスとして働く際に、どの職種で仕事を受けるかを検討してください。
ライター
フリーランスの代表的な職種例として、ライターがあります。
ライターは、Webサイトや雑誌などのメディアから依頼を受け、文章を執筆することを仕事としています。パソコンがあれば仕事ができ、特別な資格も必要ないため、未経験者でも始めやすいのが特徴です。
デザイナー
フリーランスの代表的な職種例として、デザイナーがあります。
Webサイトのデザインを手掛けるWebデザイナーや、紙の広告物をデザインするグラフィックデザイナー、デジタル機器を使いやすくデザインするUI・UXデザイナー、空間や室内の環境をデザイン・設計するインテリアデザイナーといった、さまざまな分野があります。センスだけではなく、必要なデザインソフトを使いこなすスキルも必要です。
エンジニア
フリーランスの代表的な職種例として、エンジニアがあります。
エンジニアの主な業務は、システムの開発・設計・運用です。システムエンジニアやネットワークエンジニア、サーバーエンジニア、データベースエンジニア、Webエンジニア、セキュリティエンジニアというように、専門分野によって求められるスキルが異なります。
イラストレーター
フリーランスの代表的な職種例として、イラストレーターがあります。
イラストレーターは、クライアントから依頼を受け、テーマや希望に沿ったイラストを制作する仕事です。近年では、SNSの投稿が仕事につながったり、自主的に制作したイラストをダウンロードなどで販売したりするケースも見られます。
コンサルタント
フリーランスの代表的な職種例として、コンサルタントがあります。
コンサルタントは、専門知識やスキルを活かしてクライアントが抱える課題を特定し、問題解決に向けたサポートやアドバイスを行う仕事です。経営、IT、金融、地方再生から恋愛、子育てまで、さまざまな分野で活動するコンサルタントがいます。
マーケター
フリーランスの代表的な職種例として、マーケターがあります。
マーケターは、企業から依頼を受けて、マーケティング業務を担う仕事です。中でも近年ニーズが高まっている職種に、WebやSNSを活用したマーケティング戦略を策定・実行する、Webマーケターがあります。また、Webマーケターの中でも細分化が進んでおり、SEOマーケター、広告プランナー、SNS運用者などに分かれます。
アフィリエイター
フリーランスの代表的な職種例として、アフィリエイターがあります。
アフィリエイターは、自分のWebサイトやブログ、SNS、メルマガで商品やサービスの紹介を行います。広告のクリックまたは商品・サービスが購入されると、成果に応じた報酬を受け取ることが可能です。
SEOの知識や文章スキルが求められますが、影響力が高まればPR案件の依頼も増えるでしょう。
動画クリエイター
フリーランスの代表的な職種例として、動画クリエイターがあります。
スマートフォンや動画配信サイトの普及により、動画クリエイターの需要は高まっています。BGMやテロップ挿入といった一般的な動画編集から、企画や演出、シナリオ作成、CG加工まで、スキルによって報酬はさまざまです。
カメラマン
フリーランスの代表的な職種例として、カメラマンがあります。
カメラマンは、イベントや雑誌、Webサイトに掲載する素材の撮影を行います。撮影対象は人物や動物、料理、風景など、依頼によってさまざまです。
中には、撮影した画像をダウンロード販売したり、一般消費者からの依頼を受けて出張撮影をしたりするカメラマンもいます。
編集者
フリーランスの代表的な職種例として、編集者があります。
編集者は、雑誌や書籍、情報紙、Webサイトを制作するために、企画をまとめたり進行を調整したりする仕事です。企画単位で受注する他、書籍やサイトなどを丸ごと担当するケースもあります。いずれにしても未経験では難しい仕事なので、出版社などでの勤務を経てフリーランスになる場合が多いです。
美容師
フリーランスの代表的な職種例として、美容院があります。
美容室に勤めたり店舗を構えたりせず、フリーランスとして活動する美容師もいます。一般的には、美容室の場所を一部借りて営業する「面貸し」か「業務委託」の形になります。美容師として働くには、美容師免許の取得が必須です。
ヘアメイク
フリーランスの代表的な職種例として、ヘアメイクがあります。
ヘアメイクは、テレビや映画、雑誌、CMなどの撮影現場に出向き、出演者やモデルにヘアメイクを施すのが仕事です。また、結婚式場やフォトウェディングを行うスタジオといった、ブライダル業界で働くケースもあります。
講師
フリーランスの代表的な職種例として、講師があります。
音楽や英会話、ヨガ、料理というように、フリーランスとして働く講師のジャンルは多岐にわたります。自宅を教室として利用する、場所を借りる、オンライン、出張レッスンといった、さまざまなスタイルで働くことが可能です。
フリーランスとして働くための準備や必要な手続き
フリーランスとして働くための準備と聞くと、会社といった組織に頼らず自分で仕事を見つけていかなければいけないため、多くの方がスキルを向上させるべきだと考えるかもしれません。もちろんスキルは大切ですが、それ以外にも必要な準備や手続きがあります。スムースに事業をスタートするためにも、事前準備について確認しておきましょう。
フリーランスとして働くための準備や手続き
- 独立資金を貯めておく
- 必要に応じて開業届を提出し、個人事業主になる
- 健康保険・年金の切り替えと加入手続きをする
- 毎月の経理処理や確定申告を行う
- フリーランスをサポートするコミュニティに加入する
独立資金を貯めておく
フリーランスとして働くための準備や手続きには、独立資金を貯めておくことが挙げられます。開業してからしばらくは仕事が少ない可能性もあり、案件を受注しても、報酬の入金が数か月先になることも珍しくありません。
また、資金と同時に、利用できそうな補助金がないかを調べておくと良いでしょう。フリーランスが利用できる補助金には、「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」などがあります。
必要に応じて開業届を提出し、個人事業主になる
フリーランスとして働くための準備や手続きには、必要に応じて開業届を提出し、個人事業主になることが挙げられます。継続した事業所得が得られそうな場合は、税務署へ開業届の提出が必要です。
開業届を提出して個人事業主になると、屋号を使えるようになります。また、開業届と共に所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、確定申告を青色申告で行うことが可能です。
青色申告には、所定の要件を満たすと最大65万円の青色申告特別控除を受けられるなど、多くの節税メリットがあります。
なお、開業届を提出していなくても、1月1日~12月31日の1年間の所得(事業の売上から経費を引いた金額や給与金額などの合計金額)が48万円を超えるフリーランスや、副業の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。
また、確定申告が不要な人でも、報酬から源泉徴収されているフリーランスの場合、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があるため、確認しておくといいでしょう。
- ※開業届を出すメリット・デメリットについては以下の記事を併せてご覧ください
健康保険・年金の切り替えと加入手続きをする
フリーランスとして働くための準備や手続きには、健康保険・年金の切り替えと加入手続きをすることが挙げられます。会社員からフリーランスになると、社会保険がそれまでの健康保険と厚生年金から、国民健康保険(任意継続の健康保険に加入している場合を除く)と国民年金へ変更になります。会社を退職したら、忘れずに社会保険の切り替え手続きを行いましょう。
なお、フリーランスの職種によっては、健康保険組合に加入できる場合もあります。
毎月の経理処理や確定申告を行う
フリーランスとして働くための準備や手続きには、毎月の経理処理や確定申告を行うことが挙げられます。フリーランスも、一定の所得を得ているのであれば、基本的に年に1回の確定申告を行う必要があります。また、確定申告を行うには、日々の帳簿付けが欠かせません。経理処理に追われて本業が圧迫されることのないように会計ソフトを導入し、業務の効率化を図りましょう。
手書きだと煩雑で時間がかかる帳簿付けも会計ソフトを使えばかんたんですし、確定申告の手間も軽減されるので検討してみてください。
フリーランスをサポートするコミュニティに加入する
フリーランスとして働くための準備や手続きには、フリーランスをサポートするコミュニティに加入することが挙げられます。フリーランスは、他人と接する機会が少なくなりがちなもの。このような課題を解消するには、フリーランスをサポートするコミュニティへの参加が効果的といえるでしょう。
フリーランス同士が交流できるコミュニティなら、情報交換や人脈づくりに役立つ他、紹介がきっかけで仕事の獲得にもつながるはずです。
フリーランスが開業届と確定申告の手続きを手軽にする方法
フリーランスが開業するには、税務署に開業届を提出する必要があります。開業手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん開業届」です。
「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、開業届をはじめ、青色申告承認承諾書や給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書などもスムーズに作成することができます。
また、フリーランスになると、日々経理処理を行い、年に1度は確定申告をしなければなりません。いち早く事業に集中するためにも、開業のタイミングで確定申告ソフトや会計ソフトを導入しておくといいでしょう。
初心者でもかんたんに使えるクラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、確定申告の必要書類を手軽に作成できます。
フリーランスになるなら開業届の提出や青色申告を検討しよう
会社などの組織に所属せずに、個人で仕事をするフリーランスは近年増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されています。自由度が高く、がんばり次第で高収入も狙えますが、安定した収入が保証されないといったリスクもあります。会社員の場合はまず副業から始め、事業が軌道に乗ってから独立するのも1つの方法です。
また、フリーランスになるなら、開業届を提出し、節税メリットの大きい青色申告を選択するのがおすすめです。「青色申告は難しそう」と思われがちですが、「やよいの青色申告 オンライン」のような会計ソフトを使えば、簿記や経理の知識がなくてもスムーズに青色申告ができます。
確定申告の時期になってあわてないように、フリーランスとして開業するときは、会計ソフトの導入についても検討しておきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。