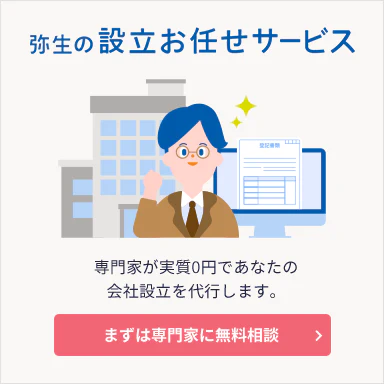法人税法とは?経営者が知っておくべき税率や企業会計との違い
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

法人税法は、株式会社や合同会社といった法人に課せられる法人税について定めた法律です。法人税は、会社の事業活動で得た所得にかかる税金で、法人は自ら法人税を算出して税務署に申告・納付しなければなりません。
法人税額を算出する会計処理は、難しいうえに企業会計における利益計算とは一致しないこともあります。法人税に関する手続きや計算方法などを理解するには、法人税法に定められている法人税の取り扱いについて知っておきましょう。
本記事では、法人税法に定められている法人税の税率や計算方法の他、企業会計との違いについて解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
法人税法とは法人税の計算方法や申告・納付手続きなどを定めた法律
法人税法は、法人が納める法人税の納税義務者や課税所得の範囲、税額の計算方法、申告・納付の手続きについて定めた法律です。法人税とは、法人が事業活動で得た所得に対して課税される国税です。
法人に課せられる税金には法人税の他、地方税である法人住民税と法人事業税もあり、3つをまとめて「法人税等」と呼ばれています。
なお、法人税に関わる法律は所得税法に含まれていましたが、1940年に法人税法として新たに制定されているため、それぞれの税法を確認する際に間違わないよう注意しましょう。
法人税法の目的は法人に対して公平に課税すること
法人税法の目的は、法人に対して公平に課税することです。法人税法の総則では法人税法の趣旨として、「法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続き並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるもの」としています。法人税法は、納税義務者や課税対象となる所得の範囲、税率、納付や還付の手続きなどを規定したものと同時に、国が法人に課税を行う根拠を示すものともいえるでしょう。
課税対象は普通法人の他、協同組合、一般社団法人、NPO法人
法人税の納税義務がある法人は、株式会社や合同会社をはじめとする普通法人の他、協同組合、一般社団法人、NPO法人などです。日本政策金融公庫のような公共法人には法人税はかかりません。
法人税の計算方法
法人は、定款で定めた1年以下の事業年度ごとに納めるべき法人税額を計算し、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告を行わなければなりません。法人税額は以下のような計算式で求められます。
法人税額=課税所得×法人税率-控除額
なお、期限内に法人税の申告・納付を行わないと延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生します。さらに、2期連続で申告期限を過ぎると青色申告が取り消されてしまいますので忘れないようにしましょう。
法人税の税率は資本金や所得によって変わる
法人税の税率は資本金や所得によって異なります。法人税率は、課税所得が高くなるほど税率が高くなる累進課税制度を採用しているからです。
例えば、資本金が1億円以下かつ、年間の所得が800万円以下なら15%の法人税率が適用されます。また、資本金が1億円以下かつ年間の所得が800万円を超える場合、年間の所得800万円以下の部分と800万円を超える部分で法人税率が異なります。
なお、法人税率は最大でも23.2%なため、個人事業主から法人化した方が節税効果を得られることがあるため、節税を検討している人は法人化も選択肢の一つとして検討してみてください。
| 税率 | 資本金1億円以下の中小法人 | 年間所得800万円以下の部分:15% |
|---|---|---|
| 年間所得800万円超の部分:23.2% | ||
| 中小法人以外の法人 | 23.2% |
法人税が課せられる所得
法人税の課税所得とは、益金(売上収入や売却収入)から損金(売上原価や販売費、損失費用)を引いた金額のことを指します。益金とは、商品・製品などの販売による売上収入や土地・建物の売却収入などが該当します。それに対し、損金とは、売上原価や販売費、災害などによる損失といった費用や損失にあたるものです。これを計算式にすると以下のようになります。
所得=益金(売上収入や売却収入)-損金(売上原価や販売費、損失費用)
なお、益金と損金は法人税法における考え方であり、企業会計上の収益や費用(経費)とは必ずしも金額が一致しません。実際には、収益から費用を引いた利益に法人税法の規定に基づく税務調整を行ったものが課税される所得となります。
※法人税の税率や所得税との違いについては以下の記事を併せてご覧ください
法人税法と企業会計の違いは目的
法人税法と企業会計の計算結果に違いが生じるのは、それぞれの目的が異なるためです。法人税法の目的は、公平な課税を行うために課税所得を把握することです。その一方で、企業会計の目的は適正な期間損益計算を行い、利益を把握して企業の財政状態や経営成績を知ることです。
そのため、計算するうえでのルールが異なります。例えば、企業会計上は経費にできても、公平に課税するには経費として損金に計上できない項目があります。法人の交際費は、企業会計上では経費にする上での上限金額はありませんが、法人税法では資本金1億円以下の中小企業の場合、年間800万円を超える部分は、費用とみなされず損金不算入となっています。
中小企業の場合、税務調整の手間を軽減するために、はじめから法人税法上の規定に従って会計処理を行うケースもあります。株式上場しているような企業規模が大きな会社の場合、企業会計のルールに従わなくてはいけないため、企業規模が大きくなるほど法人税法と企業会計の差も大きくなりがちです。
法人税の計算方法は複雑であるため、基本的には税務の専門家である税理士に確認して進めます。
法人税を抑えるためのポイント
法人税の税額が多くなると、その分会社の利益は少なくなってしまいます。法人税を抑えるためのポイントとしては、次のようなことが挙げられます。
法人税を抑えるためのポイント
- 損金を増やす
- 利益を減らす
- 特別控除を利用する
損金を増やす
法人税を抑えるには、経費のように計上できる損金を増やすことが挙げられます。損金が増えるほど課税所得は減少し、結果として法人税額も少なくなります。
例えば、青色申告であれば、赤字を最大10年間まで繰り越して翌事業年度以降の損金とすることが可能です。その他、損金計上ができるものとして生命保険料の一部、社員旅行費用の福利厚生費、在庫を整理した廃棄分の費用、決算賞与の未払費用などが挙げられます。
あらかじめ出張旅費規程を定めておけば、出張時に交通費とは別に出張手当(日当)を支給し、その金額を経費として損金計上することも可能です。出張手当は、従業員に限らず役員にも支給することができます。
利益を減らす
利益(益金)を減らすことでも課税所得は減少するため、法人税を抑えることにつながります。益金を減らすのに有効なのは、売上の計上タイミングを後ろにずらすことです。例えば、商品の出荷時点で売上を計上するよりも取引先を納品したときに売上を計上した方が、益金の計上タイミングは遅くなります。計上時期が翌事業年度にずれ込めば、当期の課税所得は少なくなるでしょう。
なお、売上の計上時期をいつにするかは、あらかじめ自社内で統一して決めておく必要があります。法人税の節税のために、納品のたびに売上計上のタイミングを変えることはできません。
特別控除を利用する
特別控除を利用して法人税の優遇措置を受けるのも法人税を抑えるポイントの1つです。例えば、要件を満たしたうえで雇用者を増加させると、1人あたり最大90万円の税額控除が受けられる「雇用促進税制」が適用できます。
また、設備投資の費用の一部について特別償却または税額控除が受けられる「中小企業投資促進税制」、前年度より給与支給額を増加させた場合に一部が税額控除される、中小企業向けの「賃上げ促進税制
」などもあります。いずれの控除も、適用にあたっては所定の要件があるので注意しましょう。
なお、税の知識がないまま、法人税を抑えようとすると脱税になってしまう可能性があります。自社にとって適正な法人税を納めるには、税務の専門家である税理士に相談してアドバイスを受けるのも1つの方法です。
法人税について相談できる税理士を探す方法
法人税の計算は、税務や会計の専門知識がないと難しく感じられるものです。法人税の確定申告でミスを防ぐには、税務の専門家である税理士に相談するといいでしょう。自力で税理士を探そうとすると、手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、会社設立や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模のパートナー会計事務所から、会社所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します。紹介料は、一切かかりません。
特に初めて会社を設立する際には、事業計画の作成や資金調達など多くの不安や疑問が生じるものです。「税理士紹介ナビ」なら、これから事業を始める方の悩みや困りごとに合わせて、最適な税理士探しをサポートします。個人事業主から法人成りするかを迷っている方にもピッタリです。
法人税法を知って適正な法人税額を申告・納付しよう
法人税法は、会社の経営者が知っておくべき法律の1つです。法人税は自社で計算を行い、申告・納付しなくてなりません。法人税法に定められた税率や計算方法を知っても税務の知識がなければ法人税の計算は難しく感じられるものです。万が一、申告期限を過ぎてしまうとペナルティも科せられてしまいますので注意が必要です。事業継続に影響が出ないよう、法人税については税理士に相談して自社にとって適切な法人税額を申告・納付しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。