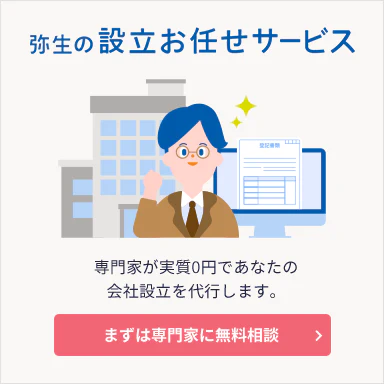起業におすすめの業種は?成功しやすいジャンルや選び方のポイント
監修者: 渡辺亨(中小企業診断士)
更新
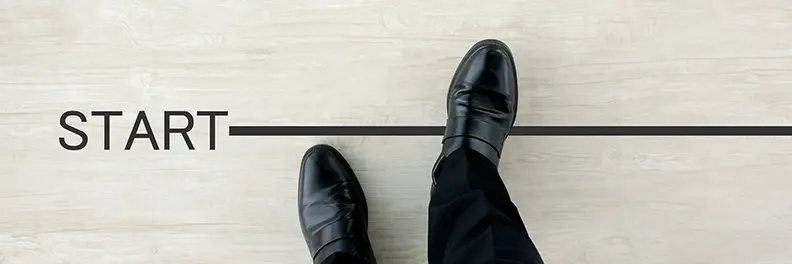
起業・開業する際には、業種を決めなければなりません。おすすめの業種や人気の業種を知っていれば、自分に合った業種を探すヒントになるほか、顧客のニーズを知る参考にもなります。
本記事では、起業した方に人気の業種や起業・開業に成功しやすいおすすめの業種、起業・開業するときの業種選びのポイントなどを解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
起業・開業した方に人気の業種は個人向けサービス業
起業した方が多い人気の業種は、個人向けサービス業です。2019~2023年に起業・開業した方を対象にした日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度起業と起業意識に関する調査」では、起業・開業した方の業種も調査されています。その調査結果からは、以下のように起業家・パートタイム起業家共に個人向けサービス業の人気が最も高いことがわかります。
起業した方の業種の割合
| 業種 | 起業家※ | パートタイム起業家※ |
|---|---|---|
| 建設業 | 8.0% | 7.4% |
| 製造業 | 5.7% | 5.7% |
| 情報通信業 | 10.7% | 10.1% |
| 運輸業 | 7.6% | 6.6% |
| 卸売業 | 1.9% | 2.4% |
| 小売業 | 10.6% | 9.0% |
| 飲食店・宿泊業 | 4.7% | 4.2% |
| 医療・福祉 | 2.4% | 4.7% |
| 教育・学習支援業 | 3.1% | 10.3% |
| 個人向けサービス業 | 21.1% | 21.9% |
| 事業所向けサービス業 | 16.5% | 12.4% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 2.6% | 1.5% |
| その他 | 5.2% | 3.9% |
- ※事業に充てる時間が1週間に35時間以上の場合が起業家、35時間未満の場合がパートタイム起業家
個人向けサービス業とは、一般消費者向けにサービスを提供する業種のことです。例えば、美容室や理容室をはじめとする各種美容サービス業、クリーニング業、家事代行業、エンターテインメントに関連する娯楽サービス業、個人向けのレンタル・リース業などが該当します。
個人向けサービス業には、顧客層に合わせたニーズの提供やコミュニケーション能力が求められますが、その点に自信のある方は、個人向けサービス業のいずれかの業種での起業・開業を検討してみてはいかがでしょうか。
※起業時の人気業種については以下の記事を併せてご覧ください
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
起業・開業には成功しやすい業種がある
さまざまな業種の中には、個人の起業・開業に向いている、成功しやすい業種があります。起業・開業のハードルが他の業種に比べて低い業種や、起業・開業後に安定した売上を目指しやすい業種があるため、その中から起業・開業する業種を選ぶのも1つの選択肢です。例えば、以下のような業種も視野に入れて、起業・開業する業種を検討してみましょう。
起業・開業で成功しやすい業種
- BtoCビジネスの業種
- 初期投資や固定費を抑えられる業種
- 将来的に成長が期待できる業種
BtoCビジネスの業種
一般消費者を対象としたBtoCビジネスの業種は、個人で起業・開業した際に成功しやすい業種の1つです。一般的に、会社(法人)が取引相手となるBtoBビジネスの場合、個人事業主という肩書では社会的な信用性の低さから契約を締結してもらえないケースもあるため、BtoCビジネスよりも事業成功のハードルは上がります。
一方、顧客が一般消費者であるBtoCビジネスであれば、事業の運営元が個人か会社かではなく、事業の内容が焦点になりやすいため、BtoCビジネスの方が個人事業主でも起業・開業しやすいといえます。BtoCビジネスに該当する業種は、例えば個人向けサービス業、飲食店、小売店、学習塾、習い事の教室、宿泊業などです。
初期投資や固定費を抑えられる業種
初期投資や固定費が抑えられる業種も、個人で起業・開業した際に成功しやすい業種の1つです。初期投資や固定費が抑えられれば、融資の返済や事業用の経費で赤字になるリスクを軽減できるため、起業直後の売上が少なくても堅実な成長を目指すことができます。
初期投資や固定費を抑えられる業種には、例えば、ネットショップの運営やライター、デザイナー、イラストレーターなどがあります。これらの業種には、商品の企画力や技術力などが求められるため、消費者に受け入れられる商品を探すスキルや、文章やイラストなどを創作するスキルに自信がある方は起業・開業を検討してみましょう。
将来的に成長が期待できる業種
将来的に市場の成長が期待できる業種も、個人で起業・開業した際に成功しやすい業種の1つです。市場の拡大が期待できるうえに参入業者が減っている業種を選ぶと、競合が少なくなるため、新規参入者でも成功しやすくなります。
例えば、建設業は、インフラの老朽化や災害対策に伴ってニーズの増加が予想されますが、少子高齢化の影響で事業の担い手は減少傾向です。また、介護サービスをはじめとする高齢者向けサービスも、今後も加速が予想される少子高齢化により需要増加が見込まれています。
市場の拡大という観点では、地方自治体が実施している助成事業を参考にするのも1つの方法です。地方自治体では、各自治体が抱える課題の解決につながり、市場の拡大が期待できる分野について助成事業を実施しているケースもあります。
東京都の「令和6年度 TOKYO戦略的イノベーション促進事業」では、都市課題を解決できる成長分野への中小企業の算入を促進するために、「防災・減災・災害復旧」「子育て・高齢者・障害者等の支援」「環境・エネルギー・節電」などの9つの分野の技術・製品開発を支援する事業が行われています。国や地方自治体による支援は、市場の成長を後押しする要素でもあるため、公的な支援のある分野での起業・開業を検討するのも良いかもしれません。
なお、事業の成長には、地域性も影響します。ある地域では飽和状態にある業種でも、別の地域では競合が少ないかもしれません。市場の成長性を判断する際には、地方自治体の商業統計調査も確認しながら、地域性といった視点も加味して検討しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
起業・開業する際の業種選びには、押さえておくべきポイントがある
起業・開業で成功を目指すには、ただ人気の業種を選べばいいというわけではなく、ポイントを押さえた業種選びが必要です。判断基準を持たずに闇雲に業種を選ぶと、モチベーションや収入面の課題に直面することがあるため、事業の継続が困難になりかねません。起業・開業する業種を検討する際には、以下のポイントを意識して、自身の起業・開業に適した業種かどうか判断しましょう。
起業・開業する際の業種選びのポイント
- 自分がやりたいと思える業種か
- 自分が持つ経歴やスキル、強みを活かせる業種か
- 競合とうまく差別化を図れる業種か
- 参入障壁が高すぎない業種か
- 業界が縮小傾向にない業種か
自分がやりたいと思える業種か
業種を選ぶ際には、自分がやりたいこと、興味のあることに関連する業種を選ぶのがポイントです。いくら人気のある業種でも自分にその業種への熱意がなければ、モチベーションの低下によって、事業を継続できなくなるおそれがあります。
起業後は、例えば思うように売上が上がらなかったり、事業上のトラブルが発生したりすることも珍しくありません。課題に直面した際に、根気よく解決策を模索するための原動力は、事業への熱意です。起業・開業したい事業が絞り込めたら、自分の興味や関心との関連性を確認して、熱意を持って取り組めそうか改めて検討しましょう。
自分が持つ経歴やスキル、強みを活かせる業種か
業種を選ぶ際には、自分のこれまでの経歴や培ってきたスキル、強みを活かせる業種を選ぶのがポイントです。未経験で知識もない業種よりも、経験や知識、人脈などを活かせる業種の方が効率良く売上を上げられるため、事業が継続しやすくなります。例えば、会社の従業員として飲食業に勤め、店舗を運営した経験がある場合は、飲食業で起業・開業することは有力な選択肢となります。
また、実店舗を構える業種の場合は、店舗の近隣地域の特徴に応じた事業を展開できるかどうかもポイントです。自宅での起業・開業を考えている場合は、自宅の近くに学校があるのであれば、学生がターゲットになる業種を選ぶといった選択肢があります。
競合とうまく差別化を図れる業種か
業種を選ぶ際には、競合とうまく差別化を図れる業種を選ぶのもポイントです。起業した方に人気の業種は、ニーズが高い一方で競合も多いため、数ある商品やサービスの中から自社を選んでもらえるように競合との差別化を図らなければなりません。
差別化を目指すには、市場ニーズを的確に把握する必要があります。例えば、競合他社の商品・サービスの調査やターゲット層へのヒアリングを調査会社に依頼してニーズを探り、そのニーズに対して競合よりも自分の強みが発揮できるポイントを探してみましょう。
参入障壁が高すぎない業種か
業種を選ぶ際には、自身にとって参入障壁が高すぎない業種を選ぶのもポイントです。参入のハードルが高い業種は、競合が少ないといったメリットがある一方で、事業開始までに時間や手間、費用がかかるため、場合によっては事業を始めるまでに生活が困窮しかねません。
参入障壁の高い業種としては、例えば、建設業があげられます。個人事業主として1人で建設業を起業・開業したい場合、許可を取得しなければならず、許可要件の中には学歴や実務経験、資格などに関する項目もあります。建設業に関する就学経験や従事経験があればクリアすることは可能ですが、そうでない場合は年単位の時間がかかる可能性もあるため、現実的ではありません。
業種を選ぶ際には、必要な許認可の手続きや費用、期間などをWeb検索で調べて、その業種で起業・開業できそうか判断しましょう。
業界が縮小傾向にない業種か
業種を選ぶ際には、業界が縮小傾向にない業種を選ぶのもポイントです。自分がやりたいことや、経験、スキルを活かせることでも、将来的に市場が縮小する業種では顧客数が減っていくため、事業の継続が困難になる可能性があります。
市場規模や市場動向は、例えば官公庁や業界団体が公表しているレポートから調べることができるため、起業・開業したい業種の候補がある場合はそのようなレポートを活用して市場傾向も確認しておきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社や事業を買収して起業・開業するという選択肢もある
起業・開業の選択肢として、ゼロから事業を立ち上げる方法のほかに考えられるのが、M&Aによる会社(法人)や事業の買収です。後継者不足に悩む中小企業の存在や、M&Aマッチングサイトの登場により、個人によるM&Aも行いやすくなっています。
会社や事業を買って起業・開業することには、自分でゼロから起業するよりも手間やコストを抑えられるといったメリットがあります。稼働中の事業モデルを引き継げるため、商品・サービスの内容、ターゲット、販売チャネル、集客方法、資金繰りなどをゼロから考える必要はありません。また、事業の課題やリスクを事前に想定できるため、対策が立てやすい点もメリットです。
M&Aの実行にあたっては、交渉力に加えて財務、税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となるため、専門家の力を借りるのも1つの方法です。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、M&Aや事業承継などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。紹介料は、一切かかりません。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社や事業を買収して起業・開業する際の流れがある
M&Aで会社(法人)や事業を買収する際には、一定の流れに沿って手続きを進める必要があります。事業買収の流れを知っておくことで、M&Aによる起業・開業をスムースに行えるようになります。
M&Aによる起業・開業を検討している場合は、以下の基本的な流れを念頭に置いて手続きを進めましょう。
会社や事業を買収して起業・開業する際の流れ
-
STEP1. 起業・開業の目的や理由を考え、条件と予算を検討する
-
STEP2. 買収先を探す
-
STEP3. 買収先候補と面談する
-
STEP4. 買収先候補と基本合意契約を結ぶ
-
STEP5. 買収先候補のデューデリジェンスを行う
-
STEP6. 買収する企業と最終契約を結ぶ
STEP1. 起業・開業の目的や理由を考え、条件と予算を検討する
M&Aを行う際は、最初にM&Aで起業・開業する目的や理由を明確にして、予算を検討します。目的や理由が明確になっていなければ、相手探しや交渉の条件、条件の中の優先順位を決めることもできません。目的や理由を明確にしたうえで、条件と買収予算を決めましょう。
STEP2. 買収先を探す
起業・開業の目的や理由を考えて条件や予算を検討したら、目的や条件に見合う交渉相手を探します。個人の場合は、M&Aマッチングサイトを利用するのが一般的です。また、各都道府県に設置されている公的相談窓口「事業承継・引継ぎ支援センター」でも、買収できる案件を探せます。利用しやすい方法を活用しながら、希望に合った買収先を探しましょう。
STEP3. 買収先候補と面談する
買収したい会社が見つかったら、相手先との面談を行います。面談までの流れとしては、まず、売り手と秘密保持契約を締結した後、基礎情報を交換します。そして、企業概要書の開示とそれに基づく質疑応答を行い、両者に進展の意向がある場合、トップ面談を行うのが一般的です。その後、買い手から売り手へ、M&Aを行う意思と大まかな条件を記載した意向表明書を提出します。
双方が納得できるまで、条件の詳細を話し合いましょう。
STEP4. 買収先候補と基本合意契約を結ぶ
面談が終わり、意向表明書の条件でM&Aを進めることに双方が合意できたら、基本合意書を締結します。基本合意書には、例えば売却金額や今後のスケジュール、デューデリジェンス(企業監査)への協力義務といった条件面についての具体的な内容が記載されます。
基本合意契約の買収条件部分は仮契約という位置付けで、秘密保持条項や損害賠償条項については法的拘束力を持たせることが一般的です。契約としての拘束力が発生するため、内容は慎重に検討しましょう。
STEP5. 買収先候補のデューデリジェンスを行う
基本合意書を締結後、最終条件交渉を行う前に、売り手の内部状況を知るためにデューデリジェンスを行います。デューデリジェンスの結果に基づいて、例えば売り手対象会社の財産・負債・リスクなどを確認し、売却金額の妥当性や最終契約に盛り込むべき条件を検討します。
デューデリジェンスは、税理士・公認会計士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。個人の場合は、M&Aマッチングサービスで用意されている簡易デューデリジェンスの利用も検討してみてはいかがでしょうか。
STEP6. 買収する企業と最終契約を結ぶ
デューデリジェンスが終わったら、これまでの合意事項やデューデリジェンスでの結果を踏まえて最終条件の交渉を行い、最終契約書を締結します。最終契約書には、売却金額や退職金の処理、役員・従業員の処遇、表明保証の履行といった必要事項が記載されます。
最終契約書の締結後、株式譲渡や事業譲渡の手続き、譲渡代金の受け取りなどを行うクロージングへと進み、M&Aは完了です。手続きに時間はかかりますが、時間をかけすぎると交渉相手の姿勢が変化することもあるため、可能な限り迅速に進めましょう。
※M&Aによる起業については以下の記事を併せてご覧ください
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
起業に必要な手続きを手軽に行う方法
起業に必要な会社設立の手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」です。
「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。設立する法人形態によって異なる必要書類も、「弥生のかんたん会社設立」であれば、画面の指示に従うだけで自動的に作成されます。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。
また、「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。専門家を探す手間を省けるほか、電子定款や設立登記書類の作成、公証役場への定款認証などの各種手続きを依頼でき、確実かつスピーディーな会社設立が可能です。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、サービス利用料金は実質0円になります。なお、登録免許税など、行政機関の手数料は別途発生します。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
起業・開業する際は目的や強みを考慮して業種を選ぼう
起業・開業する業種を選ぶ際には、自分の目的や強み、市場の動向など、さまざまな検討ポイントがあります。一般的に起業・開業しやすいといわれる業種を参考にしながら、自分がやりたいかどうか、経験やスキルを活かせるかどうかなども考慮して業種を選びましょう。
また、起業・開業したい業種が見つかったら、その業種で既に事業を展開している会社を買収するM&Aを検討するのも良いかもしれません。業種の選び方を押さえたうえで、自分に合った方法で事業をスタートさせてください。
業種が決まり、起業・開業する目処が立ったら、起業・開業に伴う煩雑な手続きは「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」で効率化するのもおすすめです。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者渡辺亨(中小企業診断士)
株式会社リノヴェクス代表取締役。経営者を助けるプロコーチ/コンサルタント/中小企業診断士/M&Aプロアドバイザー/ドリームゲートアドバイザー
コーチングを主軸とした人材育成サービスを行う、株式会社リノヴェクスを運営する傍ら、プロコーチ・トレーナー・人材育成コンサルタントとしても活動している。一般財団法人日本コーチング教育振興協会(ACEAジャパン)代表理事も務め、経営層や事業主に向けたエグゼクティブコーチングを行っている。