会社設立時の社会保険の必要書類、手続き方法を解説!サラリーマンの副業も加入は必要?
監修者: 勝山 未夢(社会保険労務士)
更新
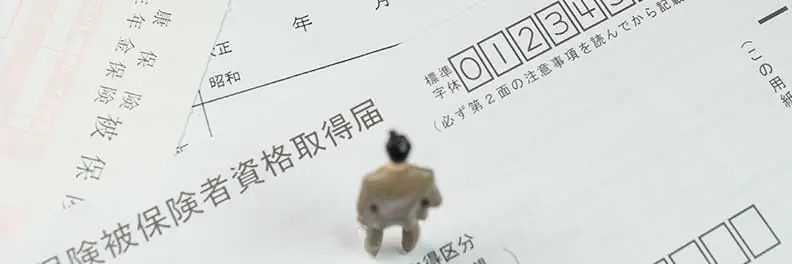
会社設立時に必要となるのが、社会保険への加入手続きです。しかし初めて会社を起こす方の場合、「会社設立時の社会保険加入のルールがわからない」「どのような書類をいつまで提出すればよいのかわからない」といった疑問や不安があるのではないでしょうか。
本記事では、会社設立時に知っておくべき社会保険の加入義務や手続きの流れ、必要書類を解説します。具体例を交えながら説明するので、初めて会社設立する方はぜひご活用ください。また、会社設立の手続きには「弥生のかんたん会社設立」をご利用ください。手順に沿って進めるだけで、株式会社や合同会社がかんたん、オトクに設立できます。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立時に社会保険への加入は必須
社会保険とは、病気やケガ、失業、障害などに対して、従業員の生活を保障する保険のことです。以下のように5種類の保険があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険(40歳以上が対象)
- 雇用保険
- 労災保険
特に会社(法人)を設立した際に、必ず加入する必要があるのが、健康保険と厚生年金保険です。健康保険法第3条・厚生年金保険法第6条により、加入が義務付けられています。
病気やケガ、失業で働けない期間に補償が受けられる雇用保険と労災保険(労働保険)は、従業員を雇用するかどうかで加入義務が変わります。今後アルバイトや、正社員を雇う予定がある場合、雇用保険と労災保険への加入手続きも視野に入れておきましょう。
なお、従業員を雇わない一人社長の場合でも、役員報酬を設定していれば社会保険への加入は必須です。雇用保険と労災保険は労働者の保険のため経営者の加入は不要ですが、健康保険と厚生年金保険は忘れずに加入しましょう。
一人社長の社会保険加入について、こちらの記事で解説しています。
サラリーマンが副業で会社設立する場合は役員報酬の有無で異なる
サラリーマンが副業で会社を設立する場合の社会保険の加入義務は、役員報酬の有無によって異なります(1人で起業する場合も同じです)。
前提として役員報酬を0に設定した場合、報酬から社会保険の保険料を徴収できないため、非加入の扱いとなります。その一方で、役員報酬を設定している場合は、副業であっても健康保険・厚生年金保険への加入が求められます。本業(サラリーマン)と、設立した会社の報酬を案分して新しい社会保険料が算出されます。新しく算出された社会保険料は、本業の会社にも通知されます。
就業規則で副業を制限している企業の場合、トラブルの原因となる場合もあるため注意が必要です。まずは会社設立の前に、勤務先で副業を認められているかを確認し、本業・副業の双方でうまくバランスを取りながら報酬を設定するのがベストでしょう。
また本業の会社に通知されたくないために、報酬があるにもかかわらず0と申告してはなりません。その罰則やペナルティは、後述の「社会保険未加入だと罰則を受ける可能性」で解説します。
社会保険未加入だと罰則を受ける可能性
前述のとおり、社会保険の加入は原則として法人の義務です。健康保険・厚生年金に加入しなかった場合、年金事務所から加入要請が届き、加入要請に応じない場合、さらに立入検査の警告文が届きます。
警告文が届いたタイミングで加入した場合、加入後に未納分の保険料を納めるだけで済みます。しかし警告文が届いた後も加入しない場合、立ち入り検査後に強制加入となります。「従業員がいないし、最初のうちは社会保険に入らなくてもバレないだろう」と考えていると、後になって思わぬ事態を招くかもしれません。例えば以下のような例です。
-
- 会社設立後、一人社長として小規模な事業を開始
- 役員報酬を得ていたが、社会保険料を支払うのを避けるため、あえて未加入で経営活動を行う
- ある日、年金事務所からの通知を無視した結果、警告文や立ち入り検査を受け、過去2年分ほどの未納保険料+延滞金の支払いを請求される
- 予想外に高額な支出が発生し、キャッシュフローが悪化。資金がなく、経営活動に悪影響がでる
報酬があるにもかかわらず社会保険に未加入の場合、罰則を受けることとなります。必ず正しい手続きを行いしましょう。
社会保険費用の支払い期日は翌月末日
健康保険・厚生年金保険の保険料は、「当月分を翌月末日までに支払う」のが原則です。例えば6月分の保険料は、7月末日までに納付しなければなりません。納付が遅れると、年金事務所から督促があったり、延滞金が加算されたりします。
社会保険料(健康保険/厚生年金保険/40歳以上の場合は介護保険を含む)は、会社負担と個人負担が1:1で折半となるしくみです。
- 【東京都・標準報酬月額30万円(介護保険加入なし)の場合】
-
- 会社負担:約42,315円
- 本人負担:約42,315円
- 会社+個人の合計:月額約84,630円
1人社長の場合でも、自分が「被保険者」となります。会社として支払う分と、自分の給与から引かれる分を合わせて、報酬額を決めましょう。
社会保険料の計算方法について、こちらの記事で解説しています。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
【全体フロー】会社設立時の社会保険手続きまとめ
保険の種類ごとの加入義務や、提出先・管轄を把握していると、手続きがスムーズに進みます。まずは、「役員報酬を受け取るか」「従業員を雇うか」で必要な保険を判断しましょう。
| 保険の種類 | 加入義務があるケース | 提出先・管轄 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 | 会社を設立して、役員報酬ありで事業を開始する場合(一人社長も含む) | 年金事務所(日本年金機構) |
| 労災保険 | 従業員を1名以上雇用している場合 | 労働基準監督署 |
| 雇用保険 | 従業員が1週間に20時間以上働き、雇用されてから31日以上の働く見込みがある場合など | ハローワーク(公共職業安定所) |
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
【健康保険・厚生年金編】会社設立における社会保険の加入に必要な書類
法人を設立した際には、設立後5日以内に健康保険・厚生年金保険への加入手続きが必要です。提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所となります。例えば事業所が東京都渋谷区の場合、管轄は渋谷年金事務所です。法人登記が完了次第、管轄の年金事務所へ電子申請または窓口提出・郵送のいずれかの方法で提出しましょう。
【必要な提出書類】
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(従業員・社長が健康保険・厚生年金保険に加入するとき)
- 健康保険 被扶養者(異動)届(家族を被扶養者にするとき)
| 書類名 | 提出先 | 提出期限 | 必要な書類 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | 法人設立後5日以内 |
|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 年金事務所 | 雇用日から5日以内 | – |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 年金事務所 | 事由発生日から5日以内 |
|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険 新規適用届は、法人が健康保険・厚生年金へ初めて加入する際に提出する書類です。提出時には、以下の書類を準備する必要があります。
- 法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)
- 法人番号指定通知書のコピー
法人登記謄本は、書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本を提出しましょう。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
従業員を採用した後、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要です。役員・従業員を含めた対象者全員分を提出します。従業員が退職して社会保険の喪失手続きを行う場合は、退職の翌日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出しましょう。
健康保険 被扶養者(異動)届
家族を被扶養者にする場合、「健康保険被扶養者(異動)届」が必要です。被扶養者として認められる家族を以下にまとめました。
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母等の直系尊属
- 三親等内の親族(同居が条件)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(同居が条件)
また扶養家族の続柄を証明するために、以下の書類提出が求められます。
- 戸籍謄本(抄本)or住民票の写し(続柄記載のもの)
- 退職証明書や離職票、課税(非課税)証明書など収入が130万円以下であることを示す書類
住民票の写しが認められるのは、認定を受ける人が同居し、被保険者が世帯主であるときに限ります。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
【労災保険編】会社設立時における社会保険の加入に必要な書類
初めて従業員を雇用する場合、業務上のケガや通勤時の災害に備える労災保険(労働基準監督署が管轄)の加入が必須です。必要な提出書類は以下のとおりです。
- 保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
| 書類名 | 提出先 | 提出期限 | 必要な書類 |
|---|---|---|---|
| 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 労働者と保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 |
|
| 労働保険概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 | – |
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
保険関係成立届
保険関係成立届は、労働基準監督署へ提出する書類です。
- 所轄の労働基準監督署
- ハローワーク
これらの場所で保険関係成立届の書類を入手できるため、郵送で請求するか取りに行きましょう。注意点として、インターネット上に保険関係成立届のサンプルや記入例が掲載されていますが、保険関係成立届は特殊な用紙が使用されているため、ダウンロードして印刷した書類は使用できません。また手続きに必要な書類は、労働基準監督署によって異なります。電話で問い合わせるなど、事前に確認するようにしましょう
労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書は、労働基準監督署へ提出する書類です。所轄の労働基準監督署かハローワークに郵送で請求するか、取りに行く必要があります。
申告書には、当該年度分の概算の労働保険料を計算して記入するようにしましょう。
計算式:(労働保険料)=(賃金総額)×労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)
申告書と同時に保険料の納付が求められます。添付書類は労働基準監督署によって異なるため、事前に確認しましょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
【雇用保険編】会社設立時における社会保険の加入に必要な書類
雇用保険は、従業員が失業した場合の給付や育児休業などに対応する保険です。労災保険の申請が終わり次第、次は雇用保険の加入手続きを進めましょう。雇用保険の加入手続きは、事業所を管轄するハローワークで行います。以下の2種類の書類を提出しましょう。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
| 書類名 | 提出先 | 提出タイミング | 必要な書類 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内 |
|
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出 |
|
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所設置届は、保険関係成立届の申請が終わり次第、申請ができるようになります。申請書類は、ハローワークインターネットサービスから様式(用紙)のダウンロードが可能です。申請する際は以下の添付書類が必要です。
- 保険関係成立届の事業主控え
- 登記事項証明書
- 事業認可証・工事契約書・不動産契約書など事業実態がわかる書類
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険適用事務所設置届と一緒に提出する書類です。雇用保険被保険者資格取得届も、ハローワークインターネットサービスから様式のダウンロードが可能です。申請の際に必要な添付書類は以下のとおりです。
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 出席簿
- 賃金台帳など
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
独立する方も副業で起業する方もあんしん!弥生のかんたん会社設立でらくらく手続き
会社設立時の社会保険(健康保険・厚生年金保険、労災保険、雇用保険)の手続きや必要書類をまとめました。しかしながら、申請に必要な書類が多く、それぞれ提出先が異なるため、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。早く事業をスタートして売上を立てなければならないのに、
- 書類用紙を探し回る
- 誤字脱字や記載漏れがないか確認する
- 書類を提出するために複数の役所を回る日程調整をする
など手間が多く躊躇してしまう方もいます。そのような方におすすめしたいのが、「弥生のかんたん会社設立」です。
画面の操作に従うだけで、会社設立に必要な手続きを進められます。初めて会社を設立する方も、副業で起業する方もかんたんに手続きを行い、会社を設立できます。もちろん株式会社だけでなく、合同会社の手続きも可能です。弥生のかんたん会社設立は無料で利用できるので、ぜひご活用ください。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立の社会保険に関するよくある質問
会社設立の社会保険に関するよくある質問をまとめました。
会社設立後の社会保険の手続きが5日を過ぎた場合はどうすればいい?
会社設立後の社会保険の手続きが5日過ぎた場合でも、さかのぼって支払いできます。早めに管轄の年金事務所に問い合わせて、支払いの意思があることを伝えましょう。手続きが遅れ、年金事務所からの連絡を無視し続けると、警告文や立ち入り検査を受ける可能性があります。安心して事業活動を行うためにも、早めに行動するのがおすすめです。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立の際に社会保険の加入は義務!弥生のかんたん会社設立でルールを守って手続き
本記事では、会社設立時の社会保険の加入ルールや申請時の必要書類などを解説しました。
-
- ポイント1:法人設立時に健康保険や厚生年金への加入は義務
- ポイント2:労災保険・雇用保険は従業員を雇ったら加入する必要がある
- ポイント3:各種申請書類ごとに管轄や提出期日が異なるためしっかり確認する
会社設立の手続きに手間はかかりますが、きちんとした手順に則れば、だれでも自分の会社を持てます。社会保険のルールを守り従業員の安心を確保して、事業を始めましょう。
会社設立の手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」です。画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できます。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。無料で利用できるので、これから会社設立を検討している方はぜひご活用ください。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者勝山 未夢(社会保険労務士)
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ所属社労士。立命館大学法学部国際法務特修卒業後、新卒より社会保険労務士法人にて勤務。









