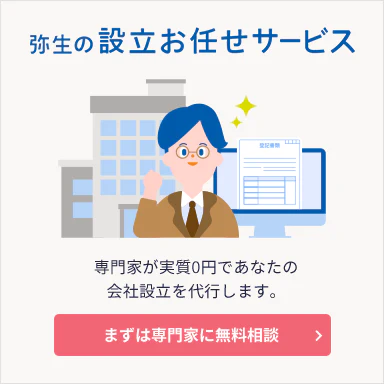脱サラ起業とは?失敗する理由と成功させるための手順を解説
監修者: 渡辺亨(中小企業診断士)
更新

働き方の多様化が進む中、サラリーマンとして働くのではなく、脱サラして起業する道を選ぶ人も少なくありません。その一方で、脱サラ起業は失敗しやすいといわれることもあるため、注意が必要です。では、脱サラ起業にはどのような特徴があり、どのように準備すれば成功しやすいのでしょうか。
本記事では、脱サラ起業の注意点や失敗する場合の理由、成功させるための手順のほか、必要な手続きを手軽に行う方法などについて解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
脱サラ起業とは、会社を退職して自分で事業を始めること
脱サラ起業とは、会社を退職して自分で事業を始めることです。脱サラは脱サラリーマンの略で、会社を辞めることを意味しています。また、起業とは新しく事業を起こすことで、広い意味では個人事業主として開業することも含まれますが、一般的には起業というと法人を設立して事業を立ち上げることを指します。
つまり、脱サラ起業とは、会社に雇用されるサラリーマンという立場から、独立して自ら会社の経営者になることです。
起業時の年齢や起業する業種については、以下のような調査結果が公表されているため、脱サラ起業を考えている方はこれらの情報も参考にして検討してみましょう。
起業者の平均年齢は43.7歳で、70.9%が脱サラ起業
日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によると、起業時の平均年齢は43.7歳で、直前の職業については70.9%が正社員・正職員です。年代については、最も多いのが40代で37.8%、ついで30代が30.1%です。起業者の中心になっているのは、30~40代で脱サラ起業をした方といえます。
この調査から、サラリーマンとして経験を積んで、起業に踏み切るケースが多いと考えられます。勤務経験を積んで経営の場で自分の力を試したい場合は、起業を検討してみてはいかがでしょうか。
自分の経験を活かせる業種で起業するケースが多い
日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によれば、仕事をした経験のある事業に関連する事業で起業した人は84.4%となっていて、自分の経験を活かせる業種で起業するケースが多いといえます。また、起業した事業の決定理由として、最も多かった回答は「これまでの仕事の経験や技能を生かせるから」(43.9%)で、ついで「身につけた資格や知識を生かせるから」(23.2%)といった結果となっています。
サラリーマンとしての経験を活かせる事業アイディアが浮かんだ場合は、起業を検討してみましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
脱サラ起業をするとさまざまなメリットがある
脱サラ起業には、サラリーマンとして勤務している場合に比べて、やりがいや収入などの面でさまざまなメリットがあります。主なメリットとしては以下の3点があげられます。脱サラを検討する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
脱サラ起業をするメリット
- 自分のアイディアを形にできる
- 働き方の自由度が上がる
- 収入をアップできる可能性がある
自分のアイディアを形にできる
脱サラ起業のメリットの1つが、自分のビジネスアイディアを実際の商品やサービスとして形にできることです。脱サラ起業をすると、事業内容を自由に決められるため、自分にとって理想的な商品・サービスを実現できる可能性があります。
例えば、サラリーマンとして仕事をしている中で商品やサービスの内容を工夫したくなったとしても、会社の方針に合わなければ実現は困難です。自分の判断で事業を進めたい場合は、脱サラ起業を検討してみましょう。
働き方の自由度が上がる
脱サラ起業のメリットの1つが、働き方の自由度が上がることです。会社員は、就業規則によって勤務時間や勤務場所、休日などが定められており、上司の指示に従って業務を遂行する必要があるため、どうしても働き方に制約はありますが、起業した場合は働き方を自分で決められます。業務や利益に影響がないのであれば、例えば働く場所を自宅メインにしたり、始業時間を自分の裁量で決めたりすることが可能です。
働き方を模索している場合も、脱サラ起業を検討してみてはいかがでしょうか。
収入をアップできる可能性がある
脱サラ起業のメリットの1つが、収入をアップできる可能性があることです。起業すると、自分の役員報酬をいくらにするかを自分で決めることができ、基本的に役員報酬に上限はないため、サラリーマンとして働く場合よりも収入がアップする可能性があります。
サラリーマンの場合は、勤務先によって決められた給与制度をベースに収入が決まるため、基本的に収入アップも制度の範囲内でしか実現できません。サラリーマンとして働く場合よりも高い収入を目指したい方は、脱サラ起業も選択肢の1つとして検討してみましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
脱サラ起業をする際は注意点がある
脱サラ起業には、メリットがある一方で注意点もあります。サラリーマンとは働き方が変わるため、注意点を押さえておかなければ生活に影響が出る可能性もあります。脱サラ起業を検討する場合は、以下の注意点も把握しておきましょう。
脱サラ起業をする際の注意点
- 収入が不安定になることがある
- 自己責任の範囲が広がる
- 事務処理の負担が増える
収入が不安定になることがある
個人事業主として脱サラ起業をした場合、収入をアップできる可能性もありますが、収入が不安定になることがある点に注意が必要です。この場合、自分の収入は事業の利益しだいとなるため、利益が多かった年と少なかった年で収入が変わることも珍しくありません。例えば、まったく利益が出なければ、収入ゼロということもあり得ます。
起業しても、事業が軌道に乗るまでに時間がかかるケースは少なくありません。個人事業主で脱サラ起業をする場合は、当面の生活費も確保しておくようにしましょう。
自己責任の範囲が広がる
脱サラ起業をした場合、自己責任の範囲が広がる点に注意が必要です。起業すると、会社の意思決定についてすべて自分で決め、その結果について責任を負わなければならないため、経営がうまくいかずに損失が出れば、場合によっては自分の報酬を減らして対応する必要があります。会社員のように、上司や会社に頼ることはできません。
例えば、従業員を雇用する場合、安全な職場環境に配慮し、給与を支払い、従業員の生活を支える責任も生じます。サラリーマンに比べてさまざまな責任を負うことになるため、その責任を自覚して慎重な判断を心掛けるようにしましょう。
事務処理の負担が増える
脱サラ起業をした場合、事務処理の負担が増える点にも注意が必要です。サラリーマンであれば勤務先が行ってくれる業務も、経営者になったら自分の責任で対応しなければならないため、負担の増加を意識しておく必要があります。例えば、法人の決算や税務申告などは手続きが煩雑になるため、決算期には事務作業に忙殺される可能性があります。
会計や決算にかかわる業務をスムーズに行うには、会計ソフトを導入するのが効果的です。弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」なら、簿記や会計の知識がなくても帳簿や決算書の作成が可能です。
また、会計ソフトを利用する場合も、税務申告は税理士に依頼するケースもあります。自分で対応できない場合は、税理士の手を借りることも検討しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
脱サラ起業で失敗する場合は理由がある
脱サラ起業は、失敗しやすいといわれることもありますが、失敗する際には理由があります。失敗を避けるために、脱サラ起業が失敗する理由を把握しておかなければなりません。
脱サラ起業が失敗する背景には以下のような理由があるため、起業を考える際はあらかじめ対策を検討してみてはいかがでしょうか。
脱サラ起業が失敗する場合の理由
- マーケティングが不足していた
- サラリーマンから経営者へ意識の変化ができていなかった
- 資金計画が不十分だった
※起業に失敗する理由については以下の記事を併せてご覧ください
マーケティングが不足していた
脱サラ起業で失敗する理由の1つは、事前のマーケティング調査が十分行われていないことです。マーケティング調査を行って情報を正しく分析できていなければ、起業しても顧客を獲得するのが難しくなるため、事業に失敗する可能性が高まります。
起業にあたっては、例えば、展開しようとしている事業の市場規模や動向、競合他社の状況、ターゲット層のニーズなどを把握しておく必要があります。国や自治体、関連団体の統計データを活用したり、現地調査やアンケート調査を行ったりするなど、個人でも行える方法を検討してみましょう。
サラリーマンから経営者へ意識の変化ができていなかった
脱サラ起業で失敗する理由の1つは、サラリーマンから経営者へ意識の変化ができていないことです。サラリーマンの場合は業務を行う方針が勤務先から示されますが、経営者は自分で事業の進め方を決めなければならないため、意識の切り替えが不十分だと、事業が滞ったり想定した利益を得られなくなったりする可能性があります。
例えば、商品やサービスの内容、業務フロー、目指すべき数値目標など、事業をうまく進めるためのしくみを自分の判断で構築していかなければなりません。経営者として判断すべき事柄は、人任せにせず主体的に判断するようにしましょう。
資金計画が不十分だった
脱サラ起業で失敗する理由の1つは、資金計画が不十分なことです。副業からスタートしたり、個人事業主として開業したりする方法があります。起業してから必要になる資金の見込みが甘いと、運転資金がショートしてしまうため、事業を継続できなくなる可能性もあります。
起業の際には、設備費のような初期投資以外に、運転資金の確保が必要です。運転資金とは、例えば店舗やオフィスの家賃、仕入代、従業員の給与など、事業を継続して運営するために必要な資金のことです。起業前に、設備資金、運転資金、経営者自身の生活費を含めた資金計画を立てなければなりません。
資金計画を立てた結果、自己資金だけでは不安がある場合は、融資による資金調達も検討する必要があります。サラリーマンは事業資金の融資を受ける機会がないため、融資を受けるのは避けたいと考える方もいるかもしれませんが、安定した事業の運営には、余裕のある資金計画が必要です。資金計画について迷う場合は、税理士や公認会計士などの専門家に相談することも検討しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
脱サラ起業をするには、ゼロから会社を設立する以外にも選択肢がある
脱サラ起業をする方法には、自分でゼロから会社を設立する以外にも、さまざまな選択肢があります。既存のしくみを活用する方法もあります。自分が行いたい事業や理想の将来像をイメージしながら、以下の方法の中から、どのような方法を選ぶかを考えてみてはいかがでしょうか。
会社設立以外の脱サラ起業の選択肢
- 副業や個人事業主から始める
- フランチャイズチェーンに加盟する
- M&Aを利用して会社を買収する
副業や個人事業主から始める
将来的に脱サラ起業を目指していても、いきなり会社を設立するのではなく、副業からスタートしたり、個人事業主として開業したりする方法があります。
脱サラして会社を設立すると収入が不安定になるおそれがあるため、副業でスタートしてサラリーマンとしての安定した収入を得ながら、事業を運営する経験を積むケースもあります。ただし、サラリーマンとしての業務に加えて副業の労力もかかるため、労力の配分を管理しなければなりません。
また、会社を退職して独立する場合でも、例えば最初は個人事業主として開業して、事業が軌道に乗ってきてから法人化を検討するといったことも可能です。いきなり会社を設立して起業するのに不安がある場合は、副業や個人事業主から始めることも検討してみましょう。
フランチャイズチェーンに加盟する
脱サラ起業では、フランチャイズチェーンに加盟し、フランチャイズオーナーとして経営者になる方法もあります。フランチャイズであれば、販売や経営のノウハウがパッケージ化されているため、他の方法に比べて少ないリスクで起業することが可能です。
ただし、フランチャイズ経営については、例えば商品のメニューも追加できない場合があるなど、フランチャイズ本部の意向による制約があるため、自由に経営したい場合は他の方法を検討しましょう。
M&Aを利用して会社を買収する
脱サラ起業には、M&Aを利用して会社を買収する方法もあります。M&Aを利用すると、自分で会社を設立するよりも手間を抑えることができ、安定した事業モデルを引き継げるため、効率的に起業できます。例えば、商品やサービス、ターゲット、販売チャネル、集客方法、資金繰りなどをゼロから考える必要はありません。また、既にビジネスモデルが確立されているため、リスクや課題を予測しやすいといった特徴もあります。
ただし、自分が起業したい業種のイメージがある場合に、その業種の案件が市場に出ているかどうかはわかりません。市場に出ていたとしても、サラリーマンの貯蓄で買収できる規模を超えた売却希望額が提示されている場合もあります。
M&Aによる起業が気になる場合は、Web上でM&Aの案件探しができるM&Aマッチングサイトを確認してみて、情報収集するところから始めてみてはいかがでしょうか。
※サラリーマンによるM&Aについては以下の記事を併せてご覧ください
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
脱サラ起業を成功させるための手順がある
脱サラ起業を成功させるためには、一定の手順に沿って進めるのが有効です。手順を押さえておけば、順をおって起業に向けた課題を1つずつ解決できるため、事業が成功する可能性を高めることができます。以下の流れに沿って、準備しましょう。
脱サラ起業を成功させるための手順
-
STEP1. 起業する目的を決める
-
STEP2. 必要な情報を集め、ビジネスモデルを考える
-
STEP3. 事業計画書を作成する
-
STEP4. 起業に必要な資金を準備する
-
STEP5. 会社に退職の意思を伝える
-
STEP6. 起業する
STEP1. 起業する目的を決める
最初に、自分がなぜ起業したいのか、その目的や理由を考えます。ビジネスモデルや事業計画を立案していく際の判断の軸にもなるため、起業の目的は最初に検討しなければなりません。
例えば、日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によると、起業した動機について最も多かったのは、「自由に仕事がしたかった」といった回答でした。ついで、「仕事の経験・知識や資格を活かしたかった」「収入を増やしたかった」「自分の技術やアイディアを事業化したかった」などの回答があげられています。
脱サラ起業で何をしたいのか、自分にどのようなメリットがあるのかを明確にしておきましょう。
STEP2. 必要な情報を集め、ビジネスモデルを考える
起業する目的を決めたら、市場規模や競合他社の状況などの必要な情報を集め、ビジネスモデルを考えます。事業の成功には、顧客に選ばれる理由が必要となるため、市場の調査・分析とそれに基づいたビジネスモデルが不可欠です。
市場調査については、例えば国や自治体、関連団体などが実施した統計データを活用すれば、個人でもある程度は市場規模をつかむことができます。実店舗をオープンさせる場合は、出店予定エリアの地域特性や住んでいる人の傾向などを調べることも可能です。
ターゲット層のニーズを分析し、具体的な販売戦略を立てましょう。
STEP3. 事業計画書を作成する
ビジネスモデルを決定したら、それを基に事業計画書を作成します。事業計画書を作成する過程で、どれだけの利益を獲得できそうかが明確になってくるため、脱サラ起業の成功の見込みも判断できるようになります。また、融資を受けて資金調達をする際にも事業計画書は必要です。
事業計画書とは、例えば、事業内容や戦略、収益見込みなど、事業をどのように展開していくかを具体的にまとめた計画書です。起業した後に資金不足で困らないように、現実的な事業計画を立てましょう。
専門家に頼らず、自力で事業計画書を作るには、弥生の資金調達ナビ「創業計画をつくる」が便利です。「創業計画をつくる」を利用すれば、創業費用や売上見込み金額などから創業後の利益や資金繰りを自動計算し、ビジネスプランを具体的な数値計画にすることができます。
STEP4. 起業に必要な資金を準備する
事業計画が作成したら、起業に必要な資金を準備します。事業計画によってビジネスにかかるコストが把握できるようになるため、何にいくらかかるかを取りまとめ、資金調達の方法を検討します。
起業に必要な資金としてあげられるのは、設備資金と運転資金の2つです。資金を準備する方法としては、例えば、サラリーマンとして貯めた資金を活用する方法の他に、金融機関から融資を受けることも可能です。自己資金だけでは足りない場合は、資金調達方法を検討しましょう。
STEP5. 会社に退職の意思を伝える
起業に必要な資金を準備できたら、勤務先に退職の意思を伝えます。退職の意思表示のタイミングは就業規則によって異なるため、あらかじめ確認しておかなければなりません。例えば、退職希望日の1か月前と決められている場合もあれば、3か月と決められている場合もあります。引き継ぎにかかる期間も考慮し、余裕を持って伝えましょう。
STEP6. 起業する
退職の意志を伝えたら、起業の手続きを行います。起業に必要な手続きは、自分で会社を設立するのか、M&Aを利用するのかなどによって異なるため、事前に確認しておくことが必要です。例えば、会社を設立する場合は会社の概要を決めるところから始める必要がありますが、M&Aであれば買収の目的と予算を最初に検討します。
起業したい方法に応じて、起業に必要な手順を調べましょう。
※会社設立やM&Aの手順については以下の記事を併せてご覧ください
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
M&Aに必要な手続きを手軽に行う方法
M&Aを利用して脱サラ起業するケースは少なくありませんが、M&Aでは交渉力に加えて、財務や税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となり、すべての手続きを自力で進めるのは困難です。M&Aを成功させるには、専門家の力を借りるのは有効な選択肢といえます。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、M&Aや事業承継などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。紹介料は、一切かかりません。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
脱サラ起業をするなら、M&Aも検討しよう
脱サラ起業をするための方法の1つが、既にある会社や事業を買収するM&Aです。M&Aを利用すると、ゼロから起業するより手間を軽減でき、リスクを想定しやすいなどのメリットがあるため、起業の選択肢としてM&Aを検討する方も少なくありません。
脱サラ起業でM&Aを利用する場合は、専門家の活用がおすすめです。M&Aや事業承継に詳しい専門家に相談しながら、スムーズな起業を目指しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者渡辺亨(中小企業診断士)
株式会社リノヴェクス代表取締役。経営者を助けるプロコーチ/コンサルタント/中小企業診断士/M&Aプロアドバイザー/ドリームゲートアドバイザー
コーチングを主軸とした人材育成サービスを行う、株式会社リノヴェクスを運営する傍ら、プロコーチ・トレーナー・人材育成コンサルタントとしても活動している。一般財団法人日本コーチング教育振興協会(ACEAジャパン)代表理事も務め、経営層や事業主に向けたエグゼクティブコーチングを行っている。