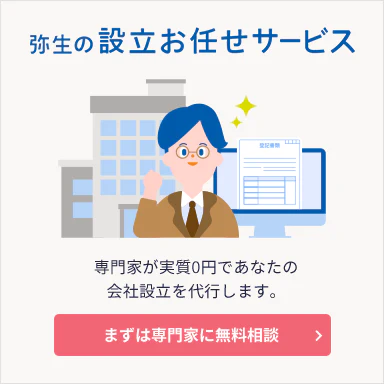会社形態の種類一覧と比較ポイントをわかりやすく解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

現在、新設立できる会社形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つです。4つの会社形態は、出資者の責任の範囲や経営スタイル、設立手続き、設立費用などがそれぞれ異なります。
新たに設立される会社の中で最も多いのは株式会社ですが、近年では合同会社を選ぶ経営者も増えています。会社設立時には、それぞれの特徴を把握したうえで、どの会社形態を選ぶかを決めなければなりません。
本記事では、株式会社、合同会社、会社合資、合名会社の4つの会社形態について、それぞれの特徴や比較する際のポイントなどをわかりやすく解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社形態を選ぶには、まずは種類を理解しておく
会社形態を選ぶには、種類を理解しておく必要があります。どのような種類があるのかを理解しておかないと、選べないためです。現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。
持分会社であるかどうかで種類が分けられる
新たに設立できる4つの会社形態のうち、株式会社を除く合同会社、合資会社、合名会社の3つを「持分会社」といい、株式会社と持分会社の違いは、所有と経営が分離しているかどうかです。
株式会社は、株式を発行して集めた資金をもとに経営する会社形態であり、出資者(株主)と経営者の役割が切り離されています。対して、持分会社は「出資者=経営者」であり、出資者自らが経営も行います。なお、持分会社では出資者のことを社員といいますが、これは従業員という意味ではありません。
自分が出資を行い、かつ、経営も行いたい方は持株会社を、株主からの出資により会社の経営のみを行いたい人は株式会社を選ぶ必要があることを留意しておきましょう。
出資者の責任範囲で種類が分けられる
4つの会社形態は出資者の責任範囲もそれぞれ異なり、「有限責任」と「無限責任」に分けられます。
万が一、会社が倒産した場合、有限責任の出資者は出資額以上の負債を負う必要はありませんが、無限責任を負う出資者は債権者に連帯して出資額以上の負債も負わなければなりません。
4つの会社形態のうち、株式会社の出資者(株主)と合同会社の出資者(社員)は有限責任です。それに対して、合資会社は無限責任社員1名以上と有限責任社員1名以上、合名会社は無限責任社員のみで構成されます。
会社が倒産した際に出資額以上の負債を負いたくない方は、有限責任の株式会社または合同会社を選ぶことを検討してみてください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社形態を選ぶには、特徴も押さえておく
会社形態を選ぶには、それぞれの特徴も押さえておきましょう。会社形態ごとの特徴を知らないと、どの会社形態が自分に合うのかが分からないためです。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの会社形態には、所有と経営の在り方や出資者の責任範囲の他にも、さまざまな違いがあります。
新規に設立が可能な4つの会社形態のうち、最も数が多いのは株式会社、次いで合同会社です。法務省「登記統計 商業・法人 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」(2023年6月)によると、会社形態別の設立登記の件数は、以下のとおりです。
| 会社形態 | 登記件数 |
|---|---|
| 株式会社 | 8,298件 |
| 合同会社 | 3,282件 |
| 合資会社 | 0件 |
| 合名会社 | 1件 |
-
※出典:法務省「登記統計 商業・法人 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数
」(2023年6月)
会社を設立するなら、株式会社か合同会社のどちらかを選ぶ場合がほとんどです。
中でも株式会社が多いのは、他の会社形態よりも知名度が高いため、取引先や金融機関からの信頼を得やすかったり、資金調達の幅が広いため事業を拡大しやすかったりするといった理由が挙げられるでしょう。
以下の会社形態ごとの特徴を参考にしながら、自社の事業内容や取引先の状況なども考慮したうえで、最適な会社形態を選ぶようにしてください。
設立可能な会社形態
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
| 株式会社 | 持分会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | ||
| 資本金 | 1円~ | 1円~ | 規定なし | 規定なし |
| 出資者の名称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
| 最低出資者数 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 |
| 責任の範囲 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 無限責任 |
無限責任 |
| 最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員(出資者)総会 | 社員(出資者)総会 | 社員(出資者)総会 |
| 役員の任期 | 規定あり(通常2年、最長10年) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 決算公告義務 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 定款の認証 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 設立費用 | 約17万円~ | 約6万円~ | 約6万円~ | 約6万円~ |
株式会社
株式会社は、株式を発行することで資金を集め、事業を行います。株式による資金調達は、株式会社以外ではできません。
株式会社の特徴は、所有と経営が分離していることです。出資者である株主と経営者の役割は切り離されており、事業活動によって得た利益の一部は、配当金という形で株主に分配されます。なお、出資者(株主)は同一でも問題ありません。特に、小規模事業者の場合には、出資者が経営者となることが一般的です。
また、4つの会社形態のうち株式会社のみ、毎年の決算公告が義務付けられています。決算公告とは、会社の成績や財務状況を出資者(株主)および債権者に明らかにし、取引の安全性を保つために行うものです。
その他、株式会社は、会社設立時に公証役場で定款の認証を受けなくてはなりません。株式会社以外の3形態の会社は、定款の作成は必要ですが認証は不要です。株式による資金調達を行いたい方や、自ら出資は行わず会社の経営のみに専念したいという方は、株式会社を選ぶことを検討してみてください。
合同会社
合同会社は、2006年施行の会社法によって新しく設けられた会社形態で、日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれます。日本では新しい会社形態ですが、設立件数は年々増加傾向にあります。
合同会社の特徴は、出資者と経営者が同一ということです。出資者と経営者の役割が切り離されている株式会社とは異なり、合同会社では出資者(社員)=経営者であり、原則として全ての社員が経営に対する決定権を持ちます。出資者自身が経営を行うため、事業を行ううえで迅速な意思決定が可能な点が、合同会社のメリットといえるでしょう。
なお、複数の社員がいる場合、業務執行権を持つ業務執行社員や代表権を持つ代表社員を、定款で定めることができます。出資者(社員)の責任範囲は、株式会社と同様に有限責任です。
合同会社には、株式会社に比べて、設立にかかる初期費用が低いという特徴もあります。例えば、法人設立登記にかかる登録免許税は、株式会社が15万円からであるのに対して、合同会社は6万円からです。また、株式会社で必須となる定款認証が不要なので、また、株式会社で必須となる定款認証が不要なので、認証手数料(1.5万~5万円)がかかりません。さらに、決算公告義務もないため、決算公告に関する費用も不要です。
その一方で、株式会社に比べて知名度が低いことや、株式発行ができないため資金調達手段が限られるといったデメリットもあります。自ら出資と経営の両方を担いたい方や、設立にかかる初期費用を抑えたい方は、合同会社を選ぶことを検討してみましょう。
合資会社
合資会社は、合同会社と同様に、所有と経営が一致した持分会社です。設立方法や設立費用なども、基本的には合同会社と同じです。ただし、有限責任社員だけで構成される合同会社とは異なり、合資会社を設立するには、無限責任社員1名以上と有限責任社員1名以上が必要になります。
そのため、4つの会社形態の中で、合資会社だけは最低でも2人以上の社員がいないと設立することができません。もし、有限社員1人のみ、もしくは無限社員1人のみになってしまった場合には、他の会社形態への組織変更が必要になります。
また、株式会社や合同会社は資本金が最低1円以上必要ですが、合資会社と合名会社は資本金が0円でも設立可能という特徴があります。
これは、合資会社と合名会社には資本金の規定がなく、金銭による出資や現物出資の他に、労務の提供による労務出資や、自身の信用を会社に利用させることを目的とした信用出資が認められているからです。労務出資と信用出資は、いずれも無限責任社員にのみ認められる出資形態です。
ただ、無限責任社員は、倒産時などには会社の負債全額に対して責任を負わねばならず、個人の負担が非常に大きくなる可能性があります。そのため、2006年施行の会社法によって合同会社が創設されて以降は、あえて合資会社を選ぶメリットが少なくなり、近年では新設数が減っています。有限責任社員と無限責任社員で会社を構成したい方や労務出資・信用出資を行いたい方は、合資会社を検討してみてもいいでしょう。
合名会社
合名会社も、合同会社や合資会社と同じく、所有と経営が一致した持分会社です。設立方法や設立費用も、基本的には合同会社や合資会社と変わりません。また、合資会社と同様に資本金の規定はなく、資本金0円でも設立可能です。
合名会社の特徴は、出資者(社員)全員が無限責任社員であることが挙げられます。無限責任社員のみということは、複数の個人事業主で構成されているようなものです。無限責任社員は会社の負債に対してすべて責任を負わなければならないので、4つの会社形態の中で最も厳しい条件にある形態だといえるかもしれません。
合名会社も、2006年の会社法施行で合同会社が創設されて以降は、メリットをあまり得られないことから新規設立の数が減少しています。無限責任社員のみで会社を構成したい方は、合名会社を選ぶことを検討されてください。
- ※会社形態別のメリット・デメリットについては以下の記事を併せてご覧ください
- 株式会社設立の人数は何人から?従業員数・役員数の条件を解説
- 株式会社と合同会社の違いは?特徴とメリット・デメリットを解説
- 合同会社とは?特徴や役職、メリット・デメリット
- 合資会社とは?設立するメリットなどをわかりやすく解説
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社形態を比較する際のポイント
4つの会社形態にはそれぞれ特徴があります。会社形態を選ぶときには、以下のポイントを比較して検討すると、自社に会社形態が見つかりやすいでしょう。
会社形態を比較する際のポイント
- 会社設立時にかかる費用
- 会社経営をするうえでの意思決定のしやすさ
- 資金調達方法の幅広さ
- 出資者の責任範囲
- 会社形態の知名度
会社設立時にかかる費用
会社形態を比較する際のポイントは、設立時にかかる費用です。
会社設立に必要な費用は、株式会社が約17万円からであるのに対し、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)は6万円からと、最低金額に3倍ほどの差があります。持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)は6万円からと、最低金額に3倍ほどの差があります。
会社設立にあたって少しでも初期費用を少なくしたい場合には、持分会社を選んだ方がメリットは大きいでしょう。また、株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、持分会社は定款認証が不要なので、会社設立にかかる時間を短縮したい方も、持株会社を選ぶといいでしょう。
会社経営をするうえでの意思決定のしやすさ
会社形態を比較する際のポイントは、会社経営をするうえでの意思決定のしやすさも挙げられます。
株式会社は出資者と経営者が切り離されているため、重要事項を決定する際には株主総会の開催が必要です。
それに対して、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)は、出資者=経営者なので意思決定がスピーディーになり、経営の自由度が高くなります。また、持分会社は不特定多数の第三者からの出資を想定していないため、会社経営に第三者が介入しにくいという特徴もあります。会社の経営に自由度を持たせたいと考えている方は、持株会社を検討してみてください。
資金調達方法の幅広さ
会社形態を比較する際のポイントは、資金調達の幅広さもあります。
4つの会社形態のうち、株式会社だけが株式発行による資金調達が可能です。将来的に大規模な資金調達を考えている場合には、資金調達方法の幅が広い株式会社が向いているでしょう。
持分会社の場合は融資や補助金、助成金などが主な手段となり、株式会社に比べて資金調達の方法が限定されます。将来的に大規模な資金調達を行いたい方は、株式会社を選択してください。
出資者の責任範囲
会社形態を比較する際のポイントは、出資者の責任範囲もあるでしょう。
株式会社と合同会社は、出資者はすべて有限責任です。もし、会社が倒産した場合、出資したお金は返ってきませんが、それ以上の責任を問われることはありません。
その一方で、合資会社は有限責任社員と無限責任社員が各1名以上、合名会社は無限責任社員のみで構成されます。無限責任社員は、会社が倒産して債権を払いきれない場合、個人資産で債権者に支払わなければなりません。有限責任である株式会社や合同会社に比べて、出資者のリスクが大きいといえるでしょう。出資者のリスクをなるべく抑えたい方は、株式会社または合同会社を選びましょう。
会社形態の知名度
会社形態を比較する際のポイントは、会社形態の知名度も挙げられます。
4つの会社形態の中で、最も知名度が高いのは株式会社です。合同会社は最近増えてきているとはいえ、株式会社に比べれば数も少なく、それほど知名度は高くないのが現状といえます。合資会社や合名会社に至っては、そのような会社形態があることを知らない方もいるかもしれません。
会社形態の知名度が低いと、取引先に資金力不足といった誤った先入観を持たれたり、採用時に人材を集めにくかったりする可能性もあります。特に、大手企業と取引をしたい場合には、社会的な信用が必要になるため、株式会社を選んだ方がいいでしょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社形態は、会社設立後に変更することも可能
会社形態は、設立後に変更することもできます。例えば、早く会社を設立したい場合や、株式上場や資金調達のことはまだ決めていないというような場合、まず合同会社を設立し、事業が安定してから株式会社に変更するのもいいでしょう。反対に、所定の手続きを行えば、株式会社から合同会社への変更も可能です。
とはいうものの、設立後すぐに会社形態を変更することになると、再度登記が必要になり費用がかかってしまううえ、事業の開始が遅れてしまいます。どの会社形態を選ぶか迷ったときには、税理士や司法書士などの専門家に相談するのも1つの方法です。
弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」では、弥生が厳選した豊富な経験と実績のある税理士・会計事務所を無料でご紹介いたしますので、ぜひご活用ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立を手軽に行う方法
会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、自分でかんたんに書類作成ができる「弥生のかんたん会社設立」と、起業に強い専門家に会社設立手続きを依頼できる「弥生の設立お任せサービス」です。
「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。
また、「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。専門家を探す手間を省ける他、電子定款や設立登記書類の作成、公証役場への定款認証などの各種手続きを依頼でき、確実かつスピーディーな会社設立が可能です。
会社設立後、専門家と相談のうえ、会計事務所との税務顧問契約を結ぶと割引が受けられ、サービス利用料金は実質0円になります。なお、定款の認証手数料や登録免許税など、行政機関への支払いは別途必要です。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社形態の違いを知って、自社に合った形態を選ぼう
現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。実際には、株式会社もしくは合同会社のどちらかを選ぶことが一般的といえます。
会社形態を検討する際、会社の規模や事業内容、将来の目的などによって重視するポイントは変わります。それぞれの会社形態の特徴を理解したうえで、自社に合った形態を選択するようにしましょう。
また、会社設立の際には、さまざまな書類の作成や手続きが必要になります。スムーズに会社の設立を進めるには、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」の活用もご検討ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。