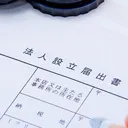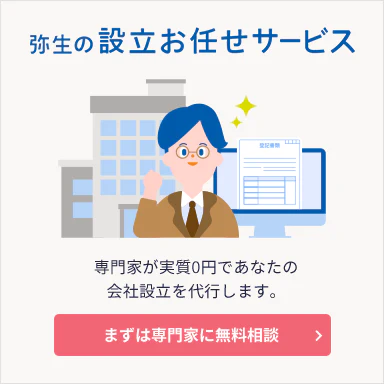新設法人とは?消費税の免除要件や免税期間が長くなる場合も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新
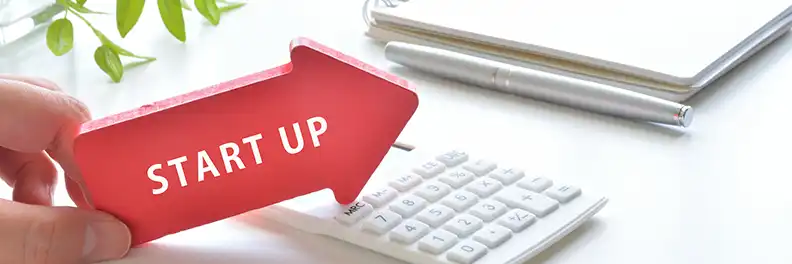
新たに設立された法人は、原則として、設立2期目まで消費税の納税義務が免除されます。ただし、新設法人がすべて消費税を免除されるわけではありません。
消費税の納税義務を免除される法人には、所定の要件が定められています。法人を設立後、できるだけ税負担を抑えるためには、消費税の納税義務を免除される要件を知っておくようにしましょう。
本記事では、消費税法で定義された新設法人の意味とともに、消費税が免除される場合の要件や消費税が免除にならない場合のほか、消費税の免税期間が長くなる場合についても解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
消費税法の新設法人とは、基準期間がなく資本金や出資金が1,000万円以上の法人のこと
新設法人には、文字どおりの新しく設立された法人という意味だけでなく、消費税法上で定義付けられた「基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人」という意味もあります。
新設法人は、原則として設立2期目まで消費税の納税義務が免除されますが、消費税法上の新設法人は資本金の額や出資の金額が1,000万円以上であるため、消費税の納税義務が免除されません。
この記事では、日本語の意味としての新設法人を「新設法人」、消費税法上における新設法人は「消費税法上の新設法人」として解説します。法人を設立する際には、消費税の納税義務について、どのような場合に免除となり、免除とならないのかを把握しておくようにしましょう。
消費税の納税義務では基準期間と特定期間が判定項目の1つになる
消費税の納税義務では、基準期間と特定期間が判定項目の1つになります。法人は、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じるため納めなければなりません。
法人の場合、基準期間と特定期間は、それぞれ以下のとおりです。
消費税の納税義務を判定する、法人における基準期間と特定期間
- 基準期間:前々事業年度
- 特定期間:前事業年度開始の日以後6か月の期間
新設法人は、原則2年間消費税を免除されます。設立2期目までは判定するための基準期間がないことにより、消費税の納税義務がありません。ただし、設立して2年以内の法人であっても、消費税の納税義務が免除されない場合もあるため注意しましょう。
法人の設立後2期目まで消費税が免除となるには要件がある
新設法人の場合、以下のいずれかの要件を満たしていれば、設立2期目まで消費税の納税義務が免除されます。なお、設立3期目以降の消費税の納税義務については、前述した基準期間と特定期間における課税売上高によって判定されるため、自社に納税義務が発生するか確認してみてください。
法人の設立後2期目まで消費税が免除となる要件
- 資本金または出資金が1,000万円未満である
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下である
- 特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下である
- 特定新規設立法人に該当しない法人である
資本金または出資金が1,000万円未満である
法人の設立後2期目まで消費税が免除となる要件として、資本金または出資金が1,000万円未満であることがあげられます。消費税法には、「事業年度の開始の日における資本金または出資の金額が1,000万円未満」という要件があるためです。
例えば、1期目の開始時点、つまり法人設立時点の資本金が1,000万円未満なら、1期目の消費税は免除されます。また、2期目開始時点でも資本金が1,000万円未満なら、2期目も引き続き消費税の納税義務が免除されます。
特定期間の課税売上高が1,000円以下である
法人の設立後2期目まで消費税が免除となる要件として、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であることもあげられます。この際の特定期間とは、設立1期目が開始してから6か月間を指します。例えば、新設法人は、基準期間も特定期間もないので、資本金が1,000万円未満なら1期目は消費税が免除されます。
ただし、1期目開始から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、2期目から消費税の納税義務が生じるため注意しましょう。
特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下である
法人の設立後2期目まで消費税が免除となる要件として、特定期間の給与等の支払い額の合計額が1,000万円以下であることもあげられます。上記の特定期間における課税売上高が1,000万円以下という要件は、給与等支払額の合計額でも判定することが可能であるためです。
例えば、設立1期目開始から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、設立1期目に続き2期目も消費税納税義務が免除されます。
なお、この給与等支払額は、発生ベースではなく支払いベースで判定されます。そのため、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えてしまった場合には、給与などの支払い金額を調整することも検討してみましょう。
特定新規設立法人に該当しない法人である
法人の設立後2期目まで消費税が免除となる要件として、特定新規設立法人に該当しない法人であることもあげられます。特定新規設立法人と判定される要件は、以下のとおりです。自社だけでなく他社もからむ複雑な要件なので、当てはまるかわからない場合には、税理士などの専門家に相談してみるといいでしょう。
特定新規設立法人と判定される要件
- 他の者が株式等の50%超を直接または間接に保有しているなど、その新しく設立された法人が支配される一定の条件に該当する
- 上記の他の者および他の者と一定の特殊な関係にある法人(特殊関係法人)のどちらかが、新規に設立する法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えている
※法人の設立後に消費税が免除される要件や注意点については以下の記事を併せてご覧ください
法人設立の1期目から消費税の納税義務が発生する場合がある
新設法人でも、条件によっては、設立1期目から消費税の納税義務が発生する場合があります。設立1期目から消費税を納税しなければならないのは、以下いずれかに当てはまるようなケースです。免税要件を満たしているつもりでも、実は消費税の納税義務があったということにならないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
法人設立の1期目から消費税の納税義務が発生する場合
- 資本金が1,000万円以上で消費税法の新設法人に該当する
- 特定新規設立法人に該当する
- 設立時からインボイス制度に対応し、課税事業者を選択する
資本金が1,000万円以上で消費税法上の新設法人に該当する
資本金が1,000万円以上で消費税法上の新設法人に該当する場合、法人設立の1期目から消費税の納税義務が発生します。
消費税法では、事業年度開始の日における資本金または出資の金額が1,000万円以上の法人は、消費税法上の新設法人に該当し、設立1期目から消費税の納税義務が生じると定められています。基準期間や特定期間の課税売上高は関係ないため、注意しましょう。
特定新規設立法人に該当する
特定新規設立法人に該当する場合、消費税法で設立1期目から消費税の納税義務が発生すると定められています。前述したように特定新規設立法人と判定される要件は複雑なので、もし判定に迷う場合には、専門家に相談しながら設立準備を進めるようにしましょう。
設立時からインボイス制度に対応し、適格請求書発行事業者を選択した場合
法人設立の1期目から消費税の納税義務が発生するのは、設立時からインボイス制度に対応し、適格請求書発行事業者になった場合があげられます。2023年から始まった適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するため、設立時から適格請求書発行事業者になる場合は基準期間と特定期間の判定にかかわらず、消費税の納税義務は免除されません。適格請求書(インボイス)を発行できる適格請求書発行事業者として登録するには、課税事業者になることが条件となるからです。
例えば、設立時からインボイス制度に対応したとすると、資本金や課税売上高の額にかかわらず、1期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。そのため、自社の取引先や顧客を想定し、適格請求書発行事業者となる必要があるかを検討するようにしましょう。
消費税の免税期間は長くなる場合がある
法人を設立するにあたって、できるだけ税負担は抑えたいと考えるものです。法人の設立後、消費税の免税期間は、以下のような場合に長くなるといえます。設立前に決めるべき事項が多いため、あらかじめ確認しておきましょう。
消費税の免税期間が長くなる場合
- 資本金を1,000万円未満にする
- 特定期間の課税売上高または給与等支払額の合計額が1,000万円を超えないようにする
- 設立1期目を7か月以下にする
- 決算期を法人の設立から1年後に設定する
- 個人事業主の3期目に法人成りをする
- インボイス制度に対応するかよく検討する
- 専門家に相談する
資本金を1,000万円未満にする
消費税の免税期間が長くなるのは、設立時の資本金を1,000万円未満にした場合があげられます。さらに、法人設立後の資本金の額も1,000万円未満であれば、免税期間をより長期にすることが可能です。
前述のとおり、例えば1,000万円以上になるような増資をするなら、すべてを資本金としてではなく半分は資本準備金として 計上したり、1期目ではなく2期目に入ってから行ったりすると、課税事業者になるタイミングを先に延ばすことができるでしょう。
特定期間の課税売上高または給与等支払額の合計額のどちらかが1,000万円を超えないようにする
消費税の免税期間が長くなるのは、特定期間の課税売上高、または給与等支払額の合計額のどちらかが1,000万円を超えないようにした場合があげられます。
前述のとおり、例えば設立1期目の前半6か月間の課税売上高、もしくは給与等支払額の合計額のどちらかが1,000万円を超えないようにすると、消費税の免税を2期目まで受けることが可能です。
なお、給与等支払額の合計額には役員報酬や賞与(ボーナス)も含まれるため、消費税の免税期間を長くするなら、経営者である自身への賞与の支給時期を下半期に設定することも検討してみましょう。
設立1期目を7か月以下にする
消費税の免税期間が長くなるのは、設立1期目を7か月以下にした場合があげられます。
例えば設立1期目が7か月以下であれば、1期目には特定期間は設定されません。そのため、法人設立から6か月間の課税売上高や給与等支払総額が1,000万円を超えても、特定期間による判定は行われず、2期目まで引き続き免税事業者となります。
もし、設立1期目の前半6か月間の課税売上高と給与等支払総額がどちらも1,000万円を超えると想定できる場合には、1期目の事業年度を7か月以下に設定すると、消費税の免税期間を2期目まで延ばせることを覚えておいてください。
決算期を法人の設立から1年後に設定する
消費税の免税期間が長くなるのは、決算期を法人の設立から1年後に設定した場合があげられます。法人の事業年度は、1年を超えない範囲であれば任意での設定が可能です。そのため、1期目を長く設定するほど、消費税の免税期間は長くなります。
例えば、設立が5月1日で決算期を12月にした場合、設立から2期目まで消費税が免除されたとしても、免税期間は1年8か月です。しかし、設立日から1年後を決算期とした場合は、2年間は消費税の納税義務が免除されます。
設立後6か月間の課税売上高や給与等支払総額が1,000万円を超えない場合、消費税の免税期間を最大限長くするには、設立から1年後を決算日にすると良いでしょう。
個人事業主の3期目に法人成りをする
消費税の免税期間が長くなるのは、個人事業主の3期目に法人成り(法人化)をした場合があげられます。消費税の納税義務が免除されるにあたり、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円以下という要件は、法人も個人事業主も同じです。しかし、消費税の課税・免税の判定においては、法人と個人事業主は別の事業者として見なされます。
そのため、例えば、まずは個人事業主として開業し2年間消費税が免税された後、法人成りしてさらに2期目まで消費税が免税されれば、免税期間を最大4年間とすることが可能になります。
個人事業主から法人成りするタイミングは、消費税の免税要件も踏まえて検討するようにしてください。
インボイス制度への対応を取引先の状況などを踏まえて検討する
消費税の免税期間が長くなるのは、インボイス制度に対応しない場合があげられます。前述したように、法人設立時からインボイス制度に対応すると、資本金の額等にかかわらず、設立1期目から課税事業者となります。
ただし、インボイス制度に対応するかどうかは、各事業者の任意です。例えば、取引先が企業の場合などはインボイス制度に対応した方がいいかもしれませんが、一般消費者向けのビジネスであれば、免税事業者のままでも問題ないかもしれません。
適格請求書の発行事業者になる手続きは、法人を設立した後でもできます。設立と同時に適格請求書発行事業者になるかどうか、自社の業種や取引先の状況などを踏まえて検討するようにしてください。
専門家に相談する
消費税の免税期間を長くなるのは、法人の設立前に税理士などの専門家に相談した場合があげられます。法人設立前から税理士に相談しておけば、事業内容や売上予測、資金繰りの見通しなどを踏まえたうえで、アドバイスを受けることができるでしょう。
法人設立後に納める税金は、消費税だけではありません。例えば株式会社の場合、資本金の額や株主構成、役員報酬などの金額、決算月などが、法人設立後の納税額に大きくかかわります。税の知識がないままこれらの事項を決めてしまうと、法人設立後に思った以上に税を負担することになるかもしれません。
法人設立にあたって相談できる税理士を探したい場合には、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」が便利です。「税理士紹介ナビ」は、法人設立や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。専門家から的確なアドバイスをもらいたい方は、ぜひご検討ください。
専門家に相談することで税負担が軽減できた事例については以下の記事を併せてご覧ください。
専門家に相談しながら会社設立を手軽に行う方法
ここまでご紹介してきたように、実際に会社設立を始める前には決めるべき事項が多く、どのように決めれば良いのか迷われることも多いでしょう。そのような場合におすすめしたいのが、「弥生の設立お任せサービス」です。
「弥生の設立お任せサービス」は、会社設立にかかわる手続きを、起業に強い専門家に丸ごと代行してもらえるサービスです。電子定款や登記書類作成、公証役場への定款認証、法務局への登記書類提出などの各種手続きを依頼できるので、事業の準備で忙しくても確実かつスピーディーに会社を設立できます。
会社の設立前から専門家に相談できるうえ、設立後に会計事務所と税務顧問契約を結ぶと、サービス利用料金は実質0円になります(登録免許税等、行政機関の手数料は別途発生します)。
法人を設立する際には消費税の免除要件を把握しておこう
新設法人は、原則として、設立2期目まで消費税の納税義務が免除されます。ただし、資本金が1,000万円以上である場合や、インボイス制度の適格請求書発行事業者になった場合には、設立1期目から消費税の納税が必要です。また、1期目の前半6か月の課税売上高または給与支払総額が1,000万円を超えると、1期目は免除されても、2期目から消費税の納税義務が生じます。
消費税の納税義務が免除されるかどうかで、法人設立後の税負担は大きく変わります。法人を設立するときは、消費税の免税要件を把握しておきましょう。
会社設立の手続きをスムーズに進めたい場合は、「弥生の設立お任せサービス」といったクラウドサービスを活用することで、専門家に相談しながら会社設立を準備できるうえ、手間とコストを抑えることが可能です。便利なクラウドサービスを上手に活用して、スムーズな会社設立を進めてください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。