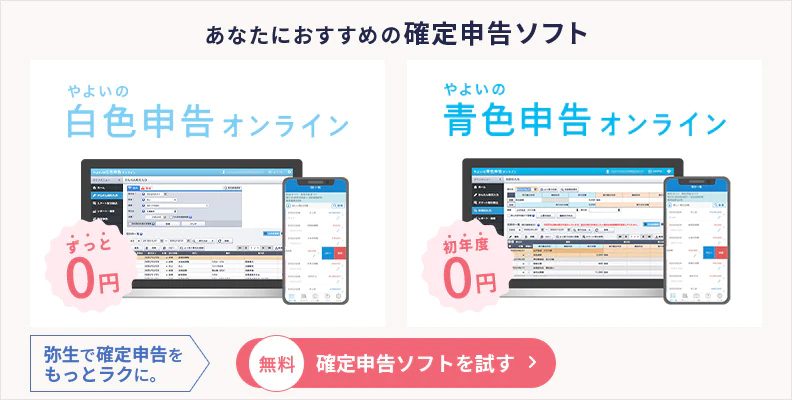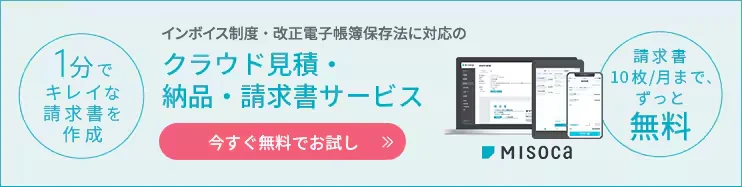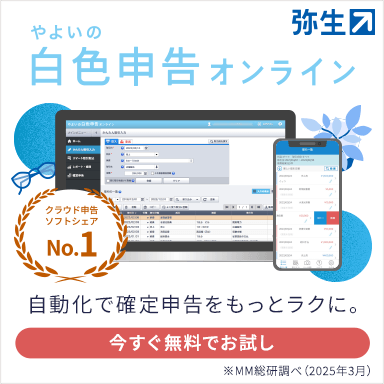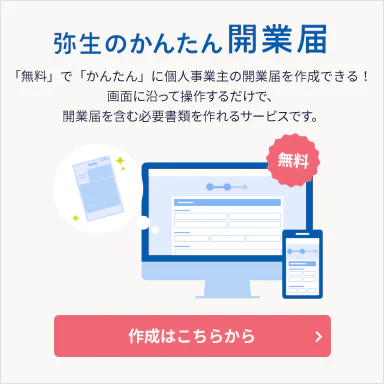副業の失敗しない始め方とは?おすすめの仕事や注意点も解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

副業を始めたいものの「何から着手すれば良いのかわからない」「トラブルにならないか心配」といった疑問や悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。初めての副業にどのような仕事を選ぶべきか、決めかねていた方もいるかもしれません。
本記事では、失敗しない副業の始め方についてわかりやすく解説します。副業を安心して始める方法のほか、副業で得られるメリットや初めての副業におすすめの仕事、副業を始める際の注意点について見ていきましょう。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
副業を安心して始める方法
副業を失敗やトラブルなく始めるには、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。まずは、副業を安心して始めるための準備の仕方を紹介します。
1. 勤め先が副業OKかを確認する
副業を始めるにあたってまず確認したいのが、本業の勤務先が従業員の副業を認めているかという点です。就業規則に副業関連の記載がないかよく確認しましょう。
副業が認められている場合であっても、勤務先によっては、副業の仕事内容や労働時間を会社に申告や報告するルールを設けていることがあります。
また、他社との雇用契約を禁止している企業においても、業務委託など雇用契約を締結しない働き方であれば問題ないというケースも少なくありません。不明点があれば勤務先の人事や総務などに問い合わせてみましょう。
2. なぜ副業をしたいのかを明確にする
次に行うのは、副業に取り組む目的を明確にすることです。副業を始めるきっかけは、収入アップやスキルアップなど、人によって異なります。目的に応じて副業選びの判断軸も変わるため、なぜ副業をしたいのかを明確にしておくことは非常に重要です。
例えば、「月◯万円稼ぎたい」「本業以外に収入を得る手段を確保したい」といった収入面が主な目的であれば、副業を選ぶ際には目標とする金額に到達可能な仕事を選ぶ必要があります。
「本業以外のスキルを伸ばしたい」「将来独立するためにスキルを身に付けたい」といった目的であれば、希望するスキルを伸ばせるかどうかが副業選びの軸となるでしょう。まずは目的を明確にしておき、目的に合った副業を探すというスタンスで臨むのがポイントです。
3. 副業に必要な時間を確保する
現在の生活スタイルの中で、副業のために確保できる時間がどれだけあるかを試算しておきましょう。本業の勤務時間外と休日の中で、無理なく副業に充てられる時間がどのくらいあるのか、必要な時間を無理なく捻出できるのかを検討しておくことが大切です。
副業で失敗しやすいパターンとして「時間があるときに副業を進める」という考え方があげられます。時間は捻出しなければなかなか確保できないため、副業に充てる時間の優先度が低くなりがちです。
反対に、「睡眠時間を削れば何とかなる」といった考え方も避けてください。副業で疲労がたまり、本業に身が入らなくなる、集中力が低下してミスを頻発するなどは本末転倒です。こうした事態を避けるためにも、副業に充てる時間をあらかじめ確保しておく必要があります。
4. 副業を選ぶ
取り組む副業を選ぶ際は、仕事内容だけでなく働き方や報酬体系に注意を払いましょう。副業には大きく分けて「時間労働型」と「成果報酬型」の仕事があります。
時間労働型は、働いた時間の分だけ報酬が支払われるタイプの働き方です。代表的なしくみとして、1時間単位で報酬が支払われる時給制があげられます。時給制のアルバイトなどは、時間労働型の働き方の一種と捉えてください。
すきまバイトやスポットワークはこのケースが多いようです。
成果報酬型は、働いた時間ではなく成果に対して報酬が支払われるタイプの働き方です。成果物の納品や役務の提供をもって報酬が確定します。成果報酬型の仕事は時間の制約が設けられておらず自由度が高い半面、たとえ長時間働いたとしても報酬が増えるわけではありません。
どちらの働き方が自分に合っているか、働きたい時間帯や現状のスキルとも照らし合わせて決めることが大切です。
副業を始めるメリット
副業を始めることによって、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。主な4つのメリットについて解説します。
収入アップ、収入経路の確保
副業を始めることによって、本業の給与以外に収入源を確保できます。厚生労働省の調査によれば、副業をしている理由として最も高い割合を占めていたのは「収入を増やしたいから」、ついで割合が高かったのは「1つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」といったものでした。収入アップや収入経路の確保を目的として副業を始める人が多いことがわかります。
本業の給与に上乗せして副収入を得ることで生活に余裕ができるだけでなく、1つの収入源に頼らざるをえない状況が緩和され、精神的にもゆとりが生まれる可能性もあります。副業の仕事量や収入をある程度調整できるようになれば、たとえ本業で「給料が上がらない」「賞与額が下がってしまった」といった問題に直面しても、自力で収入を上げられるのです。
参考:厚生労働省「副業・兼業に係る実態把握の内容等について」(2020年8月)
スキルアップ
副業を通じてスキルアップを図れる点も大きなメリットです。本業で得たスキルを副業でさらに伸ばすことや、本業では経験できない分野のスキルを伸ばすこともできます。副業に選ぶ業種・職種によっては、相乗効果で本業の担当業務をいっそう手際良く進められるようになるかもしれません。
また、業種を問わず求められる汎用スキルを磨けることも、副業に取り組むメリットの1つです。計画的に仕事を進めるスケジュール管理能力や進捗管理能力、タイムマネジメントといったスキルが、本業と副業を両立させていく中で自然と身に付いていくでしょう。本業1本で仕事をしていたときと比べると、スキルを伸ばせる点は大きなメリットです。
人脈や経験が増える
副業を通して人脈や経験が増えていくことも、副業で得られるメリットといえます。本業では仕事でかかわる機会のない企業との取引や、本業とは異なる業界の知識を得られることで、視野が広がるでしょう。
将来的にキャリアチェンジや独立を考えている方にとって、副業で培った人脈や経験が貴重な財産となることもありえます。副業の取引先が独立後も主要取引先の1つになる、本業とは別の業種で独立できるなど、自身の可能性を広げるうえで副業が重要なきっかけとなる場合もあるのです。
将来の起業・転職に向けたトライができる
ゆくゆく起業や転職を検討している方であれば、副業を通して将来に向けた準備やチャレンジができるというメリットもあります。起業や転職にはリスクが付き物です。本業以外の仕事に経験がない状態での起業や、これまでと異なる業種・職種への転職の場合、失敗する確率は高まるでしょう。
一方、本業と並行して副業に取り組む期間を確保すれば、こうしたリスクが軽減できます。たとえ副業がうまくいかなかったとしても、本業の収入があれば、生活が成り立たなくなることはありません。リスクを伴うチャレンジも、副業をトライアル期間と捉えることで実現しやすくなるのです。
初めての副業としておすすめの仕事は?
初めて副業に取り組む際は、事前準備や先行投資ができるだけ少なくて済むものを選ぶことが大切です。最初から大掛かりな準備や先行投資が必要な仕事を選ぶと、初期投資の回収に時間がかかる他、失敗したときのリスクが大きくなりやすいからです。
働く場所や働き方の特徴ごとに、初めての副業におすすめの仕事をまとめました。
■初めての副業におすすめの仕事
| 仕事の特徴 | 副業の例 |
|---|---|
| 自宅でできる仕事 | ・ポイントサイト ・アンケートモニター ・データ入力 ・テープ起こし など |
| 単発・短時間でできる仕事 | ・イベントスタッフ ・交通量調査 ・試験監督 など |
| 資格やスキルを活かす仕事 | ・Webデザイナー ・Webライター ・イラストレーター ・動画編集 など |
確保できる時間や取り組む目的に応じて、自分に合った副業を選ぶことが大切です。また、現在のリソースで始められる仕事かどうかも重視しましょう。
例えば、フードデリバリーを始めるためにバイクの免許を取得し、バイクを購入すれば、かかった費用を副業で回収するまでに多くの時間を要する可能性があります。既に所有している自転車を活用して副業を始め、軌道に乗ったらバイクの購入を検討するといったように、ステップアップしていく方が堅実です。
<見出し>
副業を始める際の注意点
副業を始めるにあたって、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。主な注意点として、次の4つがあげられます。
<小見出し>
本業に支障をきたさないようにする
副業はあくまでも、本業と並行して取り組む仕事です。副業で無理に働きすぎて睡眠不足に陥る、疲労がたまって体調を崩すなどは、本末転倒といわざるを得ません。本業に支障をきたさないよう、働く時間や働き方に気を配る必要があります。
例えば、本業の勤務時間のように、副業に充てる時間を明確に決めておくと良いでしょう。平日の勤務後に何時から何時まで、土日祝日は何時から何時までとあらかじめ決めておくことにより、オン・オフのメリハリをつけて働きやすくなります。
あるいは、「睡眠時間は必ず◯時間確保する」といった目標を決めておくのも効果的です。本業と無理なく両立できる働き方を実践し、本業に支障をきたさないように十分気を付けてください。
なお、アルバイトやパートなど雇用関係が発生する副業の場合、勤務先の企業は本業と副業の労働時間を通算するなど、労務管理が必要となります。適切な労務管理を行えるよう、本業・副業それぞれの使用者に、各企業の労働時間を報告するようにしましょう。
参考:厚生労働省「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」
副業が原因のトラブルに注意する
副業が原因でトラブルに巻き込まれないよう、注意しましょう。近年は、SNS上で副業の勧誘を多く見かけるようになりました。中にはSNSで知り合った相手から副業の依頼を受け、結果として詐欺の被害や犯罪に巻き込まれる遭うケースもあるようです。特に副業初心者の方は、SNS経由で副業の案件を獲得するのは避けた方が無難です。
また、「月100万円の副収入」「だれでも簡単に稼げる」といった甘言は、疑ってかかることが大切です。副業で収入を増やしたい方の心理を巧みに利用し、高額商材を売りつける悪質な業者も存在します。
副業の求人に応募する際は、信頼のおける企業が運営しているか、同様の仕事を経験した方が被害を訴えていないかなど、十分にリサーチしたうえで応募すべきか判断してください。
インボイスの登録が必要になる可能性も
副業の取引先や取引内容しだいでは、請求書を発行するケースもあるでしょう。その際、取引先から適格請求書(インボイス)の発行を求められる可能性があります。
インボイスを発行するには、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者として登録申請する手続きが必要です。手続き方法には次の2つがあります。
適格請求書発行事業者の登録申請方法
- e-Taxで登録申請を行う(マイナンバーカードなどの電子証明書が必要)
- 「適格請求書発行時業者の登録申請書」をインボイス登録センターへ郵送(本人確認書類の写しを添付)
なお、インボイス発行事業者として登録すると、年間の売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告・納付が必須となります。後述する所得税の確定申告と消費税の確定申告は、別の申告になるので、認識をしておきましょう。
副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要
副業の年間所得が20万円を超えると、確定申告が必須となります。所得とは、副業の売上から必要経費を差し引いた金額のことです。
例えば、副業の売上高が40万円で必要経費が10万円の場合、所得は30万円となり、20万円を超えるので確定申告が必要になります。このほか、以下に該当する場合は、副業の年間所得を問わず確定申告をすることになる可能性があります。該当するか確認しておきましょう。
副業で給与所得を得ている場合
会社員の方が、アルバイトなど雇用契約を結んで働く副業をする場合、本業以外の事業者から給与所得を得ることになります。
2か所以上から給与を受け取っている場合、確定申告が必要です。年末調整ができるのは1か所のみだからです。年間で合計いくらの所得があり、結果として所得税をいくら納める必要があるのか、自分で申告する必要があります。
副業が給与所得の場合は、所得が20万円以下か否かではなく、給与収入が20万円以下なら税務署への確定申告が不要で、20万円超なら確定申告が必要となります。
副業で雑所得・事業所得を得ている場合
副業が業務委託など雇用契約を締結しない働き方であれば、雑所得または事業所得として確定申告をすることになります。副業は雑所得に該当する場合が多いですが、生計を立てられる一定の規模で反復・継続・独立して行われていれば、事業所得と判断されるケースもあります。いずれの場合も、確定申告に備えて帳簿付けをしておくのがおすすめです。
事業所得の場合、副業の赤字を損益通算(本業の所得と副業の赤字を差し引きすること)することが可能です。ただし、損益通算をすると所得が下がるため、本業の勤め先に内緒で副業している場合は、下がった住民税額から副業をしていることがばれるリスクがあります。
また、副業の報酬から源泉徴収をされて支払われている場合、確定申告をすることによって納めすぎていた所得税が還付されることもあります。副業の年間所得が20万円以下であっても、報酬から源泉徴収されていて、還付される場合には確定申告をした方が良いでしょう。
副業以外の理由で確定申告をする場合
年間の医療費が10万円を超えている場合など、副業以外の理由で確定申告をする際は、副業の所得も併せて申告する必要があります。
確定申告書にはその人が年間にどれだけのお金を稼ぎ、結果としてどれだけの所得税を納める必要があるのかを漏れなく記載する必要があります。そのため、副業の年間所得が20万円以下であっても、副業以外の理由で確定申告が必要であれば、所得の実態をありのまま記載することが必要だからです。
住民税と消費税の申告が必要なケースもある
副業の年間所得が20万円以下の場合で確定申告が不要でも、利益が1円でも出ていれば、居住地の自治体に住民税の申告は必要です。
また、前述しましたが、副業でもインボイス対応で、適格請求書の交付が求められる場合には、適格請求書発行事業者に登録が必要なことがあるでしょう。
適格請求書発行事業者は、消費税の課税事業者なので、課税売上があれば、消費税の申告と納付、要件に従った帳簿付けは必須です。つまり、副業で所得税の確定申告が不要なケースでも、消費税の確定申告と納付が必要なことを認識して、副業を開始しましょう。
このように、副業を始めることによって本業のみの場合以上にお金の管理が重要になります。副業の雑所得では帳簿付は義務ではありません。しかし、所得の計算やお金の流れを把握するためにも、副業開始と同時に帳簿付けも行うのがおすすめです。
副業を始める際のポイント・注意点を押さえてスムーズなスタートを切ろう
副業を始めることで数多くのメリットが得られる半面、本業以外に自分で仕事を始めればこれまでになかったリスクが発生するのも事実です。副業を始める際の注意点を押さえておくことによって、副業で失敗するリスクを抑制できます。
安心して副業に取り組むためにも、今回紹介したポイントを参考にスムーズな副業のスタートを切れるようにしたいですね。さまざまなリスクを想定し、あらかじめ対策を講じておくことで、副業の開始当初に掲げた目標をより早く着実に達成できるでしょう。
副業の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。副業の所得が事業所得や不動産所得に該当する場合は、帳簿作成や確定申告・e-Tax、消費税の確定申告までできる弥生のクラウド申告ソフトを活用するとよいでしょう。初年度無料の「やよいの青色申告 オンライン」や永年無料の「やよいの白色申告 オンライン」をぜひお試しください。
なお、副業の所得が雑所得に該当する場合でも、売上や経費から所得を算出するために帳簿付けをしておくと申告が楽です。
「やよいの白色申告 オンライン」は、雑所得の確定申告はできませんが、ずっと無料で使用できるので帳簿付けに気軽にご利用ください。帳簿付けをすれば、事業所得で申告できる可能性も出てきます。ぜひご検討ください。確定申告は集計情報をもとに国税庁の確定申告コーナーで行えます。
また、業種や販売先によっては、請求書の発行が必要です。その場合、インボイス制度や電子帳簿保存法はじめ最新法令に対応したクラウド請求書作成ソフトの「Misoca」をご活用ください。
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。