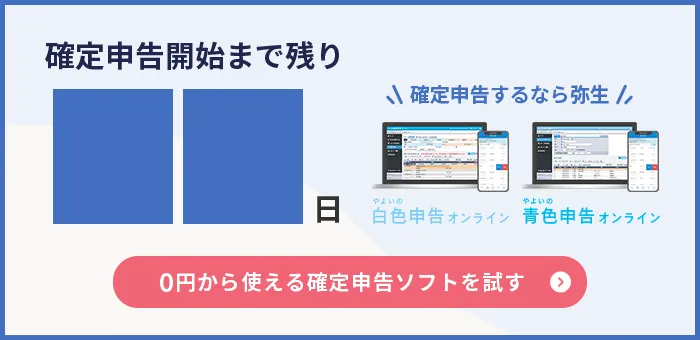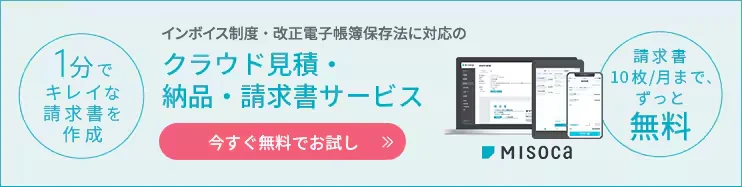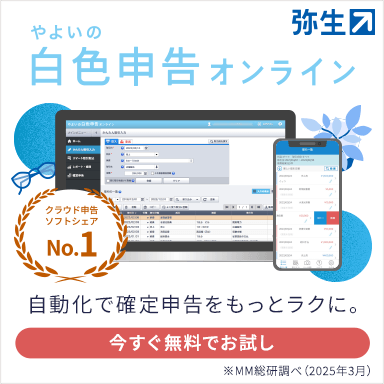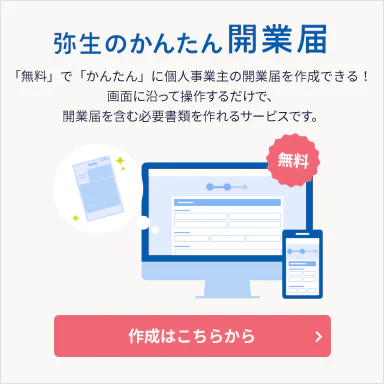副業なら何時間でも働いてよい?労働時間の考え方やルールを解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
公開
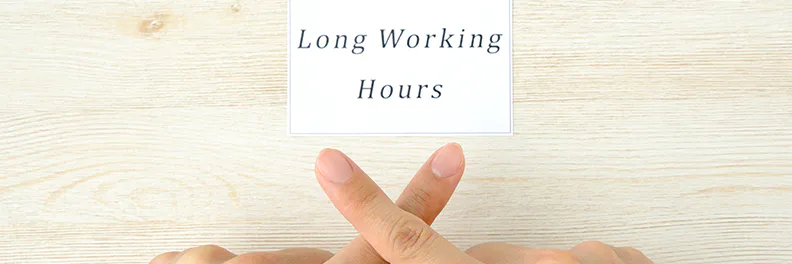
副業を始めてみたいと思っているものの、どれくらい時間を割いて良いのか、副業であれば制限なく働けるのかなど疑問に思う人もいるのではないでしょうか。健康管理や本業と無理なく両立させるためにも、副業を行う際は、本業と同様に労働時間を管理することが必要です。
ここでは、副業をする場合の労働時間の考え方やルールについてわかりやすく解説します。副業で労働時間が増加する際の注意点にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
労働時間は「本業+副業」で考える
結論からお伝えすると、副業であっても雇用されて働く場合は労働時間に含まれます。つまり、労働時間は「本業+副業」で考える必要があるのです。
まずは、労働時間の原則と、時間外労働・休日労働の定義を確認しておきましょう。
労働時間の原則
労働時間は労働基準法第32条において、原則1日8時間まで、1週間40時間までと定められています。
この法定労働時間は、就業する事業所によって制限されません。つまり、本業で1日8時間、1週間40時間働いているのであれば、副業の勤務先での労働時間はすべて法定時間外労働となります。本業と副業の勤務先でそれぞれ1日8時間、1週間40時間まで働けるということではありません。労働時間は本業・副業を通算して考える必要があります。
時間外労働・休日労働の定義
法定労働時間を超える労働については、雇用主(使用者)と従業員との間で時間外および休日労働に関する協定、いわゆる「36(サブロク)協定」を締結することで可能です。
1日8時間、1週間40時間を超える部分の労働は、時間外労働として割増賃金が適用され、通常の賃金の25%以上割増となります。労働時間が60時間を超えた分の賃金割増率は50%です。
また、休日については1週間につき最低1日、4週間につき4日以上確保するよう定められています。法定休日数に満たない場合は休日労働となるため、通常賃金の35%以上割増して支払うのが労働基準法に定められているルールです。
なお、休日労働における「休日」は、勤務先が独自に設けている休日とは異なります。例えば、完全週休2日制の企業の場合、1週間のうち1日は法定休日、もう1日は企業が自主的に設けている休日です。
休日の労働で時間外労働に当たるのは法定休日のみという点を間違えないようにしましょう。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
そもそも36(サブロク)協定とは?
36協定とは、法定労働時間を超えて働く場合の上限時間を定める取り決めのことです。雇用主と従業員との間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることにより、月45時間・年間360時間を時間外労働の上限とすることができます。
- ※特別条項を締結すれば、年間6か月まで限度時間を超えて労働することが可能
ただし、36協定を取り交わしたからといって、法定労働時間が関係なくなるわけではありません。法定労働時間を超えて働いた分については前述のとおり、所定の割増賃金を支払う必要があります。ここで注意しておきたいのが、本業と副業の労働時間に関する考え方です。
所定労働時間の通算
前述のとおり、雇用契約を締結して働く場合には、本業・副業の区別はなくどちらも労働時間に含まれます。企業ごとに従業員が働く時間は「所定労働時間」として定められていますが、この所定労働時間は、本業と副業を通算する必要があるのです。
このルールは36協定を締結している場合も同様で、通算して1日8時間・1週間40時間を超える労働時間は時間外労働となり、時間外労働時間の上限は、通算で月45時間・年間360時間(繁忙期など例外の場合も休日労働を含め月100時間未満、2~6か月平均80時間以内)となります。本業・副業それぞれの事業所で、労働時間や休日数がカウントされるわけではない点に注意しなければなりません。
所定時間外労働の通算
では、本業・副業の労働時間および時間外労働時間は、どのように通算されるのでしょうか。労働時間は本業・副業でそれぞれ所定外労働が生じた順に通算し、超過分をそれぞれの勤務先が支払うことになります。
所定時間外労働の通算例
- 本業の勤務先A社:所定労働時間8時間で、8時間勤務した
- 副業の勤務先B社:所定労働時間2時間で、A社を退勤後に2時間勤務した
上記の場合、A社を退勤した時点で1日8時間の法定労働時間に達していることから、B社での勤務時間はすべて時間外労働となります。よって、所定労働時間内に収まっていたとしても、B社は2時間分の割増賃金を支払わなければなりません。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
労働時間が通算されないケース
個人事業主やフリーランスとして副業に取り組む場合、特定の事業者と雇用契約を締結していないため労働基準法は適用されません。ですから、本業との労働時間の通算は不要です。労働時間が通算されるのは、あくまでも雇用契約を締結している場合に限られます。
また、農業や畜産業など、労働時間の規制が適用されない業種もあります。本業・副業がこうした業種に該当する場合は、労働時間を通算する必要はありません。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
本業、副業ともに会社に雇用されている場合の労働時間
本業と副業がいずれも雇用契約を締結している場合、労働時間が通算されます。例えば、正社員として働いている方が、副業でアルバイトをするようなケースです。
この場合、割増賃金は本業・副業のどちらから支払われるのか、副業の労働時間を本業の勤務先に申告すべきなのか、ポイントを絞って解説します。
割増賃金は本業と副業のどちらから支払われるのか
割増賃金の支払いは、所定時間外労働が発生した順となります。実際にどのように割増賃金が支払われるのか、2つの例で見ていきましょう。
本業の所定労働時間7時間、副業の所定労働時間2時間の場合
- A社(本業)で7時間勤務
- B社(副業)で2時間勤務
→労働時間が通算9時間のため、法定労働時間を超えた1時間分の割増賃金をB社が支払う。
本業の所定労働時間6時間、副業の所定労働時間2時間の場合
- A社(本業)で8時間勤務
- B社(副業)で3時間勤務
→労働時間が通算11時間のため、3時間分が法定時間外労働となる。A社は所定労働時間外の2時間分、B社は所定労働時間外の1時間分の割増賃金を支払う。
2つ目の例では、A社での労働時間は本来なら法定労働時間内に収まっています。本業のみの労働時間であれば、所定労働時間を超えた2時間分の残業手当を支給するかどうかは事業者の判断で決めて構いません。
しかし、副業と通算すると3時間分の割増賃金を支払う必要があることから、本業・副業の所定労働時間に基づき支給すべき割増賃金が決まります。
副業での労働時間は本業の勤務先へ申告するべきか
労働時間は本業・副業で通算しなければなりませんが、副業での労働時間は本業の勤務先に申告すべきなのでしょうか。労働時間は自己申告のため、労働者が自分で申告しない限り本業・副業の各勤務先は通算の労働時間を把握できません。つまり、申告しなければ法定労働時間を超えて働くこともできてしまうのが実情です。
ただし、法定労働時間を超えて就業させていたことが判明すると、本業・副業の勤務先がいずれも労働基準法に違反していることになり、是正勧告や司法処分の対象となる可能性があります。よって、副業の労働時間は本業の勤務先へ正確に申告すべきでしょう。
また、今後において副業の労働時間を把握できるような仕組みが作られる可能性もゼロではないでしょう。
本業が管理モデル(簡便な労働時間管理の方法)を導入した際の対応
労働者からの申告に基づき、本業・副業の勤務先はそれぞれ労働時間を確認する作業が複雑になることが想定されます。そこで、事業者は労働時間の管理をより簡便に行うための「管理モデル」を取り入れることも可能です。
管理モデルとは、あらかじめ本業と副業の労働時間が時間外労働の限度である単月100時間未満・複数月平均80時間以内に収まるよう、それぞれの事業者が労働時間の上限を設定し、その範囲内で労働に従事させる管理方法です。
管理モデルの導入により、他社の労働時間を事業者が管理しなくても、労働基準法に則った管理が可能となります。
裏を返せば、勤務先が管理モデルを導入した場合、労働者は自分で責任を持って労働時間を管理しなければなりません。また、本業の勤務先が管理モデルを導入した際には、労働者は副業先に法定時間外労働の割増賃金の支払いを求める必要があります。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業で労働時間が増加する際の注意点
本業に加えて副業を始めるとなると、全体の労働時間が増えるのは避けられないケースがほとんどでしょう。ここからは、副業開始に伴って労働時間が増加する際の注意点を解説します。
労働時間は、健康とのバランスを優先する
本業と副業の労働時間を通算するルールは、そもそも過重労働を防ぐために設けられています。見方を変えると、本業と副業に並行して取り組むとなると、働きすぎてしまうリスクが高まるということです。
労働時間は、健康とのバランスを意識して判断する必要があります。収入増やスキルアップを図ることも重要ですが、健康を害してしまうようでは本末転倒です。
特に個人事業主やフリーランスのように、労働時間が通算されないケースでは働きすぎに注意しましょう。
副業時の労災保険の取り扱いを押さえておく
就業内や通勤中で発生した労働災害については、就業先の労災保険を使用して補償するのが基本的なルールです。つまり、本業での労災には本業の労災保険が適用され、副業での労災には副業先で加入している労災保険が適用されます。
2020年9月に改正労働者災害補償保険法が施行され、労災保険によって支給される給付額は本業・副業の賃金額を合算した額を基準に算出されるようになりました。
一般的に副業の収入は本業の収入よりも少額となるケースが多いことから、副業先で起きた労働災害によって本業でも就業できない期間が生じた場合、休業補償給付が少額となってしまうおそれがあったためです。副業の勤務先で労災保険を使用する場合にも、本業の労災保険に影響を及ぼす可能性があることから、副業先で労災保険に加入した際には、本業の勤務先に報告しておくと良いでしょう。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業を始める際は労働時間などの管理を徹底しよう
働き方が多様化するにつれ、副業に取り組む人も増えつつあります。副業をする際には、今後ますます労働者自身の管理能力が問われていくことになるでしょう。雇用契約を締結する副業を始める際は、労働時間の管理を徹底することが大切です。
また、副業の収入が増えていくと確定申告が必要な所得額(年間20万円超)に達する可能性があります。雑所得では帳簿付けは義務ではありませんが、売上と経費などから所得を算出するので、副業でも帳簿付けをしておくと所得の計算が容易です。万一の税務調査の際も帳簿を備え付けておくと好印象となることでしょう。帳簿付けをしておくと事業所得として確定申告ができる可能性もあります。なお、雑所得の場合でも適格請求書(インボイス)発行事業者の場合は、インボイス制度に従って帳簿付けが必要です。
クラウド白色申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」なら、初心者の方でも手軽に帳簿付けができます。確定申告に備えて、「やよいの白色申告 オンライン」を活用した帳簿付けを始めてみてはいかがでしょうか。ただし、「やよいの白色申告 オンライン」は、事業所得の確定申告のみに対応しているため、雑所得の場合は、「やよいの白色申告 オンライン」の帳簿や集計資料の数字をもとに国税庁の確定申告サイトから申告をしましょう。
また、業種や取引によっては請求書を発行する場合もあります。請求書を発行する際には、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件に従って作成・保存することが重要です。
請求書や見積書、納品書をテンプレートで簡単に作成でき、インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しているクラウド請求書ソフト「Misoca」を活用して、請求関連業務を効率的に進めていくことをおすすめします。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。