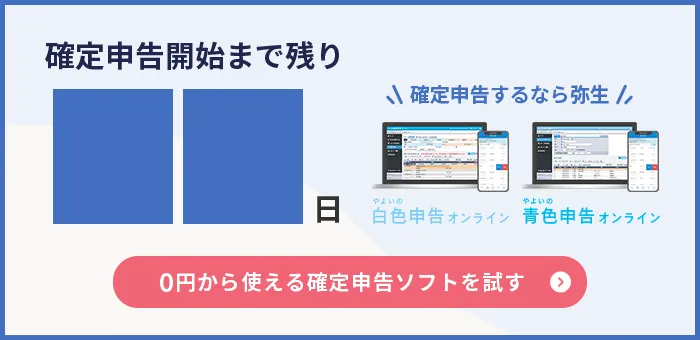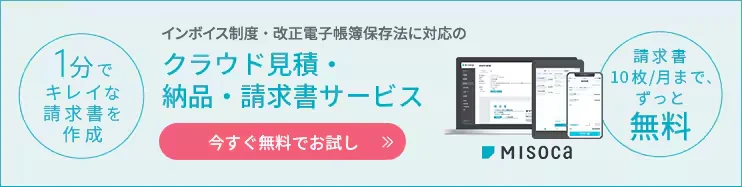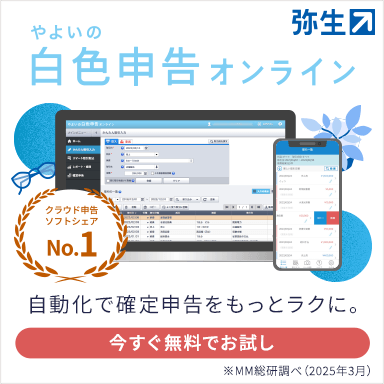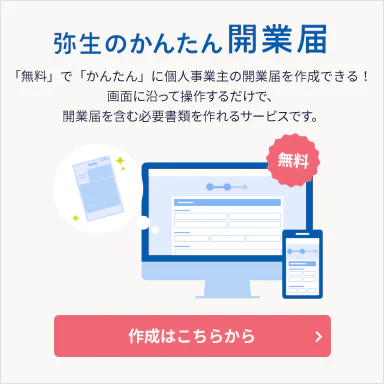副業すると社会保険料はどうなる?副業時の社会保険の注意点を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
公開

会社員が副業をした場合、気になるのは社会保険料への影響です。特に「社会保険料が今よりも増えるのではないか?」と心配している方は少なくないのではないでしょうか。
本記事では、社会保険料の基礎知識や加入要件、副業をした場合の社会保険料の取り扱いについて解説します。併せて、副業によって社会保険料が増加するケースや、本業・副業先の企業の両方で社会保険に加入する場合の社会保険料の計算方法についても紹介するので、参考にしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
副業を行っている際の社会保険の取り扱い
副業を行っている場合、本業の会社員以外にアルバイトなどで従業員として働いているか、個人事業主として働いているかによって社会保険の取り扱いが以下のように異なります。
副業を行う人自身が対応しなければならない手続きもあるため、注意が必要です。
本業と副業先の両方の社会保険に加入するケースがある
アルバイトやパートといった従業員として働く副業の場合、本業と副業先の両方で社会保険に加入するケースが想定されます。社会保険の加入有無は雇用形態によって決まるのではなく、所定労働時間や賃金、従業員数(被保険者数)といった条件に基づいて決定されるためです。後述した社会保険の加入条件に該当すれば、副業であっても勤務先で社会保険に加入することになる可能性があります。
ただし、単純に本業・副業先の両方で社会保険に加入すれば済むわけではありません。こうしたケースはあくまでもイレギュラーであり、保険の種類によって対応が異なります。
雇用保険は、主な収入を得ている本業の勤務先でしか加入できません。一方、労災保険については、本業と副業、それぞれの事業所で加入することになります。
健康保険・厚生年金保険については、条件を満たす場合は両方の事業所で加入手続きをすることになり、その後、従業員に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することが義務付けられています。この場合、以下のように手続きを行わなければなりません。
本業・副業の両方で健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たす場合の手続き
1. 副業先に別の企業で社会保険に加入していることを報告する
副業先で社会保険に加入することになるとわかった時点で、本業の勤務先で社会保険に加入している事実を、副業先に報告してください。副業先の企業は従業員を雇用するにあたり、年金事務所または事務センターに「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。このとき、2か所以上の事業所で勤務していることを記載する必要があるからです。
2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出する
副業先への報告を行ったら、従業員は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を作成し、年金事務所または事務センターに提出します。就業先である2つの事業所のうち、「主たる会社」がどちらなのかを指定する必要があるからです。
本業先と副業先のどちらを「主たる会社」に指定するかは自由に選択できます。ただし、提出後は主たる会社で加入した社会保険を利用することになり、担当する年金事務所も主たる会社を管轄する事務所となる点に注意が必要です。一般的には、本業の勤務先を主たる会社に指定するケースが多いでしょう。
個人事業主の副業であれば社会保険に変更はない
副業を個人事業主として進める場合には、社会保険に変更はありません。
個人事業から生じる儲けに対しては、保険料がかからないということです。引き続き本業の勤務先で社会保険に加入し、保険料も従来どおり本業の給与から控除されます。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業で2か所以上から給与があるときの社会保険の注意点
複数の事業所でアルバイトなどの副業をする場合、社会保険の取り扱いで注意しなければならない点があります。以下の3点は、正しく理解して適切に対応するようにしてください。
副業でも条件を満たしたら社会保険加入が必要
社会保険で注意したいポイントとして、社会保険の加入条件は雇用形態によって決まるものではないという点が挙げられます。
しばしば「正社員は社会保険に加入するが、アルバイトなど非正規雇用の場合は加入しない」と勘違いしているケースが見られますが、これは誤りです。副業でアルバイトやパートとして働く場合も、一定の条件を満たせば社会保険に加入する必要がある点に注意してください。
健康保険・厚生年金保険の複数加入時は自身で手続きが必要
健康保険・厚生年金保険に複数の事業所で加入する際には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出は従業員自身で行う必要があります。本業・副業先の事業所や年金事務所に手続きを行ってもらえるわけではない点に注意が必要です。
健康保険に関しては、複数の事業所で就業していたとしても、発行される保険証は1枚のみです。どの事業所が「主たる会社」であるかを自分で決め、年金事務所や事務センターに届け出ることにより、発行される健康保険証が決定されます。一般的には、本業の健康保険に加入するケースが多いでしょう。
この場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して、本業の勤務先が主たる会社である旨を届け出なくてはなりません。
具体的な手続きとしては、日本年金機構のWebページから書式をダウンロードしたうえで、必要事項を記入して年金事務所または事務センターへ提出します。
提出期限は、2か所以上の事業所で勤務を開始した日から10日以内です。年金事務所または事務センターに書類を持ち込んで直接提出する方法のほか、郵送や電子申請による提出も選択できます。
社会保険の加入手続きを怠った場合の注意点
副業先が社会保険への加入手続きを怠った場合、従業員にも不利益が発生する可能性があるため、注意しなければなりません。
健康保険・厚生年金保険について「虚偽の申請をする」「日本年金機構による加入指導に従わない」などの場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が事業主に科されることがあります。加えて、本来支払うべきだった保険料の過去2年までさかのぼって納付することになる可能性もあります。
保険料は従業員も負担しなければならないため、多額の支払いが発生する可能性があるのです。副業の勤務先で社会保険に加入する必要がある場合には、適切に手続きが行われているかを確認することが大切です。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業によって社会保険料が増えるケース
副業を始めたことに伴い、納める社会保険料が増えるケースも想定されます。社会保険料が増える可能性があるのは、以下の2パターンです。
非正規雇用で副業をしているケース
アルバイトやパートなどの非正規雇用で副業をしている場合、勤務先が健康保険・厚生年金保険の適用事業所で、さらに働き方などが加入条件を満たすのであれば、それぞれの事業所で社会保険に加入することになります。このようなケースでは、加入する社会保険が増えることに伴い、納めるべき社会保険料も増えます。
社会保険料は各事業所で按分されてそれぞれの給与から控除されるため、従業員が自分で社会保険料の支払い手続きをする必要はありません。ただし、副業を開始した日から10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を自分で提出する手続きは、忘れないようにしてください。
一方、副業の勤務先が社会保険の非適用事業所である場合や、働き方が加入条件を満たさない場合であれば、社会保険への加入は不要です。引き続き、本業の勤務先のみで社会保険に加入するため、社会保険料も増えることはありません。
副業で会社を設立しているケース
副業で会社を設立して自身が代表者として就任し、役員報酬を受け取る場合には社会保険に加入する必要があります。代表者1人のみの会社であっても、原則として社会保険への加入義務が生じる点に注意してください。この場合、本業の勤務先と副業で設立した自身の会社の両方から社会保険料が控除されるため、本業のみの場合と比べて納めるべき社会保険料が増えるのです。
もっとも、役員報酬を0円またはごく少額に設定している場合や、法人化せず個人事業主として事業を営む場合は、社会保険に加入する必要はありません。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
会社員と個人事業主で異なる社会保険
アルバイトなどのように雇用契約を締結して従業員として働く場合を除くと、副業ワーカーは「個人事業主」に分類されます。まずは、会社員と個人事業主で、社会保険にどのような違いがあるのか整理しましょう。
会社員が加入する社会保険
会社員が加入する社会保険は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類です。それぞれ、以下のような特徴があります。
健康保険
日本は国民皆保険制度を採用しているため、すべての国民が健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入することになっています。会社員が加入するのは、基本的には勤務先が加入している健康保険です。保険料は給与額に応じて定められており、毎月の給与や賞与から控除(天引き)されます。保険料は会社と従業員が折半して納めるのが原則です。
介護保険
40~64歳の会社員は、健康保険とともに介護保険にも加入します。介護保険料も健康保険料と同様、給与額に応じて保険料が決まるしくみです。また、保険料の納付についても、健康保険と同様に会社と従業員が折半して納めます。
厚生年金保険
会社員の年金保険は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て構造になっています。保険料は、会社と従業員が折半して納め、健康保険・介護保険と同様に給与・賞与から控除される仕組みです。
厚生年金の保険料を支払うと国民年金の保険料も負担したことになるため、会社員は自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
雇用保険
雇用保険は、失業した際の失業手当の支給などを行う保険給付事業と、失業防止のための助成金支給や在職者・離職者への職業訓練などを行う雇用安定事業・能力開発事業で構成される制度です。保険料は保険給付事業分については会社と従業員が折半して納付し、雇用安定事業・能力開発事業分は事業主が負担します。
労災保険
労災保険は、従業員に業務上や通勤中の傷病、障害、死亡などが発生した場合の保険給付を目的とした社会保険です。保険料を負担するのは事業主であるため、従業員の給与から保険料が控除されることはありません。
個人事業主が加入する社会保険
個人事業主は、加入する社会保険が会社員と異なります。個人事業主が加入するのは、「国民健康保険」「国民年金」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つですが、雇用保険と労災保険については、自分自身のために加入するのではなく、従業員を雇用した場合に従業員のために加入する必要がある点を認識しておきましょう。それぞれ以下のような特徴があります。
国民健康保険
国民健康保険は、住所地の市区町村・都道府県が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合のもので構成されています。会社員が加入する社会保険とは異なり、個人事業主の国民健康保険には、原則として傷病や出産による休業時の所得保障を目的とした給付制度はありません。保険料は自治体または国民健康保険組合ごとに決定される仕組みです。
国民年金
個人事業主が加入する年金保険は、すべての国民が加入する国民年金です。会社員が加入する年金保険の1階建て部分(基礎年金)に相当します。保険料は定額制です。
介護保険
個人事業主も会社員と同様、介護保険に加入する必要があり、40歳以上が被保険者となります。国民健康保険料と併せて納付する仕組みです。
雇用保険
個人事業主は雇用された労働者ではないため、自分自身のための雇用保険に加入することはできません。しかし、従業員を雇用した場合は、原則として従業員のために雇用保険に加入する必要があります。この場合、事業主として保険給付事業分の一部と雇用安定事業・能力開発事業分の全額の負担が必要です。
労災保険
雇用保険と同様に労災保険も、自分自身のために加入することは原則としてできませんが、一人親方や中小事業主が任意で加入できる特別加入という制度があります。
また、個人事業主として従業員を雇用した場合には、従業員の傷病・障害・死亡などのリスクをカバーするために加入しなければなりません。労災保険の保険料は、事業主として全額負担することになります。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
従業員が加入する社会保険の加入条件
従業員が加入する健康保険・介護保険・厚生年金保険と雇用保険には、加入条件があります。
まず、健康保険・厚生年金保険と、健康保険加入者が加入することになる介護保険については、事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となっていることが必要です。
適用事業所となるのは、給与または役員報酬を支給している従業員・役員が1人以上いる法人や、農林漁業やサービス業など以外で従業員数が常時5人以上の個人事業主が該当する強制適用事業所と、強制適用事業所に当てはまらなくても任意で加入している任意適用事業所です。
加えて、加入対象者となる従業員が以下のような労働時間などの条件を満たしている場合に、事業主はその従業員について社会保険加入のための手続きを行わなければなりません。
| 種類 | 加入条件 |
|---|---|
| 健康保険・介護保険・厚生年金保険 |
|
| 雇用保険 |
|
労災保険については、すべての労働者が加入しなければならないため、雇用された段階で加入条件を満たすことになります。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
本業と副業両方で社会保険に加入している場合の社会保険料の計算方法
本業と副業の両方で社会保険に加入している場合の計算方法を、具体例で確認していきましょう。東京都で、本業の給与30万円と副業の給与10万円を得ていて、40歳未満で介護保険を支払っていない場合、社会保険料は以下のように計算します。
社会保険料の計算例
健康保険料・介護保険料自己負担額=41万円(標準報酬月額)×10%(保険料率)÷2=2万500円
厚生年金保険料自己負担額=41万円(標準報酬月額)×18.3%(保険料率)÷2=3万7,515円
-
※全国保健協会「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
」
標準報酬月額は、本業と副業を合算して算出するのが基本的な考え方です。合算した給与額を元に標準報酬月額が算定され、納めるべき社会保険料が事業所ごとに按分されます。
つまり、控除すべき社会保険料が増えることによって、本業以外で給与収入を得ている事実が勤務先に伝わるのは避けられません。本業の給与計算にも影響をおよぼすことになるため、あらかじめ勤務先に伝えておくことが大切です。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業で社会保険の加入が必要になる場合は、適切に手続きを行おう
社会保険の加入対象は拡大し続けており、副業の雇用形態や労働条件によっては社会保険への加入が必要になる可能性があります。副業であれば社会保険への加入は不要というわけではないため、十分に注意してください。本記事で紹介した社会保険の加入条件や副業をする際の社会保険の取り扱いを押さえ、必要に応じて勤務先への報告や届出などの手続きを漏れなく行うことが大切です。
また、副業の収入が増えるにつれて、確定申告が必要な金額に達する可能性もあります。具体的には、年間の売上から経費を差し引いた所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。所得を正確に把握するには、副業収入の帳簿付けを習慣化した方がよいでしょう。
個人事業主向けクラウド白色申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」は、銀行明細やクレジットカードなどの取引データ、レシートや領収書のスキャンデータ、スマホアプリで撮影したデータなどを自動で仕訳できます。帳簿付けが初めての方や簿記がわからないという方でも、簡単に帳簿が作成することが可能です。
雑所得の場合、帳簿付けは義務ではありませんが、帳簿を付けておけば所得の算出がスムーズにできるようになります。また、雑所得の場合でも適格請求書発行事業者になっているケースでは、インボイス制度に対応した帳簿付けは必要です。
帳簿付けをしておけば、青色申告が可能な事業所得で申告できる可能性も出てきます。
確定申告やインボイス対応で、手軽に帳簿付けを始められる「やよいの白色申告 オンライン」を活用してみてはいかがでしょうか。なお、「やよいの白色申告 オンライン」は事業所得の確定申告のみに対応しているため、雑所得の確定申告では、「やよいの白色申告 オンライン」の帳簿や集計資料の数字をもとに国税庁の確定申告サイトから申告しましょう。雑所得の確定申告は簡単なので、国税庁の確定申告書作成サイトを使うとすぐに完成することができます。
加えて、業種や取引によっては、請求書の発行が必要になるケースも想定されます。その場合、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件に従って、請求書を発行しなければなりません。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応した請求書や見積書、納品書を、テンプレートで簡単に作成できるクラウド請求書ソフト「Misoca」を活用して、請求関連業務の効率化を図ることをおすすめします。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。