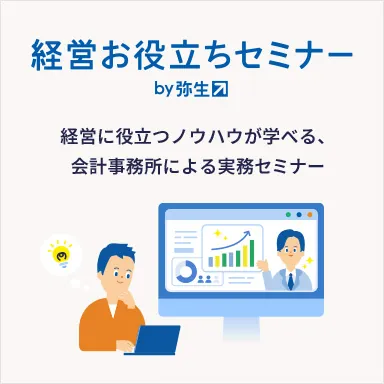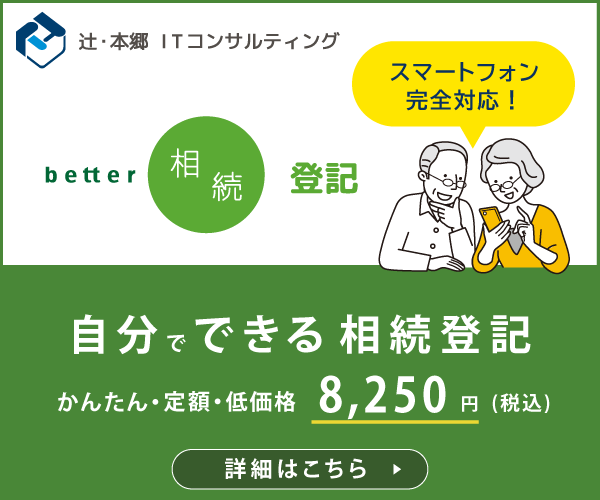事業譲渡とは?
執筆者: 飛渡 貴之(弁護士) / 椛島 慶祐(司法書士)
更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら
事業譲渡とは何か?概要を解説
事業譲渡とは
事業譲渡については、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負うもの」(最判昭40.9.22)をいうと考えられています。つまり、事業譲渡とは、会社の事業の全部ないし一部を第三者に譲渡する手法をいいます。そのため、後述する手法(合併等)と異なり、事業譲渡を選択する場合には、事業譲渡後も会社を引き続き経営することができ、特定の事業を切り離して譲渡することもできます。
他の組織再編行為との比較
(1)吸収合併
吸収合併は、効力発生日において、存続会社が消滅会社の権利義務を承継する組織法上の行為です(会社法750条1項)。
一方、事業譲渡は、効力発生について法定されているものではなく、当事者間の契約によって権利義務が移転する取引行為です。そのため、譲受会社にとっては、簿外債務や偶発債務を引き継ぐリスクが少ない手法といえます。
(2)吸収分割
吸収分割は、効力発生日において、承継会社が吸収分割契約に定めた分割会社の権利義務を承継する組織法上の行為です(会社法759条1項)。
そのため、契約内容によって承継する権利義務の範囲の特定が可能である点で、事業譲渡と類似するものといえます。
もっとも、吸収分割が組織法上の行為である一方で、事業譲渡が、効力発生について法定されているものではなく、当事者間の契約によって権利義務が移転する取引行為である点で異なります。
事業譲渡に関する会社法の定め
(1)競業禁止
譲渡会社は、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行うことはできません(会社法21条1項)。
ただし、当事者間において、競業避止義務を負わない旨を合意することは可能です。
(2)商号使用
まず、前提として、譲受会社が、譲渡の対象となる事業に係る債務を引き受けない旨を事業譲渡契約において定めている場合は、譲渡会社の債権者に対して責任を負いません。
しかしながら、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うことになります(会社法22条1項)。
(3)債務引き受け
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者に対し弁済の責を負うことになります(会社法23条1項)。
(4)事業譲渡の承認
譲渡会社においては、事業の全部の譲渡または重要な一部の譲渡について、株主総会の決議が必要となります(会社法467条1項)。
そのため、事業の一部を譲渡する譲渡会社においては、譲渡対象の事業が「重要」か否かによって株主総会決議の要否が決定されることになります。
(5)事業譲渡の承認が不要な場合
上述したとおり、譲渡会社においては、株主総会の決議が必要となる場合がありますが、略式事業譲渡等の場合には株主総会決議は不要です(会社法468条)。略式事業譲渡等とは、事業譲渡にかかる契約の相手方が、当該事業譲渡をする株式会社の特別支配会社である関係にある会社間の事業譲渡をいいます。
(6)反対株主の株式買取請求権
会社法上は、事業譲渡に反対する株主が保有する株式を、事業譲渡を行う会社に買い取らせることによって、株主の権利保護を図っています(会社法469条)。
事業譲渡の実行の流れ
資産・負債、権利・義務等の承継
(1)総論
事業譲渡は、吸収合併や吸収分割と異なり、権利義務が包括承継されることはなく、個々の取引により権利義務を個別に承継するものであるため、当該取引の相手方の同意が必要となります。また、事業を営む許認可等については、原則として譲受会社が取得する必要があります。
(2)不動産
上述したとおり、事業譲渡は、個々の取引により権利義務を個別に承継するため、譲受会社が、不動産の所有権を第三者に対抗するためには、個別に移転登記を行う必要があります。
(3)動産等
動産等も、不動産の場合と同様に、譲受会社が、動産の所有権を第三者に対抗するためには、個別に引き渡しを受ける必要があります。なお、動産の対抗要件としての「引き渡し」(民法178条)には、現実の引き渡し(民法182条1項)、簡易の引き渡し(民法182条2項)、占有改定(民法183条)、指図による占有移転(民法184条)があります。
(4)債権
売掛金等の債権も、動産等と同様に、譲受会社が、債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、個別に確定日付のある証書による債権譲渡通知を行う必要があります。
(5)債務
買掛金等の債務は、譲受会社が併存的債務引き受けをする場合であれば、譲渡会社と譲受会社との間で行うことができます(民法470条1項、3項)。
一方、譲受会社が免責的債務引き受けをする場合には、譲渡会社と譲受会社だけでは行うことができず、債権者の承諾も必要となります(民法472条1項、3項)。
(6)担保
まず、担保権者が事業譲渡を行う場合ですが、抵当権等の個別担保は、随伴性を有するため、事業譲渡をすると債権の譲渡に随伴して譲受会社に移転します。ただし、抵当権について、第三者に対して対抗要件を備えるためには、移転登記をする必要があります。
次に、担保権設定者が事業譲渡を行う場合ですが、事業譲渡によって担保権付き物件が移転します。ただし、担保権と債務は別個のものであるため、譲受会社が債務引き受けをしない限り、担保されている債務は変更されません。
デュー・デリジェンス
事業譲渡以外の組織法上の手続き(吸収合併、株式譲渡等)と同様に、譲受会社が、自社グループではない外の会社から事業を譲り受ける場合には、事業譲渡後に問題が生じうる事項に関して、各種事項についてデュー・デリジェンス(D・D)を行うことが一般的です。
D・Dの具体的な内容として、事業譲渡実行後の事業運営の検討、対象事業の価値の評価、事業譲渡契約の検討等があります。特に、通常の法務デュー・デリジェンスにおいては、設立等、株式、許認可等、資産(不動産・動産・知的財産等)、負債、契約関係、人事労務、環境、紛争関係、子会社関連等といった分野について調査を行うことが一般的ですが、事業譲渡は、対象会社の法人格そのものに着目した手続きではなく、会社の個々の事業に着目した取引であるため、組織法上の手続きと異なる点があることに注意が必要です。
会社法以外の規制
独占禁止法
(1)規制内容
独占禁止法は、事業譲受け等に関して、同法16条に掲げる行為をすることにより、「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない」旨を規定しています(独占禁止法16条参照)。次に掲げる行為とは以下のとおりです。
-
一 他の会社の事業の全部または重要部分の譲受け
-
二 他の会社の事業上の固定資産の全部または重要部分の譲受け
-
三 他の会社の事業の全部または重要部分の賃借
-
四 他の会社の事業の全部または重要部分の経営の受任
-
五 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
(2)手続規制
独占禁止法は同法16条2項本文において、一定の要件を満たす場合には、事業または事業場の固定資産の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないとしています。ただし、事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合には、届け出が不要になります(独占禁止法16条2項但書)。ここにいう、企業結合集団とは、会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であって他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社から成る集団をいいます(独占禁止法10条2項)。
労働法
ここでは、事業譲渡に伴う雇用契約の帰趨について述べます。
(1)従業員の引き継ぎ
事業譲渡においては、譲渡会社の従業員が譲受会社に承継されるのかが問題となりますが、実務上は、ある従業員を譲受会社に承継させ、雇用契約を引き継がせるためには、従業員本人の同意を取る必要があります。
(2)従業員の解雇
事業譲渡において、従業員の個別同意が得られず、譲受会社に承継されない従業員が出る場合があります。このような場合であっても、事業譲渡をしたことで事業がなくなったことを理由には解雇することは原則としてできません。そのため、一般の整理解雇と同様の判断基準により検討していく必要があります。
そして、事業譲渡が、特定の従業員のみを排除するなどの目的でなされた場合には、解雇権濫用法理の潜脱とされることもあり得るので注意が必要です。
倒産法
ここでは、支払停止状態にある会社の事業譲渡の注意点及び、破産手続と事業譲渡について述べます。
(1)支払停止状態にある会社の事業譲渡の注意点
会社の経営状態が芳しくない状態で事業譲渡をする場合には、詐害行為取消権(民法424条)を行使されたり、破産管財人に否認権(破産法160条以下)を行使されたり、事業譲渡についての株主総会(会社法467条1項等)に反対されてしまう等のリスクがあります。
(2)破産手続と事業譲渡
破産手続開始決定があり、会社が行っていた事業に換価価値がある場合には、裁判所が選任した破産管財人が裁判所の許可を得て事業譲渡を行うこととなります(破産法78条2項3号)。
また、上述のとおり、譲渡会社の資産状況が悪化している状況で事業譲渡している場合には、破産管財人に否認権(破産法160条以下)を行使される可能性があります。
事業譲渡のメリット・デメリット
売り手側のメリット・デメリット
売り手側のメリットとしては
- 事業全体ではなく、売りたい事業のみ譲渡できる
- 残したい従業員や資産を残せる
という点が挙げられます。当然、譲渡によって収益も発生する点も現実的にメリットとなります。
一方、デメリットとしては
- 負債が残る可能性がある
- 手続きが複雑になる
という点です。特に譲渡した事業について、個別に取引を行うため手続きが複雑になりがちです。取引先との基本契約や従業員の雇用契約などの契約を引く継ぐために手続きが多くなります。
買い手との契約の締結の仕方次第で回避できる可能性もありますので、事前に留意しましょう。
買い手側のメリット・デメリット
買い手にもメリットがあり、以下の点が挙げられます。
- リスクのある事業を承継する必要がない
- 負債や債務を引き継がない
買いたい事業のみを選択でき、不要な事業は引き継がない上に、必要な資産や負債のみ買収できます。
買い手側のデメリットとしては
- 買収した資産も課税対象になる
- 従業員との再契約が必要になる
というコストと工数の両方で負担が増える可能性があります。
【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら
この記事の執筆者飛渡 貴之(弁護士)
弁護士法人キャストグローバル代表弁護士。滋賀県生まれ、関西大学総合情報学部卒業後、パチプロをしていたことで、パチンコメーカーに就職し、新商品の企画開発に5年間携わる。
勤務中、土地家屋調査士の資格を取得し、独立を目指し司法書士の勉強を始め、退社後、合格。司法書士業務をするも、より質の高い法的サービスを提供したいとの思いから、弁護士を志す。
一般企業での会社員経験と定期的に国内外の優良企業を視察して得られた知識経験を生かしたコンサルタント色のある提案が多くの企業に喜ばれて、多数の企業を顧問に持つ。
この記事の執筆者椛島 慶祐(司法書士)
司法書士法人キャストグローバル在籍。福岡県生まれ。日本大学法学部法律学科卒業後、2014年司法書士試験合格。
2015年司法書士登録し、司法書士法人キャストグローバルに入社以来「企業法務、法務支援」に特化して創業者や中小事業、大企業の法務手続きを精力的に支援。これまでに500社以上の登記手続きやコンサルティングの実績がある、中小企業から大企業まで取引先は多岐に渡る。