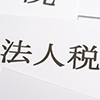合同会社の決算のやり方とは?決算から確定申告までの流れを解説
更新

合同会社の決算をどのように進めればよいのか、株式会社の場合とどう違うのか、疑問に思ってはいませんか。決算や確定申告は法人の義務であることから、期限内にきちんと遂行する必要があります。
本記事では、合同会社と株式会社の決算の違いや、決算を行う時期、確定申告の際に提出が必要な書類についてわかりやすく解説しています。合同会社の決算・確定申告を自分で行うことは可能かどうかにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社にも決算や確定申告が必要
合同会社には、決算や確定申告を行う必要があるのでしょうか。結論からお伝えすると、株式会社など他の企業形態と同様に、合同会社にも決算や確定申告が義務づけられています。
合同会社は、2006年に施行された新会社法で新設された企業形態の1つです。出資者と経営者が同一である点が株式会社との大きな違いでしょう。株主=経営者であることから、意思決定のスピードが早く、小資本で設立しやすいことが合同会社の主な特徴です。
合同会社が納めなければならない税金には、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税(課税事業者のみ)の4つがあります。合同会社も会社法に則って事業年度ごとに決算を行い、決算書を作成しなければなりません。決算書に基づいて法人税等を計算し、確定申告を行うのが基本的な流れです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社の決算と株式会社の決算の違い
合同会社と株式会社の決算には、どのような違いがあるのでしょうか。主な違いは手続きの流れです。
株式会社は、株主総会で決算内容等の承認を得たうえで、確定した決算に基づいて法人税等の計算を行う必要があります。それに対して、合同会社には株主総会がないため、出資者である社員(役員に相当)の合意により、迅速な意思決定が可能です。このように、合同会社は株式会社と比べて簡易的な手続きで、スピーディーに決算を進められます。
また、株式会社には決算公告(決算に関する情報を公に告知すること)の義務がありますが、合同会社にはありません。こうした点も、合同会社の決算に関する手続きが簡便化されている一例といえます。
なお、株式会社、合同会社を問わず、事業年度開始の日における資本金の額または出資金の額が1億円を超える場合には、e-Tax(電子申告)による申告が義務づけられているため注意しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社の決算はいつ行う?
合同会社の決算月は、1年以内であれば自由に決められます。決算月とは事業年度の最終月のことです。事業年度の初月から最終月までの期間の業績を基に、決算や確定申告を行います。
例えば、4月1日~3月31日を事業年度と定めたとします。この場合、決算月が3月となるためこの月に決算を行うことになります。決算月の決め方には特定のルールはありませんが、一般的には9月末、12月末、3月末といった四半期の最終月を決算月として設定しているケースが多く見られます。
なお、決算月は法人設立時に決定するほか、決定した決算月を設立後に変更することも可能です。決算月を変更する場合には定款に事業年度が記載されていれば定款を変更し、異動届書や総社員の同意書もしくは議事録を所轄の税務署に提出する必要があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社の決算から確定申告までの流れ
合同会社における決算から確定申告までの流れを解説します。具体的には、以下のステップで順番に進めていきましょう。
- 合同会社の決算から確定申告までの流れ
-
-
1.帳簿書類を整理する
-
2.決算整理仕訳を行う
-
3.決算書を作成する
-
4.計算書類の承認を行う
-
5.法人税等の確定申告と納税を行う
-
1 帳簿書類を整理する
合同会社において決算を行う際、まずは帳簿書類を整理しましょう。決算書を作成する際には、日々の取引を適切に記録し、正しく帳簿に反映させなければなりません。通常は決算月においても月次決算を行い、そのうえで年に一度の年次決算を行い帳簿の記載に漏れがないかを確認することが大切です。
また、売掛金、買掛金などの残高も正確であるかどうかを、請求書や領収書などの帳票を通じて検証します。預金残高などについては、通帳や残高証明書を確認し、残高を一致させる必要があります。
2 決算整理仕訳を行う
帳簿書類の整理が完了したら、次は決算整理仕訳をしましょう。決算整理仕訳とは、年次決算の際に行う特別な仕訳です。決算時点で、期中に作成した帳簿とずれが生じないよう修正し、企業の財産や収益を会計上適切に処理します。
決算整理仕訳の流れは、以下のとおりです。
- 決算整理仕訳の流れ
-
-
1.現金・預金の残高を実際に確認し、帳簿との過不足がないか確認する
-
2.売掛金や買掛金の金額を確認する
-
3.経過勘定を確認する(前払金、前受金、未払金、未収入金など)
-
4.決算時点の棚卸資産を確認する
-
5.固定資産を確認する(減価償却など)
-
6.有価証券の期末時価を確認する
-
7.貸倒引当金を設定する
-
決算整理仕訳についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
3 決算書を作成する
決算整理仕訳が完了したら、次は決算書を作成しましょう。合同会社は、主に損益計算書、貸借対照表、社員資本等変動計算書、個別注記表の4つの書類を決算書として作成し、提出します。
4 計算書類の承認を行う
決算書が作成できたら、計算書類の承認を行いましょう。株式会社であれば、株主総会のような特定の組織機関において計算書類の承認を得なくてはなりません。合同会社の場合、その必要はありません。会社法上も合同会社の決算書類の承認方法は定められていないため、定款の規定に従うことになります。定款に特段の規定がなければ業務執行社員全員の合意で問題ないでしょう。
5 法人税等の確定申告と納税を行う
計算書類の承認が得られたら、最後に法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)の確定申告と納税を行いましょう。決算日から2か月以内に確定した決算に基づき、法人税等の確定申告書を提出します。期限にあたる日が土曜日、日曜日、祝日などの場合は、その翌日(休み明けの平日)が期限です。申告期限の延長の申請をしている場合、提出期限は消費税を除いて決算日から3か月以内となります。また、課税事業者の場合は消費税についても同様の手続きがあります。消費税については、法人税の申告期限延長の特例を受けている法人に限り、「消費税申告期限延長届出書」を提出して、消費税の確定申告の期限を1月延長することができます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社の確定申告に必要な書類
合同会社が確定申告を行うには、どのような書類が必要になるのでしょうか。ここでは、合同会社の確定申告に必要な書類について、それぞれ解説します。
合同会社の確定申告時に提出が必要な書類一覧
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 法人税申告書 | 法人が事業で得た所得について申告するための書類 |
| 適用額明細書 | 租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する書類 |
| 貸借対照表 | 決算日時点での財務状況を示す書類 |
| 損益計算書 | 一定期間の収益と費用の損益計算をまとめた書類 |
| 社員資本等変動計算書 | 社員資本の変動事由を報告するための書類 |
| 勘定科目内訳明細書 | 貸借対照表や損益計算書の勘定科目の内訳を示す書類 |
| 法人事業概況説明書 | 法人の業務状況について示す書類 |
法人税申告書
法人税申告書とは、法人が事業で得た所得について申告するための書類です。法人税申告書は別表一から十九まであり、会社の状況により必要となる別表や明細書は異なります。詳しくは国税庁の「[手続名]法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)」記載を参照してください。
適用額明細書
適用額明細書とは、租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する書類です。適用額明細書は、法人税額や所得金額を減額する特例を適用した場合に、会社が適用した特例を一覧にして明示する役割があります。そのため、租税特別措置法などの適用がある場合、適用額明細書が必要となります。
貸借対照表
「企業がどれだけ財産を保有し、債務を負っているか」という決算日時点での財政状態を示す書類が、貸借対照表です。左右の金額が均衡状態を保っていることから、英語表記のBalance Sheetを略して、「B/S(バランスシート)」とも呼ばれます。
すべての会社は決算の際に、損益計算書と共に、必ずこの貸借対照表を作成しなければなりません。貸借対照表を見ると、会社が保有する現金や建物、ソフトウェアなどの形のない財産を含めた「資産」、いずれ返済しなければならない「負債」、返済義務のない自己資本である「純資産」を把握することができます。
損益計算書
損益計算書とは、ある一定期間の収益と費用の損益計算をまとめた書類で「P/L」とも呼ばれます。収益・費用・利益の3つの要素から成り立ち、「企業がどの程度売上を上げて(収益)」「費用を何に使って(費用)」「どれくらい儲けが出たのか(利益)」がひと目でわかります。貸借対照表と同様、すべての会社は決算の際に、必ずこの損益計算書を作成しなければなりません。
社員資本等変動計算書
社員資本等変動計算書とは、企業の純資産の変動を記載したもので、一会計期間における変動額のうち、主として、社員に帰属する部分である社員資本の各項目の変動事由を報告するための決算書類です。「社員資本」と「社員資本以外」に分けて、それぞれ当期首残高、当期変動額合計、当期末残高を記載します。貸借対照表や損益計算書ではわかりにくい純資産の部の流れを把握できます。
勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書とは、貸借対照表や損益計算書の勘定科目の内訳を示した決算書類です。決算日の翌日から2か月以内に、税務署へ提出する必要があります。勘定科目内訳明細書を提出することで、税務署は会社の各勘定科目ごとの数字の内訳をある程度細かく把握することができます。
法人事業概況説明書
法人事業概況説明書とは、法人の業務状況について示す書類です。法人名、納税地、事業内容、期末従業員数の状況、主要科目などを記載します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社の確定申告の期限
合同会社は、事業年度終了日の翌日から2か月以内に確定申告を行う必要があります。例えば、3月が決算月の会社であれば、2か月後の5月31日が確定申告の期限です。
なお、確定申告だけでなく税金の納付も同様の期限となっています。決算書の作成を計画的に進めると共に、納税準備金を確保しておくことが大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社が決算後に税金を納付しなかった場合のペナルティ
確定申告書の提出が期限内に終わっていても、法人税等を期限内に納付しなかった場合は、ペナルティが発生します。法人税等の支払い期限は「事業年度終了日の翌日から2か月以内」です。申告と納付のどちらも、2か月以内に行わなければならないことを忘れないようにしましょう。
原則的には、期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞税が課されることになります。また、期限までに申告をしなかった場合は「無申告加算税」の対象となり、故意に隠蔽した場合には、懲罰的な「重加算税」の対象となります。さらに、期日内に申告・納税できたとしても、内容に誤りがあった場合には同様にペナルティが発生する場合があります。
個人事業主の場合、自分で所得税の確定申告を行う人もいますが、法人の場合は計算が複雑で、税額も大きくなることが多いため、専門家の知識が必要です。申告書の作成は、税理士や会計士に依頼をするか、クラウド型会計ソフトを利用するのがおすすめです。個人事業主から法人化(法人成り)したばかりの方は注意しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
合同会社の決算・確定申告は自分でできる?
合同会社の決算・確定申告を自分で(一人会社の代表社員が自ら)行うことは法律上可能です。ただし、株式会社よりも手続き等が簡便化されているとはいえ、個人事業と比べて作成する書類が多く複雑なことから、税理士や会計事務所に依頼するケースの方が多いでしょう。
決算・確定申告を自分で行うメリットとして、税理士費用を削減できることや、財務状況を自ら把握して経営に活かせることなどがあげられます。その一方で、専門的な知識が求められること、時間と手間がかかること、節税対策が十分にできないことなどがデメリットです。
売上規模が小さい場合や、特段の節税対策を必要としない場合などは、自力での決算・確定申告を検討してもよいでしょう。ただし、日々の経理業務が正確に行われていることが前提となります。決算時のミスや混乱を防ぐには、会計ソフトを活用して日頃から記帳を丁寧に進めるのが得策です。
また、専門家に依頼する場合も日々の帳簿付けや収支管理、財務状況の把握ができていると、決算や確定申告をスムーズに進めやすくなります。会計ソフトですべての税務申告書を作成できるわけではありませんが、決算・確定申告に向けた準備を着実に実施しておくためにも、使いやすい会計ソフトの導入を検討することをおすすめします。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
日々の記帳を正確に実施して決算や確定申告をスムーズに進めよう
合同会社は株式会社と比べて、決算や確定申告をより簡潔に進めやすいというメリットがあります。その一方で、株式会社・合同会社を問わず法人の決算・確定申告は、個人事業主の確定申告と比べて作成すべき書類が多く、作業も煩雑になりがちです。自力で決算・確定申告を行う場合はもちろんのこと、税理士などの専門家に依頼する場合も、日々の正確な記帳が必須となります。会計ソフトを活用して、日々の記帳を正確かつ効率的に進めてみてはいかがでしょうか。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
よくあるご質問
合同会社に決算は必要?
合同会社は法人の一形態ですので、株式会社などの法人と同様に決算が義務づけられています。合同会社が納めるべき税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税(課税事業者のみ)の4つです。したがって、会社法に則って事業年度ごとに決算を行い、決算書を作成する必要があります。さらに、決算に基づいて法人税等を計算し、確定申告を行わなければなりません。
合同会社に決算が必要かについては、詳しくはこちらをご確認ください。
合同会社に決算はいつ行う?
合同会社の決算は定款に定められている事業年度に基づき、決算月に行います。決算月は1年以内であれば自由に決めることが可能です。例えば事業年度が4月1日~3月31日であれば、3月に決算を行います。申告書の提出期限は原則として2か月後の5月31日です。
決算をいつ行うかについては、詳しくはこちらをご確認ください。
合同会社の決算は自分でできる?
合同会社の決算は、他の会社形態と同様に経営者自身が自分で行っても法律上の問題はありません。ただし、複雑な作業を伴うことになるため、税理士や会計事務所に依頼する会社が多いのが実情です。決算を自力で行うことで、税理士費用を削減できたり、財務状況を自ら把握しやすくなったりするメリットを得られます。その一方で、専門的な知識が必須となるほか、時間や手間がかかることや節税対策を十分に施せないケースも多いことがデメリットです。
合同会社の決算を自分でできるかについては、詳しくはこちらをご確認ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。