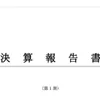決算業務とは?決算の流れや注意点、効率化のポイントなどを解説
更新
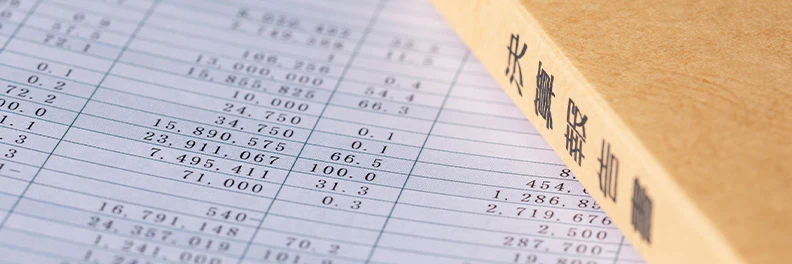
決算業務は、年間または一定期間の全取引をまとめて、決算書類を作成する作業のことです。重要な業務ではあるものの、タイトなスケジュールの中で進めることも多く、いかに正確かつ効率的に行うかがポイントとなります。
本記事では、決算の種類や決算業務の流れ、事前に準備したい具体的な作業について解説しています。決算業務の効率化につながる工夫にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
決算業務とは一定期間の全取引をまとめる業務
決算業務とは、事業年度ごとなど一定期間の企業の全取引をまとめて、決算書類を作成する作業のことです。一連の作業を通じて作成される決算書類は、経営判断や納税額の確定、株式会社に関しては株主への報告などに用いられます。そのため、正確性と期限の厳守が求められる重要な業務です。
決算業務の種類・頻度・目的を整理
決算業務には、毎月行う月次決算業務や四半期ごとに行う四半期決算業務、1年ごとの本決算業務などがあります。年間の全取引をまとめる本決算業務は、すべての法人に義務付けられていて、納税額を決定するうえで欠かせません。
決算業務の種類・頻度・目的
| 種類 | 頻度 | 目的 |
|---|---|---|
| 年次決算(本決算) | 事業年度ごと |
|
| 中間決算(半期決算) | 6か月ごと |
|
| 四半期決算 | 3か月ごと |
|
| 月次決算 | 1か月ごと |
|
上場企業と非上場企業の決算業務の違い
決算業務で作成する財務三表のうち、上場企業・非上場企業のどちらにも作成義務があるのは、貸借対照表と損益計算書の2つです。キャッシュ・フロー計算書に関しては、上場企業にのみ作成義務があります。
また、上場企業の場合、決算開示には「45日ルール」と呼ばれるものがあります。これは、決算期末後45日以内に、株主などに対して決算内容を開示するというルールです。45日を超えた場合の罰則はありません。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
決算業務はいつ行う?
決算業務の中でも、年次決算(本決算)業務を行う時期について解説します。法人の場合、個人事業主の場合に分けて見ていきましょう。
法人の場合
法人の年次決算は、会計期末に実施します。法人の場合、会計期間は任意で決められますが、国の会計年度が4月から3月のため、これと合わせて3月31日を決算日としている企業が少なくありません。
決算業務を行って確定した法人税等は、原則として決算日から2か月以内に申告します。3月31日が決算日の企業であれば、5月31日が申告期限です。
個人事業主の場合
個人事業主の会計期間は毎年1月1日から12月31日と決められています。年が明けたタイミングで決算業務を行う流れです。前年の1月1日から12月31日までの収益と費用を取りまとめ、年間の所得を算出します。
所得税の確定申告書は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に提出します。その際、青色申告者の場合には青色申告決算書、白色申告者の場合には収支内訳書など、決算の結果を示す書類を添付する必要があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
決算業務の流れ
期末に行う決算業務の流れについて、経理担当者が実際に行う決算業務のフローを、段階を追って見ていきましょう。 例えば株式会社の場合、法人税等の申告は原則として決算日から2か月以内、株主総会の開催は決算日から3か月以内となり、タイトなスケジュールの中で決算業務を進める形となります。
決算業務の流れ
-
1.
決算残高を確定させる
-
2.
決算整理仕訳をする
-
3.
決算書を作成する
-
4.
税金の申告書を作成する
1. 決算残高を確定させる
法人において決算業務を行う際には、まず決算残高を確定させましょう。
帳簿で管理しているすべての勘定科目(現金、預金、売掛金、買掛金、借入金、固定資産など)の残高を比較して、決算日時点での勘定科目の残高と実際の残高が一致しているかを確認します。
決算残高が確定した後は、「勘定科目内訳明細書」(勘定科目の詳細を示した書類)を作成します。それぞれの勘定科目の残高の確認方法は以下のとおりです。
各勘定科目の残高の確認方法
| 勘定科目 | 確認方法 |
|---|---|
| 現金や小口現金 | 手元の金庫等で確認する |
| 預金残高や借入金 | 金融機関に「決算日現在の残高証明書」の発行を依頼し、残高を確認する |
| 買掛金、未払金 | 決算日時点で経費計上しているが、支払はされていないものを集計し、残高を確認する |
| 在庫商品や材料 | 棚卸をして、実際の在庫を算出することで残高を確認する |
| 固定資産 | 年度内の新規取得、除却・売却を確認し、減価償却費を計算して帳簿上の残高を確定させる |
2. 決算整理仕訳をする
決算書の作成に先立ち、決算整理仕訳を行います。決算整理仕訳とは、減価償却の計上などによって帳簿上のズレを修正したり、企業の財産や収益を会計上適切に処理したりする特別な仕訳のことです。具体的には、期末棚卸高に応じた売上原価の計算や、固定資産の減価償却費の計上、貸倒引当金の設定などが含まれます。
3. 決算書を作成する
仕訳がすべて完了したら、決算書の作成へと移ります。法人決算で作成する主な決算書は以下のとおりです。
法人決算で作成する主な決算書
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 貸借対照表(BS) | 決算日現在の資産と負債、純資産の状態を表す決算時の残高一覧のような書類 |
| 損益計算書(PL) | 収益と費用の損益計算をまとめ、一事業年度の利益を把握するための書類 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 財務活動、営業活動、投資活動における現金の動きを記載した書類。上場企業に作成義務あり |
| 個別注記表 | 貸借対照表や損益計算書など各決算書類の注記事項を一覧にしてまとめた書類 |
| 株主資本等変動計算書(SS) | 1年間を通した株主資本の変動を表す書類 |
| 個別注記表 | 貸借対照表や損益計算書に関する注記など、各計算書類に記載されていた注記を1つの書面として一覧表示する計算書類 |
| 事業報告書 | 事業年度ごとの会社の事業内容や状況について報告する書類 |
| 事業報告の附属明細書 | 事業報告を補足する重要な事項を示す書類 |
個人事業主に関しては、青色申告の場合は損益計算書や貸借対照表などで構成される青色申告決算書を作成します。白色申告の場合は収支内訳書を作成しましょう。
4. 税金の申告書を作成する
決算書を作成し終えたら、税金の申告書を作成します。法人の場合は法人税、法人事業税、法人住民税、消費税(課税事業者のみ)を、原則として決算日の翌日から2か月以内に納付しなければなりません。
個人事業主に関しては、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を作成し、所得税を納付します。消費税の課税事業者は消費税の確定申告と消費税の納付も3月31日までに行う必要があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
決算業務における注意点
決算業務における注意点を解説します。
日頃から請求書データや領収書等の会計資料の整理を徹底しておく
決算業務をスムーズに行うためには、日頃から取引先名や取引年月日、金額などの請求書データや領収書等の会計資料の整理を徹底しましょう。決算業務を行うことができる期間は、わずか2か月しかありません。多くの企業は決算業務の期間内に、決算書をはじめとする多くの書類を作成する必要があります。
そのため、そこから請求書データや領収書等の会計資料の整理を始めていては、決算に間に合わなくなる恐れがあります。経理担当者は、日々の業務で取り扱う請求書データや領収書等の会計資料をすぐに検索できるよう、事前に整理しておくことが大切です。
できる限り前倒しで決算準備を進めておく
できる限り前倒しで決算準備を進めておくことも、決算業務をスムーズに行うコツです。決算業務に慣れていない人や、決算の知識が不足している人が作業を行う場合は特に、極力前倒しで準備を進めておきましょう。無理なスケジュールを立てると、経理担当者の業務負担が増し、ミスを招きかねません。そうならないためにも、計画的に準備を進めることが大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
決算業務前に準備しておきたい具体的作業
決算業務に向けた準備として以下の5つの作業を進めておくと、決算業務がスムーズに進行し、速やかに決算書の作成へと移れるでしょう。
決算業務をスムーズにする事前作業
- 倉庫や店舗にある在庫を点検し、数量や保管状態を確認する「実地棚卸」を行う場合は、在庫の場所がわかる倉庫の見取り図や、作業のタイムスケジュールの作成、役割分担を決めるなどの準備をする
- 帳簿と一致しているか確認が必要な、現金・預金・借入金の残高を確認しておく
- 実際の残高と一致しているか確認が必要な、取引先ごとの売掛金や買掛金の残高を確認しておく
- 受取手形や支払手形の記入帳と帳簿の残高が一致しているか確認しておく
- 固定資産台帳の金額と帳簿の固定資産の金額が一致しているか確認しておく
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
決算業務を効率化するには?
決算業務はただでさえ膨大なデータを扱う大変な業務です。情報をあらかじめ整理しておき、効率的に業務を進めなければなりません。
ここでは、決算業務を効率化するポイントについて紹介します。
決算業務を効率化するには?
- 月次決算を行う
- 提出する書類や納税の期限から逆算して作業する
- 会計システムを使用する
月次決算を行う
決算業務を効率化したいのであれば、月次決算を行うことが大切です。月次決算とは、1か月ごとの決算業務のことで、月次損益計算書と月次貸借対照表を作成します。
月ごとの帳簿をまとめて正確な月次決算報告書を作成しておけば、年次決算の際に業務を大幅に軽減できます。月次決算を行っていれば、年次決算の前にさまざまな予測が立てられるため、そこから得た情報を節税対策や予算修正、資金計画などに活かすことも可能です。
また、金融機関から融資を受ける際、月次決算報告書をすぐに提出できるので、融資を受けるまでの期間を短縮できる場合もあります。
提出する書類や納税の期限から逆算して作業する
提出する書類や納税の期限から逆算して作業することで、決算業務を効率化できます。提出前に何かしら問題が発生する可能性も考慮して、予備日を含めたスケジュールを立てておきましょう。「いつまでに、どの作業が終わっていなければならないのか」を考えて、見直してみることが大切です。
会計システムを使用する
会計システムを活用することで、決算業務を効率化できます。最近は、会計ソフトやクラウドシステムを導入する企業も増えています。これらを利用すれば日々の経理業務を自動化でき、正確な帳簿管理が可能です。日々の経理業務の正確性が上がれば、決算業務における工数を削減でき、効率的に決算業務を行うことができるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
「弥生会計 Next」を導入して、決算業務を効率化しよう
決算業務は、決算書類の作成を通じて年間の全取引をまとめ、会社の経営状態や財務状況を把握するための業務です。月次決算を着実に実施するなど、必要な準備を行っておくことで事業年度末の決算業務をスムーズに進められるでしょう。正確な決算書類を作成するには、日々の経理業務をミスなく進めることが大切です。クラウド会計ソフト「弥生会計 Next」を活用して、決算業務の効率化を図ってみてはいかがでしょうか。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
よくあるご質問
決算業務でやることは?
決算業務の基本的な流れは「決算残高の確定」「決算整理仕訳の実施」「決算書の作成」「税金の申告書の作成」という4つのステップです。決算書類のうち、貸借対照表と損益計算書に関しては、上場企業・非上場企業を問わず作成が義務付けられています。上場企業の場合は、これに加えてキャッシュ・フロー計算書の作成も必須です。
決算業務でやることについては、詳しくはこちらをご確認ください。
決算業務で大変なことは?
決算業務では、膨大な量の取引を取りまとめて決算書に正しく反映させる必要があります。会計ソフトを活用するなどして、日頃から取引先名や取引年月日、金額などの請求書データや、領収書等の会計資料の整理を徹底しておくことが大切です。また、月次決算を実施して月ごとの取引内容を確定させておくことにより、決算業務をスムーズに進めやすくなるでしょう。
決算業務の大変さについては、詳しくはこちらをご確認ください。
決算業務はいつが忙しい?
法人の年次決算は各社が任意に決めた会計期間末に行われますが、3月31日を決算日としている企業が多い傾向です。個人事業主の場合は会計期間が毎年1月1日から12月31日までと決められているため、年が変わったタイミングで決算業務を実施するのが一般的です。提出すべき書類や納税の期限から逆算して作業を進めておくことで、決算業務を効率的に進めやすくなります。提出前に何らかの問題が発生する可能性も考慮して、余裕をもったスケジュールを立てておきましょう。
決算業務の忙しい時期については、詳しくはこちらをご確認ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。