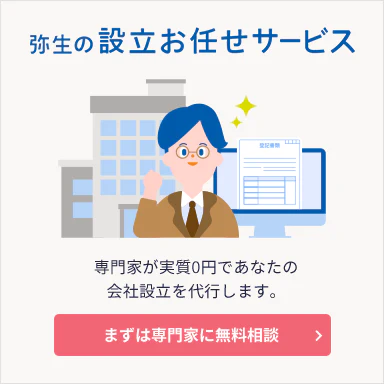飲食店の開業費・初期費用はいくら?資金調達方法や抑えるポイント
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

飲食店を開業しようとするとき、必ず考えなければいけないのが開業費です。飲食店を開くには、物件の取得費用や内外装費、機器・設備費、広告費など、さまざまな費用がかかります。
ただ、飲食店といっても、席数の多いレストランなのか、気軽に使えるカフェなのか、テイクアウト中心の小規模の店なのかといったように、どのようなお店を開きたいかによって、開業に必要な資金は変わります。
本記事では、開業費の相場や飲食店の開業にかかる費用の内訳、開業費を抑えるポイントを解説します。開業費を調達する方法についてもご紹介しますので、開業費を用意する際に参考にしてください。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業費は相場を参考にして考えよう
飲食店の開業費は、相場を参考にして考えてみてください。一般的な開業費の相場をもとにすることで、自分がどの程度開業費が必要なのかをイメージしやすくするためです。
まずは、一般的な開業費の相場を確認して、開業費の相場をつかみましょう。
飲食店を開くには1,000万円程度の費用が必要
日本政策金融公庫国民生活事業が2022年4月から同年9月にかけて融資した企業のうち、融資時点で開業後1年以内の企業7,032社(不動産賃貸業を除く)を対象とした日本政策金融公庫総合研究所の「2023年新規開業実態調査」(2023年11月)によれば、開業費の平均値は1,027万円、中央値は550万円です。また、開業費の分布は、以下のようになっています。
開業費の相場
- 500万円未満:43.8%
- 500万~1,000万円未満:28.4%
- 1,000万~2,000万円未満:18.8%
- 2,000万円以上:9.0%
上記を見ると、開業費が500万円未満の割合が最も多く、4割以上を占めていますが、必要な資金額は業種によって変わります。
飲食店の場合は、店舗を借りる契約金に加えて内外装の工事や設備投資が必要なので、開業時の費用が高額になりがちです。店舗の規模や業態によっても異なりますが、一般的に飲食店を開くには、1,000万円程度の開業費が必要といわれているため、その程度の金額を見積もっておくと良いでしょう。
- ※飲食店の起業・開業については以下の記事を併せてご覧ください
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
飲食店の開業費の内訳には運転資金や生活資金も含める
飲食店の開業にあたっては、何にどのぐらいの費用がかかるかを想定し、開業費を準備しておく必要があります。また、開業してすぐは売上が安定しない場合も多いため、当面の運転資金や生活資金の確保しておくようにしてください。
飲食店の開業にかかる費用には、主に以下が挙げられます。
飲食店の開業にかかる費用
- 物件取得費用
- 店舗設備費用
- 運転資金
- 生活資金
物件取得費用
飲食店を開業するには、物件取得費用がかかります。賃貸物件を借りる場合、「敷金」や「礼金」「仲介手数料」「保証金」が必要になるからです。加えて、一般的には前払い家賃として、10か月分程度の家賃が必要です。
いわゆる居抜き物件で、過去に入居していた店舗の内装や厨房設備、什器などをそのまま利用する場合には、前の借主に対して造作譲渡料を支払わなければなりませんが、一から内装を行う場合よりもかかる費用は安くなる場合が多いようです。開業資金があまり用意できない場合には、居抜き物件での開業も検討してみましょう。
店舗設備費用
飲食店を開業するには、店舗設備費用がかかります。看板や店舗の装飾などの外装工事のほか、壁や床、天井、厨房、配管などの内装工事も行うためです。内装工事にかかる費用は、カウンターのみの小さなお店で600万円以上、内装にこだわると1,500万円以上かかることもあります。
水道管や排水設備を引き入れるための工事が必要になるため、厨房といった水回りは高額になりがちです。事前に調べておくようにしてください。その他、厨房機器やテーブル、椅子、レジなどの機器・設備を揃えるための費用も必要です。
電話やインターネットなど通信回線の工事が必要な場合には、費用も開業費に含んでおきましょう。
運転資金
飲食店を開業するには、運転資金がかかります。家賃や光熱費、仕入れ代金、人件費といった費用は、飲食店を運営していくうえで継続的にかかるためです。
飲食店の開業直後は、思うように売上が上がらないことも珍しくありません。しかし、たとえ売上がゼロであっても、運転資金は毎月継続的に必要です。飲食店を開業するときは、多くの飲食店が事業を軌道に乗せるまでに半年以上かかったという結果もあります。そのため、店舗設備などにかかる初期費用に加え、最低でも6か月分の運転資金を準備しておいた方が良いでしょう。
生活資金
飲食店を開業するには、自分自身の生活資金がかかります。事業を成長させることも必要ですが、自分の生活もあるためです。上記のとおり、売上が安定するまでの期間を考えると、こちらも運転資金と同様に、6か月分程度の生活費を用意しておくと安心です。
自宅の家賃や光熱費、食費など、生活に必要な費用を計算し、資金計画に組み込んでおきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
飲食店の開業費を抑えるためのポイント
飲食店を開業するにはさまざまな費用がかかりますが、開業費の中でも大きな割合を占めるのは、店舗や設備などにかかる初期費用です。費用を抑えるには、次のような方法を試してみるといいでしょう。
飲食店の開業費を抑えるためのポイント
- 事業計画の見直し
- 居抜き物件を借りる
- 物件の希望条件を変更する
- 中古やアウトレットの備品を購入する
- 設備のリース契約を活用する
- 自分で店舗を改装する
事業計画の見直し
飲食店の開業費を抑えるためのポイントには、事業計画の見直しが挙げられます。
事業計画とは、どのように事業を運営し、どう利益を上げていくのかという、具体的な行動計画です。開業費を計算し、想定よりも高すぎると感じた場合は、事業計画が適切かどうかを見直すことで改善できる場合があるためです。
事業内容や収益見込みなどをまとめた事業計画書は、後述する開業費を調達する場面でも必要になります。
弥生の資金調達ナビ「創業計画をつくる」を利用すると、創業費用や売上見込み金額などから創業後の利益や資金繰りを自動計算し、飲食業に合わせた具体的な数値計画を作成することができます。
また、事業計画の立て方に迷ったときは、税理士などの専門家に相談するのも1つの方法です。
弥生の「税理士紹介ナビ」なら、会社設立や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家を無料でご紹介可能なので、利用を検討してみましょう。
居抜き物件を借りる
飲食店の開業費を抑えるためのポイントには、居抜き物件を借りることも挙げられます。
前のテナントの設備や内装をそのまま使える居抜き物件を選べば、内装費や設備費の削減が可能になるためです。
レストラン、カフェ、居酒屋など、開業したい店舗と同じ業態の居抜き物件を利用できれば、店舗設備にかかる費用を抑えることができるはずです。
特に、高額になりがちな水回りの工事が不要になれば、開業費全体の金額もかなり変わってくるはずなので、選択肢のひとつになるでしょう。
物件の希望条件を変更する
飲食店の開業費を抑えるためのポイントには、自分が借りたい物件の希望条を変更することもあります。
出店する場所や店舗の広さなどを優先しすぎると、物件の賃料が高くなってしまうためです。敷金や礼金、仲介手数料などは家賃を基準に設定されるので、家賃が低いほど初期投資を抑えることが可能です。
必要な売上と確保したい席数、集客見込みなどを想定し、条件を満たす出店場所や坪数の物件を探してみてください。
中古やアウトレットの備品を購入する
飲食店の開業費を抑えるためのポイントには、中古やアウトレットの部品を購入することも挙げられます。
テーブルや椅子、棚、厨房機器などにリサイクル品やアウトレット品を活用するのも、費用を抑えるためには効果的です。特に、厨房機器は高額なので、中古品を利用すれば初期費用の大幅な削減が見込めます。開業準備に取り掛かる前に、新品で購入する物と中古でも問題ない備品を整理しておくといいでしょう。
設備のリース契約を活用する
飲食店の開業費を抑えるためのポイントには、設備のリース契約の活用もあります。厨房機器や什器、レジなどの設備を、購入する必要がなくなるためです。
リース契約を活用すれば、機材購入のための高額な初期費用は必要ありません。ただし、毎月のリース代金を運転資金に組み込んでおいてください。
自分で店舗を改装する
飲食店の開業費を抑えるためのポイントには、自分で店舗を改装することも挙げられます。
店舗の装飾にこだわりすぎず、できるだけ自分で行えば、業者に内装工事を依頼するのに比べて費用を抑えられるためです。
最近では動画やSNSでもDIYのやり方を学べるので、自分で空き時間に少しずつできるところもあるはずです。自分が作りたい店舗のイメージ画像を集めておくと、イメージをぶらさずに改装を行えるでしょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
飲食店の開業費を増やすためには資金調達も考えよう
飲食店の開業費を増やすためには、資金調達も検討したい方法の1つです。
開業費の全てを自己資金でまかなうことができれば理想的ですが、実際にはなかなか難しいものです。前述の日本政策金融公庫総合研究所の「2023年新規開業実態調査」(2023年11月)によると、開業時に苦労したこととしては、資金繰りや資金調達を挙げる人が59.6%と、最も多い結果になっています。
資金繰りで苦労している起業家が多いため、開業費の内訳に運転資金や生活費も含めて考えた方が良いといえます。資金調達をすればある程度まとまった資金を入手できるので、余裕を持って経営を行うことができるため、検討するようにしてください。
開業費における資金調達先は、金融機関等からの借り入れと自己資金が約9割
資金調達先は、金融機関等からの借り入れと自己資金が全体の約9割を占めています。
日本政策金融公庫総合研究所の「2023年新規開業実態調査」(2023年11月)によれば、開業時の資金調達額の平均は1,180万円となっています。また、資金調達先としては、金融機関等からの借り入れが平均768万円(平均調達額に占める割合は65.1%)、自己資金が平均280万円(同23.8%)であり、合わせると全体の88.8%を占めます。
開業資金が自己資金だけでは足りないときには、次のような調達方法を検討してみてください。
飲食店の開業費の調達方法
- 親族から調達する
- 日本政策金融公庫の融資を受ける
- 制度融資を利用する
- 補助金や助成金を利用する
親族から調達する
飲食店の開業費の調達方法には、親族から調達することが挙げられます。
飲食店を開業するときに、親族から資金提供を受けるケースは少なくないためです。ただし、開業にあたってお金を借りた場合には、たとえ親族からの借入金であっても自己資金とは見なされないため注意しましょう。金融機関に融資を申し込む際にも、借入金を自己資金とすることはできません。
なお、親族から贈与されたお金であれば自己資金に含まれますが、贈与税が課される可能性もあるため、注意が必要です。
日本政策金融公庫の融資を受ける
飲食店の開業費の調達方法には、日本政策金融公庫の融資を受けることが挙げられます。
日本政策金融公庫は国が100%出資している政府系金融機関で、起業・開業時に利用できる融資制度があるためです。
日本政策金融公庫の融資を希望する場合には、日本政策金融公庫に直接問い合わせるだけでなく、近隣の商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、都道府県の生活衛生営業指導センターといった場所でも相談が可能です。日本政策金融公庫のWebサイト「融資制度を探す」でも、融資情報について確認できるかチェックしてみましょう。
制度融資を利用する
飲食店の開業費の調達方法には、制度融資を利用することも挙げられます。
自治体・金融機関・信用保証協会が連携して行う制度融資は、信用保証協会が創業間もない会社の債務保証をすることで、金融機関からの融資を受けやすくするしくみになっているからです。そのため、事業実績のない時期の開業費の調達にも利用しやすいでしょう。融資を希望する場合は、お近くの信用保証協会に直接問い合わせるか、指定金融機関を経由して申し込みができるので検討してみてください。
補助金や助成金を利用する
飲食店の開業費の調達方法には、補助金や助成金を利用することが挙げられます。
補助金・助成金は、中小企業庁や厚生労働省などによる支援制度であるためです。いずれも受給には審査があり、一定の資格が必要な場合もあるため、条件を確認しておきましょう。
以下は、飲食店が開業時に利用できる主な補助金・助成金なので、自社が要件に当てはまりそうな場合は利用を検討してみてください。
飲食店の開業時に利用できる主な補助金・助成金
| 補助金・助成金名 | 概要 |
|---|---|
| トライアル雇用助成金 | 安定した就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により一定期間試行雇用した場合に、費用の一部が助成されます。例えば、飲食店業界での経験がない人材を採用する際などに、この制度を利用して見極められるでしょう。 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用者の正社員化や待遇改善を行った場合に助成が行われます。正社員化支援と処遇改善支援でコースが分かれ、申請までの流れが異なります。例えば、アルバイトで勤務していた方を正社員として登用する場合などに可能です。 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度などの制度変更に対応するために、必要な経費の一部を補助する制度です。例えば、モバイルオーダーシステムの導入などに利用可能です。 |
| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者が、ITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。通常枠に加え、会計ソフトなどの導入費用の一部を補助するデジタル化基盤導入枠や、サイバー攻撃のリスクを軽減するためのセキュリティ対策推進枠もあります。例えば、外国人観光客に向けて、翻訳ロボットを導入する際などに利用可能です。 |
- ※創業時に利用できる補助金については以下の記事を併せてご覧ください
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
起業や開業の手続きを手軽に行う方法
飲食店の開業を機に、会社を設立する場合があるでしょう。会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」です。「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。
また、まずは個人事業主として開業し飲食店の運営を行う場合もあります。開業手続きを手軽に行いたい場合には、「弥生のかんたん開業届」がおすすめ。「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、開業届をはじめ、青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書などもスムーズに作成することができます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
飲食店の開業にかかる費用を計算して、しっかり準備しておこう
飲食店を開業するには、店舗設備の初期費用や運転資金、生活資金などをあらかじめ準備しておく必要があります。飲食店の開業費の目安は1,000万円程度だといわれていますが、必要な金額は店舗の規模や業態、提供するメニューなどによって異なります。飲食店を開業するときに綿密な事業計画を立てて、必要な資金をシミュレーションしておきましょう。
また、会社を設立する場合には「弥生のかんたん会社設立」、個人事業主として開業する場合には「弥生のかんたん開業届」などのクラウドサービスを利用すると、必要書類の作成などの手続きがスムーズに行えます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。