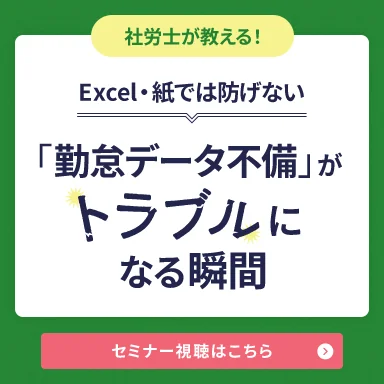タイムカードの計算方法は? 労働時間と賃金の基本的な考え方も解説
更新

タイムカードに記録された時刻から労働時間を計算する際は、総労働時間、時間外労働時間、休憩時間などを正確に算出することが重要です。
本記事では、タイムカードの効率的な計算方法、タイムカードに反映するべき労働時間、労働時間の計算、時間外労働の割増賃金などを解説します。また、勤怠情報の管理期間や注意点、適正に管理をしていない場合の労働基準法違反などのリスク、計算に関するよくある質問も紹介しているので、タイムカードの計算方法を検討する際の参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
タイムカードの効率的な計算方法
タイムカードの計算には、電卓やExcelを使用する、勤怠管理システムを使うなどの方法があります。効率的に計算するには、それぞれの特徴をふまえて自社に合った計算方法を導入することが大切です。
電卓やExcelで計算する
タイムカードから給与を計算する場合、手作業なら電卓を使うのがおすすめです。特に60進数を計算できるボタンがあるものを使えば、専用のボタンを使いながら、8時30分を「8」「30」などの操作で入力できるため、簡単に勤務時間の計算が可能です。
ただ、10進法のみの一般的な電卓は、7時間30分を「7.5」と自分で10進数に変換してから計算する必要があり、「分」を「時間」に変換する手間がかかります。また、電卓での計算は手軽にできる一方で、どうしても入力間違いなどの人為的なミスが起こりやすいため、最近はExcelなどの表計算ソフトを使って勤務時間を計算するのが一般的です。
Excelなら、関数を使用した表に数値を入力するだけで労働時間の算出が可能です。インターネット上にはサイトから無料でダウンロードして使えるテンプレートもあるため、それを用いると効率的に勤怠管理を行えます。ただし、Excelでも数値の入力は人が行うため、入力ミスが発生するリスクはあります。加えて、集計や法改正のたびにファイルを追記修正したりする手間がかかる点に注意が必要です。
勤怠管理システムを使う
最も効率的なタイムカードの計算方法は、勤怠管理システムや給与計算ソフトを導入することです。勤怠管理システムを使用すれば、手動で出勤時間や退勤時間を入力しなくても、勤怠データの活用によって労働時間の合計や残業時間の合計などの労働時間が自動集計されます。
さらに給与計算ソフトを導入すると、給与の自動計算も可能です。導入によって入力時に生じやすい人為的ミスを減らせるだけでなく、入力やExcelファイル修正などにかかる手間を削減でき、作業効率を大幅に向上できます。ただし、システムの導入には初期設定費用や導入サポート費用などの導入コストがかかる点を理解しておきましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
タイムカード管理における労働時間と賃金の基本的な考え方
タイムカードで労働時間を管理する場合、労働時間に含まれる時間と含まれない時間に注意が必要です。労働時間は切り捨てをする計算が認められていないため、タイムカードに記載されている時間は原則として1分単位での計算が求められます。
原則的に着替えや準備時間も労働時間に含まれる
厚生労働省が2017年に策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間を以下のように規定しています。
「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」
-
引用:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
」P.1
つまり、実際に業務に従事した時間だけでなく、その準備や後片付けに費やした時間も労働時間に当たるといった内容です。そのため、使用者には労働者に賃金を支払う義務が生じます。具体的には制服への着替え、待機中、資料作成のための情報収集や機材の後片付け、業務に必要な研修などの時間も労働時間に該当します。
休憩時間は差し引く
休憩時間は労働時間に該当しないため、給与計算の際には休憩時間を差し引いて計算します。ただし、休憩前後の打刻は義務ではなく、タイムカードに休憩時間が記載されていない場合もあります。
休憩時間の記録がなく出退勤の時間のみのタイムカードを使用しているなら、給与計算時には休憩時間の計算漏れに注意が必要です。シフト制で毎日の休憩時間が異なる場合や残業によって休憩時間が普段と異なる場合などには、その都度正確な休憩時間を記載しておくことが重要です。
原則として1分単位で計算する
労働基準法第24条において、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。賃金の全額を労働者に支払わなければならない、この「全額払いの原則」があるため、使用者は労働者の労働時間を残業時間まで1分単位で正確に記録・管理して、労働に応じた賃金を支払わなければなりません。労働者が遅刻・早退・中抜け等した場合に賃金控除できるのは、遅刻した時間を1分単位で計算した賃金に限られます。
-
引用:e-Gov法令検索「労働基準法 第二十四条」
労働時間の計算を15分単位や30分単位に設定し、「17時12分で退社したので17時退社とする」といった労働時間の切り捨てを行うと、労働基準法に抵触します。電卓やExcelでの集計時には労働時間の過剰な切り捨てに注意しましょう。
-
参照:厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」
1か月単位での端数処理はできる
時間外労働や深夜労働、休日労働などの労働時間については、事務処理の簡略化を目的としたものとして、例外的に認められる処理方法があります。1か月単位で、時間外労働・深夜労働・休日労働などそれぞれの合計時間に1時間未満の端数が生じた場合、30分未満の端数は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることが可能です。
1日ごとの労働時間や残業時間を計算する際に、上記の端数処理をすることは労働基準法違反となります。ただし、1日ごとの端数処理であっても、端数は常に切り上げるとする処理であれば問題ありません。
法定労働時間を超えたら割増賃金を支払う
労働基準法で定められている法定労働時間は、1日8時間、1週間では40時間です。法定労働時間を超える時間外労働をさせる場合は、使用者は労働者に割増賃金を支払わなければなりません。
割増の割合は、通常の賃金の2割5分以上(月60時間を超過する場合は5割以上)です。通常の時給が1,000円なら、時間外労働に対して、割増分を含む時給1,250円(1,500円)以上の賃金を支払う必要があります。
-
参照:e-Gov法令検索「労働基準法」
法定労働時間の例外
ただし、法定労働時間には例外もあります。商業や映画(映画制作を除く)、演劇、保健衛生や接客娯楽の業種で労働者が10人未満の事業場は特例措置の対象となるため、週の法定労働時間を44時間として計算することができます。この場合は週44時間を超えた部分の労働時間に割増賃金が生じます。
また、時間外労働だけでなく、22~5時の深夜労働や、休日出勤(法定休日・所定休日)に対しても割増賃金は発生します。ここでいう法定休日とは、労働基準法で定められた週1日、または月4日の法定休日に出勤することです。その一方で、所定休日とは、法定休日ではない休日のことです。
深夜労働の割増賃金は時間外労働と同じく通常の賃金の2割5分以上で、休日出勤の割増賃金について、所定休日の場合は、通常の賃金の2割5分以上、法定休日の場合は3割5分以上と定められています。
深夜労働や休日労働の割増賃金
時間外労働で深夜労働になる、休日出勤で深夜労働になる場合など、割増賃金が重複している場合には該当する割増賃金をすべて支払わなければなりません。例えば、深夜の時間外労働には2割5分の割増が2つ該当するため、合計5割以上の割増賃金を支払う義務が生じます。
ただし、法定休日には法定労働時間が定められていないため、休日出勤に時間外労働の加算が生じないことは覚えておきましょう。また、割増賃金計算においては、1時間当たりの割増賃金額に円未満の端数が生じた場合の端数処理が認められています。
従業員の勤怠情報は5年間保管する
タイムカードを始めとした従業員の勤怠情報の保管期間は、労働基準法第109条、143条で「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない」と定められています。(現在は、その期間が例外的に3年となっている。)
-
引用:e-Gov法令検索「労働基準法 第百九条」
労働時間計算後すぐに書類を破棄してしまった場合、給与支給ミスなどで再計算が必要になった場合に正確な給与計算ができません。また、労働基準監督署が労働時間について調査に来た際、勤怠情報の提出を求められる可能性もあります。他にも第三者から開示を求められる場合があるため、決められた期間は大切に保管しておきましょう。正社員だけでなく契約社員や派遣社員、アルバイトやパート従業員のタイムカードも保管が必要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理を正確に行わなくてはならない理由
勤怠管理は、法律で定められている業務のひとつです。また、勤怠管理を正確に行うことが従業員エンゲージメントの維持向上にもつながります。
適正な勤怠管理は会社としての義務である
労働基準法第108条では、勤怠管理を次のように定めています。
「使用者は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」
-
引用:e-Gov法令検索「労働基準法 第百八条」
賃金計算の基礎となる事項とは、労働時間や労働日数、休日出勤の日数、時間外労働時間数などの勤怠情報のことです。賃金台帳に毎月の賃金計算に必要な勤怠情報をまとめて正確な勤怠管理を行うのは企業の義務であり、それを怠れば労働基準法違反に当たります。法令に則した事業活動を行うためにも、勤怠管理を正確に行う必要があります。
不適切な勤怠管理は従業員エンゲージメントの低下につながる
労働安全衛生法第66条の8では、事業者は労働時間が厚生労働省令で定める時間を超える労働者に対して、医師の面接指導を受けさせる必要があるとしています。しかし、勤怠管理が適切に行われていなければ、医師の面談が必要か否かの判断も困難です。
勤怠管理を怠り休日出勤や労働時間を把握できていないと、従業員に過重労働を課してしまう、医師の面接など必要な措置を講じられないなどのリスクが生じます。従業員の就業状況を適切に管理できなくなり、従業員のエンゲージメント(企業への信頼や貢献意欲)の低下、さらには退職者の増加や業績の悪化を招く可能性があります。
-
参照:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理を行う際の注意点
勤怠管理を行う際には、正確に管理するために入力ミスや計算ミスを防ぐ工夫が必要です。データを入力した後のデータ改ざん防止、割増賃金額に影響する休憩時間や残業時間といった勤怠情報の抜けや漏れにも注意します。
入力ミスや計算ミスを防ぐ工夫をする
従業員の労働状況を把握するためにも、勤怠管理は非常に重要です。法令や就業規則に則した勤務状況であるか、過度な残業時間や休日出勤がないかを確認することで、従業員の働き方にも配慮できます。また、ワークライフバランスの整った職場環境づくりは、企業の評価を高めることにもつながります。そのためには、各従業員の勤怠管理を正確に行わなければなりません。集計作業でも、できるだけ入力ミスや計算ミスを少なくするための工夫が必要です。
データの改ざんを防ぐ
タイムカードを用いて勤怠管理を行う場合には、入力後のデータ改ざんを防ぐことが大切です。タイムレコーダーにタイムカードを入れて出勤時間と退勤時間を打刻する管理方法では、従業員が遅刻した場合などに他の社員に打刻を依頼したり手書きで時間を記入したりするデータ改ざんのリスクがあります。
特にExcelをタイムカードとして使用する場合にはデータ改ざんに注意が必要です。Excelに出勤、退勤時刻を従業員が自分で入力する方法では、何度も時刻を入力、上書きできるため、入力ミスやデータ改ざんのリスクが高まります。勤怠データの改ざんが容易に行われる状態では、管理に問題があると判断されます。
休憩時間や残業時間の見落としに注意する
タイムカードを使った勤怠管理では、休憩時間や残業時間などの見落としが生じやすくなります。タイムカードには休憩時間の打刻義務がないため、計算時には、労働時間に対して設定されている休憩時間を考慮して忘れずに計算することが重要です。
割増賃金の計算に用いる残業時間は、時間外労働、深夜、休日労働(所定・法定)などを区別して集計します。労働時間とは別に残業時間を見落とさず計算しなければならないため、集計方法にはミスを防ぐための工夫が必要です。中抜け、時間休、時差出勤などの勤務方法や休憩時間を会社が定めている場合には、ルールに基づいて適切に管理を行います。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
タイムカードの計算に関するよくある質問
タイムカードの計算の際には、勤務時間の切り捨ての仕方にも注意が必要です。誤った計算方法をしないために確認しておきたい、タイムカードの計算方法に関するよくある質問を紹介します。
タイムカードは15分単位や30分単位で計算していい?
タイムカードに記録されている1日の勤務時間を15分や30分単位で計算することは、労働基準法に違反します。労働基では勤務時間を1分単位で算出すると定めているため、残業時間の計算だけでなく遅刻した時間の計算も15分や30分単位ではなく1分単位で行います。
ただし、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間を1か月単位で算出している会社の場合には、1か月におけるそれぞれの労働時合計を30分単位で切り捨て、切り上げする計算が可能です。1時間に満たない端数が出た場合は、30分未満の端数については切り捨て、30分以上1時間未満の場合は1時間に切り上げて計算できます。
労働時間を15分単位で切り捨てていたらどうなる?
1日の労働時間を15分単位で切り捨てる計算方法は、労働基準法に違反する可能性があります。例えば、本来は18時退社でもタイムカードの打刻時間が18時7分だった場合、原則として1分単位で給与を計算するため7分の労働時間が発生します。
もし7分の労働時間を切り捨てて計算した場合には、労働基準法違反で30万円以下の罰金か6か月以下の懲役が科される可能性があります。また、労働者には5年間(当面のあいだは3年)未払賃金を請求する権利があるため、後で切り捨てていたことが発覚した場合、労働者から支払いを請求されることもあります。
参照:厚生労働省「労働者の皆さま 未払賃金が請求できる期間などが延長されます」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算の効率化にはシステムを導入しよう
適正な勤怠管理を行い従業員の賃金を正確に計算することは、企業利益のためにも重要です。正しい労働時間を算出するためには、タイムカードの計算を適正に行う必要があります。ただし、電卓やExcelを使用した計算方法では人為的ミスが発生する恐れがあるため、注意が必要です。
タイムカードの計算には、給与計算ソフトの導入がおすすめです。弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」の勤怠管理機能(※)は、さまざまな打刻手段に対応しており、自社の就業規則に合わせた柔軟な勤怠管理を行えます。また、給与計算業務に必要な機能も網羅しているため、計算業務の負担やミスの軽減にもつながります。自社に合ったシステムを活用して、業務を効率よく進めましょう。
- ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。