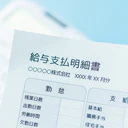給与台帳とは?保存期間・記載項目・賃金台帳との違いなどを解説
更新
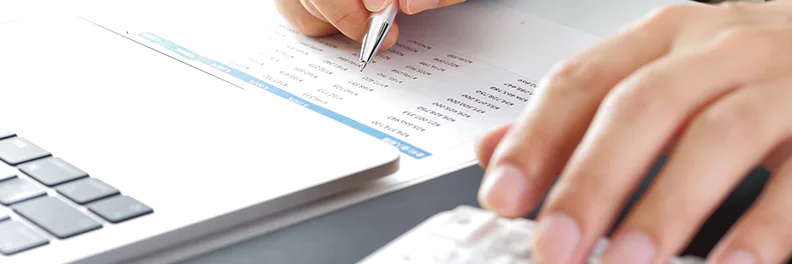
給与計算に関係する帳簿の1つに「給与台帳」があります。しかし、給与台帳という言葉を聞いたことがあっても、作成の目的や書き方、賃金台帳や給与明細との違いがよくわからず、「何のための台帳なのだろうか」と疑問に感じている方もいるかもしれません。
本記事では、給与台帳の概要や役割、保存期間、記載項目のほか、給与台帳と賃金台帳の違いについて詳しく解説します。さらに、給与計算に関するよくある質問とその回答も紹介します。労務管理をスムーズに行うためにも、給与台帳の定義を正しく理解しておきましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
給与台帳とは給与情報を記載した帳簿のこと
給与台帳とは、従業員の給与に関する情報のみを記載した帳簿です。従業員ごとに給与支給内容を一覧化した社内管理用の帳票であり、企業が給与計算の結果を記録・管理する目的で任意で作成します。名称についても法律上の定義はなく、多くの企業で慣習的に「給与台帳」と呼ばれているものです。
給与台帳と混同されやすいものに「賃金台帳」があります。両者は法的な位置づけや実務上の目的が異なります。給与台帳が任意で作成する帳票であるのに対し、賃金台帳は労働基準法により作成と保存が義務付けられた法定帳簿です。
また、給与台帳の実務上の目的は、社内での給与計算の確認や記録ですが、賃金台帳は法令遵守を目的とした帳簿であり、労働基準監督署の調査などにも使用されます。
給与台帳は企業が任意で作成するもの
給与台帳は企業が任意で作成するものです。作成は各企業の判断に委ねられており、法律による作成義務や規定はありません。そのため、記載項目・書式・用紙のサイズ・レイアウトなどは各企業が自由に設定できます。
また、担当者や年度ごとにフォーマットや記載項目が異なると、管理が煩雑になるおそれがあります。給与台帳を作成する際は、形式や記載内容に関する社内ルールを定め、統一して運用することが望ましいでしょう。
給与台帳の保存期間の目安
法的な作成義務のない給与台帳は、保存期間も企業の裁量に任されています。3年や5年を目安に処分する企業もあれば、10年間保存する企業もあります。保存期間に関する規定はないため、社内でルールを定めておくといいでしょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与台帳に記載する8つの項目
給与台帳を作成する際は、従業員ごとに以下の8つの項目について記載するのが一般的です。各項目について詳しく解説します。
氏名
給与を支払った従業員の氏名を記入します。社員番号などを設定している場合は、併せて記載しておくと管理がしやすくなります。また、結婚などで氏名に変更があった場合は速やかに修正しましょう。
性別
従業員の性別を記載します。名前と性別を記載することで、どの従業員の情報なのかがより明確になります。
賃金計算期間
賃金計算期間とは、給与計算の対象になる期間のことです。例えば月末締めの場合は「4月1日~4月30日」、25日締めなら「4月26日~5月25日」と記載します。
労働日数
賃金計算期間のうち、実際に労働した日数を記載します。休日出勤も含めたすべての出勤日数を記入しましょう。なお、有給休暇は労働したものと見なされるため、労働日数に含まれます。記載にあたっては、有給休暇であることが後で見てわかるようにしておきます。
労働時間数
労働日数と併せて、時間外労働や休日労働の時間も含めた労働時間数も記載します。また、労働日数と同様に、有給休暇分の時間も労働時間に含みます。
労働時間は1分単位で計算するのが原則のため、タイムカードなどの出勤記録を基に、正確な時間を記入しましょう。
時間外労働時間数
上記の労働時間数のうち、時間外労働の時間数を記載します。時間外労働とは、原則として1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超える労働時間をいいます。
時間外労働について詳しくは、こちらの記事で解説しています。
基本給、手当の種類とその額
従業員に支払う給与について、基本給や手当といった項目ごとに記載します。時給制の場合は「時給×労働時間数」、日給制の場合は「日給×労働日数」が基本給となります。
また、通勤手当や住宅手当、家族手当、臨時手当などの各種手当、さらには賞与についても、種類ごとに金額を記載します。
基本給について詳しくは、こちらの記事で解説しています。
控除項目とその額
社会保険料や税金など、給与から控除される項目とその金額を、それぞれ記載します。積立金や組合費など、会社独自の控除項目がある場合も、忘れずに記入しましょう。
社会保険料について詳しくは、こちらの記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与台帳と賃金台帳の違い
給与台帳と賃金台帳は、作成の目的や記載項目に大きな違いがあります。
賃金台帳は、労働基準法によって作成および保存が義務付けられている帳簿であり、記載事項も法令で明確に定められています。
その一方で、給与台帳は、法的な作成・保存義務のない社内管理用の帳票であり、記載事項も企業ごとに自由に設定できます。
給与台帳と賃金台帳の違いについて、詳しくは以下の表でご確認ください。
| 項目 | 給与台帳 | 賃金台帳 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 社内の管理帳票(作成任意) | 法定帳簿(作成義務) |
| 根拠法令 | なし | 労働基準法第108条 |
| 記載内容 | 自由(支給・控除など給与明細の内訳が一般的) | 法で定められた記載項目 |
| 目的 | 給与計算の確認、記録 | 法令順守、監督署調査対応 |
| 作成方法 | 任意のフォーマット | 手書きや表計算ソフトのほか、給与ソフトで出力可能(対応状況は製品により異なる) |
賃金台帳とは
賃金台帳は、労働者名簿および出勤簿と併せて「法定三帳簿」と呼ばれる帳簿の1つです。労働基準法第108条により、経営者や事業主、個人事業主など労働者を雇用する使用者には、賃金台帳の作成が義務付けられています。
記載対象となるのは、使用者が雇用するすべての従業員です。正規雇用の社員、パート、アルバイトだけでなく、雇用期間が1か月未満の日雇い労働者も含まれます。その一方で、取締役などの役員は原則として労働基準法上の「労働者」には該当しませんが、使用人兼務役員など、労働者としての地位を有する場合には賃金台帳の作成対象となります。
作成が任意である給与台帳とは異なり、賃金台帳は給与などを支払うたびに遅延なく記入することが、労働基準法で定められています。
賃金台帳について詳しくは、こちらの記事で解説しています。
賃金台帳に記載する10の項目
賃金台帳には、労働基準法により以下の10の項目について記載することが定められています。
- 賃金台帳に記載が必要な項目
-
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 休日労働時間数
- 深夜労働時間数
- 基本給、手当の種類とその額
- 控除項目とその額
賃金台帳の書式や用紙
賃金台帳は法律によって作成が義務付けられている帳簿で、記載項目も明確に定められていますが、書式や用紙に関する規定はありません。記載内容が守られていれば、レイアウトや用紙のサイズ、データのファイル形式などは、各企業が自由に決められます。
弥生では、従業員の氏名や性別、労働日数、賃金の計算期間など、給与の支払い状況を記載する、賃金台帳のエクセルテンプレートをダウンロードできます。社会保険料や所得税、住民税など賃金から控除される項目も記載できます。
賃金台帳の保存期間
賃金台帳の保存期間は、最後に記入した日から5年間です。ただし、最後に給料を支払った日が記入日より遅い場合は、その支払日から5年間が保存期間となります。
賃金台帳の保存期間は3年間となっていますが、最終的には5年間に統一されるため、早めに切り替えておくとよいでしょう。なお、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合は、保存期間が7年間となります。
賃金台帳の作成・保存を怠った場合の罰則
賃金台帳を適切に作成・保存していない場合は、労働基準法に抵触することとなり、30万円以下の罰金刑の対象となります。
また、賃金台帳の作成を怠ったり、記載項目に不備があったりした場合は、労働基準監督署から是正勧告書が交付されるのが一般的です。この勧告書には、不備の内容や是正の期日などが記載されています。是正勧告に従わない場合は、罰則の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与台帳に関するよくある質問
給与台帳は、賃金台帳のように法律で作成・記載・保存に関するルールが定められているものではないため、管理や運用の際に迷うことがあるかもしれません。ここでは、給与台帳に関してよくある質問とその回答を紹介します。
給与台帳は給与明細で代替できる?
給与台帳と給与明細では原則的に役割が異なるため、代替することはできません。
給与明細が給与台帳の役割の一端を担うことはできます。給与明細は各従業員の月ごとの支給内容を明記したもので、勤怠記録や控除内容なども記載されています。給与台帳は一般的に従業員の過去分も含めた累積記録です。そのため、給与明細を毎月きちんと保存しておけば、給与台帳に近い形で情報をまとめられます。
ただし、給与明細はあくまで従業員が給与の内訳を確認するための書類です。その一方で、給与台帳は労務管理のために作成する帳簿で、給与に関する情報が体系的にまとめられています。給与明細では体系的な記録が不足しているため注意しましょう。
給与明細書について詳しくは、こちらの記事で解説しています。
給与台帳はアルバイトやパートも作成する?
給与台帳は企業が任意で作成する書類のため、対象者の範囲にも明確な決まりはありません。一般的には給与台帳を作成する場合、アルバイトやパートも含めた全従業員が対象になることが多いものの、正社員の分だけ作成しても問題はありません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
賃金台帳は給与計算ソフトで作成・保存すると効率的
給与台帳は、法定帳簿である賃金台帳とは異なり、企業が任意で作成する書類です。給与台帳の一般的な記載項目は賃金台帳でもカバーされているため、給与台帳を作成せず賃金台帳のみを作成する企業も少なくありません。
給与計算業務や賃金台帳の作成などを効率的に行うには、「弥生給与 Next」の導入がおすすめです。「弥生給与 Next」では勤怠情報をもとに給与を自動計算できるほか、給与・労務・勤怠管理といった複数の業務をシームレスに連携し、バックオフィス業務かかる手間の削減を実現します。給与業務の効率化を目指す際は、ぜひ導入をご検討ください。
-
※本記事は2025年11月6日時点の情報を基に制作しています
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。