マイナンバー導入後の給与計算業務の変化とは?取り扱い方などを解説
更新
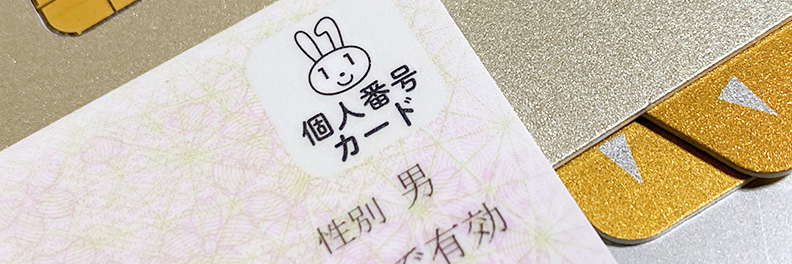
マイナンバー制度の導入に伴い、給与計算業務においても、マイナンバーへの対応が求められるようになりました。給与計算業務で取り扱う書類の中には、従業員のマイナンバーを記載しなければならないものがありますが、大切な個人情報なので、管理にあたっては十分な配慮が必要です。
では、そもそもなぜ企業が従業員のマイナンバーを取得する必要があるのでしょうか。
本記事では、マイナンバー制度導入が給与計算業務に与えた影響や、給与計算業務で従業員のマイナンバーが必要になる場面の他、マイナンバーを取り扱う際の注意点などについて解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
企業が従業員のマイナンバーを取得する理由
マイナンバーとは、国内に住民票を有するすべての人に1つずつ付与される、12桁の個人番号です。行政の効率化と国民の利便性を高めるために、2016年1月よりマイナンバー制度が開始されました。
マイナンバーは、「社会保障」「税」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、異なる複数の機関が保有する個人情報が、同一人物のものだと確認するために活用されます。企業が従業員のマイナンバーを取得するのは、このうち社会保障と税にかかわる手続きを行うためです。
社会保障とは「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の総称です。その中の社会保険は、従業員が加入する健康保険や厚生年金保険、雇用保険などのことを指しており、それらの手続きにはマイナンバーが必要になります。
また、企業は給与から源泉徴収した所得税を従業員に代わって納めますが、税金の手続きにも従業員のマイナンバーが必要です。このような社会保険関係と税金の手続きを行うために、企業は従業員のマイナンバーを取得し、適切に管理しなければなりません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
マイナンバー制度による給与計算業務への影響
マイナンバー制度の導入は、従業員からのマイナンバー収集や提出書類への記載など、給与計算業務に大きな影響を与えました。マイナンバー制度導入後の給与計算業務の変更点について、改めて確認していきましょう。
全従業員からのマイナンバー取得
社会保険と税金の手続きに使用するため、企業は従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。マイナンバーの取得が必要なのは、パートやアルバイトも含めた全従業員です。従業員に扶養家族がいる場合は、該当する家族のマイナンバーも取得対象になります。
従業員からマイナンバーを取得する方法についても注意が必要です。企業が従業員にマイナンバーの提供を依頼する際には、その利用目的を明示したうえで、マイナンバーカード(個人番号カード)などで本人確認を行います。
また、社会保険や税金関連(年末調整等のためにマイナンバーの入力が必要であり、当月の給与計算については不要)の書類にマイナンバーを記載するため、税務関連システムにも個々の従業員のマイナンバーを追加しなければなりません。税務関連システムがマイナンバーの管理に対応していない場合は、システムの見直しも必要になるでしょう。
社会保険や税の手続きにマイナンバーを記載
給与計算業務の中で行う社会保険の手続きでは、主に以下のような場合に従業員のマイナンバーが必要になります。
マイナンバーが必要な社会保険の手続き
- 健康保険や厚生年金保険などの資格取得・喪失届
- 健康保険・厚生年金保険の免除に関する申出書・終了届 等多数
詳細は、日本年金機構「マイナンバーを記載する届書等一覧」から確認が可能です。
健康保険や厚生年金保険、雇用保険の資格取得届や資格喪失届は、従業員のマイナンバーを記載して提出します。また、産休中や育休中の社会保険料の納付について、免除の申請・終了の届け出を行う書類にも必要です。対象となる従業員のマイナンバーを記載し、健康保険組合や日本年金機構に提出します。
さらに、給与計算業務で出てくる税金の手続きにおいても、以下のような場合に従業員のマイナンバーが必要になります。
マイナンバーが必要な税金の手続き
源泉徴収票
年末調整時に作成する源泉徴収票は、従業員本人に交付する他、翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。税務署に提出する源泉徴収票には、従業員と扶養家族のマイナンバーを記載します。
給与支払報告書
給与支払報告書は、市区町村が従業員の住民税額を算出するために必要な書類です。企業は、個々の従業員に対して1年間に支払った給与額について給与支払報告書を作成し、市区町村に提出する義務があります。この給与支払報告書には、マイナンバーの記載が必要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
マイナンバーの保管と廃棄
従業員のマイナンバーは、取得時に明示した目的のために必要である場合に限り、企業で保管することが可能です。ただし、マイナンバーの保管にあたっては、マイナンバー法の規程に基づく適切な対処が求められます。
マイナンバー法に則った管理が必要
マイナンバー法は、正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、マイナンバーの取得や利用・保管に関するさまざまなルールがまとめられた法律です。マイナンバーを扱う際には、マイナンバー法にもとづいて管理をする必要があります。
例えば、法律によって一定期間の保存が義務付けられている書類にマイナンバーが記載される際には、関連書類の保存期間が終了するまで、厳重に保管しなければなりません。また、書類を紙で管理する場合は施錠できるキャビネットなどに保管し、電子データで管理する場合はシステムのセキュリティ強化やパスワード設定・アクセス権限を付与するなど、情報漏洩のないように管理体制を強化する必要があります。
さらに、従業員の退職などによりマイナンバーが不要になった場合は、速やかに適切な方法で破棄する義務があります。紙なら焼却処分、データなら専用ソフトを使って復元不可能な形にするなど、破棄の方法にも注意が必要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
マイナンバー取り扱いにおける注意点
マイナンバーは従業員の大切な個人情報のため、マイナンバー法によって取得や管理の方法が厳密に決められています。従業員のマイナンバーを取り扱う際には、具体的にどのような点に注意するべきなのか確認していきましょう。
取得の際の本人確認
従業員のマイナンバーを取得する際には、本人確認が必要です。本人確認の方法のうち最も簡単なのは、マイナンバーカードを提示してもらうことでしょう。
マイナンバーカードがない場合は、通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証明書で本人確認を行います。
また、扶養家族に関しては、従業員が事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員はマイナンバーを確認する者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
目的外利用の禁止
マイナンバーの取得にあたっては、利用目的を明示することが法律で定められています。従業員にマイナンバーの提供を依頼する際には、企業はその利用目的を明らかにして本人に通知しなければなりません。
マイナンバー法では、たとえ本人の同意があったとしても、利用目的を超えてマイナンバーを使用してはいけないと定められています。当初の目的以外でマイナンバーを利用する場合は、従業員に対して再度目的の明示が必要です。目的の通知を怠ったり目的外の利用をしたりすると、法律違反になるため注意しましょう。
なお、源泉徴収票作成のために取得したマイナンバーを、翌年以降の源泉徴収票にも利用するような場合は、利用目的の範囲内として認められます。
情報の安全管理
企業は、取得したマイナンバーに関する情報漏洩を防ぐために、適切な体制を整えなければなりません。マイナンバーの保管にあたっては、個人情報保護委員会のガイドライン(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン)に沿った安全管理措置の徹底が求められます。
企業が対応すべき安全管理措置は、主に以下のとおりです。
組織的安全管理措置
組織的安全管理措置は、正しい安全管理のために組織の体制を整えることです。マイナンバーを取り扱う従業員の責任を明確にすると同時に、組織の安全管理体制やマニュアルを整備しなければなりません。
人的安全管理措置
人的安全管理措置は、従業員がマイナンバーを適切に取り扱えるよう教育などを行うことです。例えば、マイナンバーの取り扱いに関する定期的な研修の実施や、秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込むなど、知識をつけるようにします。
物理的安全管理措置
物理的安全管理措置は、マイナンバーを管理する区域や、盗難防止策などを決めることです。マイナンバーを管理する区域への入退室制限の他、マイナンバーを取り扱う機器や電子媒体の適切な保管のための対策などが求められます。
技術的安全管理措置
技術的安全管理措置は、電子機器でマイナンバーを管理する際に行うべき対策のことです。パソコンのシステムを利用してマイナンバーを管理する場合は、セキュリティの高いシステムを導入するとともに、適切なアクセス制御を行う必要があります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算業務では適切なマイナンバー管理が必要
給与計算業務の中には、従業員のマイナンバーを扱う場面が多く出てきます。給与計算業務に関連して取得したマイナンバーは、マイナンバー法やガイドラインに従い、適切な方法で管理しなければなりません。特に、マイナンバー制度の導入以前に比べて給与計算業務に複雑な工程が増えたため、効率化や安全な情報管理について検討する必要があるでしょう。
給与計算にかかわる業務の効率化を目指すなら、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与計算、社会保険料の計算、年末調整を確実にできるうえ、給与支払報告書の電子提出にも対応。さらに、マイナンバー法に則り、業務手順や安全管理措置にも対応しています。便利な給与計算ソフトを活用して、給与計算業務の効率化を目指しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。








