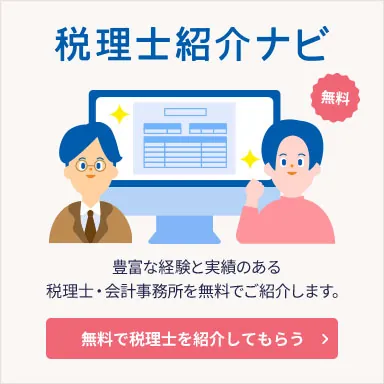顧問税理士とは?顧問契約のメリットや契約前に注意すべき点
監修者: 高崎 文秀
更新

企業が持続的に発展していくためには、税務会計に関する専門的な知識が重要です。税理士と顧問契約を締結すれば、税務会計の業務を一任することが可能で、節税対策や財務計画に関する専門的なアドバイスも受けられます。本記事では顧問税理士に依頼できる主な業務や一般的な費用相場、税理士と顧問契約を結ぶメリット、契約前の注意点などについて解説します。
顧問税理士とは
顧問税理士とは、法人や個人事業主などを対象として一定期間の顧問契約を結んだ税理士を指します。税理士は国家資格を有する税務の専門家であり、「税務相談」と「税務書類の作成」、そして「税務代理」の3つは税理士の独占業務です。
通常、税理士に業務を依頼する場合、税務書類の作成費用や1時間あたりの相談料といった形式で個別の支払いが発生します。顧問税理士は、月額または年額の顧問料を支払うことで、決算書の作成や節税対策の提案、法人税や消費税の申告など、専門的な知識が必要な税務に関して総合的なサポートを提供してくれます。
年間取引数が少ない小規模事業者や売上高が1,000万円に満たない個人事業主などは、スポット契約で税務を依頼するケースが少なくありません。しかし事業規模が大きく年間を通じて節税対策を講じたい企業や、複数の店舗を経営する事業者などは、自社の本業に専念するためにも税理士と顧問契約を結ぶのが一般的です。
顧問税理士に依頼できる主な業務
税理士は税務の専門家として法人や個人事業主の税務会計を総合的にサポートします。顧問税理士に依頼できる代表的な業務は以下の4つです。
- 日常的な税務相談・アドバイス
- 税務書類の作成
- 節税対策の提案
- 税務調査の立ち会い・対応
日常的な税務相談・アドバイス
顧問税理士は、日常的な税務相談やアドバイスも行ってくれます。例えば、法人の営業活動などで発生する接待交際費は原則として損金に算入できませんが、法人税法や租税特別措置法に基づいて、一定の要件を満たせば一定額までは算入できることになっています。こうした、どこまで経費として認められるのか迷う場面で、的確なアドバイスを受けることができます。
さらに、税務の観点からの経営相談などにも応じてもらえます。例えば、企業が設備投資を行う際には、導入時の初期費用や継続的な管理コストを分析するのはもちろん、資産の取得価額や減価償却費などを算出したうえで、中長期的な投資計画を立案する必要がありますが、企業の財務状況を把握している顧問税理士は、投資計画や事業戦略に対して的確にアドバイスしてくれます。
税務書類の作成
税務書類の作成は税理士の主要業務のひとつです。税務書類とは、税務官公署(国税庁、国税局、税務署など)に提出する申告書であり、具体的には損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書、法人税申告書や消費税申告書などがあり、さらにこれらに付随する書類として、源泉徴収票、法定調書、償却資産税申告書なども挙げられます。こうした税務書類の作成を請け負えるのは税理士または税理士法人だけです。
企業は事業年度に得た所得に応じて法人税を納める義務があります。法人税申告書を作成して税務官公署に提出しなくてはなりませんが、このとき重要なことは、決算書に記載されている情報が正確に転記されていることです。税理士は税務書類作成のプロフェッショナルであり、申告手続きの正確性を担保して、税務上のリスクを軽減します。
節税対策の提案
顧問税理士からは節税対策に関する提案やアドバイスも受けられます。例えば社用車を購入する場合、節税に効果的なのは4年落ちの中古車です。新車の普通自動車は法定耐用年数が6年と定められており、減価償却費の計上は通常、6年間をかけて行います。4年落ちの中古車は法定耐用年数が2年ですが、定率法を用いて減価償却費を計算する場合には1年(月割り)で減価償却できます。仮に事業年度の初めに4年落ちの中古車を購入したとすれば、取得価額の全額をその年度における減価償却費として経費計上できる(期首の月から使用開始の場合)ため、大きな節税効果が見込めます。
こうした節税の仕組みを理解するためには、減価償却資産を費用化する会計処理の仕組みを学ばなくてはなりません。税理士と顧問契約を結べば、減価償却のほかにも、税務の専門知識にもとづいた節税対策の提案や、補助金や助成金の提案などを受けられます。
税務調査の立ち会い・対応
税務調査の立ち会いも顧問税理士に依頼できる業務のひとつです。法人税や消費税、所得税などは申告納税制度が採用されており、法人も個人も自らが税額を計算して申告します。その際に税額の計算ミスや記載漏れ、あるいは虚偽の申告や悪質な不正などの可能性も懸念され、申告内容に間違いがないかを確認するために税務調査が行われることがあります。
税務調査では調査官が決算書や総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳・買掛帳、請求書、領収書などから、申告内容に間違いがないかを詳細に確認します。税務調査に対応するためには税法や会計に関する知識が不可欠です。税理士の立ち会いがなければ、調査官の質問や要求に的確に対応することは難しく、申告が適切に行われていないと判断されれば、追徴課税を課される可能性があります。顧問税理士がいれば調査官とのやり取りを代行してもらえるため、税務調査に対するリスクを抑えられます。
顧問税理士の報酬額・費用相場
法人の場合で「月額2~5万円」、個人事業主の場合は「月額1~3万円」が目安です。ただし、この金額はあくまでも目安であり、依頼内容や業務範囲、訪問頻度、あるいは企業規模によって変わってきます。一般的に税理士の顧問料は、年間売上高と訪問回数、記帳代行の有無によって決まります。
企業規模が大きければ取引数も多くなり、税理士が行う仕訳業務の負担も増すため、顧問料が高くなる傾向があります。一例として年間売上高が5,000万~1億円の法人で、税理士の訪問頻度が毎月1回の場合、記帳代行を含む月額の顧問料は3~5万円程度が目安です。一方、年間売上高が1,000万円未満の個人事業主で、税理士の訪問頻度が毎月1回の場合、記帳代行を含む月額の顧問料は2~3万円程度が一般的な相場です。
ただし、法人税や所得税などの確定申告については、顧問料とは別に決算申告費用が発生します。金額は税理士事務所によって異なりますが、顧問料の4~6か月分が目安です。税理士報酬の相場については以下の記事も参考にしてください。
関連記事
税理士と顧問契約を結ぶメリット
企業や個人事業主が顧問契約を結ぶ主なメリットとしては、
- 本業に専念できる
- お金に関するさまざまなアドバイスが受けられる
- 決算業務を正確に行える
- 税務調査に対応してもらえる
といったことが挙げられます。
本業に専念できる
大きなメリットのひとつが、企業価値の向上に直結する本業にリソースを集中できることです。事業活動におけるすべての業務は等しく重要ですが、限りある経営資源を効率的に運用するためには、人的資源や資金などのリソースを自社の本業に集中させることが望ましいです。
会計業務では日々の取引を「売上」「売掛金・買掛金」「消耗品費」「接待交際費」などの勘定科目に分類(仕訳)し、帳簿にその内容を記入(記帳)する必要があります。仕訳や記帳などは事業活動において重要な業務ですが、利益の創出やブランド価値の確立にはつながらず、本業とは呼べません。上述したように、事業規模が大きくなるほどに日々の取引数は増えるため、仕訳や記帳に追われれば、本業に専念すべきリソースが浪費されてしまうかもしれません。顧問税理士に税務会計を委託すれば、商品・サービスの設計・開発やマーケティング活動といった、収益に直接つながる本業にリソースを集中できます。
お金に関するさまざまなアドバイスが受けられる
2つめのメリットが、設備投資や節税対策、資金繰りといったお金に関する税務相談を受けられることです。経営者は、企業の成長と事業の発展に必要な資金をどのように調達し、いかにして効率的に運用するかを常に考える必要があります。特に中小企業の場合は大企業のように豊富な資金調達手段を持たないため、決算上では黒字でも、資金繰りが原因で黒字倒産に至るケースが少なくありません。
顧問税理士は企業の財務状況や事業の収支状況を把握しており、中長期的な財務計画の立案や投資計画の策定に関して的確なアドバイスを くれます。試算表や月次資金繰り表の作成方法なども熟知しており、銀行融資を引き出す事業計画書の考え方などに関してもサポートしてくれます。お金に関する有効なアドバイスを受けることで、資金ショートに至るリスクを抑えられます。
決算業務を正確に行える
3つめのメリットが、決算業務の正確性と信頼性を担保できることです。決算業務のなかで最も重要な年次決算では、まず事業年度分の記帳の整合性を確認したうえで、決算整理前に残高試算表を作成します。次に決算整理仕訳で未処理の取引や仕訳帳の勘定科目を整理し、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」などの決算書を作成します。
決算書の作成業務は煩雑になりやすく、さらに簿記や会計の専門知識も不可欠です。法人税申告書は決算書にもとづいて作成されますが、確定申告後に計算ミスや記載漏れが発覚した場合には修正申告をしなくてはならず、さらなる業務が発生してしまいます。税理士と顧問契約を結べば、決算業務を委託できるだけでなく、決算書や法人税申告書の正確性と信頼性を担保し、税務官公署から指摘を受ける可能性と追徴課税のリスクを減らせます。
税務調査に対応してもらえる
先述したように税務調査の立ち会いは、顧問税理士に依頼できる業務のひとつです。調査の主な目的は申告内容の確認と不正行為の防止であり、一般的には過去3年分の帳簿や資料がチェックされます。申告内容に誤りがあれば5年分まで遡り、不正が疑われる場合は過去7年分の申告内容が調査されます。その際には取引の実態や交際費の使途、領収書の詳細、減価償却の方法、損金の振り分け処理など、調査官の細かい質問に対応しなくてはなりません。
顧問税理士は、調査官とのやり取りを代行してくれるとともに、適切な対応ができるようにサポートしてくれます。税務調査の結果によっては追徴課税が発生することもあり、事実の隠蔽や悪質な不正と判断された場合には重加算税の対象となるリスクを孕んでいます。税務調査を受ける側は大きなプレッシャーに晒されますが、取引の実態を把握している顧問税理士の立ち会いがあれば適切な対応が期待できます。
税理士と顧問契約を結ぶデメリット
デメリットをあえて挙げれば、月額または年額の顧問料を支払わなければならないことです。税理士と顧問契約を結ぶことで自社の本業に専念するリソースを確保し、節税対策や資金繰りのアドバイスを受けられるため、中長期的な視点で見た場合は 顧問料をはるかに上回る利益を期待できます。しかし、売上規模の小さな小規模事業者や個人事業主の場合、月額2~3万円は決して小さな金額ではありません。1か月あたりの顧問料が経済的負担となる事業者の場合、会計ソフトを利用して仕訳や記帳を自らが行い、必要最低限の税務をスポット契約で依頼するといった方法もあります。
税理士と顧問契約を結ぶ前に注意すべき点
税理士と顧問契約を結ぶことでさまざまなメリットを得られますが、いくつかの注意すべき点もあります。なかでも押さえるべきポイントとしては、
- 税理士との契約内容を確認しておく
- 自分に合う税理士を選ぶ
の2つです。
税理士との契約内容を確認しておく
顧問契約を結ぶ前に確認しておきたいのが契約内容の詳細です。例えば顧問料が月額3万円として、契約内容に記帳代行や税務相談、無料の電話サポートなどが含まれているのか、1か月あたりの訪問回数は何回かといったことは確認すると良いです。 契約内容の確認を怠った結果、「顧問料に記帳代行は含まれない」「対面の打ち合わせはタイムチャージ制」などの重要事項を見逃してしまい、さらなる費用が発生してしまうかもしれません。契約書には顧問契約の期間や解除条件、違約金などに関する条項が設けられている場合があるため、契約前にしっかりと確認しましょう。
自分に合う税理士を選ぶ
顧問税理士との相性は重要です。税理士の主要業務は税務相談・税務書類の作成・税務代理ですが、人によって得意分野は異なります。例えばIT分野に詳しかったり、税務調査に強かったり、事業承継やM&Aを得意としていたりなど、さまざまです。税理士が自社の業界特有の課税基準や優遇措置を把握していない場合には、本来経費として計上できる要素を見逃してしまうかもしれません。そのほかにも業務への誠実さや節税に対する価値観、税制への倫理観、相談に対する対応の真摯さなど、人間的な特性や相性も考慮したうえで、自社に合った税理士を選ぶことが大切です。
良い税理士を手間と時間をかけずに探す方法
自分に合った税理士と顧問契約を結びたいと思っても、自力で税理士を探そうとすると手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、起業全般や税、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模の全国12,331のパートナー会計事務所から、ぴったりの税理士や会計事務所を最短で翌日にご案内できます。完全無料で、会社所在地や業種に合わせた最適な税理士をご紹介します(2025年8月時点)。
「税理士紹介ナビ」には、事業者のお困りごとに沿って弥生スタッフが最適な税理士や会計事務所を紹介する「税理士紹介サービス」と、ご自身で自由に税理士を探すことのできる「税理士検索
」の2つのサービスがありますので、ご自身の状況に合ったサービスをご活用ください。
「税理士紹介ナビ」はこんな方におすすめ
「税理士紹介ナビ」は、特に次のような方におすすめです。
初めて会社を設立する方
会社を設立する際には、必要な手続きや資金調達など多くの不安や疑問が生じることがあります。「税理士紹介ナビ」なら、これから事業を始める方の悩みや困りごとに合わせて、最適な税理士探しをサポートします。個人事業主から法人成りを予定している方にもぴったりです。
起業後の会計処理や決算が不安な方
会社を運営するうえでは、法人税や地方税、消費税など、さまざまな税や固定資産の知識が必要になります。そのような場合も、会計処理や決算に関することをまとめてプロに相談できます。
できるだけ節税したい方
「節税したいが方法がわからない」という方にも「税理士紹介ナビ」はおすすめです。税理士からのアドバイスで節税方法を理解できれば、戦略的な経営にも役立つでしょう。
記帳業務を丸ごとプロに任せたい方
日々の取引を記帳するには手間や労力がかかります。売上が増えるとともに経理作業量も増え、負担が大きくなってしまうでしょう。記帳業務を税理士に丸投げできれば、その分しっかり本業に集中できるようになります。
顧問税理士は頼もしい経営のパートナー
顧問税理士とは、法人や個人事業主などを対象として、一定期間の顧問契約を結んだ税理士です。「税務相談」「税務書類の作成」「税務代理」は税理士の独占業務であり、税理士以外は行えません。顧問契約を締結すれば、節税対策の提案や税務調査の立ち会いなども含めて、税務の包括的なサービスを受けられます。
顧問税理士の費用(顧問料)相場は、法人で「月額2~5万円」、個人事業主は「月額1~3万円」です。この金額はあくまでも目安であり、依頼内容や業務範囲、訪問頻度、企業規模などで変わってきます。
税理士にはそれぞれに得意分野があるため、顧問契約を締結する前に自社のビジネスモデルとの相性などを考慮しなくてはなりません。顧問税理士は税務の専門知識で事業活動をサポートしてくれるパートナーといえる存在です。自社に適した顧問税理士を見つけるためには、弥生の「税理士紹介ナビ」の活用をおすすめします。
この記事の監修者高崎 文秀
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。