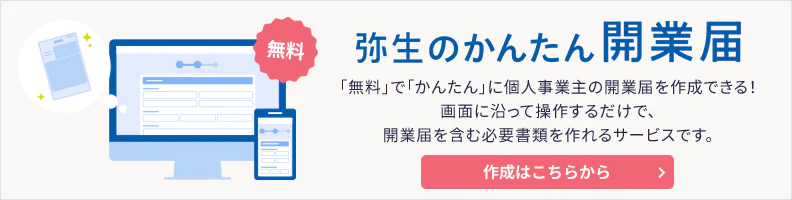【起業したい】個人事業の開業届の費用はいくら?支払いが発生するケースも解説
監修者: 宮川 真一(税理士)
更新
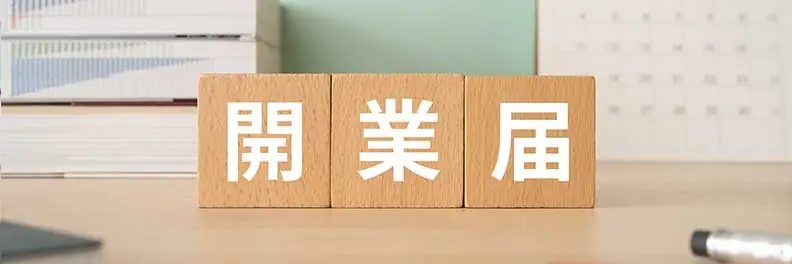
事業を始めるために「開業届」の提出が必要ですが、「開業届の手続きに費用はかかるのか」「費用が発生する場合はいくらになるのか」など手続きする際の費用に関して疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
結論として、開業届自体は無料で提出できます。費用は一切かかりません。しかし、開業届の手続き以外に費用がかかるケースがあります。本記事では、個人事業の開業届の費用や、支払いが発生するケースを解説します。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主の開業届の手続きに費用は発生しない
個人事業主の開業届の手続きの際に、費用は発生しません。そのため、開業届の申請費用や収入印紙代は不要です。届出書は国税庁の公式サイトから無料でダウンロードでき、直接持参することで開業の手続きができます。もし仮に開業届の記入漏れが見つかった場合でも、その場で修正可能です。
会社設立のように大きなお金がかかることはないので、安心して開業届の手続きを進めましょう。ただし手続き以外に費用が発生するケースがあります。開業届の提出を進める際はしっかり理解しておきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主の開業届の手続き以外に費用がかかるケース
個人事業主の開業届の手続き以外に費用がかかるケースをまとめました。
- 開業届を郵送で送る場合
- 遠方の税務署に出向く場合
- 税理士に依頼する場合
開業届を郵送する場合
開業届を郵送する場合、税務署まで出向く手間がない点がメリットです。しかし、封筒代や切手代がかかるため、郵送する前にトータルの費用を把握しておきましょう。
例えば、切手と封筒を購入し、定形外郵便で送ると仮定するとおおよそ300円ほどかかります。意外と安価に感じるかもしれませんが、記載の不備があった場合、提出した開業届は差し戻され、あらためて提出する必要があります。再度郵送する際は、もう一度封筒代や切手代を支払う必要がある点に注意しましょう。
遠方の税務署に出向く場合
自宅の場所によっては、開業届を提出するために遠方の税務署まで出向く必要があります。街の中心部に住んでいたとしても、近場の税務署の管轄から外れることで、郊外の税務署まで出向くケースもあるのです。この場合、電車やバスなどの公共交通機関を利用するための交通費がかかります。また、車を利用する場合は、ガソリン代や駐車場代がかかる点に注意が必要です。事前に自身がどの税務署の管轄になるか確認し、おおよその交通費を把握しておきましょう。
自宅と税務署の距離が遠い場合は、e-Taxの利用も検討してみてください。利用者識別番号を取得することで、自宅にいながら24時間いつでも無料で開業届を電子で提出できます。
税理士に依頼する場合
個人事業主の開業届の手続き自体は難しいものではなく、基本的に自分だけで完結できます。税理士に依頼する選択肢もありますが、ほとんどの場合は必要ありません。
もちろん円滑に開業の手続きを進められるという利点があるものの、そのぶん税理士に依頼する費用がかかります。0円で開業届の手続きを代行し、開業後に顧問契約を必須としている税理士事務所もあれば、単発で数千円〜数万円程度で依頼を受けてくれる事務所もあります。今後、確定申告や複雑な税務処理を税理士に依頼するのもよい選択肢です。目的に合わせて税理士への依頼を検討しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
費用は一切なし!楽々かんたんに開業届を提出する方法
開業届は税務署から書類をダウンロードして、1から自分で作成することもできますが、「弥生のかんたん開業届」を利用して作成することもできます。「弥生のかんたん開業届」は、開業届を提出するために、費用は一切かかりません。
また、開業にあたって、開業届以外に青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書も作成して提出する場合、一度入力した内容は自動的にすべての書類に転記されるため、何度も同じ情報を入力する煩わしさがありません。
- フリーランスの方
- 新たに事業を始める方
- 副業したい方
上記に当てはまる方は、ぜひ「弥生のかんたん開業届」を活用してみてはいかがでしょうか。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業届を出したほうがいい場合・出さないほうがいい場合
原則として開業届の提出は義務です。事業を始める際は必ず開業届を提出するようにしましょう。ただし自分の状況によっては、開業届の提出を控えたほうがいいかもしれません。「出したほうがいい場合」と「出さないほうがいい場合」を紹介します。
出したほうがいい場合
前述のとおり、開業届の提出は義務であるという理由もありますが、提出するメリットも多くあります。
-
- 青色申告青色申告をする場合、最大65万円の控除が受けられる(青色申告承認申請書の提出が必要)
- 屋号の名義で銀行口座を開設し、資金の管理を明確にできる
- 信頼度・信用度が向上するため、取引先との契約を進めやすくなる
このような社会的・金銭的なメリットを考慮すると、事業を始める際は開業届を提出することがベストな判断といえます。手続きする手間はかかりますが、それ以上の恩恵を受けられるため、早めに開業届の手続きを進めましょう。
出さないほうがいい場合
開業届の提出にはさまざまなメリットがありますが、出す際に注意が必要なケースもあります。特に以下のような状況に当てはまる場合、開業届の提出だけでなく、事業を始めるかどうかも検討してみるのもよいでしょう。
-
- 健康保険の被扶養者から外れたくない場合:
開業届を出すと、個人事業主として事業を開始したとみなされ、配偶者の扶養から外れる可能性がある - 失業保険を申請する場合:
失業給付は、これから職を探す人が受け取れるもの。しかし開業届を出すと事業を開始したとみなされ、求職者ではなくなり給付の対象外となる
- 健康保険の被扶養者から外れたくない場合:
また、会社の健康保険組合に加入している場合も、開業届を提出する前に会社の健康保険組合の扶養条件を確認することが重要です。
こちらの記事でも詳しく解説しています。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業届の費用に関するよくある質問
開業届を出すにはいくら稼ぐ必要がある?
開業届の提出は「原則として事業を始めてから1か月以内」と定められています。売上や所得にかかわらず、事業を始めたら早急に開業届の手続きを進めましょう。ただし、所得の種類や状況によっては、開業届の提出を検討する目安となる基準がいくつか存在します。
・事業所得、不動産所得、山林所得の場合
これらの所得を得る事業を開始した場合、開業届の提出が必要です。所得金額にかかわらず、事業開始から1か月以内に提出することが推奨されます。一般的に、所得が48万円を超えると所得税の納税義務が生じるため、この額がひとつの目安となります。
・副業の場合
副業で得ている所得が「事業所得」に該当する場合には、開業届の提出が必要ですが、「雑所得」に該当する場合には、開業届の提出は必須ではありません。しかし、雑所得でも、継続的・反復的に行われ、事業とみなされる場合には、開業届の提出が必要になる場合があります。確定申告では、副業などで得た所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
開業届の手続きに必要なものは?
紙で開業届を提出する場合、開業届とマイナンバーカード、もしくは開業届と身分証明書、マイナンバーが必要です。電子で提出する場合は、開業届のみで手続きが完了します。後々余計な手間がかからなくて済むよう、事前に必要書類をしっかり把握して準備するようにしましょう。
開業届の提出に必要な書類はこちらの記事で解説しています。
開業届を1年以上出し忘れているけど大丈夫?
開業届を1年以上出し忘れていても、ペナルティはありませんが、青色申告ができなくなるデメリットがあります。原則として、開業届は事業開始から1か月以内に提出しなければなりません。
開業届を提出することで、青色申告による控除を受けられる、社会的な信用度が上がるなど、さまざまなメリットがあります。「開業届の提出が面倒でなかなか手続きが進められない」という方は、「弥生のかんたん開業届」を活用してみてください。画面の操作に沿って進めるだけで、個人事業主の開業届を無料で簡単に作成できます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
費用をかけず正確に!開業の手続きは「弥生のかんたん開業届」がおすすめ
本記事では個人事業主の開業届の費用についてまとめました。基本的に開業届の提出に費用はかかりません。ただし郵送する場合は封筒代や切手代が必要となります。税務署まで出向く場合は、交通費がかかってくるでしょう。初めて開業届を提出する方は不安に感じるかもしれませんが、きちんとした方法に則ればだれでも開業を実現できます。
「開業届の提出を楽に進めたい」という方は、「弥生のかんたん開業届」をご活用ください。画面の指示に従って操作を進めるだけで、無料で簡単に開業届を作成できます。これから事業を始める方、開業届を提出せずにすでに事業を始めている方におすすめです。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
この記事の監修者宮川 真一(税理士)
税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表
税理士/CFP®
1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応をはじめ、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っている。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事する。