割増賃金とは?発生する条件と割増率、計算方法を解説
更新
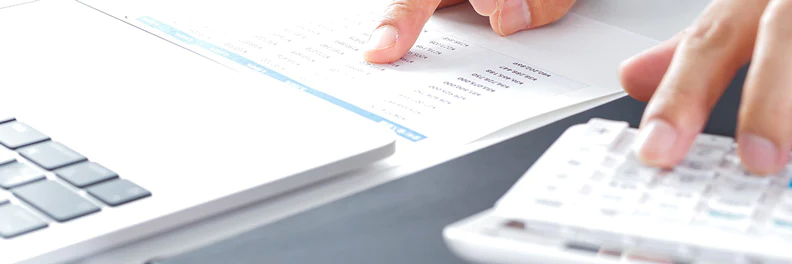
割増賃金は、法定労働時間外の労働や休日の労働、深夜の労働に対して支払われるお金です。従業員が一定の条件を満たす労働をした場合は、必ず割増賃金を支払わなければならないと、労働基準法で定められています。割増賃金を正しく支払わなければ違法となり、未払い賃金が発生し、従業員の会社に対する信頼度も低下します。
本記事では、割増賃金の発生する条件や割増率のほか、割増賃金の計算方法についてわかりやすく解説します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
割増賃金とは時間外や休日、深夜に労働したときに支払われる賃金のこと
割増賃金とは、法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金です。労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週40時間と定めています。これを超える労働が、割増賃金の対象となる残業時間です。また、週に1度の法定休日に労働した場合も割増賃金の対象です。割増賃金の割増率は、労働した時間などに応じてそれぞれ決められています。
なお、割増賃金が支払われる制度が作られた目的には、以下の2つがあります。
割増賃金制度が作られた目的
- 労働者への補償:法定労働時間を超える労働を行った従業員に対して、通常よりも高額な賃金を支払う補償をする
- 時間外労働の抑止:割増賃金を設定して企業に負担を与えることで時間外労働を抑止し、法定労働時間内で業務を完了できる体制づくりを促す
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
割増賃金の種類と割増率
割増賃金にはさまざまな種類があり、種類に応じた割増率が設定されています。ここでは、「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」それぞれの定義と割増率について見ていきましょう。
時間外労働
時間外労働とは、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働のことです。時間外労働には、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。さらに、時間外労働が月60時間(法定休日の労働時間を含まず、所定休日の労働時間を含む)を超える場合は、50%以上を支払います。
従業員に法定労働時間を超える労働をさせるためには、従業員の過半数で組織する労働組合、または従業員の過半数を代表する従業員と、36協定を締結しなければなりません。36協定を締結し、労働基準監督署に届け出て、初めて法定労働時間を超える労働が法律上認められます。
ただし、時間外労働は、原則として1か月45時間、1年360時間を超えられません。臨時的な事情があって労使が合意した場合でも、以下のような複数の要件を守ることが必要です。
臨時的な事情で時間外労働する場合の要件
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が2~6か月の期間で月平均80時間以内、および月100時間未満
- 月45時間を超えるのは年6か月まで
なお、会社は法定労働時間の1日8時間以内であれば、従業員の所定労働時間を自由に設定できます。1日の所定労働時間を6時間や7時間に設定した場合は、残業が発生したとしても、残業時間を含めた労働時間が8時間以内であれば、割増賃金の対象になりません。通常の1時間当たりの賃金を基に、働いた時間分の賃金を支払います。このような残業を、法定内残業と呼びます。
休日労働
労働基準法では、週に1日または4週に4日の休日を「法定休日」と定めています。法定休日に労働した従業員には、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
なお、週に2日以上休日がある場合、法定休日以外の休日を「所定休日」と呼びます。所定休日に割増賃金はありませんが、週40時間を超える労働をしている場合は残業と見なされ、同様の割増賃金が発生します。
深夜労働
深夜労働とは、22時から翌朝5時までの労働です。法定時間外労働の割増賃金は25%以上ですが、時間外労働かつ深夜労働になった場合は、法定時間外労働の割増賃金25%と深夜労働の割増賃金25%の合計で、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
ここまでご紹介した時間外労働、休日労働、深夜労働をまとめた割増率は、以下になります。
| 割増賃金の対象となる労働 | 割増率 |
|---|---|
| 法定内残業(1日8時間、週40時間以内) | 割増なし |
| 時間外労働(1か月60時間※以内) | 25%以上 |
| 時間外労働(1か月60時間※超) | 50%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(22時から5時まで) | 25%以上 |
| 時間外労働+深夜労働(1か月60時間※以内) | 50%以上 |
| 時間外労働+深夜労働(1か月60時間※超) | 75%以上 |
| 休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
- ※休日労働を除く
残業手当の計算方法についてはこちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
割増賃金計算の事前準備
割増賃金を計算するためには、事前準備として1時間当たりの基礎賃金を算出しなければなりません。出来高給や時給、週休、日給、時給に応じた1時間当たりの基礎賃金の計算方法や、基礎賃金から除外される手当についてご紹介します。
1時間当たりの基礎賃金を算出する
1時間当たりの基礎賃金額を算出する方法は、給与形態によって異なります。自社の給与形態に応じた1時間当たりの基礎賃金の計算方法を知っておきましょう。
月給の場合
月給制の場合は、月給を月平均所定労働日数で割った金額が1日当たりの基礎賃金です。所定労働日数は、以下の式で算出できます。
月給における所定労働日数の計算式
所定労働日数=(365日-年間所定休日数)÷12か月
ただし、通常は就業規則に労働日数の定めや残業代の計算方法が規定されています。就業規則の日数に応じて計算しましょう。
例えば、1か月の月平均所定労働日数が21日、1日の所定労働時間が8時間(固定)、月給が30万2,400円の従業員なら、1時間当たりの基礎賃金は30万2,400円÷(8時間×21日)で1,800円です。
週給の場合
週給の場合は、1週間の週平均所定労働時間で1時間当たりの基礎賃金を求めます。週によって所定労働時間が違うときは、4週間の平均で計算します。
例えば、週給5万円で1週間当たりの週平均所定労働時間が25時間の場合、5万円÷25時間で2,000円が1時間当たりの基礎賃金です。
日給の場合
日給の場合は、日給額に1日の所定労働時間を割ることで1時間当たりの基礎賃金を算出できます。日給1万円で所定労働時間が8時間なら、1万円÷8時間で1,250円が1時間当たりの基礎賃金です。
時給の場合
時給制の場合、1時間当たりの賃金が時給となります。別途計算する必要はありません。
出来高給の場合
出来高給で給与が支払われている従業員は、それぞれの月の総労働時間と支給額を基に1時間当たりの基礎賃金額を求めます。算出方法は以下のとおりです。
出来高給における1時間当たりの基礎賃金の計算式
1時間当たりの出来高基礎賃金=出来高払給÷総労働時間
例えば、該当月の出来高払給が40万円、総労働時間が200時間だった場合の1時間の基礎賃金は、40万円÷200時間で2,000円になります。
基礎賃金から除外される手当に注意
月給や週給の基となる基礎賃金は、基本給だけでなく各種手当も含まれます。ただし、以下の手当については含まずに計算します。
家族手当
扶養家族の人数等に応じて支払われる家族手当は、基礎賃金に含まれません。ただし、例えば扶養家族の数に関係なく、一律で1万円といった一律支給の場合は計算に含めます。
通勤手当
通勤にかかった実費を支給する場合は、基礎賃金から省きます。一律支給の場合は、基礎賃金に含めて計算しなければなりません。
別居手当
通勤の都合で家族と別居する場合に支給する別居手当は、基礎賃金に含まれません。
単身赴任手当
単身赴任の従業員に対して支給する単身赴任手当は、基礎賃金には含まれません。
子女教育手当
従業員の子女が教育を受けるのに必要な経費として支給される子女教育手当は、基礎賃金に含まれません。
住宅手当
家賃の一定割合を補助するなど、実費に応じて支払われるのが住宅手当です。「賃貸住宅に住んでいる従業員に対して2万円」というように、一律で支給される手当は計算に含めます。
臨時に支払われた賃金
結婚手当など、臨時的に支払われる手当は、基礎賃金に含まれません。
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
賞与など、毎月は支給されない賃金は基礎賃金に含まれません。
除外される手当は、手当の名称ではなく限定列挙で決まります。不明点がある場合は、労働基準監督署などに確認してください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
割増賃金の計算方法
ここからは、残業の種類などに応じた割増賃金の計算方法をご紹介します。なお、計算式の割増率は法律に定められた下限の数値でご紹介しますが、これよりも高く設定する分には問題ありません。ただし、賃金規程などに明記して、すべての従業員に対して公平に適用させる必要があります。
また、残業代計算で1円未満の端数が出るときがあります。その場合は、賃金支払い5原則による全額払いの原則に基づき、1円未満の端数は切り上げて計算しましょう。
時間外労働(残業)における割増賃金
深夜残業に該当しない一般的な残業に対する割増賃金の計算式は、以下のとおりです。
時間外労働の割増賃金の計算式
割増賃金=1時間当たりの基礎賃金×労働時間×1.25
ただし、時間外労働が1か月当たり60時間を超えた場合は、超えた部分についての割増賃金を以下の計算式で算出します。
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金の計算式
割増賃金=1時間当たりの基礎賃金×労働時間×1.5
休日労働における割増賃金
休日に働いた場合の割増賃金の計算式は、以下のとおりです。
休日労働の割増賃金の計算式
割増賃金=1時間当たりの基礎賃金×労働時間×1.35
休日労働に深夜労働が重なった場合は、休日労働の割増率35%に深夜労働の割増率25%を加算して、60%の割増率になります。
休日の深夜労働の割増賃金の計算式
割増賃金=1時間当たりの基礎賃金×労働時間×1.6
深夜労働における割増賃金
深夜22時から翌朝5時までに働いた場合の割増賃金の計算式は、以下のとおりです。
深夜労働の割増賃金の計算式
割増賃金=1時間当たりの基礎賃金×労働時間×1.25
ただし、深夜に残業をした場合は、時間外労働25%に深夜労働の割増賃金25%が上乗せされ、50%の割増率になります。以下の計算で手当を算出します。
深夜残業の割増賃金の計算式
割増賃金=1時間当たりの基礎賃金×労働時間×1.5
出来高給における割増賃金
出来高給の人が残業をした場合、割増賃金は以下の計算式で算出します。
出来高給の割増賃金の計算式
割増賃金=(出来高給の総額÷総実労働時間)×労働時間×1.25
ただし、深夜労働は以上に追加で25%の割増率になります。その他、休日労働などにおける割増率は、出来高給以外の場合と同様です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
割増賃金を払わない場合は罰則を受けることもある
割増賃金の支払いは、法律に定められた義務です。割増賃金を支払わなかった場合、以下の罰則の対象となります。
労働基準監督署の是正勧告を受ける
割増賃金の支払いが行われていない場合、労働基準監督署から是正勧告の対象となります。その場合は、立ち入り検査などが行われる場合もあります。
未払金に加えて付加金(割増賃金と同一額)と遅延損害金を支払う
従業員は未払いの割増賃金を請求する場合、未払金に加えて、未払いの残業代と同額程度の付加金を裁判所に対して支払いを命じるように求めることができ、一定割合の遅延損害金の支払い対象となります。
なお、付加金とは、労働基準法114条に定められており、裁判所が労働者の請求により、割増賃金等を支払わなかった会社に対して、会社が支払わなければならない金額と同一額の支払いを命じることができるという制度です。
悪質な場合は、刑事上の罰則が適用される
労働基準監督署の是正勧告によっても割増賃金の未払いが続き、悪質だと判断された場合、刑事上の罰則の対象となります。割増賃金の未払いには、労働基準法違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
割増賃金に関する注意点
ここまでご紹介してきた割増賃金に関しては、いくつかの注意点があります。それぞれ、詳しく解説します。
割増賃金の支払いに代えて代替休暇を付与できる
1か月に60時間を超える残業をした場合は、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。この場合、代替休暇についての労使協定を締結している場合、割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を付与することも可能です。
ただし、代替休暇の使用には労使協定の締結が必要で、なおかつ取得するかどうかは従業員が決めます。事業主側が指定することはできません。また、代替休暇を取得した場合でも、25%以上の割増賃金分については支払いが必要です。
変形労働時間制を採用している場合は計算方法が異なる
変形労働時間制とは、1か月以内の期間において、法定労働時間の総枠の範囲内で労働時間を決められる制度です。月末が繁忙期で月初は閑散期といった企業では、変形労働制を採用することで、月初の労働時間を短く、月末の労働時間を長く設定できます。
変形労働時間制を採用している企業では、1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えたりしても、割増賃金の対象にならない場合がありますが、以下のように変形期間内の労働時間が上限を超える場合は、残業代の支払いが必要です。
変形労働時間制における割増賃金の対象
- 1週間単位の変形労働時間制の場合:1週間の法定労働時間の総枠を超えた時間が割増賃金の対象
- 1か月単位の変形労働時間制の場合:「月の日数÷7×40時間」を超える労働が割増賃金の対象
- 1年単位の変形労働時間制の場合:「365日÷7日×40時間」で1年の労働時間を算出し、超えた時間が割増賃金の対象
ただし、それぞれの制度ごとに適正な時間管理に基づき、原則的に日、週、月、年単位で法定労働時間を超過した時間を把握し、賃金の精算が求められます。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
複雑な割増賃金の計算は給与計算ソフトで手軽に行おう
割増賃金の計算方法は、残業の種類や給与形態によって変わります。計算方法が複雑なため、手計算をしているとミスにつながる可能性があります。支払うべき割増賃金が未払いにならないように注意しなければなりません。
割増賃金の計算を正確、かつ簡単に行うなら給与ソフトの活用がおすすめです。「弥生給与 Next」は、給与計算や年末調整業務を効率化し、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています。自社に合ったツールを活用して、業務の効率化を目指しましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。


