給与明細の保管期間は何年?いつまでどうやって保管するかを解説
更新
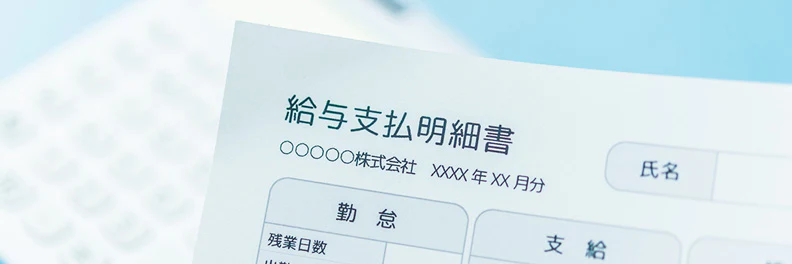
給与明細書(給料明細書)は、会社が従業員に対して、給与計算の根拠として交付する明細書です。給与明細書の発行は、所得税法に定められた会社の義務です。それでは、発行した給与明細書の控えや、交付された給与明細書は、どのように保管すればよいのでしょうか。本記事では、給与明細書の発行義務の有無や給与明細書の保管方法、会社が保管すべき書類などについて解説します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
給与明細書を保管すべき理由とは?
会社や従業員に、給与明細書の保管義務はありません。会社が作成した給与明細書の控えを保管する必要はありませんし、従業員も受け取った給与明細書をどのように扱っても問題ありません。
とはいえ、給与明細書を保管しておくことがメリットになることもあります。まずは会社と従業員、それぞれの立場から、給与明細書を保管しておくべき理由を見ていきましょう。
会社側の保管理由:トラブル防止のため
会社は、従業員に給与明細書を交付する義務がありますが、発行した給与明細書の控えの保管義務はありません。しかし、作成した給与明細書の控えを保管せず破棄してしまった場合、従業員から「給与明細書の数字が間違っているのではないか」と問い合わせがあっても、どのような明細を発行したのか確認できないといった事態になりかねません。
もちろん、給与明細書に記載されている給与の支給額や控除額、勤怠時間といった内容は、賃金台帳などの形で保管されています。しかし、仮に従業員が申告してきた給与明細書の数字と賃金台帳の数字が違っていた場合、給与明細書自体の控えがなければ、なぜそのような事態が起こったのか原因を究明することも難しくなるでしょう。
給与明細書の控えの保管は義務ではありませんが、事業活動の一環として、従業員に対して正式に交付した書類の1つです。万が一問題があった場合に、速やかに原因を特定して修正するためにも、保管しておくことをおすすめします。
従業員側の保管理由:収入を証明するため
従業員に、受け取った給与明細書を保管する義務はありませんが、2年ほど保管しておくとよいと考えられます。
給与明細書は、従業員の月々の収入を証明する書類です。そのため車のローンを契約したり、賃貸住宅を借りたりする際に、提出を求められることがあります。また、住宅ローンの契約を行う際も、直近の収入の証明として提出を求められる可能性があるでしょう。これは、課税証明書や源泉徴収票で実態を確認できない場合に、一般的に収入を証明するための補足情報として給与明細書が用いられるためです。
給与明細書は毎月交付されるものですから、少し待てば新しいものを受け取れます。しかし、ローンの契約などに際しては、「直近◯か月分の給与明細書」というように、複数枚の提出を求められることがあります。スムーズに手続きを進めるために、給与明細書を保管しておくことをおすすめします。
また、将来的に給与に関して、以下のようなトラブルが生じた場合、給与明細書は支払われた給与の内訳を証明する資料になります。
給与にかかわるトラブル例
手続き上のミスで税金が未納になっていた
給与からは雇用保険料や所得税、住民税が控除されているにもかかわらず、会社側の納付が漏れていて未納になっていた場合は、給与明細書が給与から控除されていたことを証明する資料になります。
金額が間違っている
給与支払額が間違っていた場合、実際の計算根拠や支給額を示すために給与明細書が役立ちます。
残業時間が実際と違い未払い賃金がある
実際に働いた残業時間と、残業代が支払われている残業時間に乖離があると、残業代の未払いといった問題につながります。タイムカードと給与明細書を照らし合わせれば、残業時間の計算に問題がないかどうかを確認できます。
トラブルが実際に起こった場合はもちろんですが、「もしかして未払いの残業代があるのでは?」と、不安に思ったときにも役立つのが給与明細書です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
会社は給与明細にかかわる書類の保管義務がある
会社に給与明細書の保管義務はありませんが、給与明細書に関連する賃金台帳や労働者名簿といった書類の保管は必要です。会社が保管する義務がある書類について、保存期間別に紹介します。
5年保管が必要な書類
労働基準法で会社に5年間の保管を義務付けているのは、以下の8つの書類です。以前の保管期間は3年でしたが、2020年4月から、改正労働基準法の施行によって保管期限が5年になりました(ただし、法改正の経過措置として当分の間は3年)。
労働者名簿
労働者名簿は、従業員の氏名、生年月日、住所、性別、異動などの履歴のほか、業務内容、雇用した年月日、退職した年月日、退職理由などを記載した書類です。従業員を1人でも雇用したら、従業員ごとに必ず作成しなければならない書類です。
賃金台帳
賃金台帳は、給与計算の基になる帳簿です。従業員を1人でも雇用したら、必ず作成しなければいけません。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間、基本給、手当、賃金控除額などについて記載します。
雇い入れに関する書類
雇い入れに関する書類は、雇用契約書や労働条件通知書、雇入決定通知書、履歴書などが該当します。
解雇に関する書類
解雇に関する書類は、解雇決定関係書類や解雇予告除外認定関係書類などが該当します。
災害補償に関する書類
災害補償に関する書類は、労災に当たるケガや病気の診断書や補償の支払い関係書類、領収関係書類などです。
賃金に関する書類
賃金に関する書類は、賃金決定関係書類や昇給・減給に関係する書類などです。
労働関係に関する重要な書類
労働関係に関する重要な書類には、出勤簿やタイムカードなど、従業員の勤怠管理に利用している書類が該当します。その他、労使協定書や、各種許認可書、退職関係書類、休職・出向関係書類なども含まれます。
年次有給休暇管理簿
年次有給休暇管理簿は、2019年から新たに保存が義務付けられた帳簿です。有給休暇の取得日、付与日、日数を記載する必要があります。
上記のうち、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿は、「法定三帳簿」と呼ばれる重要性の高い帳簿です。
7年保管が必要な書類
給与に関係する書類のうち、以下の書類は7年間保存する必要があります。「税金に関連する書類は7年間保存する必要がある」と考えておくとよいでしょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、従業員が所得税の扶養控除などを受けるために必要な申告書です。会社の多くは、年末調整の際に翌年分を提出してもらいます。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出がない従業員に対しては、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」を参照し、源泉徴収する所得税を通常よりも高い乙欄に明記されている数字を基に計算しなければなりません。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書の3つを1つにまとめた書類は、7年の保管が必要です。年末調整時に、基礎控除や配偶者控除などを利用する従業員が提出します。
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、年末調整の際、生命保険料控除などを利用する従業員が提出する申告書です。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を利用する従業員が年末調整時に提出する申告書です。
退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書は、退職所得の支給を受ける従業員が提出する申告書です。退職所得の受給に関する申告書を提出した従業員は、退職金に関する確定申告が原則不要になります。
源泉徴収簿(作成した場合)
源泉徴収簿は、年末調整を行う際に会社が任意で作成する帳簿です。作成義務はなく、フォーマットも決まっていませんが、正確かつ能率的な所得税計算を行うために作成が推奨されています。源泉徴収簿を年末調整の根拠として利用した場合は、7年間保存しなければなりません。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与明細書はどのように保管する?
会社にも従業員にも、給与明細書やその控えを保管する義務はありません。しかし、会社は賃金台帳と併せて給与明細書の控えを5年保管している場合が多いでしょう。従業員の保管期間は会社によってまちまちですが、2年ほど保管しておくとよいと考えられます。
また、給与明細書をソフトウェアにより、データ化することができる場合には、いつでも給与明細書を出力できるように、ファイルをバックアップしておくとよいでしょう。
紙の給与明細書の場合
紙の給与明細書は、ファイルに保管するか、電子化して保管しましょう。
ファイルに保管する方法
給与明細書を支給月ごとにまとめて、ファイルなどに入れて保管します。
電子化して保管する方法
給与明細書をスキャナなどで取り込んでデータ化し、保管します。その他、従業員には紙に印刷した給与明細書を交付し、社内的には印刷前のデータを保管しておくといった運用も可能です。
電子データでの給与明細書の場合
給与明細書をメール添付やクラウド上から送付する方法で交付している場合は、そのままデータとして保管します。データでの給与明細書の保管には、場所を取らない、管理が簡単、検索が容易といったメリットがあります。
給与明細の電子化についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
会社が給与明細書の保管をした方がよい理由
会社には給与明細書の保管義務がありませんが、義務がなくても保管しておくのがおすすめです。給与明細書を保管した方がよい理由は、以下のとおりです。
従業員が紛失して再発行を依頼されることがある
従業員から「明細をなくしてしまったから再交付してほしい」と依頼される可能性があります。このとき、明細の控えを破棄してしまっていると、改めて明細を作成しなければいけません。同じデータを使って発行するとはいえ、操作ミスなどの理由で、数字の異なる明細を作ってしまう可能性もゼロではないでしょう。控えが保存してあれば、最初に交付したものとまったく同じ書類を確実に発行できます。
なお、再発行は、必ずしも義務ではありません。
賃金支払いの証拠になる
給与明細書は、いつ、どのような根拠で、いくらの給与を支払ったかを示す証拠になります。賃金台帳を作っていたとしても、それはあくまでも社内的なもので、従業員に公開するわけではありません。給与明細書を作成して従業員に交付することで、お互いに「こういった理由で、この金額の給与を支払いました」という認識のすり合わせを行えます。
万が一、従業員から「給与が支払われていない」「給与額が違う」といった申し出があった際も、給与明細書が保管してあれば、支払いの根拠として提示できます。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与明細書や給与関連書類は適切な方法で保管しよう
給与明細書を保管する義務はありませんが、関連する書類は保管しなければなりません。給与明細書についても、併せて保管しておくとよいでしょう。再発行依頼などがあった際も、控えがあれば簡単に再発行が可能です。
給与明細を簡単に作成・保管するなら、弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」がおすすめです。発行した給与明細書はデータとして保管できるため、場所を取りません。過去の履歴も簡単に確認できますし、給与明細の再発行も容易です。給与計算業務の効率化に、ぜひお役立てください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。


