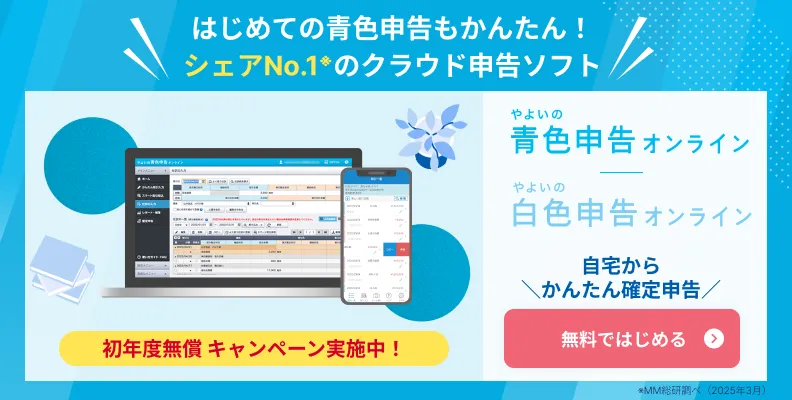一人親方の確定申告を解説!やり方や必要書類、経費で落とせるものを解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
更新

一人親方として独立・開業して働いている方は、所得を申告して納税額を確定させるために、確定申告をしなければなりません。確定申告には青色申告と白色申告の2つの方法があり、それぞれに特徴があります。しかし、専門的な知識がない状態で手続きをするのは心細く、どの申告方法を選べばいいか迷うのも無理はありません。
本記事では、申告方法の選び方や経費計上のコツ、必要書類、注意点などを詳しく解説します。本記事を読むことで、確定申告の基本的な流れを理解し、自分に合った方法で正しく手続きを進めるための知識を得られます。
一人親方が確定申告を行う際のやり方は2つ
一人親方は個人事業主の一種です。そのため、確定申告が必要です。申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットをふまえたうえで、自身の状況に適した方法を選択してください。
青色申告
青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を提出している必要があります。帳簿付けには複式簿記が求められるため、手続きがやや複雑で負担に感じるかもしれません。しかし、青色申告特別控除による節税効果が期待できるため、基本的には青色申告がおすすめです。最大65万円の控除を受けられるため、節税メリットが大きいです。
また、赤字の3年間繰り越しや、家族への給与を経費として計上できるといったメリットもあります。最近では使いやすい確定申告ソフトが登場しており、それを利用すれば簿記の知識がない初心者でも複式簿記に対応できるため、ソフトを活用して手続きを進めることで負担を軽減できます。
白色申告
白色申告は、青色申告と異なり、簡易な方法による記帳が認められています。ただし、青色申告特別控除などの節税メリットはありません。そのため、収入が少ない一時的な仕事の場合や、税負担が多少増えても記帳の手間を減らしたい場合には、白色申告も選択肢の1つとなります。
一人親方が確定申告で経費計上できる費用
一人親方として独立・開業すると、予想以上にさまざまな出費が発生します。以下では、確定申告で経費として計上できる費用を紹介します。漏れなく経費を計上することで、最終的に税負担を軽減することが可能です。
旅費交通費
「旅費交通費」として経費計上できる項目には、自動車のガソリン代、電車代、ETCを含む高速料金、出張時のホテル代や食事代などが含まれます。これらは業務に関連している必要があり、例えば、現場間の移動で使用したガソリン代や高速道路代などが該当します。一方、個人用の交通費は経費として計上することができません。そのため、事業用と個人用を分けて領収書を保管するなど、日常的に適切に管理することが重要です。
保険料
事業継続に必要な損害保険の場合、その保険料は経費になります。例えば、作業車に対する自動車保険、事業所や店舗にかける火災保険や地震保険などが該当します。ただし、プライベートで使用する自動車や自宅の保険料は経費になりません。
事業とプライベートの両方で使用する場合は、家事按分を適用し、事業で使用している割合のみが経費として認められます。自動車やバイクの家事按分は、一般的に使用回数や走行距離によって算出されます。建物の家事按分は、面積などによって算出されます。
なお、保険料であればすべてが経費になるわけではありません。生命保険料や一人親方労災保険料などは経費として申告できないため、注意が必要です。
運送費
部材、残材、必要機器類などの運搬にかかる運送費は、通常「荷造運賃」として計上します。具体的には、宅配便、バイク便、船舶輸送、航空輸送などが該当します。
外注費
外注費とは、事業の一部を他の個人事業主や企業に委託する際に発生する費用です。例えば、営業用のパンフレットを印刷会社に依頼した場合の費用や、ホームページの制作・管理を依頼した場合にかかる費用を計上します。
組合費
一人親方が労災保険の補償を受けるためには、一人親方団体に加入する必要があります。加入時に支払う入会金や組合費は、「諸会費」もしくは「租税公課」として経費に計上できます。どちらの勘定科目を使用するかは任意ですが、毎年一貫した方法で処理することが重要です。
地代家賃
事業用として使用するオフィスや店舗、駐車場などの賃料は、「地代家賃」として計上できます。ただし、自宅としてプライベートで使う部分は経費として認められません。プライベートと事業の両方で使用している場合は、家事按分によって事業用途に該当する部分のみが経費として計上されます。
材料費
仕事に必要な工具や備品の材料費は、「消耗品費」として計上できます。一人親方の場合、建築資材や修理に必要な部品、塗料や接着剤など、事業に直接関係するものが対象です。
通信費
事業用の固定電話や携帯電話の使用料、プロバイダー費用、Wi-Fi利用料などのインターネット関連費用は「通信費」として計上できます。また、郵便代やはがき代、ホームページの管理費、有線放送の使用料なども通信費に含まれます。ただし、自宅を事務所として使用している場合の固定電話や、プライベートと兼用している携帯電話の費用については、事業に使う割合を家事按分する必要があります。
一人親方が確定申告で経費計上できない費用
一人親方が確定申告をする際には、経費として計上できるものとできないものを正しく区別することが大切です。原則として「事業に関係のない費用は計上できない」と覚えておきましょう。例えば、仕事用の車両であっても、それを用いてレジャーに行った際のガソリン代は経費には含まれません。公私の区別があいまいにならないよう注意しましょう。なお、特別加入制度を利用して支払う労災保険料については、経費として計上できませんが、社会保険料控除の対象になります。
一人親方の確定申告ではしっかりと棚卸することが大切
一人親方が正しく利益を算出するためには、棚卸しが欠かせません。棚卸しとは、在庫を年末時点で正確に把握し、その価額を棚卸資産として計上する作業です。売上総利益は「売上-売上原価」で計算され、売上原価は「期首棚卸資産+当期仕入高-期末棚卸資産」として求められます。年末時点での在庫を適切に管理することで、正確な利益や経費が明確になり、税金対策を講じる際に役立ちます。
一人親方が確定申告を行う際の注意点
一人親方が他の人に仕事を依頼した際に支払う作業報酬を「給与」とするか「外注費」とするかには注意が必要です。雇用関係に近い形態で業務を監督している場合や、他の人に代わることができない状態での作業であれば、「給与」として処理することが適切です。給与扱いにすると源泉徴収や社会保険の加入義務が発生しますが、無理に外注費扱いにしないよう気を付けましょう。税務調査で指摘を受ける可能性もあるため、正しい処理を心がけることが大切です。
一人親方が確定申告を行う際の必要書類
確定申告に必要な書類は、青色申告、白色申告のうちどちらを選択するのかによって異なります。
青色申告の場合は、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 売上や支出がわかる書類
- 各種控除に必要な証明書
白色申告の場合は、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 収支内訳書
- 売上や支出がわかる書類
- 各種控除に必要な証明書
確定申告書
収入や所得金額、算出した税額を記入する書類で、国税庁のホームページから確定申告書をダウンロードできます。一人親方が使用するのは、確定申告書の第一表と第二表です。
青色申告決算書または収支内訳書
青色申告を選択する場合、青色申告決算書を作成します。この書類は損益計算書と貸借対照表の2つで構成され、事業の収益や支出の詳細、資産と負債の状況を報告します。一方、白色申告では収支内訳書を使用し、売上や経費を簡易にまとめて計算します。どちらも、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。一人親方は一般用様式を使用します。
売上・支出がわかる書類
1年間の収入を確認するための売上台帳や請求書、支出を確認するための領収書などを揃える必要があります。確定申告の時期になって焦らないよう、定期的に売上台帳を付けておく必要があります。これらの書類は、確定申告書などを作成するための材料であり、税務署へ提出するものではありません。ただし、税務調査時に提示を求められる可能性があるため、大切に保管してください。
各種控除に必要な証明書
各種所得控除の申告に際しては、国民健康保険料および国民年金の払込証明書など、支払額を確認できる資料の提出が必要です。
その他
マイナンバーカードなどのマイナンバーを確認できる書類も必要です。扶養控除や配偶者控除を申請する場合は、対象となる親族・配偶者のマイナンバーも必要です。全員分のマイナンバーを記載した住民票があると一覧できます。
また、還付を受ける場合には、口座の情報も必要です。ネット銀行など一部の金融機関には、還付金を受け取ることができないものもあるため、気を付けましょう。
さらに、減価償却が必要な資産がある場合は、固定資産台帳を作成します。特定の様式は設けられていませんが、勘定科目、件名、取得年月日、取得価額、耐用年数、減価償却累計額、帳簿価額、および数量などの情報を網羅する必要があります。
一人親方が確定申告を行う際の流れ
確定申告は、以下の6つのステップで進行していきます。
1.帳簿の作成
正確な申告を行うためには、日々の取引を正しく帳簿に記録することが重要です。特に青色申告を選択する場合には、複式簿記での帳簿付けが必要です。日々の記録をこまめに行い、取引内容をきちんと把握することで、確定申告時の負担を軽減できます。
2.所得金額の計算
個人事業主である一人親方の所得金額は、事業所得になります。事業所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。正確に把握するために、日ごろから売上や経費の管理が重要です。
3.各種控除の計算
一人親方が利用できる代表的な控除には、労災保険料や医療費控除があります。多くの一人親方は、一人親方団体を通じて労災保険に加入しており、支払った保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。また、医療費控除は年間の医療費総額から保険金で補填された分と10万円を差し引いた金額が対象です。
4.所得税額の計算
所得金額から各種控除の合計金額を差し引いた課税所得金額に基づいて、所得税額を算出します。所得税は累進課税制度であり、課税所得金額が高くなるにつれて税率も高くなるしくみです。
5.確定申告書の作成
確定申告書は、手書きで作成することも可能です。国税庁のホームページからダウンロードし、必要事項を記入して作成します。また、国税庁が提供する「確定申告書作成等コーナー」では、画面の指示に従って必要事項を入力すれば、納税額が自動で計算されます。完成した申告書は印刷して提出するほか、e-Taxでオンライン提出もできます。
さらに、確定申告ソフトを利用して簡単に申告書を作成することも可能です。画面の指示に従うだけですばやく申告書が完成するので、特に慣れていない方には初心者向けの会計ソフトの利用をおすすめします。
6.税務署に確定申告書を提出
確定申告書の準備が整ったら、税務署に提出します。e-Taxを利用する方法、郵送による方法、税務署窓口への直接持ち込みの3つの選択肢があります。e-Taxは手続きがスムーズで、時間の節約になりますが、直接持ち込むことで安心できる方もいるかと思います。自分に合った方法を選んでください。
1人親方も確定申告についてしっかりと把握しておこう
一人親方は確定申告する必要があります。一人親方でインボイス制度を機に適格請求書発行事業者になった場合は、消費税の申告も必要です。手続きが面倒に感じることがあるかもしれませんが、税務調査で問題が発生しないよう、ルールに従って適切に対応しましょう。
確定申告ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても確定申告は可能です。初心者で使いやすいクラウド確定申告ソフトが、「やよいの白色申告 オンライン」と「やよいの青色申告 オンライン」です。確定申告の負担を軽減するために、ぜひご活用ください。
photo:Thinkstock / Getty Images
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。