個人事業主は労働保険料を経費に計上できる?勘定科目・仕訳例も解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
更新
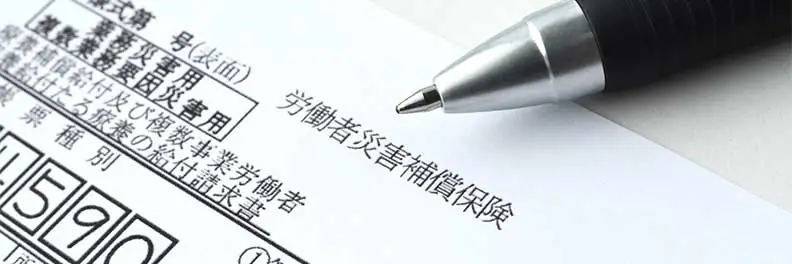
労働保険料とは「労働者災害補償保険」と「雇用保険」それぞれの保険料を合算したものです。個人事業主が労働保険料を経費として計上できるかどうかは、雇用する従業員の有無によって異なります。従業員を雇用している場合は、労働保険料を「法定福利費」として経費に計上できますが、例えば、建設業で一人親方が自身の労働保険料を支払っている場合などは経費計上できません。
本記事では、これらの違いについて詳しく解説するとともに、労働保険料の概要、ケース別の労働保険料の勘定科目と仕訳をまとめています。従業員の雇用を検討しており、その場合の経費計上の方法などを知りたいと思っている個人事業主の方はぜひ記事を参考にしてください。
そもそも労働保険料とは?
労働保険は「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称したもので、いずれもすべての労働者の雇用と生活を守ることを目的とした、国が設けている社会保険制度です。
労災保険は、業務中や通勤中に発生した事故や災害によるケガや病気、障害、死亡などに対して補償するものです。一方、雇用保険は、失業した場合や事情により働けなくなった場合に給付されるもので、再就職や起業などを支援します。
それぞれの対象者は以下の通りです。
- 労災保険:パートやアルバイト、派遣などの非正規雇用者を含むすべての労働者
- 雇用保険:労働時間などに関する一定の条件を満たす場合に限り、非正規雇用者も対象
事業主は労働者を1人でも雇用している場合、労働保険に加入し、保険料を納付する義務があります。
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合算したものであり、計算の基礎となるのは、従業員に支払われる賃金総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)です。労災保険料は事業主が全額負担しますが、雇用保険料は事業主と労働者が分担します。
なお、事業主は毎年6月1日~7月10日の手続き期間内に、労働保険料の申告・納付を行わなければなりません。
労災保険
労働者が業務中や通勤中に、ケガや病気、死亡などを引き起こした場合に給付金を支給する制度です。労働者本人とその家族を保護するために設けられています。保険対象は、企業が雇用している労働者であり、すべての雇用形態が該当します。
通常、個人事業主や会社の役員は労災保険の対象外ですが、建設業や林業など危険性の高い事業を営む個人事業主の場合は、特別加入制度の利用が可能です。この制度により、個人事業主も労働者と同様に、労災保険の給付を受けられるようになります。
給付金の種類として、以下が挙げられます。
- 療養補償給付:治療費の支給
- 休業補償給付:休業中の賃金の一部補償
- 障害補償給付:障害が残った場合の補償
- 遺族補償給付:労働者が死亡した場合の遺族への補償
参照:厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」
雇用保険
労働者が失業した場合や育児休業・介護休業などを取得する場合、労働者の雇用と生活を守るための給付金が支給される制度です。また、教育訓練を受けた場合にも、就職の促進を目的に給付されます。
給付金の種類として、以下が挙げられます。
- 求職者給付:失業者に支給される
- 育児休業給付:育児休業の取得者に支給される
- 介護休業給付:介護休業の取得者に支給される
- 教育訓練給付:教育訓練の受講者(在職者や離職者など)に支給される
労災保険と同様、個人事業主は雇用保険の対象外であり、個人事業主に雇用されている労働者のみ加入できます。
雇用保険に加入するためには、事業主が所定の手続きを行うことが必要です。新たに労働者を雇用した場合や労働者が退職した場合などにも、適切な手続きを施さなければなりません。
参照:厚生労働省「雇用保険制度」
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
個人事業主の労働保険料は経費として計上できる?
個人事業主の労働保険料は、経費として計上できる場合とできない場合があります。以下より、それぞれを詳しく解説します。
一人親方の場合は経費計上できない
通常、労働者を遣わずに事業を行う「一人親方」や個人事業主は労災保険の対象外です。ただし、上述した通り、建設業や林業など危険性の高い事業を営んでいる場合は、特別加入制度を利用して労災保険に加入できます。
一人親方が自身のために支払った労災保険料の経費計上は認められません。なぜなら、労災保険は本来、雇用されている労働者を対象としたものであり、一人親方の加入は特例だからです。しかし、一人親方が特別加入によって支払った労災保険料は、確定申告で社会保険料として控除が可能なので、結果的に節税につながります。
従業員を雇用している場合は経費計上できる
個人事業主が労働者を雇用している場合、その労働者のために支払った労災保険料の経費計上ができます。経費計上の条件は、雇用している労働者全員分の保険料を支払うことです。この条件を満たせば、労災保険料を「法定福利費」としての経費計上が認められます。ただし、特定の労働者1人に対して支払った保険料は経費として見なされないため、労働者全員に対して等しく支払っていることが求められます。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
労働保険料の勘定科目と仕訳をケース別で解説
以下より、労働保険料の勘定科目と仕訳について、「一人親方の個人事業主が自身の労働保険料を支払った場合」と「個人事業主が雇用している労働者の労働保険料を支払った場合」の2つのケースで解説します。
一人親方の個人事業主が自身の労働保険料を支払った場合
上述した通り、一人親方が自身のために支払った労働保険料の経費計上は認められません。事業主側の負担が義務付けられているわけではないので、帳簿への記帳は不要です。
ここでは、事業用の口座から労働保険料を支出したケースを想定していますが、この場合の勘定科目は「事業主貸」となります。例えば、事業用の口座から40,000円を支払った場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 40,000 | 普通預金 | 40,000 | 労災保険料 |
このように仕訳することで、事業用の口座から支出された金額が、事業主個人の支出として処理されます。
個人事業主が雇用している従業員の労働保険料を支払った場合
個人事業主が労働者のために支払った労働保険料は、「法定福利費」として経費計上が可能です。また、労働者が負担する労働保険料を、事業主が一時的に立て替えた場合は「立替金」として計上します。
例えば、労働保険料40,000円を現金で納付し、法定福利費を利用する場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 40,000 | 現金 | 40,000 | 労働保険料納付 |
同じく立替金を利用する場合は以下の通りです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 22,000 | 現金 | 40,000 | 労働保険料納付 |
| 立替金 | 18,000 | 労働保険料労働者負担分 |
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
労働保険料は正しく仕訳しよう
労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は業務中や通勤中のケガや病気などに対する補償を行い、事業主が全額負担します。雇用保険は失業時や休業時に給付を行うもので、事業主と労働者が負担します。一人親方が特別加入する場合、その保険料の経費計上は認められませんが、労働者のために支払う労働保険料は「法定福利費」として経費計上が可能です。
「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」は、日々の記帳データをもとに、決算書や確定申告書を作成できるクラウド申告ソフトです。税務署に行く必要はなく、e-Taxによる確定申告にも対応しています。経理業務の効率化に活用しましょう。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。










