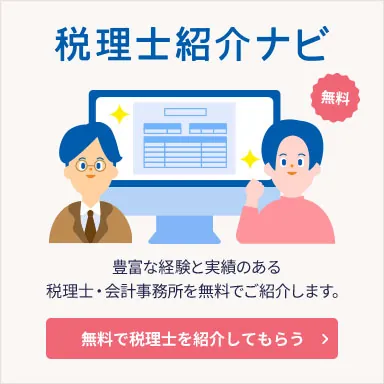税理士報酬の相場はいくら?顧問料が変動する要因や税理士を選ぶ際のポイントを解説
監修者: 高崎 文秀
更新

税理士との顧問契約にかかる費用は、法人か個人事業主かだけでなく、依頼内容や、やりとりの頻度などによっても変わってきます。本記事では、税理士の顧問料が変動する要因、顧問料の費用相場、費用を抑えるコツ、税理士選びでチェックするポイントなどについて解説します。
税理士に依頼する場合の報酬相場
ここでは、税理士に業務を依頼する場合の報酬の相場を、以下に分けて解説します。
- 月額の顧問料
- 決算申告の依頼費用
- 相続税申告の依頼費用
顧問契約の依頼費用(月額顧問料)
税理士の顧問料はさまざまな要因で変動しますが、年間を通して定期的に業務を依頼した場合の月額料金はいくらくらい必要なのでしょうか。業務内容などによっても異なってきますが、だいたいの目安は次に挙げる通りです。
| 法人 | 個人事業主 | |
|---|---|---|
| 記帳代行なし | 2万円~ | 1万円~ |
| 記帳代行あり | 4万円~ | 3万円~ |
決算申告の依頼費用
決算申告とは、事業での一定期間の収支を決算書にまとめ、管轄の税務署へ提出して納税することを指します。顧問契約することなく、決算申告のみ依頼することも可能です。その場合の費用相場は15万~25万円程度です。
顧問契約をして、月々の料金を支払っていたとしても、一般的に決算申告の費用は別料金となります。顧問契約を交わしている場合には、月額顧問料の4~6倍かかるのが相場であるため、料金が3万円であれば決算申告の費用は12~18万円が目安となります。ただし、この費用はあくまで目安です。会社の売上規模や従業員数などによって業務量は変わってくるため、料金も変動します。記帳代行を依頼するのか、申告書類の作成のみを依頼するのかなど、依頼する業務範囲によっても料金は変わってきます。
相続税申告の依頼費用
相続税の申告を依頼する場合の基本報酬の相場は、遺産総額の0.5~1.5%程度です。例えば、遺産総額が5,000万円の場合であれば、税理士報酬は25万~75万円が相場です。ただし、 この費用もさまざまな要因で変わってきます。一般的には、遺産総額にもとづいて基本報酬が算出されますが、相続人の数や財産の評価の難易度などによって加算報酬額が基本報酬にプラスされるようになっています。加算報酬額が発生するケースとしては、相続人が2人以上いる場合、被相続人が自宅以外の不動産や非上場株式を所有していた場合、相続税申告の期限が間近で依頼した場合などがあります。
相続時には一般的に確定申告の必要はありませんが、遺産の売買などで確定申告を依頼する場合の費用相場は数万円~20万円程度です。
税理士への依頼は顧問契約が前提
税理士に相談するときは、法人の場合も個人事業主の場合も、基本的に顧問契約を結んでいることが前提です。顧問契約の形態には、年間を通して定期的にやりとりする月次決算型と、決算期にのみやりとりをする年1決算型との2種類があります。顧問契約のほかにもスポット契約という依頼方法もあります。それぞれの特徴は下記の通りです。
年間を通して定期的にやりとりをする契約形態
年間を通して定期的に税務や節税対策、融資、資金繰りなどの相談をする契約形態で、「月次決算型」と呼ばれます。この契約形態のメリットは、定期的なやりとりが発生するため、税理士が会社の経営状況を把握しやすく、決算申告や年末調整などにスムーズに対応できることです。定期的に経営状況を相談することで、適切なタイミングで節税対策などについてアドバイスをもらえることもメリットとして挙げられます。税理士からの適切なアドバイスについては、資金調達面などにおいても同様です。金融機関からの融資や公的機関からの補助金・助成金を受ける際にも、経営面を考慮した、有効なアドバイスを期待できます。
一般的に税理士とのやりとりは毎月行いますが、四半期または半年ごとに1回という場合もあります。顧問料は月単位あるいは年単位で発生します。月次決算型では、報酬が高額になりがちであることがデメリットですが、経営面でプラスになるメリットが大きい契約形態です。
毎年、年に1回だけやりとりをする契約形態
年に1回、法人の決算申告や個人事業主の確定申告のみを依頼する契約形態です。1年(1回)限りの場合はスポット契約と呼ばれますが、毎年依頼する場合は顧問契約扱いとなり、「年1決算型」や「1回決算型」などと呼ばれます。個人事業主の多くは、この契約形態を選択しています。メリットは、経営者や経理担当者の決算や確定申告に関する業務上の負担が減ることです。一方で、月次決算型に比べて税理士とのやりとりが少ないぶん、年間を通じた節税対策などのアドバイスは受けにくくなります。費用面では、基本的に決算申告や確定申告の業務に対する報酬のみが発生するため、月次決算型に比べ安く収まる傾向にあります。しかし、例外もあり、例えば、日々の記帳業務を自社できちんと行えていない場合には、当該作業に対して別途料金が発生することがあります。確定申告の費用相場についてはこちらの記事も参照してください。
関連記事
スポット契約には継続義務なし
「スポット契約」とは、税理士に依頼する業務が発生したタイミングで、単発で締結する契約のことです。1回限りの契約であり、継続して依頼する義務はありません。具体的な業務としては、記帳代行をはじめ、決算書や各種申告書の作成、申告業務の代行などが挙げられます。取引件数の少ない企業や、顧問契約を結ぶほどの余裕がない企業などで多く採用されています。大きなメリットは、必要な業務が発生した際に限定して契約する形態であるため、顧問契約に比べれば、費用を抑えられることです。しかし、定期的なやりとりは発生しないため、税理士が取引の内容や状況を正確に把握することは難しくなります。売上や経費の認識に食い違いが生じてしまったり、決算書の正確性が損なわれたりするリスクもあり、十分な節税対策が行えないこともあります。中長期的なサポートを希望する場合には顧問契約の方が適していますが、社内の経理体制がしっかりと整っており、年間を通したアドバイスも不要だという会社であれば、スポット契約の方が適しています。
税理士の顧問料が変動する要因
税理士の顧問料はさまざまな要因によって変動します。主な要因としては、以下の4つが挙げられます。
- 会社の売上規模
- 従業員数
- 面談頻度
- 記帳代行の依頼有無
ここでは、それぞれについて簡単に解説します。
会社の売上規模
顧問料は、依頼元である会社の売上規模によって変わってきます。一般的に会社の売上規模が大きければ大きいほど取引数は多く、税理士の作業量が増えるため、金額も高くなります。
従業員数
会社の従業員数も顧問料を変動させる要因のひとつです。特に給与計算や年末調整を依頼している場合には、従業員の数に応じて税理士の業務量は増減します。これらの業務を依頼する場合には、月額料金とは別に、従業員数に合わせた費用が設定されていることがあります。
税理士の面談頻度
面談頻度は月に1回、四半期に1回、1年に1回など、契約内容によってさまざまです。頻度が高ければ、そのぶん税理士が稼働する時間が増えるため、顧問料も高くなります。
記帳代行の依頼有無
記帳代行を依頼するかどうかも顧問料に影響します。記帳代行とは、領収書や請求書の控え、通帳のコピーなどの必要書類を税理士に渡して、帳簿を作成してもらうことです。一般的に仕訳数によって料金は異なってきますが、基本料金でどこまで対応してくれるかは、事前に確認しておく必要があります。
税理士に依頼すべきかどうかの判断基準
税理士に依頼すべきかどうかを悩んでいる場合には、以下の3つが判断基準になります。
- 予算
- 月々の仕訳数
- 経理処理をこなせる人材の有
予算
顧問契約を結ぶのであれば、法人の場合は年間30万~40万円、個人事業主の場合は同じく10万~30万円の予算が必要です。依頼内容が増えるほど料金も上がっていきます。予算は、依頼内容や件数を考慮したうえで立ててください。税理士に支払う報酬は経費として処理することが可能で、節税対策にはなりますが、そもそも年間数十万円を支払う余裕があるのかどうかを見極める必要があります。
月々の仕訳数
二つめの判断基準となるのが月々の仕訳数です。仕訳数が多ければ多いほど、事業に充てられるはずの時間が減ってしまうため、税理士に依頼する意義は大きくなります。しかし仕訳数によって料金は変動し、多くなれば一般的に料金は高くなります。仕訳作成業務を自社で難なくこなせており、通常業務には大きな影響が出ていないようであれば、税理士に必ずしも依頼しなくても良いでしょう。
会計や会計ソフトに詳しい従業員の有無
社内の従業員で経理処理をこなせる人材や会計ソフトを扱える人材がいて、かつ会社規模がそれほど大きくなければ、社内で経理業務を行ったとしても、本業への影響もそれほど大きくはならないと考えられます。このような場合には、決算申告や確定申告での漏れや間違いをなくすという目的で、申告書類の作成業務のみを税理士に依頼するという方法もあります。
税理士を選ぶ際のポイント
税理士を選ぶ際には、費用以外にもチェックしておくべきポイントがあります。
- 自分と相性や考え方が合うか
- 顧問料の内訳が明確か
- 素早く対応してもらえるか
- 自社の業界・業種への知識があるか
- 経営に関する知識や経験は豊富か
自分と相性や考え方が合うか
税理士に依頼する場合には、自社の経営に関して重要な情報を共有し、相談することになります。依頼先の相手は、自分と相性や考え方が合っており、「一緒に仕事をしたい」と思えるくらい信頼できる人物が望ましいと考えられます。例えば、コミュニケーションが円滑にできる、気軽に相談できそうな雰囲気がある、といったことも考慮すべきポイントです。
顧問料の内訳が明確か
基本料金は安く抑えられていても、実はオプションメニューが細かく設定されており、終わってみれば、当初の想定以上に高額になってしまったというケースはめずらしくありません。顧問料の内訳は明確に示されているかどうかは、必ずチェックしてください。提示された金額と内容を確認することはもちろん、依頼内容に対して金額が適正なものかどうかを見極めることも大切です。
素早く対応してもらえるか
業務を依頼した際や何かを相談した際に、素早く対応してくれるかどうかも、税理士を選ぶ際のポイントのひとつです。顧問税理士になかなか連絡がつかないようでは、ストレスがたまるばかりでなく、経営判断の遅れにつながるかもしれません。初回の相談時や見積もりを受け取った際などに、先方とスムーズにやりとりが進むかどうかも確認すべきです。
自社の業界・業種への知識があるか
ひと口に税理士といっても、経験してきた業界・業種は人それぞれです。例えば業種が異なれば、効果的な節税方法も異なります。自社の業界・業種に豊富な知識をもっている税理士を選べば、具体的かつ有効な節税策を提案してくれるはずです。担当してきた企業の規模が自社と同等(あるいはそれ以上)かどうかもチェックポイントです。
経営に関する知識や経験は豊富か
税務のみならず、経営に関しても豊富な知識や経験をもっているかどうかをチェックすることも大切です。経営の相談に答えるためには、税務の知識だけでは不十分です。資金調達や補助金・助成金に関する質問などにも的確に回答してくれる税理士であれば、幅広い面からの経営サポートを期待できます。
税理士の費用を抑えるコツ
費用を抑える方法としては、以下3つの方法が挙げられます。
- 記帳業務を自社で行う
- 面談回数を減らす
- 自社のニーズとマッチしているかを考える
記帳業務を自社で行う
会計ソフトなどを活用し、記帳業務を自社で行えば、最大1万円程度の費用を削減することが可能です。記帳を自社で行えば、経営状態をタイムリーに把握することができるといったメリットもあります。
税理士の面談回数を減らす
面談回数が多いほど、顧問料が高くなる傾向にあります。そのため、面談回数を減らすことで、費用を抑えられる可能性があります。対面ではなくオンライン面談にしたり、自分から税理士事務所を訪問することで料金がさがることもあります。ただし、面談回数が多いほど税理士の経営に対する理解は深まるため、費用対効果を考えることが大切です。
自社のニーズとマッチしているかを考える
契約内容を見直すことも、顧問料を抑えるポイントのひとつです。例えば、月額顧問料を相場よりも安く設定している税理士の場合、基本的には税金の計算のみを行い、経営相談や税務調査の立ち会いなどには別料金を設定していることがあります。今後の事業展開や節税対策について相談したいと考えている場合、このような税理士と顧問契約を結ぶと、定期的に相談ができず、料金も割高になってしまいかねません。顧問料に含まれる業務内容を見直し、自社のニーズとマッチしているかどうかを再検討することをおすすめします。
最適な税理士を探すには?
自分に合った税理士に相談したいと思っても、自力で税理士を探そうとすると手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、起業全般や税、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所から、ぴったりの税理士や会計事務所を最短で翌日にご案内できます。完全無料で、会社所在地や業種に合わせた最適な税理士をご紹介します(2025年8月時点)。
「税理士紹介ナビ」には、事業者のお困りごとに沿って弥生スタッフが最適な税理士や会計事務所を紹介する「税理士紹介サービス」と、ご自身で自由に税理士を探すことのできる「税理士検索
」の2つのサービスがありますので、ご自身の状況に合ったサービスをご活用ください。
「税理士紹介ナビ」はこんな方におすすめ
「税理士紹介ナビ」は、特に次のような方におすすめです。
初めて会社を設立する方
会社を設立する際には、必要な手続きや資金調達など多くの不安や疑問が生じることがあります。「税理士紹介ナビ」なら、これから事業を始める方の悩みや困りごとに合わせて、最適な税理士探しをサポートします。個人事業主から法人成りを予定している方にもぴったりです。
起業後の会計処理や決算が不安な方
会社を運営するうえでは、法人税や地方税、消費税など、さまざまな税や固定資産の知識が必要になります。そのような場合も、会計処理や決算に関することをまとめてプロに相談できます。
できるだけ節税したい方
「節税したいが方法がわからない」という方にも「税理士紹介ナビ」はおすすめです。税理士からのアドバイスで節税方法を理解できれば、戦略的な経営にも役立つでしょう。
記帳業務を丸ごとプロに任せたい方
日々の取引を記帳するには手間や労力がかかります。売上が増えるとともに経理作業量も増え、負担が大きくなってしまうでしょう。記帳業務を税理士に丸投げできれば、その分しっかり本業に集中できるようになります。
報酬相場を把握して信頼できる税理士を選ぼう
税理士報酬はさまざまな要因で変動します。顧問契約には、年間を通して定期的にやりとりをする形態と、毎年1回決算申告や確定申告だけを依頼する形態があります。顧問契約はせず、1回きりのスポット契約をするという選択肢もあります。いずれにしても継続的な付き合いになることを見据えたうえで、信頼できる税理士と契約を結ぶことが大切です。
税理士を選ぶ際には、費用面以外にも「自分と相性がいいか」「営んでいる事業への理解が深いか」といった要素も重要なポイントです。無料相談に対応している税理士事務所もありますので、顧問契約をする前にできるだけ話を聞いてみてください。「どうやって税理士を探したらよいかわからない」という場合には、弥生の「税理士紹介ナビ」を活用することをおすすめします。
この記事の監修者高崎 文秀
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。