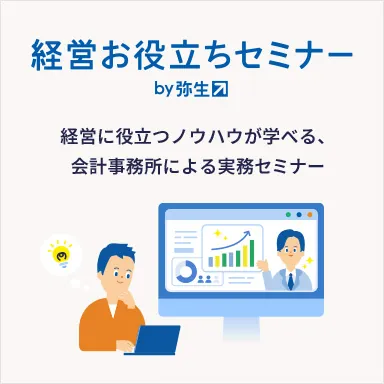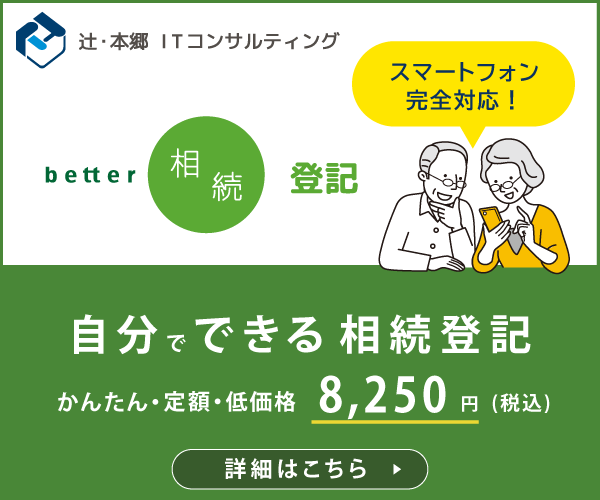ベンチャー企業を買収する方法やメリット、M&Aにおける注意点を解説
更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら
海外に比べると、日本はベンチャー企業が育ちにくいとされてきましたが、日本銀行の「わが国ベンチャービジネスの現状と課題 」(2022年6月)によると、資金調達額の増加と共に、ベンチャー企業数も増加しており、改善の動きが見られるとされています。また、ベンチャー企業への投資額の他、ベンチャー企業を買収するM&Aも増加傾向にあります。
ここでは、ベンチャー企業を買収する方法や買収するメリットの他、ベンチャー企業を買収する際の注意点について解説します。
ベンチャー企業のM&Aが増加している背景
株式会社レコフの「1-3月期のM&A件数、最多更新。金額は25.7%減少 」(2022年4月)によると、2022年1月~3月期の日本企業のM&A件数は1,124件で過去最多を更新しました。そのうち、ベンチャー企業を買収したM&Aは442件で前年同期から12.5%増、M&A全体に占めるベンチャー企業のM&Aの割合は39.3%で前年1年間の水準とほぼ変わらず推移しています。
このように、近年ベンチャー企業を対象としたM&Aが活況である背景としては、以下2つの事情があると考えられます。
イグジット(投資回収)の方法としてM&Aが定着したこと
ベンチャー企業のイグジット(投資回収)の方法には、IPOとM&Aがあります。従来、ベンチャー企業は、IPOで株式公開により広く投資家から資金を集めてさらなる事業拡大を目指すか、株式公開によって創業者利益を得ることを目標とすることが多くありました。しかし、IPOはハードルが高く、実施できる企業は限られています。近年ではM&Aの有用性が広まったことやIPOよりも短期間でイグジットが可能であることから、ベンチャー企業にもM&Aが定着しつつあります。
M&Aによるイグジットで新たな挑戦に乗り出せること
ベンチャー企業のオーナー経営者は、M&Aを行うことで創業者利益を手にしたり、安定した経営基盤を得て新たな挑戦に乗り出したりすることが可能です。M&Aによるイグジットを成功させれば、投資家や起業家としての新たな道が開かれる可能性があり、こうした挑戦に魅力を感じているオーナー経営者がいることもM&A増加の要因の1つといえます。
ベンチャー企業を買収するメリット
ベンチャー企業の買収において買手は大企業が中心ですが、ベンチャー企業同士のM&Aも行われています。買手が完全に経営権を得るM&Aだけでなく、ベンチャー企業が出資者を募り、募集に応じた大企業やファンド、個人が出資するケースも少なくありません。
ベンチャー企業の評価は、一般的な企業評価の基準となる資産総額や保有しているブランドより、その企業が持つノウハウや優秀な人材、熱心なファンの存在を主な評価対象とすることが一般的です。こうした魅力的なベンチャー企業を買収するメリットには、以下のようなことが挙げられます。
新規事業への参入、既存事業とのシナジー効果を得られる
ベンチャー企業を買収するメリットとして、新たな市場でのブランド力を獲得できることが挙げられます。一からブランドを作り上げると多額の費用や時間、労力がかかるうえに、新たな市場では参入に失敗するリスクもあります。既に一定分野で結果を出しているベンチャー企業を買収することで、時間や費用、リスクを大幅に削減できます。
また、自社の事業と親和性の高いベンチャー企業を買収することで、両社のノウハウや技術の融合によって新しい商品が生まれる、売上がアップするなどのシナジー効果が望めることもメリットです。
新規分野などの人材を確保できる
ベンチャー企業を買収するメリットとして、新規分野に優れた人材を確保できることが挙げられます。自社で新規分野の人材の採用や育成をすると、費用がかかる他、多くの時間や労力も必要になります。M&Aによって、ベンチャー企業ならではの即戦力として活躍できる人材を確保することで、スピーディーな事業成長が可能です。
今後大きく成長する可能性のある企業の経営に関与できる
ベンチャー企業への出資は、買手にとって今後大きく成長する可能性のある企業の経営に関与できるチャンスといえます。資本業務提携によって、お互いのノウハウや技術も共有できる他、ベンチャー企業の成長次第では、株主として大きな利益を得ることも可能です。
個人投資家なら税制上の優遇を受けられる
個人投資家がベンチャー企業を買収した場合、エンジェル税制という税制上の優遇措置を受けることができます。エンジェル税制には2種類あり、ベンチャー企業への投資額から2,000円を引いた金額をその年の総所得金額から控除できる「優遇措置A」、ベンチャー企業への投資全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる「優遇措置B」があります。詳しくは中小企業庁のWebサイト「エンジェル税制の仕組み 」をご確認ください。
ベンチャー企業の買収方法
企業や個人が、広義の意味でベンチャー企業を買収する方法としては、ベンチャー企業への出資と株式譲渡によるM&Aがあります。それぞれの詳細は以下のとおりです。
ベンチャー企業への出資で資本業務提携する
ベンチャー企業の買収には、ベンチャー企業に一部出資することで資本業務提携する方法があります。資本業務提携によって株式を保有するため、将来的にベンチャー企業が成長したときに大きなリターンを得ることができます。ただし、一般的にベンチャー企業主導で投資タイミングごとに出資者募集が行われるため、常に出資のチャンスがあるわけではありません。
出資は、ベンチャー企業の出資者募集のタイミングに応じて直接交渉する他、ベンチャーキャピタルや投資型クラウドファンディング経由でも可能です。
株式譲渡によるM&A
株式譲渡によるM&Aは、ベンチャー企業そのものを買収する方法になります。売手から見ればM&Aによるイグジットであり、創業者やベンチャー企業の株式を保有するファンドが、株式譲渡によって投資資金を回収することを指します。
株式譲渡によるM&Aもベンチャー企業が買手を募集する形をとることが一般的です。株式譲渡によるM&Aを行う場合、将来性に期待できるベンチャー企業は多くありますが、創業者が成長の限界を感じて事業を手放そうとしているケースもあるので注意が必要です。
ベンチャー企業を買収する際の注意点
ベンチャー企業は、時代のニーズに敏感で収益性が高く、属人的な事業運営が行われていることが多くなっています。属人的だからこそ早いスピードで、創造力を発揮できる点もベンチャー企業の強みといえます。しかし、買収によって経営陣が変わると、これまでの強みが生かせないということも起こりかねません。そうならないためにも、ベンチャー企業を買収する際は、特に以下の3点に注意が必要です。
ベンチャー企業の価値算定
ベンチャー企業の価値は、帳簿上の資産の他、事業の将来性や企業が持つノウハウ、人材、魅力的な商品・サービス利用者数などを見越したうえで決まります。いくら事業計画が立派でも、実際は絵に描いた餅だったということがないよう、ベンチャー企業の現状と事業内容を調査して、買収価額などの価値算定が妥当であるかを判断することは非常に重要です。
買収のタイミング
ベンチャー企業の買収は、ベンチャー企業が主導でタイミングを決めることが一般的です。M&Aを希望するベンチャー企業の中には、今後の成長がまだ見込める時期だけでなく、IPOを目指していたものの行き詰まって、創業者利益を確保できる時期に売却したいと考えることもあります。その場合でも、売手と買手の双方がメリットを享受できればいいですが、ベンチャー企業が主導の場合は、買収のタイミングを見極めることも大切です。
キーマンとなる人材の流出
ベンチャー企業を買収後、キーマンとなる人材を引き続き雇用できるかも注意が必要です。創業社長がキーマンとなる人材を連れて退職してしまい、別会社で似たような事業を始めてしまうケースがあります。対策としては、売買契約で競業を禁止する、あえて一部の株式を創業者に残しておくといった方法がありますが、まずはキーマンとなる人材の退職を防ぐことが必要です。
また、経営陣や経営手法が変わることでキーマンとなる人材のモチベーションが下がり、退職してしまう場合があります。事前に雇用条件を話しておく他、ある程度の株式を渡して発言権を保証したりすることも有効です。
ベンチャー企業のM&Aの事例
ベンチャー企業では、保有株式の現金化による投資回収や事業成長のスピードアップを理由にM&Aを行うことがありますが、ここでは実際に行われたM&Aの事例2つをご紹介します。
1つは、葬儀紹介サービスや葬儀場のフランチャイズ展開、EC事業などを行っているベンチャー企業が、関西・北陸地方などに複数の屋号で葬儀場を展開していたベンチャー企業を買収したケースです。売手は各地域の小規模葬儀会社をM&Aで買収し、サービスを一元化して事業拡大を行っていましたが、コロナ禍の影響により、早い段階で売却を決断。葬儀事業は地域密着型のビジネスという特徴があるため、既存屋号の知名度や信頼、ノウハウをそのまま獲得したいという買手の狙いとマッチし、M&Aが成立しました。
また、植物性食品に特化したポータルサイトやECサイトを運営するベンチャー企業を食品や化粧品の製造販売、バイオ燃料の製造開発などを行っているバイオテクノロジー企業が買収したケースもあります。
両社の目指す方向性が一致していること、買手のブランド力や資金力、売手のユーザー基盤や事業プラットフォーム、情報発信力を組み合わせることで、大きなシナジー効果が生まれるとの判断からM&Aが成立しました。M&A後も売手の代表は変わらず、グループの一員として事業を続けています。
このように、ベンチャー企業では事業撤退時期の見極め、事業成長の可能性を判断したうえで、売手の課題と買手のニーズがマッチすれば、買収しやくなります。
M&A案件を探す方法
M&Aでは、買手のニーズとマッチした売手を探すことや、交渉力に加えて財務、税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となります。すべての手続きを自力で進めるのは困難なため、M&Aを成功させるには、専門家の力を借りることも大切です。中小企業の案件を探すなら、M&Aのマッチングサービスの活用がおすすめです。費用も比較的リーズナブルです。また、小規模案件を中心に掲載していますので、これから事業を始めたい個人の方や、これから事業を拡大したい方、事業の多角化を目指したい方にもぴったりです。
まずは、専門家に相談してみよう
ベンチャー企業のM&Aは、今後大きく成長する可能性のある企業に関与できる他、ユニークなサービスやノウハウ、専門分野の人材が確保でき、自社の既存商品やサービスとのシナジー効果が期待できるなど、さまざまなメリットがあります。
まずは「M&A・事業承継相談窓口 by BATONZ」で相談してみましょう。