貸倒損失とは?3つの要件や貸倒引当金との違い、仕訳方法を解説
更新
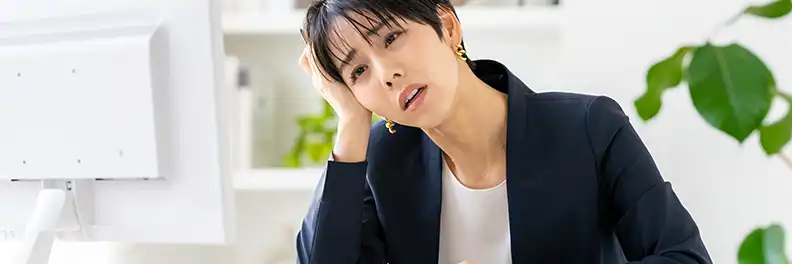
事業を営んでいると、取引先の倒産や債務超過によって、売掛金などの債権が回収不能となる「貸倒れ」が発生することがあります。このような場合に生じた損失を計上する勘定科目が「貸倒損失」です。貸倒損失は、損金として計上できるため、適切に処理すれば法人税などの税負担を軽減できます。ただし、貸倒損失は、対象となる債権や計上のタイミング、損金算入が認められる要件などが定められています。そのため、万一、貸倒れが発生した場合に備えて、貸倒損失の取り扱いルールを正確に把握しておきましょう。
本記事では、貸倒損失として処理できる3つの要件や貸倒損失と混同されやすい貸倒引当金との違いなどを解説する他、貸倒損失の仕訳方法についても紹介します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒損失とは、取引先に対する債権が回収できなくなった際に計上するもの
ビジネスにおいて、貸したお金が返ってこなかったり、商品などの売上代金が支払われなかったりすることを、貸倒れといいます。貸倒損失は、債権が予期せず回収不能となり、貸倒れが発生した際に用いられる勘定科目を差します。取引先の倒産や債務超過などによって、売掛金や貸付金といった金銭債権が回収不能になった場合は、その損失額を貸倒損失として会計処理しなければなりません。なお、貸倒れによる損失自体を貸倒損失と呼ぶこともあります。
貸倒損失は、損益計算書上で費用として計上されることで、企業の当期純利益に影響を与えるものです。これは、財務諸表全体の中でも損益計算書に直接関わる処理であり、結果として貸借対照表にも影響が及びます。具体的には、売掛金など営業上の取引で生じた貸倒れは「販売費及び一般管理費」、貸付金などの営業外の取引で生じた貸倒れは「営業外費用」、臨時的かつ金額が大きい場合は「特別損失」に分類されます。
回収不能になった債権をそのまま帳簿に残しておくと、実際には回収見込みのない資産が計上されたままとなり、資産の金額が実態よりも多く見えるため、企業の財務状況を正確に把握できません。その結果、外部の投資家や金融機関などの利害関係者に対して、実態よりも財務状況が良好に見える誤った情報を与えてしまい、企業評価・信用に悪影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
貸倒損失を計上するのは、このような悪影響を防ぐためです。また、貸倒損失は、要件を満たせば損金算入ができます。債権が回収できないと、企業にとっては大きな損失となりますが、貸倒損失として損金算入できれば法人税等の負担が軽減され、多少なりとも財務上の負担を軽くできる意味合いもあります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒損失の対象となる売上債権
貸倒損失の対象となるのは、事業の遂行上で発生する売掛金、貸付金、前渡金、その他これらに準ずる債権です。例えば、受取手形や未収入金、事業取引に伴い差し入れた保証金・預け金、従業員に対する貸付金なども、貸倒損失の対象に含まれます。
貸倒損失の要因としては、取引先の倒産、債務超過、経営悪化などがあげられます。ただし、貸倒損失には税務上厳格な規定があり、企業側の都合で自由に計上できるわけではありません。貸倒損失を計上するには、後述する一定の要件を満たす必要がある他、計上できるタイミングも定められているため注意しましょう。
売上債権については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒損失として処理できる3つの要件
貸倒れが発生したときに貸倒損失として処理する場合は、債務者の資産状況などを精査したうえで、所定の要件を満たすことが求められます。具体的には、「法律上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」の3つのいずれかに該当しなければ、貸倒損失として損金算入は認められません。
貸倒損失の3つの要件について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
法律上の貸倒れ
法律上の貸倒れとは、法的に金銭債権が消滅した場合を指します。具体的には、以下の理由に基づき切り捨てられた金額が、法律上の貸倒れに該当します。
法律上の貸倒れに該当するケース
-
1.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
-
2.法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
-
3.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
法律上の貸倒れが発生した場合は、その事実があった事業年度に貸倒損失を計上します。なお、貸倒れが生じた事業年度以外では、損金に算入できないため注意しましょう。
事実上の貸倒れ
事実上の貸倒れとは、債務者の資産状況や支払能力などからみて、金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合を指します。事実上の貸倒れが発生した場合、その事業年度において貸倒損失として損金に算入することが可能です。
なお、事実上の貸倒れとして認められるのは、債権の全額が回収不能な場合に限られます。一部の貸倒損失計上は認められないため、注意しましょう。また、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒損失の計上はできません。
形式上の貸倒れ
形式上の貸倒れとは、取引停止から一定期間経過しても弁済がない場合を指します。具体的には、以下の事実が発生した場合に、貸倒損失の計上が認められます。なお、形式上の貸倒れの対象となるのは、売掛債権のみで、貸付金などは形式上の貸倒れには含まれません。
形式上の貸倒れに該当するケース
-
1.継続取引のあった債務者について、資産状況や支払能力が悪化し、その債務者との取引(最終取引日や最終入金日などのうち最も遅い時点)を停止してから1年以上経過した場合(継続的な取引が前提となるため、例えば不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権は対象外となります)
-
2.同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合には、形式上の貸倒れとされ、その売掛債権の額から備忘価額を差し引いた残額を、貸倒損失として損金処理ができます。備忘価額とは、貸倒れなどで実質的には価値がなくなってしまった資産に対して、帳簿上の記録を残すために付ける金額で、1円などごく少額に設定されることが一般的です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒損失と貸倒引当金の違い
貸倒損失と混同されやすいものに、「貸倒引当金」があります。貸倒損失と貸倒引当金の大きな違いは、「債権の回収不能が確定しているかどうか」という点にあります。
貸倒引当金とは、将来、発生が予想される貸倒れに備えて設定される勘定科目です。将来起こる可能性のある貸倒れに備えた見積額なので、損失はまだ発生しておらず、確定もしていません。貸倒引当金の主な目的は、費用収益対応の原則に従い、当期の費用と収益を対応させることです。売上とそれに対する貸倒れが、事業年度(会計期間)をまたいで起こった場合、貸倒損失を対応すべき収益に結び付けることが難しくなり、正確な損益計算を行うことができなくなります。そのため、会計処理上、あらかじめ貸倒引当金として回収不能になりそうな見込額を計算し、マイナスの資産(評価性引当金)として計上することが認められています。
その一方で、貸倒損失は、実際に発生した貸倒れの損失を費用として処理する際に用いられる勘定科目です。貸倒引当金が将来の貸倒れの可能性に備えて見積計上するのに対して、貸倒損失の計上時は、債権が回収不能となり損失が確定しています。貸倒引当金を計上したからといって、必ずしも貸倒損失が発生するとは限らず、反対に、貸倒引当金を計上していなくても、予想外の理由によって貸倒損失が発生することもあります。
貸倒引当金については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒れが発生したときの消費税の処理
貸倒れが発生したとき、課税事業者の場合は、消費税の処理に注意しましょう。売掛金など、消費税の課税対象となる取引における債権が貸倒れとなると、当初に計上された売上にかかる消費税額が、実際の状況に対して過大になります。そのため、回収不能になった分の消費税額を、貸倒れとなった課税期間の消費税額から控除することが必要です。例えば、売掛金1万1,000円(本体価格1万円+消費税1,000円)が貸倒れとなった場合、貸倒損失に対応する1,000円分の消費税を、その課税期間の消費税から控除できます。
消費税の納付額は、原則として、売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引いて求めます。売上債権に貸倒れが発生した場合は、納付税額は、売上にかかる消費税額から仕入税額および貸倒損失にかかる消費税を控除して算出することが必要です。
なお、貸倒が発生した年度において免税事業者の場合は、貸倒損失にかかる消費税を控除できません。また、免税事業者の時に発生した売上についても、その後課税事業者になったとしても貸倒損失にかかる消費税は控除できません。
また、貸付金などの不課税取引においては、貸倒れが発生しても消費税控除の対象外です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒損失の仕訳方法
ここからは、貸倒損失を計上する場合の仕訳方法を紹介します。ケース別に、具体的な貸倒損失の仕訳例を確認していきましょう。
取引先が倒産して売掛金が回収できなくなった場合の仕訳例
仕訳は、あらかじめ貸倒引当金を計上しているかどうかによって異なります。取引先が倒産して売掛金が回収不能になり、貸倒損失を計上する場合の仕訳例は、以下のとおりです。
仕訳例:前期の売掛金15万円について貸倒れが発生した。前期に貸倒引当金10万円を計上している。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 100,000円 | 売掛金 | 150,000円 |
| 貸倒損失 | 50,000円 | ||
仕訳例:前期の売掛金15万円について貸倒れが発生した。前期に貸倒引当金の計上はしていない。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 150,000円 | 売掛金 | 150,000円 |
取引先が倒産して売掛金のうち80%が切り捨てられた場合の仕訳例
取引先が倒産し、すべての債権者が同一の基準で売掛金のうち80%を切り捨てた場合は、貸倒損失となります。この場合、切り捨てられた金額を貸倒損失として処理します。
仕訳例:取引先A社に対する売掛金10万円が未回収だが、A社が倒産し、債権者集会により、売掛金の80%を切り捨てることが決定された。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 80,000円 | 売掛金 | 80,000円 |
最後の弁済から督促をしても1年以上弁済がない場合の仕訳例
取引停止後1年以上経過しても弁済がない場合は、売掛債権の額から「備忘価額」を差し引いた残額を、貸倒損失として計上します。備忘価額とは、債権の存在を帳簿上に残すために、通常1円などの極めて少額で設定される金額のことです。完全に債権を削除してしまうと、過去に債権があったことや貸倒損失した事実が帳簿上から確認できなくなってしまうため、法的な対応や将来的な回収の可能性に備えて、形式的に債権の記録を残しておく目的で使用されます。ちなみに、事実上の貸倒れとなったときには、借方の貸倒損失を1円、貸方の売掛金を1円とし、備忘価額分を消す処理を行うことが必要です。
仕訳例:取引先A社に対する売掛金20万円について、連絡がつかないまま取引停止後1年以上が経過した。そのため、備忘価額を1円に設定して貸倒損失を計上した。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 199,999円 | 売掛金 | 199,999円 |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒損失を防ぐための方法
売掛金や貸付金などが回収できなくなると、企業にとっては大きな損失となり、資金繰りにも悪影響を及ぼす可能性があります。こうした貸倒れを未然に防ぐには、どのような対策が有効なのでしょうか。以下に、効果的な防止策を紹介します。
回収期日の管理を徹底する
回収期日の管理を徹底することは、貸倒損失を防ぐための基本的な方法です。
例えば、売掛金であれば、請求書を発行した後、期日ごとに入金状況をしっかり確認します。定期的な確認により、入金遅延や誤りも早期に発見でき、迅速な対応が可能になります。
取引先の情報収集を徹底する
貸倒損失を防ぐには、取引先の信用状況を把握するため、情報収集は欠かせません。
特に、新たに取引を開始する前や高額取引・取引条件の変更時には、情報収集を徹底しましょう。例えば、取引先が上場企業であれば、公開されている財務諸表を通じて財務状況を把握できます。中小企業など、財務諸表の確認が難しい場合は、信用調査会社の活用も有効な手段です。
支払が滞ったときは早めに対応する
取引先からの支払が滞ったときに早めに対応することも、貸倒損失を防ぐ方法の1つです。
支払期日を過ぎた時点で迅速に督促を行い、滞納が長期化しないようにしましょう。支払遅延が繰り返される場合は、取引自体の見直しも検討する必要があります。
現場と連携する
貸倒損失を防ぐには、経理・管理部門だけでなく、現場部門との連携が不可欠です。
例えば、営業部門など、取引先と直接関わる現場の情報は、貸倒れリスクをいち早く察知する重要な手段となります。現場で得た取引先の情報を経理・管理部門と共有することで、リスクを早期に発見し、タイムリーな対応策を講じることができるでしょう。
内容証明郵便を送付する
内容証明郵便を送付することも、貸倒損失を防ぐ方法としてあげられます。
内容証明郵便は、送付日時・送付者・送付先・内容を公的に証明できる制度です。取引先からの支払滞納が続く場合は、請求書や督促状などを内容証明郵便で送付することをおすすめします。送付日時や内容などを正式な記録として残すことで、いざというときに証拠としての効力を発揮します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
貸倒れのリスクに備えて、貸倒損失について正しく理解しておこう
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などが回収不能となった際に計上される損失の勘定科目です。一定の要件を満たせば、貸倒損失は損金算入ができます。貸倒れによる損失の影響を軽減するには、貸倒損失の計上ルールを正しく理解することが大切です。
併せて、貸倒れを未然に防ぐ対策も欠かせません。金銭債権の管理には、会計ソフトの活用が有効です。例えば、「弥生会計 Next」を使えば、売掛金の仕訳がスムーズに行えるうえ、銀行口座を連携させれば入金状況もすぐにチェックできます。会計ソフトを活用して日々の取引を正確に管理し、貸倒れのリスクに備えましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。








