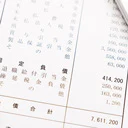経営分析とは?基本指標と実務への活かし方をわかりやすく解説
更新

経営分析は、さまざまな数値指標を基に企業の経営状態を把握し、改善の手がかりを導き出す手法です。一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な考え方を押さえれば実務で活かせます。例えば、資金繰りの改善や利益率の見直し、設備投資の判断、銀行融資の審査などにも役立てられるでしょう。
本記事では、経営分析の定義や会計担当者が経営分析を理解する意義、主な分析指標をわかりやすく解説します。財務との関係や活用する際の注意点にもふれていますので、経営状態の見える化や課題の発見にお役立てください。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経営分析とは?
経営分析とは、企業の財務データや業務データを基に、経営の現状や課題を把握し、今後の意思決定に役立てるための手法です。表面的な数字からは読み解けない経営上のリスクや強み・弱みを可視化し、根拠ある判断材料として活用されます。
近年では、経営分析の対象は財務情報にとどまらず、従業員の離職率や顧客満足度といった非財務データも重視されるようになってきました。このように、経営分析では「数字の奥にある背景」まで読み取る多角的な視点が求められています。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計担当者が経営分析を理解する意義
経営分析は、経営戦略に関わる専門的な手法という印象を持たれがちですが、経営分析を理解することは、実は会計担当者にとっても大きな価値があります。
そもそも会計担当者には、売上や利益、資産や負債といった財務データを記録・処理するだけでなく、それらの数字が何を示しているのかを読み解く力が求められています。特に中小企業では、社長や経営陣との距離が近いため、会計担当者が経営判断に必要な情報を取りまとめたり、数字から見える問題点を指摘したりする場面も少なくありません。自社の業績変化にいち早く気づき、経営層に対して有益な提案を行うためにも、会計担当者が経営分析の視点を持っておく必要があります。
経営分析は、経営層だけが行うものではありません。現場に近い立場だからこそ、会計担当者としての価値を発揮できるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経営分析を行う目的
経営分析を行う最大の目的は、企業の現状を的確に把握して経営判断の質を高めることにあります。例えば、売上や利益といった数値を把握することは重要ですが、それらの数値を見るだけでは会社の実情は見えてきません。そこで、経営分析では数値同士を比較し、傾向や変化を読み解くことで、より深い理解を得られます。経営分析を行う具体的な目的としてあげられるのは、以下の4つです。
経営状態の可視化
経営分析の第一歩は、企業の経営状態を客観的な数値で「見える化」することです。売上・利益・費用・資産といった多様な数値情報を整理し、全体像や収益構造などの経営全体の仕組みが明らかになれば、「今、会社がどのような状態にあるのか」を誰が見てもわかるようになるでしょう。
例えば、売上の内訳を部門別に分類したり、固定費と変動費のバランスを整理したりすることで、現状のビジネスモデルや収益構造の特徴が明確になります。このように、数字の関係性を俯瞰して把握することで、勘や経験に依存しない情報共有や判断が可能となり、社内での意思決定の土台が整うのです。
経営課題の発見
経営分析によって、可視化されたデータの中から異常値や変化の兆しを読み取り、具体的な経営課題を早期に見つけることができます。例えば、利益率の急落や在庫の滞留、売上債権の増加といった現象は、数字を通してこそ明確に把握することが可能です。こうした問題は、現場の肌感覚だけでは気づきにくく、対応が遅れることも少なくありません。課題を数値で特定できれば、経営判断の精度が上がり、的確な解決策をスピーディーに打ち出すことができます。
他社や過去との比較
競合他社や自社の過去の実績と比較できることも、経営分析に取り組む目的の1つです。業界平均や同業他社と自社の財務指標を比較することにより、自社の強み・弱みをより客観的に把握できます。
また、自社内の過去数年間の業績推移を分析すれば、改善傾向にあるのか、悪化しているのかを具体的に見極められるでしょう。こうした比較を通じて、これまで気づかなかった自社の強みや弱みを発見できることも、経営分析によってもたらされる効果といえます。
ステークホルダーへの説明資料
経営分析で得られたデータは、融資先や出資者などのステークホルダーに対する説明資料にも活用できます。融資をはじめとする資金調達の場面では、経営の健全性を示す信頼できるデータを求められるケースは少なくありません。自社の財務状況や今後の見通しをわかりやすく整理し、客観的な判断材料として提示することで、外部からの信頼を得ることにもつながります。経営分析は、こうしたステークホルダーへの説明資料を作成するうえでも重要なプロセスであるといえるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
財務分析とは?経営分析との違い
財務分析とは、企業の財務諸表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書など)に基づいて、収益性・安全性・効率性といった観点から経営状態を数値で評価する分析手法です。企業の健全性や収益構造を客観的に把握することを目的としています。
それに対して、経営分析は、こうした財務分析の結果を踏まえて、原因や背景を深掘りし、今後の改善や戦略立案につなげるプロセスです。例えば「売上は好調でも利益が伸びない」といった状況があった場合、財務分析でその事実や数値面から要因を見いだすことはできますが、業務フローや市場環境、人的資源などの非財務的な要素まで含めて総合的に検討するのは経営分析の役割です。
つまり、財務分析が「経営の現状を知る」ための分析であるのに対し、経営分析は「現状を基にどう動くか」を導くための手法といえるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経営分析の主な7つの指標
経営分析を行ううえで、指標の選定は非常に重要です。見るべき数字を見誤れば、適切な判断はできません。ここでは、経営状態を多角的に把握するために押さえておきたい主な7つの指標について見ていきましょう。
収益性
収益性とは、企業がどれだけ効率よく利益を生み出せているのかを示す指標です。売上や資産、自己資本といったリソースを用いて、どの程度の利益を出せているかを評価します。
具体的に使われる主な指標は、以下です。
| 指標 | 概要 | 計算式 |
|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 売上高に対する営業利益の割合 | 営業利益÷売上高×100 |
| ROA(総資産利益率) | 企業の資産活用効率を示す指標 | 当期純利益÷総資産×100 |
| ROE(自己資本利益率) | 自己資本に対する純利益の割合 | 当期純利益÷自己資本×100 |
収益性が高い企業は、より少ないコストで利益を確保できていると判断できます。本業で稼ぐ力や資産・自己資本の活用効率を評価するうえで役立つのが収益性の分析です。
安全性
安全性とは、企業の財務基盤の健全性や返済能力を示す指標です。倒産リスクや借入依存の度合いを評価するために用いられます。特に企業が金融機関から融資を受ける際、将来的にきちんと返済できるかを判断する材料として、安全性の指標が重視されるケースが少なくありません。
具体的な指標として用いられるのは、以下のような指標です。
| 指標 | 概要 | 計算式 |
|---|---|---|
| 流動比率 | 流動資産と流動負債のバランスを示す指標 | 流動資産÷流動負債 |
| 自己資本比率 | 総資本に占める自己資本の割合を示す指標 | 自己資本÷総資本×100 |
- ※総資本とは(負債+純資産)のことであり、基本的には総資産に一致します。
これらの指標を活用することで、企業が財務的にどれだけ安定しているか、また外部からの資金にどれほど依存しているかを把握することができます。
流動比率についてはこちらで解説していますので、参考にしてください。
生産性
生産性とは、企業が人的資源や物的資源をどれだけ効率よく活用できているかを示す指標です。限られた資源から最大限の成果を上げることが、競争力のある経営には欠かせません。生産性を軸に経営分析を行うことにより、コスト管理の適正化や組織改善といった施策に役立てることが主な目的です。
代表的な生産性指標には、以下のようなものがあります。
| 指標 | 概要 | 計算式 |
|---|---|---|
| 労働生産性 | 人材活用の効率性を評価する指標 | 付加価値額÷従業員数 |
| 資本生産性 | 資本の運用効率を評価する指標 | 付加価値額÷総資本 |
- ※「付加価値額」は、営業利益+人件費+減価償却費などで算出されることが一般的です。
生産性を軸とした経営分析を行うことで、無駄なコストの削減や業務プロセスの改善など、より具体的な経営施策につなげやすくなります。
効率性
効率性とは、企業が保有する資産をどれだけ効率的に事業活動へ活用できているかを示す指標です。在庫や売掛金、固定資産などが売上につながっているかを数値で可視化できます。効率性が高い企業は、資産を無駄なく運用できているといえるでしょう。
以下が代表的な指標としてあげられます。
| 指標 | 概要 | 計算式 |
|---|---|---|
| 総資本回転率 | 資産全体の活用効率を評価する指標 | 売上高÷総資本 |
| 固定資産回転率 | 固定資産を活用してどれだけ売上を生み出しているかを示す指標 | 売上高÷固定資産 |
| 棚卸資産回転率 | 棚卸資産がどれだけ効率的に売上に結びついているかを示す指標 | 売上高÷棚卸資産(売上高の代わりに売上原価を使う場合もある) |
効率性の低下は、過剰在庫や設備投資の過多といった問題の兆候でもあります。定期的に指標を確認し、資産活用の見直しに役立てることが大切です。
成長性
成長性とは、企業がどの程度事業を拡大し、利益を伸ばしているかを示す指標です。売上や利益の増加率を確認することで、事業の拡大性を把握できます。
一般的に以下のような指標が用いられます。
| 指標 | 概要 | 計算式 |
|---|---|---|
| 売上高増加率 | 前期に対して売上高がどれだけ伸びたかを示す指標 | (当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100 |
| 経常利益増加率 | 前期に対して経常利益がどれだけ伸びたかを示す指標 | (当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益×100 |
売上や利益の増加が一時的な要因によるものか、継続的な成長につながっているのかを見極めることが、経営判断において重要です。
損益分岐点
損益分岐点とは、企業が赤字を脱し、利益を得られる最低限の売上水準のことです。商品やサービスを提供するには、さまざまな固定費や変動費などさまざまなコストが発生します。売上が伸びていても、これらのコストがかかりすぎていれば、利益は出ません。
損益分岐点を把握することで、どれくらいの売上を確保すれば黒字になるのかが明確になります。これは、収支構造を見直すうえでも役立つ指標です。
損益分岐点を算出するための計算式は、以下のとおりです。
損益分岐点=固定費÷{1−(変動費÷売上高)}
例えば、この計算結果から「変動費の割合が高すぎる」といった課題を発見できれば、コスト構造の改善に取り組むきっかけとなり、利益率の向上につなげることができます。
債務償還能力
債務償還能力とは、企業が借入金を返済できる能力のことです。金融機関が融資の可否や限度額を判断する際にも重視されるポイントで、財務健全性を評価するうえで重要な指標の1つです。代表的な指標として「債務償還年数」があり、これは借入金を何年で返済できるかを示します。
債務償還年数は、次の計算式で求められます。
債務償還年数=借入金÷(経常利益+減価償却費−法人税等)
計算式に含まれる「経常利益+減価償却費」は、企業の営業活動によって実際に得られるキャッシュ・フローの一例です。このキャッシュ・フローを基に、借入金を返済するのに必要な年数を見積もることで、企業の返済余力を客観的に判断します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経営分析に使われる3つの財務諸表
経営分析を行ううえで欠かせないのが、企業の財務状況を数値で示す財務諸表です。このうち「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュ・フロー計算書」は財務三表と呼ばれ、経営の健全性や収益構造を把握するための基本資料とされています。
これら財務三表は、単体ではなく相互に関連付けて分析することが重要です。それぞれの役割を理解しておくことで、より実態に近い経営分析が可能になります。
貸借対照表(BS:Balance Sheet)
貸借対照表は、ある時点での企業の資産・負債・純資産の状況を一覧にまとめた表です。左側に資産、右側に負債と純資産が記載されており両者の合計金額が必ず一致することからバランスシートとも呼ばれています。
記載されている項目
- 資産:現金・預金、売掛金、固定資産など、企業が保有する財産など
- 負債:買掛金、借入金、未払費用など、支払義務や返済義務があるもの
- 純資産:資本金、利益剰余金、自己株式など、返済義務のない企業の自己資本
貸借対照表からわかること
- 財務の安全性
- 支払能力
- 資金構成
損益計算書(PL:Profit and Loss Statement)
損益計算書は、会計期間における企業の売上・費用・利益の状況を明らかにする財務諸表です。企業がどれだけ収益を上げ、どれだけの費用をかけて、最終的にどの程度の利益を得たのかを把握できます。
記載されている主な項目
- 売上総利益(粗利):売上高−売上原価
- 営業利益:売上総利益−(販売費+一般管理費)
- 経常利益:営業利益+営業外収益−営業外費用
- 税引前当期純利益:経常利益+特別利益−特別損失
- 当期純利益:税引前当期純利益−法人税等
損益計算書からわかること
- 収益力
- 利益の内訳
キャッシュ・フロー計算書(CF:Cash Flow Statement)
キャッシュ・フロー計算書とは、一定期間における資金の出入りを示す計算書です。ここでいうキャッシュには、現金のほか、すぐに使える預貯金などの現金同等物も含まれます。
企業間の取引では、売上が立ってもすぐに現金が入ってこない掛取引が一般的です。そのため、実際に手元にある現金の状況を把握するには、損益計算書だけでなく、キャッシュ・フロー計算書を確認する必要があります。
記載されている項目
- 営業活動によるキャッシュ・フロー:商品の販売やサービス提供など本業に伴う資金の増減
- 投資活動によるキャッシュ・フロー:設備投資や有価証券の売買などによる資金の増減
- 財務活動によるキャッシュ・フロー:借入や返済、配当金の支払いなどによる資金の増減
キャッシュ・フロー計算書からわかること
- 現金の出入りとその内訳
- 利益と手元資金のズレ
- 資金繰りの状況や健全性
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経営分析の実施手順
経営分析は、ただ数値を集めて比較するだけでは効果を発揮しません。目的を明確にし、分析に必要な情報を正しく収集・整理することで、はじめて実務に活かせる示唆が得られます。ここでは、経営分析を進める際の基本的な手順を紹介します。効果的に経営分析を行うためにも、以下の手順に沿って進めることが重要です。
1. 分析の目的を決める
経営分析は目的によって手法や指標が異なります。資金調達のための財務健全性評価なのか、事業戦略見直しのための収益性評価なのかなど、まずは分析の目的を明確に設定しましょう。
2. 必要なデータを集める
目的に応じて、貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書といった財務諸表を中心に、売上実績や予算データ、各部門別の業績の数値、場合によっては業界平均なども収集します。
3. 指標を選定し、分析を行う
収益性や安全性、生産性、成長性などの観点から適切な指標を選び、数値を算出・比較します。必要に応じて次のような比較も加えると、より客観的な評価が可能になります。
分析に用いる比較方法
- 過去との比較
- 業界平均や競合他社との比較
- 自社における目標値との比較
このように複合的な観点から分析を進めることによって、経営状態の良い点や課題点が浮かび上がってきます。
4. 分析結果から課題と改善策を導く
経営分析によって明らかになった課題や傾向を基に、次に取るべきアクションを検討します。分析結果は、今後の意思決定や具体的な改善策の立案に活用される重要な材料です。
また、経営状態は常に変化するため、実施した改善策がどの程度効果をもたらしたのかを継続的に観察し、必要に応じて施策を見直すことも欠かせません。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経営分析は会計の専門性をさらに活かす一歩になる
経営分析は、日々の会計で扱っている数字を経営視点で読み解き、意思決定に役立てるための取り組みです。会計担当者は、帳簿の正確な記録や資金管理など、企業運営を支える重要な役割を担っています。そこに分析の視点を加えることで、経営の課題や改善のヒントが見えてくるでしょう。
しかし、経営分析には、多くの数値を集計・整理する工程が発生するため、一定の手間がかかるのも事実です。こうした作業を正確かつ効率よく進めるためには、会計ソフトの活用が効果的です。
普段の会計業務に経営分析を取り入れることで、会計担当者としての視野が広がり、企業への貢献度も高まります。会計担当者としての付加価値をさらに高めるためにも、会計ソフトの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。