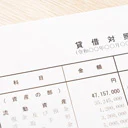株主資本比率とは?高いメリットや計算方法、改善方法を解説
更新

企業の財務状況を評価する指標の1つが、株主資本比率です。株主資本比率とは、総資本に占める株主資本の割合のことを指します。一般的には、株主資本比率が高いほど、企業の財務状況は安定しているといわれます。ただし、株主資本比率は、単に数値を算出するだけでなく、その結果を適切に分析し経営に活かすことが重要です。
本記事では、株主資本比率が高いことによるメリットや計算方法、目安、改善する方法について解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率は、総資本に占める株主資本の割合を示す指標
株主資本比率とは、企業の総資本(自己資本と負債を合わせた額)に占める株主資本の割合を示す財務指標です。
株主資本は、株主からの出資(資本金や資本剰余金)や企業の利益の蓄積(利益剰余金)などから構成される、返済義務のない自己資本を指します。株主資本比率は、企業の財務健全性や安定性を判断するために活用される指標であり、投資家・金融機関といった外部のステークホルダーだけでなく、企業自身にとっても重要な判断材料となるものです。株主資本比率が高い企業は、借入金などの外部資金に頼らず自立的な経営を行っていると評価されやすく、財務の安定性が高いと見なされます。
その一方で、株主資本比率が低い場合は、財務的に不安定になりやすく、経営上のリスクが高まる可能性があります。このように、自社の財務健全性を客観的に判断するうえで、株主資本比率は重要な指標となるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率と自己資本比率の違い
株主資本比率と自己資本比率は、いずれも企業の財務健全性を測るために使われる代表的な指標で、しばしば同じような意味で扱われることもあります。しかし、両者は厳密には異なる概念に基づいており、対象とする資本の範囲に違いがあります。
自己資本比率は、総資本に占める「自己資本」の割合を示す指標です。それに対して、株主資本比率は、自己資本の中でも「株主に帰属する部分」である株主資本に着目した指標を指します。いずれも返済義務のない資本ですが、構成要素に若干の違いがあるため注意しましょう。
株主資本は、株主が出資した資本(元手)と、事業で得た利益の蓄積を指し、具体的には「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」「自己株式」の4つで構成されます。株主資本の金額は、資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計から、自己株式がある場合はそれを差し引いて求めます。計算式にすると、以下のとおりです。
株主資本の計算式
- 株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式
その一方で、自己資本は、株主資本に「評価・換算差額等」や「新株予約権」を加えたものを指します。つまり、自己資本のうち株主に帰属する部分が、株主資本に該当します。
株主資本と自己資本の勘定科目と概要
| 区分 | 勘定科目 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 自己資本 | 株主資本 | 資本金 | 株主からの出資によって得られる事業活動の元手資金 |
| 資本剰余金 | 株主からの出資金のうち、資本金に充当しなかった資金 | ||
| 利益剰余金 | 事業活動で得られた利益の蓄積 | ||
| 自己株式 | 会社が保有する自社株 | ||
| 評価・換算差額等 | 売買目的以外で保有する有価証券や土地などの購入価格と、現在の時価との差額(評価損益) | ||
| 新株予約権 | 事前に決定された価格や条件に基づいて、新株の交付を受けることができる権利を付与したもの | ||
ただし、評価・換算差額等は、有価証券や土地などの時価変動によって発生します。また、新株予約権が発生するのは主にベンチャー企業や上場企業のため、非上場の中小企業では、株主資本と自己資本がほぼ同一と見なされるのが一般的です。したがって、株主資本比率と自己資本比率も中小企業の財務分析においてはほぼ同義と考えて差し支えありません。
資本金についてはこちらで解説していますので、参考にしてください。
利益剰余金についてはこちらで解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率が示す企業の健全性
株主資本比率は、企業の財務健全性や安定性を判断する重要な指標です。この比率は、総資本に対して株主資本がどれほど占めているかを示すものであり、特に企業のリスク耐性を数値として把握できる点が評価されています。株主資本比率が高い企業は、返済義務のある借入金などに依存せず、株主からの出資や利益の蓄積によって安定した財務基盤を築いているとみなされます。景気後退や自然災害、突発的な業績悪化など、外部環境の変動にも柔軟に対応しやすく、資金繰りの悪化リスクが比較的小さいといえるでしょう。
その一方で、株主資本比率が低い企業は、自己資本が少なく他人資本の影響を受けやすい状態にあります。また、借入金に大きく依存した財務体質となっているため、金利の上昇や資金調達の制限などが、業績に直接的な影響を及ぼす可能性もあります。
株主資本比率の高低による企業の状態と特徴
| 株主資本比率 | 企業の状態 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 高い | 財務基盤が安定している |
|
| 低い | 財務的に不安定になりやすい |
|
株主資本比率を継続的にモニタリングすると、企業の財務体質の変化や改善の兆しを早期に把握でき、経営判断の質を高めることが可能です。自社の株主資本比率を定期的に確認し、資本構成を見直すことは、持続可能で健全な財務戦略を立てるうえでの手掛かりとなります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率が高いことによるメリット
株主資本比率が高いことには、財務面でさまざまなメリットがあります。
株主資本比率が高いことによるメリット
- 利息負担を抑えられる
- 資金繰りに余裕が生まれやすい
- 不測の事態への耐性が高い
- 対外的な信頼を得やすい
- 資金調達や事業拡大がスムーズに進むv
株主資本比率が高い企業は、外部からお金を借りるのではなく、自己資本によって資産を多く賄っています。その結果、借入金に伴う利息負担を抑えられ、資金繰りにも余裕が生まれやすくなります。また、景気後退や業績悪化といった不測の事態にも、財務基盤が堅固であれば落ち着いて対処でき、深刻な混乱が生じにくくなるでしょう。
さらに、株主資本比率が高い企業は、外部からも財務運営の堅実さが評価され、金融機関や投資家、取引先からの信頼を得やすくなります。こうした信頼関係は、将来的な資金調達や新規事業の展開を進めるうえでもプラスに働き、企業の持続的な成長を後押しする要因となります。
このように、企業の信頼性、安定性、成長性のすべてに良い影響を与える点が、株主資本比率が高いことによるメリットです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率の計算方法
株主資本比率を使って企業の財務健全性を評価するには、その計算方法を正確に理解する必要があります。ここからは、株主資本比率の計算方法について解説します。
株主資本比率の計算式
株主資本比率は、以下の計算式で求められます。
株主資本比率の計算式
- 株主資本比率(%)=株主資本÷総資本×100
株主資本は、「資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式」の式により算出できます。また、総資本とは、企業が保有するすべての資本のことで、企業の資産がどのように調達されたかを示すものです。総資本は、自己資本(純資産)と負債の合計で構成され、総資産の金額と一致します。
必要な財務データの収集
株主資本比率の計算に必要な「株主資本」や「総資本」は、財務諸表(決算書)の1つである貸借対照表で確認できます。
株主資本は、貸借対照表の「純資産の部」に記載されており、中小企業では、純資産の部の合計額が株主資本に該当するのが一般的です。また、総資本は、貸借対照表の右側の「負債の部」と純資産の部を合計することで算出できます。なお、貸借対照表では「資産=負債+純資産」となり、記載される左右の金額は必ず一致するため、貸借対照表の左側に記載されている「資産の部」の合計額を見れば、総資本の額がわかります。
他社の株主資本比率を確認する場合も、必要な財務データは貸借対照表から読み取ることが可能です。上場企業であれば、公式サイトのIRページから有価証券報告書や決算短信の貸借対照表を確認し、株主資本・総資本の額を算出します。非上場企業の場合は、決算公告によって開示された貸借対照表で、株主資本や総資本を確認できます。
株主資本比率を正確に算出するには、信頼性のあるデータを正確に読み解く力が必要です。企業の健全性を適切に判断するためにも、正確な情報に基づいた分析を心掛けましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率の目安
一般的には、株主資本比率が30%以上であれば、財務的に健全な水準とされています。ただし、この目安は業種や企業規模によって異なり、一律に「何%が良い」とは言い切れません。
中小企業庁「中小企業実態基本調査 令和6年確報(令和5年度決算実績)」より、中小企業の平均的な株主資本比率を計算すると、約41.13%です。しかし、これを業種別に見ると、建設業は45.86%と平均を上回る一方で、宿泊業・飲食サービス業は14.44%と大幅に下回っており、業種によって大きな差があることがわかります。
このように、業種によって適正な水準が異なり、ビジネスモデルや資金調達構造によってもばらつきがあります。したがって、「株主資本比率が高いから良い、低いから悪い」と画一的に評価するのではなく、業種別の傾向を把握したうえで比較・分析することが大切です。業種分類の理解は、投資判断や企業分析の精度を高めるうえで欠かせない視点といえるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率が低い場合のリスク
株主資本比率が低い企業は、財務面で多くのリスクを抱えやすくなります。中でも注意したいのが、以下のようなリスクです。
財務的な影響
株主資本比率が低いと、借入金依存の経営と見なされ、取引先からの信用を得にくく、資金調達や新規取引に悪影響を及ぼす可能性があります。借入がある場合、利息の支払も大きな負担となります。また、金利の上昇により利息負担が増加し、キャッシュ・フローを圧迫する可能性があるでしょう。景気悪化によって売上が減少すれば、返済負担が一層重くのしかかり、資金繰りが厳しくなるおそれがあります。さらに、借入金の返済に追われる状況では、利益を内部留保や設備投資などに回す余力が限られ、企業の成長戦略、競争力強化の妨げとなることもあります。
投資家への影響
株主資本比率は、投資家が企業の安全性を測る指標として重視されるものです。株主資本比率が低い企業は、財務の安全性が乏しいと判断され、長期投資や新規投資の対象になりにくい傾向があります。加えて、株主資本比率は単なる財務指標ではなく、経営者の財務に対する姿勢や方針が反映されます。過度な借入に頼らず、堅実な財務運営を行っているかどうかは、投資家が経営陣を評価するうえで注目されるポイントです。株主資本比率が極端に低いと、短期的な利益追求や無理な事業拡大に傾いていると受け取られ、投資家の不安を招く可能性があるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率を改善する方法
企業の財務安定性を確保し、外部からの信頼を得るためには、株主資本比率を高めることが大切です。ここでは、株主資本比率を改善する効果的な方法を2つ紹介します。
資本政策の見直し
株主資本比率を改善する方法は、資本政策の見直しです。
資本政策とは、企業がどのように資金を調達し、どのような資本構成で経営を進めていくかを定める方針や戦略を指します。資本の調達・配分・構成にかかわる資本政策は、企業の財務戦略の基盤であり、株主資本比率を改善するには方針の明確化が不可欠です。
株主資本比率を高めるには、借入金などの他人資本に過度に依存せず、株主資本を積み増すことが求められます。例えば、増資を通じて自己資本を積み増す、過度な借入を避けるなど、自社の成長段階・財務状況に応じた対策が求められます。特に、中小企業では資本政策が形式的になりやすいですが、企業価値や信用力の向上を目指すには戦略的な視点で資本構成を見直し、自己資本の比率を高めるための調達手段、資本配分の最適化を図ることが大切です。資本政策の見直しは、企業の財務健全性と将来的な成長の両方を支える出発点となるでしょう。
利益の再投資
利益の再投資も株主資本比率を改善する方法の1つです。
利益は、企業が自力で生み出す最も基本的で持続可能な資金源であり、その使い道によって将来の財務構造が大きく左右されます。事業拡大や設備投資、人材育成などに利益を再投資することで、企業の収益基盤を強化し、将来的な内部留保の増加につながります。内部留保の蓄積によって純資産が増加し、結果として株主資本比率が高まっていくでしょう。また、利益の再投資は競争力の向上にもつながり、中長期的な成長の基盤となります。
短期的に見れば、配当によって株主に利益を還元することも大切ですが、財務の安定を優先する局面では慎重な判断が求められます。利益の継続的な再投資は、財務健全性を維持するための基本戦略であり、経営者の資本に対する姿勢が問われる重要な要素です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
株主資本比率を適切に分析して財務安定性の向上を目指そう
株主資本比率は、企業の総資本に占める株主資本の割合であり、財務安定性や健全性を評価するための重要な指標です。一般的に、株主資本比率が高い企業は、安定性や健全性が高いと評価されますが、その適正水準は業種・企業規模によって異なります。自社の財務安定性を把握するには、株主資本比率を定期的に確認し、同業他社と比較することが大切です。
株主資本比率を計算するには、株主資本や総資本といった財務情報が欠かせません。これらの情報は、貸借対照表(決算書)から確認できます。貸借対照表の数値に誤りがあると、株主資本比率の計算が正確に行えないため注意しましょう。弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」は、入力した仕訳データを基に、貸借対照表などの決算書を自動で作成できます。会計ソフトを活用して決算書を正確かつ効率的に作成し、株主資本比率の分析に役立てることをおすすめします。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。