外注費とは?給与との違いや区分する基準、仕訳方法などを解説
更新
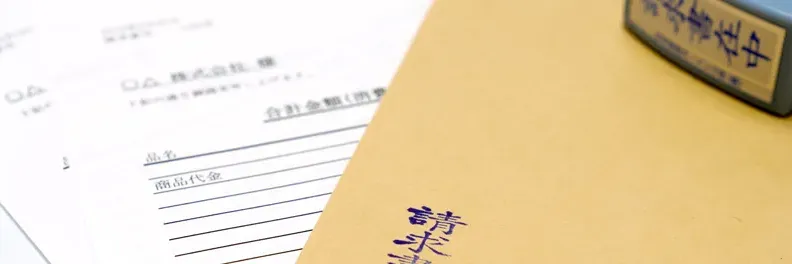
外注費とは、外部の個人や法人に業務を発注した際に発生する費用で、支払時には外注費の勘定科目を使用します。ただし、「自社の仕事を他者へ依頼した費用のすべてが外注費にあてはまる」というわけではありません。特に、個人に支払った費用については、それが外注費か給与かを正しく区分しないと、税務調査で指摘を受ける可能性があります。外注費を適切に処理するには、「外注費の定義」と「給与との違い」を正しく理解することが大切です。また、外注費の中には、支払う際に源泉徴収が必要なものもあるため注意しましょう。
本記事では、外注費の概要や給与との違い、外注費と給与を区分する基準と併せて、外注費の仕訳方法についても解説します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
外注費とは外部の個人や法人に業務を発注した際の費用のこと
外注費とは、自社の業務の一部を、外部の個人や法人に委託するときに支払う費用のことです。
事業を運営していると、社内では対応が難しい業務や外部に依頼したほうが効率的な業務が発生することがあります。そのような業務を外部に依頼した場合、対価として支払った費用は外注費の勘定科目で処理します。外注費に該当する費用の例は、以下のとおりです。
外注費に該当する費用の例
- 清掃業者にオフィスの清掃業務を委託した費用
- 個人のWebデザイナーにホームページの作成を委託した費用
- 派遣会社に派遣社員を依頼した費用
なお、外注費は給与や支払手数料、販売促進費などと混同されやすい勘定科目です。外注費とこれらの勘定科目は、支払の根拠となる契約や支払う相手、業務の内容などによって区別されます。特に、外注費と給与は、税金の取り扱いが異なるため慎重な判断が必要です。
外注費が発生する主な契約
外注費は、外部の個人や法人との契約により発生します。外注費が発生する主な契約は、以下のとおりです。
請負契約:委託者が成果物に対して受託者へ報酬を支払う契約
請負契約は、受託者(受注者)が期日までに仕事を完成させ、委託者(発注者)が成果物に対して報酬を支払うことを定めた契約です。成果物によっては、委託者による検査や確認が行われ、問題がないと判断された時点で納品完了とします。
委任契約:物理的な成果物がなく、法律行為を委任する契約
委任契約は、物理的な成果物がなく、法律行為を委任する契約です。例えば、弁護士や税理士、司法書士といった専門家に業務を委任する際の契約は委任契約に当たります。
準委任契約:物理的な成果物がなく、非法律行為を委任する契約
準委任契約は、物理的な成果物がなく、非法律行為を委任する際の契約です。必ずしも一定の結果を出すことが報酬の支払条件とされておらず、役務の提供そのものが報酬の根拠となります。
労働者派遣契約:派遣会社と派遣先企業が結ぶ契約
労働者派遣契約は、派遣会社と派遣先の企業(人材を受け入れる事業者)が結ぶ契約です。自社が派遣社員を受け入れる場合、派遣元の派遣会社と労働者派遣契約を締結します。
外注費と業務委託費の違い
外注費と同じ意味の勘定科目として、業務委託費が使われることもあります。業務委託費とは、業務の一部を外部に委託した際に支払う報酬です。企業によっては、外注費を業務委託費という勘定科目で処理することもあります。業務委託費に該当するのは、上にあげた契約のうち、請負契約、委任契約、準委任契約に基づいて支払う報酬です。そのため、派遣会社に支払う費用は、業務委託費には当たりません。外注費は、自社の業務の一部を、外部の個人や法人に委託するときに支払う費用全般を指すのに対し、業務委託費は、契約によって遂行される業務の報酬を指すという点が異なります。
外注費と給与の違い
給与は、雇用契約(労働契約)に基づき、労働の対価として従業員に支払われる報酬です。雇用契約では、雇用者と労働者の間には雇用関係があり、労働者には労働基準法や労働契約法が適用されます。その一方で、外注費は、請負契約などを結んだ外部の個人や法人に対して、成果物・役務の対価として支払う報酬です。委託者と受託者の間に雇用関係はない他、仕事を請け負う受託者は労働者ではないため、労働基準法や労働契約法などは適用されません。また、外注費と給与には、支払条件や源泉徴収と社会保険料の扱い、消費税の課税対象かどうかといった点にも違いがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
外注費と給与の主な違い
| 外注費 | 給与 | |
|---|---|---|
| 支払の相手 | 外部の個人や法人 | 従業員 |
| 契約形態 | 請負契約など | 雇用契約(労働契約) |
| 源泉徴収 | 原則として不要 (個人に支払う特定の報酬のみ必要) |
必要 |
| 社会保険料 | 不要 | 給与からの控除と事業主負担分の支払が必要 |
| 消費税 | 課税対象で課税仕入として仕入税額控除の対象になる | 課税対象にならない(不課税) |
支払条件
外注費と給与との違いは、支払条件です。
給与は労働の対価のため、成果物の有無にかかわらず、毎月計算した給与の金額を決まった日に支払う必要があります。それに対して、外注費は成果物や役務に対する対価であり、成果物の納品または役務の提供がなければ支払は発生しません。また、支払期日も契約内容によってそれぞれ異なります。
源泉徴収と社会保険料
源泉徴収と社会保険料の扱いも外注費と給与では異なります。
源泉徴収とは、給与や賞与、報酬などにかかる所得税および復興特別所得税(以下、所得税)を差し引き、納税者本人に代わって国に納付することです。従業員に給与を支払う際、雇用者には源泉徴収の義務があります。さらに、要件を満たした従業員については、給与からの社会保険料の控除(天引き)と、社会保険料の事業主負担分の支払が発生します。
その一方で、外注費の場合は、原稿料や講演料、士業に支払う報酬といった個人事業主に支払う一部の報酬を除き、委託者に源泉徴収の義務はありません。また、委託者が外注費から社会保険料を控除したり、社会保険料を支払ったりすることもありません。
消費税
消費税の課税対象かどうかも、外注費と給与との違いのひとつです。
外注費が消費税の課税対象であるのに対して、給与には消費税はかかりません。そのため、外部の個人や法人に支払った外注費は、課税仕入として仕入税額控除の対象となります。
外注費と支払手数料の違い
外注費と支払手数料では、契約の種類が異なります。
支払手数料は、事務委託手数料や業務委託手数料などを処理する勘定科目です。一般的に外注費のうち、弁護士や税理士、公認会計士などといった、いわゆる士業に業務を依頼して支払った費用については、支払手数料の勘定科目を用います。法的な手続きなどを委託する場合の委任契約の報酬は支払手数料、それ以外(請負契約、準委任契約など)は基本的に外注費、と覚えておくといいでしょう。
なお、支払手数料の勘定科目は、士業への報酬以外にも、仲介手数料、登録手数料、解約手数料、証明書等の発行手数料、各種役所・銀行手数料など、業務で発生する手数料を処理する際にも使います。また、士業への報酬の多くは、支払手数料ではなく支払報酬料の勘定科目で処理します。業務を依頼する士業が個人事業主である場合、報酬を支払う際には原則、源泉徴収が必要です。弁護士法人や税理士法人など、支払先が法人であれば、源泉徴収は必要ありません。
外注費と販売促進費の違い
外注費と販売促進費との違いは、費用を利用する目的です。販売促進費は、自社の製品やサービスの販売を促進するために支出した費用を計上する際に用いる勘定科目を指します。例えば、自社の魅力を伝えるためにグッズやサンプルを配布したり、キャンペーン・イベントを開催したりする際にかかる費用などが該当します。グッズやサンプルの配布、イベントの開催などは、外部の事業者に依頼して実施することが多いため外注費と混同されがちですが、売上増加を目的とした直接的な宣伝費用は販売促進費として計上しましょう。
なお、販売促進費と混同されやすい勘定科目に広告宣伝費があります。広告宣伝費は、企業やブランド、製品などを宣伝するための費用を支出した際に使用する勘定科目です。例えば、Web広告を出稿したり、チラシを配布したりする際にかかった費用は、広告宣伝費に該当します。その一方で、販売促進費は、製品やサービスの販売を促進するために支出した費用です。不特定多数に向けた大々的な広告費などではなく、多くの場合、一定範囲内の顧客への販売促進に必要な費用を指します。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
外注費と給与を区分する基準
外注費と混同されやすい勘定科目のうち、最も注意が必要なのが給与です。士業に支払う支払手数料や外注先に支払う販売促進費は、大きな意味では外注費の一部であり、いずれも課税仕入に該当します。しかし、給与は人件費であり、外注費とはまったく性質が異なるものです。企業にとっては、社会保険料の支払が発生せず、仕入税額控除の対象になる外注費は、給与を支払うよりもコストがかかりません。そのため、税務署も、「本来給与と見なされるものを外注費として処理していないか」と厳しくチェックする傾向にあります。
前述したとおり、外注費は請負契約などに基づいて支払う報酬なのに対し、給与は雇用契約に基づいて支払う報酬です。ただし、支払う報酬が外注費か給与かは、単に形式的な契約形態だけで判断されるものではありません。以下の5つの項目をふまえ、総合的に外注費か給与かを判断する必要があります。
他の人が代替できるか
外注費と給与を区分する基準は、「依頼する業務を他の人が代わって行うことができるか」という点です。
外注費の場合は、基本的に業務の代替ができます。例えば、契約上問題がなければ、業務を受ける契約者本人ではなく他のスタッフが業務を行ったり、外注先からさらに外部に業務を委託したりしてもかまいません。定められた成果さえ提示されれば、実際に誰が業務を担当したかにかかわらず、報酬は支払われます。
それに対して、給与は、あくまで個人の労働に対して支払われるものです。本人が仕事をしていなければ、他の人が代わって遂行した成果物を提示しても、給与の支払はありません。このことから、業務の代替が可能なら外注費、代替できない場合は給与と判断できるでしょう。
労働時間に拘束性があるか
労働時間の拘束性の有無も外注費と給与を区分する基準です。
外注費は、請負などの契約形態によっては業務にかかった時間ではなく、仕事の成果物に対して支払われます。例えば、成果物が完成するまでにかかった時間が1週間でも1日でも、支払われる外注費の金額は同じです。また、準委任などの一定の契約を除いて業務時間について委託者から指示を受けたり、報告したりする必要もありません。委託者が業務時間を指定し、その業務時間に応じた報酬が支払われる場合、外注費ではなく給与と判断される可能性が高いでしょう。
委託者の指示が詳細か
委託者からの指示の詳細さも、外注費と給与を区分する基準のひとつです。
上述した労働時間の他、業務の進め方や手順、勤務場所などが委託者から細かく指定されている場合、支払われる報酬は給与と判断される可能性が高いでしょう。その一方で、委託者が業務の具体的な手順や方法を受託者に委ねる場合は、報酬は外注費として扱われることになります。
期限内に納品できなかった場合に作業対価を請求できるか
外注費と給与を区分する基準としては、契約で定められた期限内に納品できなかった場合に作業対価を請求できるかどうかもあげられます。
外注費の場合は、請負など一定の契約についてはいかなる理由があっても受託者が契約の期限内に納品できなかった場合には委託者に作業対価を請求できません。その一方で、給与は労働の対価のため、労働者が期限内に納品できなかったとしても作業対価の支払が発生します。
業務に必要な道具を用意するのは誰か
業務に必要な道具を用意する者が誰なのかという点も、外注費と給与を区分する基準です。
外注費が支払われる業務委託では、業務に必要な道具や材料、機材などは受託者が自分で調達するケースが多いです。そのため、委託者が業務に必要な道具を支給している場合、その実態を見て雇用関係にあると見なされる可能性が高くなります。ただし、契約によっては、業務に必要な道具を委託者が支給する場合もあるでしょう。
外注費の仕訳方法
ここからは、外注費を支払ったときの仕訳方法について紹介します。法人と個人のケースの仕訳例について見ていきましょう。
法人に外注費を支払う場合の仕訳例
仕訳例:外注先のデザイン会社へデザイン制作料として10万円を普通預金から支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 外注費 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
仕訳例:税理士法人に業務を委任し、報酬として5万円を支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
外部の法人へ業務を依頼した場合は、外注費の勘定科目を用いますが、税理士法人などの士業に業務を依頼した場合には、報酬を支払手数料の勘定項目で仕訳を行います。
個人に外注費を支払う場合の仕訳例
仕訳例:個人の職人に部品の修理を依頼し、工賃1万円を現金で支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 外注費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
個人に業務を依頼した場合も外注費の勘定科目を用います。なお、個人に支払う外注費のうち、原稿料や講演料、士業に支払う報酬については、源泉徴収が必要になります。源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲は、国税庁のWebサイトで確認できます。
以下のケースでは、源泉徴収した税額を預り金として計上します。
仕訳例:フリーランスのデザイナーへデザイン制作料として、10万円から源泉徴収額1万210円を差し引いて支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 外注費 | 100,000円 | 普通預金 | 89,790円 |
| 預り金 | 10,210円 | ||
仕訳例:税理士に業務を委任し、報酬の5万円から源泉徴収税額5,105円を差し引いて支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 50,000円 | 普通預金 | 44,895円 |
| 預り金 | 5,105円 | ||
外注費が給与と指摘された場合の影響
前述したように、外部の個人に支払う報酬が外注費か給与になるかは、慎重に判断する必要があります。外注費として処理していた費用が、税務調査で給与であると判断された場合、以下のような影響があります。
源泉所得税を過去の分までさかのぼって納める必要がある
外注費は個人に支払う特定の報酬を除いて源泉徴収の必要はありません。しかし、給与は原則として源泉徴収が必要です。もし、本来は給与とされるものを外注費として処理していた場合、納付すべき源泉所得税を納めていないことになります。そのため、本来納税の必要があった源泉所得税を、過去の分までさかのぼって納めなければなりません。
消費税の負担が増える
外注費は消費税の課税対象となる一方で、給与は課税対象外です。また、外注費は課税仕入として仕入税額控除の対象になります。仕入税額控除とは、消費税の納付額を計算するときに、売上にかかる消費税から仕入にかかった消費税を差し引くしくみのことです。例えば、売上を11万円(10万円+消費税1万円)、外注費を5,500円(5,000円+消費税500円)と計上していたとしましょう。この場合、消費税の納付額は、「1万円-500円=9,500円」です。しかし、この外注費が給与だった場合、消費税の課税対象外となるため、控除する消費税額(控除対象消費税額)がないので、納付額は1万円になります。よって、外注費が給与と指摘されることで、消費税の負担が増える可能性があります。
延滞税と加算税が発生する
上述したように、本来納付すべき源泉所得税や消費税を納めていなかった場合、ペナルティとして追徴課税が発生します。主な追徴課税には、「過少申告加算税」「延滞税」「不納付加算税」があります。
過少申告加算税は、申告期限内に提出した納税額が過少である場合に課される加算税です。不納付加算税は源泉徴収した所得税を法定期限までに納めなかった場合に、それぞれ加算されます。これらの加算税は、原則として一括納付が義務付けられています。また、延滞税は税金を納付期限までに納めなかった場合に課税されます。
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
外注費の意味を知って適切に処理しよう
外注費とは、外部の個人や法人に業務を委託するときに支払う費用のことです。ただし、外部に支払った費用がすべて外注費になるわけではありません。特に、外注費と給与は正しく区別しないと、税務調査で指摘を受け、追徴課税や各種加算税の対象になることがあります。外注費を適切に会計処理するためには、会計ソフトが役立ちます。外注費の効率的な管理をするためにも、弥生の会計ソフトの利用をぜひご検討ください。外注費の意味や給与との違いをしっかりと理解し、適切に処理するようにしましょう。
無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる 会計業務のはじめかた】をダウンロードする
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。









