経費精算ルールの作成方法は?重要性や作成時のポイントなどを解説
監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)
更新
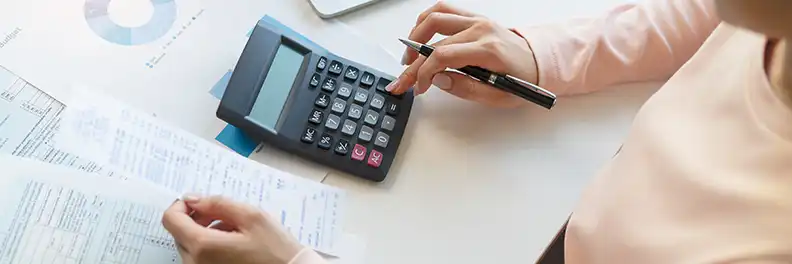
経費精算は、企業ごとにさまざまなルールが存在します。経費申請時の留意点や経費として認めるか否かの判断基準が明文化されていないと、申請者や経理担当者によって解釈にずれが生じることにもなりかねません。こうした事態を防ぐには、明確な経費精算ルールを定めておくことが大切です。
本記事では、経費精算ルールを整備することの重要性や、ルールに盛り込むべき項目、策定時の注意点を解説します。自社の経費精算ルールが適切かどうかチェックする際に、ぜひお役立てください。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算にルールが必要な3つの理由
経費精算ルールは、精算内容を適切に管理するための重要な仕組みです。精算内容が適切に管理されていなければ、決算時の会計処理や税務申告にも悪影響を及ぼすおそれがあります。ここでは、経費精算ルールが必要な3つの理由を紹介します。
不正や申請ミスを防ぐため
経費精算ルールを設けるべき最大の理由は、私的な支出が経費に紛れ込むといった不正を未然に防ぐことにあります。例えば、支出したものが「経費になるのか、ならないのか」といった判断を申請者の自己判断に委ねていると、本来は経費として認められないはずの支出まで経費に計上されてしまうことにもなりかねません。
また、ルールを設けることは申請ミスや内容の不備を軽減する効果もあります。例えば、交通費を申請する際に「行き先」「業務内容」「利用した路線」を必ず記載するよう定めておけば、経理担当者は記載された内容と金額の妥当性を照合でき、私的利用や誤った申請が紛れていないかをチェックしやすくなります。
精算業務の効率化と処理の平準化のため
精算業務を効率化するとともに、処理フローを平準化することも経費精算ルールが必要な理由の1つです。明確なルールが設けられていない場合、申請者ごとにフォーマットや記載事項が異なるため、確認や差し戻しに伴う作業が頻発しやすくなります。
あらかじめ経費申請ルールを整備しておけば、申請者ごとのばらつきを最小限に抑え、結果として申請者・承認者・経理担当者の三者にとってスムーズな精算を実現できるでしょう。
経費精算業務の属人化を防ぎ、透明性を確保するため
経理担当者による経費精算業務の属人化を防ぎ、透明性を確保することも、ルールが必要とされる理由の1つです。経費精算に関わる判断が暗黙の了解や経理担当者の経験則に依存する状態になると、担当者の異動や退職に伴う引き継ぎが困難になります。曖昧な運用を排除し、誰しもが適切な判断を下せる状況にするためには、ルールの明文化が欠かせません。明確なルールにもとづいて経費精算がなされていることは、企業会計の透明性を確保するうえでも重要です。
経費精算の流れや経費精算書の種類、効率化のポイントについては以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算ルールの作成方法
経費精算ルールを策定する際には「何を・誰が・どのように申請・処理するのか」を明確にすることが大切です。ここでは、定めておくべき基本的な項目と具体的な作成方法、経費精算ルールの例をご紹介します。
精算の対象となる経費の範囲
経費精算ルールには、まずは「どのような支出が精算の対象になるか」を明示することが重要です。対象となる経費が多岐にわたる場合は、併せて「対象外となるもの」を明記しておくと申請時のトラブル防止につながります。以下は、対象となる経費・対象外とする経費の例です。
対象となる経費の例
- 業務上の交通費(電車代・バス代など)
- 宿泊費(出張時のビジネスホテル)
- 会議時の飲料代(社内打ち合わせ・外部との商談)
- 文房具や封筒などの消耗品費
- 業務用の携帯通信費
対象外とする経費の例
- 通勤定期区間内の交通費
- 業務と無関係なプライベートでの支出(例:通勤中の寄り道にかかる交通費や食事代など)
- 同僚との私的な飲食代(例:勤務時間外の飲み会や個人的なランチなど)
勘定科目の分類基準
さまざまな経費をどの勘定科目に分類して仕訳すべきかについても、あらかじめ基準を設けておくことが大切です。特に申請者や経理担当者が迷いやすいと想定されるケースについては、分類基準を事前に統一しておくとよいでしょう。
以下はよくある勘定科目の分類例です。
勘定科目の分類基準の例
- 取引先との飲食 → 「交際費」
- 社内会議でのお茶・お菓子 → 「会議費」
- 切手や封筒などの購入 →「消耗品費」または「通信費(目的による)」
- ※切手は実際に使用するまでは「貯蔵品」
領収書や証憑の添付
経費精算申請書に添付すべき領収書や証憑のルールについても、具体的な規程を設けておきましょう。原則として、経費精算時には領収書の添付を義務付けるのが一般的です。その一方で、電車代のように領収書が発行されない支出に関する取り扱いも明確に定めておく必要があります。
また、電子データによる領収書提出の可否や、金額に応じた添付要件を定めておくことも重要なポイントです。あわせて、電子帳簿保存法(電帳法)の保存要件に従った提出方法を明記することで、法令対応にもつながります。具体的には、以下の例のように詳細な提出方法・記入事項を明示することをおすすめします。
領収書や証憑添付ルールの例
- 1,000円未満の電車代などは領収書不要(交通系ICカードの場合は利用履歴で代用)
- 電子領収書はPDFまたは画像(jpg、png形式)での添付可
- 紙の領収書は原本を経理へ提出
- 領収書のあて名は「〇〇株式会社」と記載
精算申請の方法と期限
経費申請をする際の提出方法や必要書類、提出期限も明確に定める必要があります。精算は経費が発生した時点からできるだけ期間を空けずに処理するのが理想ですが、日々発生する経費に都度対応するのはあまり現実的ではありません。よって、申請の締め日を設け、月単位などでまとめて申請を受け付けるのが一般的です。
経費の申請漏れや提出の遅延が発生すると、期間中の収支を正確に把握できなくなってしまいます。特に月次・期末には経理担当者が計上するべき月や会計年度の経費として計上することができるように、提出期限を超過することがないように注意しましょう。以下のようなルールに則って運用するよう徹底していくことが求められます。
精算申請の方法・期限の例
- 精算申請はクラウド経費精算システムを使用
- 毎月5営業日以内に前月分を提出
- 紙の場合は、上長の捺印入り申請書+領収書を経理まで提出
- 申請が遅れた場合は備考欄に理由を明記し、上長承認を得てもらう
経費精算の期限を過ぎてしまった場合の対応についてはこちらで解説していますので、参考にしてください。
経費精算の承認フロー
経費精算申請書が提出された後の承認プロセスをルール化しましょう。金額によって承認権限が異なる場合には、その基準を具体的に記載しておくことが大切です。また、自己決裁を禁止するルールを明確に定めておくことも重要なポイントといえます。自己決裁とは、申請者と承認者が同一人物であることを表す言葉です。
例えば、経費精算の承認者が部門長のみの場合、部門長本人が申請者であれば自ら承認できてしまいます。自己決裁は経費の不正申請にもつながりやすいことから、必ず申請者以外の第三者が申請内容をチェックする仕組みにしなければなりません。以下は申請金額ごとの承認フローの一例です。
経費精算内容の承認フロー例
- 3万円以下:所属上長が承認 → 経理へ提出
- 3万円超〜10万円以下:部門長承認 → 経理へ提出
- 10万円超:事前に取締役会などへの申請・承認を得たうえで精算可能
- すべての精算は経理が最終確認を行い、内容に問題がなければ支払処理へ進む
精算の支払方法とタイミング
精算後の支払方法についても、経費精算ルールの中で明示しておく必要があります。例えば、現金または振込かといった精算方法、給与と合算して支払または別日に支給されるといった支払日やタイミング、振込先などもあわせて記載しておかなければなりません。一般的には、以下の例のように締め日と支払日をあらかじめ決めておくと良いでしょう。
精算の支払方法の例
- 毎月15日締め、月末振込
- 原則として、給与口座と同じ口座へ振込処理
- 1,000円未満の少額は現金払い
- 支払に不足・過剰があった場合は、次回精算時に相殺処理を行う
仮払金・立替金の取扱い
出張や接待など、まとまった支出が見込まれる際には、会社が社員に対して事前に仮払金を渡す場合があります。その一方で、社員が自分で立て替えて支払う「立替金」も日常的に発生します。
仮払金・立替金の取扱いルールについても経費精算ルールに記載し、ルールに則って運用していくことが大切です。具体的には、以下の例にあるように申請の期日や金額の上限、差額精算の方法などを明記しておくのが望ましいでしょう。
仮払金・立替金の取り扱いルールの例
- 出張の仮払申請は出発の3営業日前までに申請、接待の場合は実施予定日の3営業日前までに申請
- 仮払額の上限:出張1泊につき1万円まで、接待の場合は1回につき3万円まで
- 仮払金と実際の使用額に差額が出た場合は、精算書で差額を返金または追加精算を行う
仮払金についてはこちらで解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算規程別に押さえておくべきポイント
経費精算の中でも交通費・出張費・交際費などの個別規程に関しては、業種や企業文化、これまでの慣習などによって必要な記載が異なります。それぞれの規程において押さえておくべきポイントをまとめました。各規程の主な対象経費と必ず記載すべき項目を確認しておきましょう。
経費精算ルールに記載する主な項目と記載すべき項目一覧
| 規程 | 主な対象経費 | 必ず記載すべき項目 |
|---|---|---|
| 交通費規程 | 電車・バス・タクシー代、ICカード利用など |
|
| 出張費規程 | 宿泊費、日当、交通費、出張先での飲食費など |
|
| 交際費規程 | 取引先との飲食費、贈答品費用など |
|
| 消耗品費・備品規程 | 文房具、PC周辺機器、事務用品など |
|
| 福利厚生費規程 | 社員懇親会、慶弔見舞金、社内イベント参加費など |
|
| 研修費規程 | セミナー参加費、参考書籍購入費、外部講師依頼費など |
|
| 在宅勤務費規程 | 通信費、電気代の一部、在宅業務用の備品費用など |
|
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算ルールを策定する際によくある失敗と対策
経費精算ルールを策定するにあたって、よくある失敗例をまとめました。ルール整備の際に気をつけておきたいポイントなので、事前に確認しておきましょう。
ルールの周知ができていない
経費申請ルールを定めても、周知されていなければルールに則った運用がなされません。ルールはあるものの、現場の社員が目を通していなかったり、必ず守るべき重要なルールとして認識されていなかったりする場合、誤った申請が横行することもありえます。
なぜ経費申請のルールが必要とされているのか、遵守されなかった場合にどのようなトラブルにつながるおそれがあるのか、丁寧に説明することが重要です。また、ルールは社内ポータルなど誰もがすぐに確認できる場所に掲載し、経費申請の際には必ず確認するよう周知しましょう。
イレギュラー対応が増えてルールが曖昧になる
策定した経費申請ルールから逸脱したイレギュラー対応が増えていくと、ルールそのものが曖昧になりがちです。例えば、特定の部署のみ申請方法が異なっているにもかかわらず、その状況が黙認されていると、ルールそのものが形骸化することにもなりかねません。
その一方で、経費申請にはさまざまな状況がありえることから、例外を認めざるをえないケースもあるでしょう。そのような場合には、例外ルールをどのように設け、明文化するかがポイントとなります。各部門の社員にヒアリングを実施するなど、現場の実態を踏まえたルールを策定することが大切です。
過去のルールが更新されない
現場の実態とかけ離れた古いルールが根強く残っており、新たなルールが浸透しないといった事態も起こりえます。例えば、「10万円超の経費精算には事前の申請・承認が必要」というルールが設けられたとしても、「以前は10万円を超える場合も事後精算で問題なかった」と複数の社員が認識していれば、事前申請のフローが徹底されない状況に陥りかねません。
新たな経費精算ルールを運用し始める際には、「2025年〇月〇日運用開始」のようにいつから新しいルールが運用されるのかについて明確な日付を記載し、社内に周知する必要があります。また、その後もルールどおりに運用されているか定期的にチェックし、現場の実態とずれが生じているようならルールそのものを見直していく必要があるでしょう。
申請・承認のIT化が追いつかず非効率になっている
経費精算フローの一部をIT化したつもりでも、「申請は紙」「承認はメール」「支払は現金」といったように、アナログとデジタルが混在してしまうと、かえって運用が非効率になりかねません。そのため、真の意味でのIT化を実現するには、申請から支払までを一貫してデジタル化することが重要です。
例えば、経費の申請・承認から会計ソフトへの入力までが継ぎ目なく行われるようにすることで、経費精算に関するすべてのフローをIT化できます。これにより、場所やタイミングを問わず申請・承認ができるようになるだけでなく、経理担当者のチェックの手間も軽減されるでしょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算ルールは企業の規模を問わず必要不可欠な仕組み
経費精算ルールは、大企業だけでなく中小企業にとっても必要な仕組みといえます。申請ミスや不正を防ぎ、経理業務の負担を軽減するためにも、ルールを明確に定めたうえで、社内に共有し続けることが重要です。
近年では経費精算のIT化やペーパーレス化を推進する企業が増え、従来のルールが現状と合わなくなるケースも増えつつあります。経費精算のルールも、現場の実態に合わせてアップデートしていく必要があるでしょう。
経費精算の効率化を図るには、会計ソフトを活用するのも有効な方法です。ルールの策定とあわせて、効率化に役立つツールの導入を検討してみてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)
東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員
お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。








