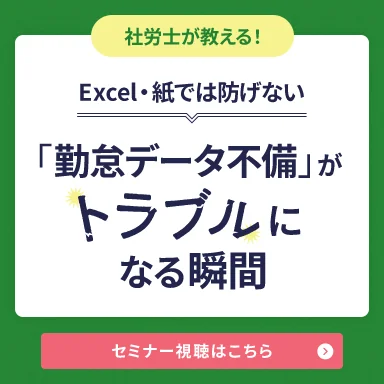アルバイトやパートの有給休暇の計算方法は?要件や付与日数を解説
更新
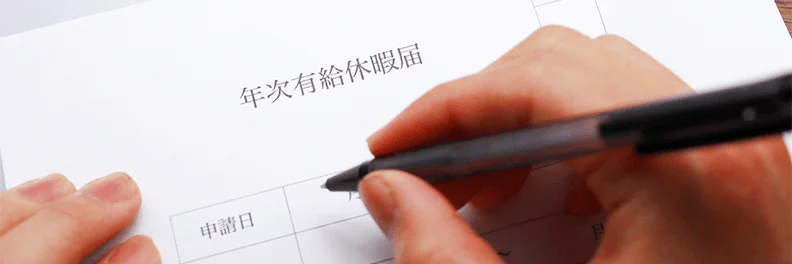
有給休暇は、正社員だけではなく、アルバイトやパートでも取得可能です。ただし、アルバイトやパートの場合、有給休暇の取得要件や付与日数の計算方法が正社員とは異なる場合があるため注意が必要です。
本記事では、アルバイトやパートが有給休暇を取得できる要件や、有給休暇の付与日数の計算方法、有給休暇を取得した際の賃金の計算方法などについて解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
アルバイト・パートも有給休暇を取得できる
会社は、アルバイトやパートなどの短時間労働者に対しても、要件に該当すれば有給休暇を付与しなければなりません。「有給休暇は正社員しか取得できない」というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、有給休暇は所定の要件さえ満たせば、雇用形態に関係なく取得可能です。
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」といい、その名のとおり「給与が発生する休暇」です。有給休暇を取得した日は、実際に働くことはありませんが、賃金が支払われます。
有給休暇は、労働者の心身の疲労回復とゆとりある生活のために労働基準法で定められた制度であり、原則として事前申請で、会社は従業員からの有給休暇取得の請求を拒否することはできません。また、有給休暇を取得する理由によって取得を拒否したり、有給休暇を取得した分の賞与を減らしたりといった、従業員に不利益となるような行為は禁止されています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイト・パートが有給休暇を取得できる要件
アルバイトやパート従業員が有給休暇を取得するには、「6か月以上勤務を継続的にしている」「全労働日の8割以上出勤している」という2つの要件を満たす必要があります。以下で詳しく見てみましょう。
6か月以上勤務を継続的にしている
有給休暇は、入社から6か月以上継続して勤務している従業員に対して付与されます。働き始めてから6か月がたっていない従業員は、有給休暇を取得することはできません。この「6か月以上」には、シフト日数は関係なく、週1日勤務でも週4日勤務でも、入社日が同じなら、半年後の同じタイミングで有給休暇が付与されます。
全労働日の8割以上出勤している
有給休暇付与のもう1つの要件が、全労働日の8割以上出勤していることです。有給休暇を取得するには、就業規則や雇用契約で定められた所定労働日数の8割以上を出勤している必要があります。入社日から6か月経過後を基準日と定め、継続して勤務していても、その基準日までの出勤率が8割未満だった場合は有給休暇が付与されません。なお、その後は基準日ごとに有給が付与されることになります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
有給休暇の付与日数の計算方法
従業員に付与される有給休暇の日数は、労働基準法によって定められています。アルバイトやパートの有給休暇の付与日数は、下記のように就業時間・日数によって計算方法が変わります。
週30時間以上、または週5日以上の従業員
アルバイトやパートで週30時間以上、または週5日以上のシフトで働いている場合は、6か月以上継続して8割以上出勤していれば、年間10日の有給休暇が付与されます。この要件は、雇用形態に関係なく、すべての従業員に適用されます。
従業員の出勤率は、「(実際の出勤日数÷所定労働日数)×100」で計算が可能です。その後は、以下のように、勤続年数を重ねるごとに有給休暇の日数が増え、6年6か月たつと1年ごとに20日の有給休暇が付与されるようになります。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
-
※厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得
」
週30時間未満、かつ週4日以下の従業員
労働時間が週30時間未満で、かつ週4日以下のアルバイトやパートの場合は、週または年間の所定労働日数によって、有給休暇の付与日数が決まります。パートやアルバイトの有給休暇は、週1日または年間48日以上の勤務日数から発生します。フルタイム従業員と同様に「(実際の出勤日数÷所定労働日数)×100」で出勤率を計算し、半年以上継続して8割以上出勤していれば、有給休暇が付与可能です。
付与される有給休暇の日数は、所定労働日数が週によって決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は、労働日数を割り出すための便宜的な方法として直近6か月の労働日数の2倍や、前年の所定労働日数を基準とした「1年間の所定労働日数」によって判断することがあります。例えば、勤続年数6年6か月以上になると、付与される有給休暇は、週4日勤務であれば最大15日、週3日なら11日、週2日なら7日、週1日なら3日となります。
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | ||
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
-
※厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得
」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイト・パートの有給休暇付与に関する注意点
労働基準法では、有給休暇に関するさまざまなルールが定められています。従業員に有給休暇を付与する際には、以下の点に注意が必要です。
年5日の有給休暇取得が義務化されている
労働基準法の改正により、2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日の有給休暇を取得させることが義務付けられています。この義務化の対象は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態を問わず、有給休暇の付与日数が10日以上であれば、会社は基準日(有給休暇を付与した日)から1年以内に最低でも5日を取得させなければなりません。
週30時間未満かつ週4日以下のアルバイトやパートでも、週4日勤務なら勤続3年6か月、週3日勤務なら勤続5年6か月以上で、有給休暇の付与日数は10日になるため、年5日の取得が必要です。もし年間5日の有給休暇を取得させなかった場合は、使用者(会社)が労働基準法違反で罰金や指導の対象となってしまうため注意しましょう。
年次有給休暇管理簿の作成・保管が義務付けられている
労働基準法では、使用者(会社)の義務として、年次有給休暇管理簿を作成することに加え、3年間保管する義務があります。このように管理することで、有給休暇取得の意識付けにもつながります。取得させるべき従業員を見落としてしまうことがないように、心掛けましょう。
有給休暇の請求権は2年で時効になる
付与された有給休暇を1年のうちに消化しきれなかった場合は翌年への繰り越しが可能ですが、有給休暇の請求権には2年の時効があります。時効までに使いきれなかった分の有給休暇は、自動的に消滅するため注意が必要です。
例えば、正社員や、週30時間以上または週5日以上のアルバイト・パートの場合、勤続6年6か月以上であれば有給休暇の付与日数は最大20日です。これを翌年に繰り越すと、計算上は40日になります。
産前産後休業などもカウントしたうえで有給休暇を計算する
有給休暇の付与日数を判断する基になる勤続年数は、産前産後休業や育児休業、介護休業、労災休業期間中の日数も、出勤日数として含めたうえでカウントします。なお、産休や育休、介護休業などを取得している期間中に有給休暇を取得することはできません。しかし、年次有給休暇の出勤率を算出する際には、その休業期間を全日出勤したと見なして出勤率を算定し、有給休暇を付与しなければならないので注意しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
有給休暇を取得した際の賃金の計算方法
アルバイトやパートを含めた従業員が有給休暇を取得した場合、賃金は主に3つのいずれかの方法で計算します。どの計算方法を選ぶかは各企業の任意ですが、採用した方法については賃金規程や就業規則に明記する必要があります。では、時給制や日給制で働くアルバイト・パートの場合、どのように賃金を計算するのか確認していきましょう。
通常賃金から計算する方法
有給休暇を取得した日も通常どおり出勤したと見なして賃金を計算する方法です。所定労働時間が一定なら、通常賃金は「時給×有給取得日の所定労働時間」または「1日分の日給額」となります。
このとき注意が必要なのが、曜日によって雇用契約である勤務時間が異なるケースです。例えば、月曜日が6時間勤務、火曜日が4時間勤務で固定されているアルバイト従業員が、月曜日に有給休暇を取得したら6時間分、火曜日なら4時間分の時給を支払うことになります。
平均賃金から計算する方法
直近3か月間の平均賃金から計算する方法では、原則として、有給消化日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して算出します。しかし、賃金が時給や日給、出来高払い給与などで労働日数が少ない場合のように、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します。
なお、過去3か月間の賃金は、締切日ごとに、基本給、通勤手当、時間外手当など諸手当を含んだ賃金の総額にから算出します。
標準報酬日額から計算する方法
社会保険料を計算するベースとなる「標準報酬月額」を日割りして「標準報酬日額」を算出し、その金額を有給休暇1日当たりの金額とする方法です。なお、標準報酬月額は健康保険と厚生年金保険で別々に定められていますが、有給休暇取得時の賃金を計算する際には、健康保険の標準報酬月額を用います。標準報酬日額は、以下の計算式で求めます。
標準報酬日額の計算式
標準報酬日額=標準報酬月額÷30
アルバイトやパートといった短時間労働者の標準報酬月額は、支払基礎日数(賃金の支払い対象になる労働日数)によって、次のように算定されます。
| 支払基礎日数 | 標準報酬月額の決定方法 |
|---|---|
| 3か月とも17日以上ある場合 | 3か月の報酬月額の平均額を基に決定 |
| 1か月でも17日以上ある場合 | 17日以上の月の報酬月額の平均額を基に決定 |
| 3か月とも15日以上17日未満の場合 | 3か月の報酬月額の平均額を基に決定 |
| 1か月または2か月は15日以上17日未満の場合(1か月でも17日以上ある場合は除く) | 15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額を基に決定 |
| 3か月とも15日未満の場合 | 従前の標準報酬月額で決定 |
-
※全国健康保険協会「標準報酬月額の決め方
」
なおこれらの標準報酬日額を算出する方法以外にも、被保険者の報酬が、昇(降)給などの固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、上記の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する随時改定を行います。このように標準報酬月額を変更することがありますので、注意しましょう。
なお、標準報酬日額から算出した賃金は、通常賃金や平均賃金から算出した賃金より、有給休暇取得時の賃金が低くなる可能性があります。そのため、標準報酬日額から計算する場合は、労使協定の締結が必要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算ソフトでアルバイト・パートの給与計算を簡単に!
正社員と同様に、アルバイトやパートであっても、要件を満たした従業員には所定の日数の有給休暇を付与する必要があります。また、有給休暇は付与するだけではなく、積極的な取得を促すことも大切です。従業員が有給休暇を取得した際には、定められた方法で賃金計算をしなければなりません。有給休暇取得時の賃金計算は従業員によってそれぞれ異なるため、ミスのないように注意を払う必要があります。さらに、正社員、アルバイト、パートと、給与形態の異なる従業員がいる場合は、計算がより複雑になります。
アルバイト、パートの有給休暇を含めた給与計算をスムーズに行うには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。
弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています。自社に合った給与計算ソフトを活用して、業務を効率良く進めましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。