有給休暇の付与日数は?付与時期や最大日数、注意点も解説
監修者: 下川めぐみ(社会保険労務士)
更新

有給休暇は、条件を満たすすべての労働者に取得する権利がある制度です。活用することで、従業員が適切に休息を取り健康を保てるだけでなく、企業にとっても生産性が高まるなどのメリットがあります。本記事では、有給休暇の概要や付与日数、付与するタイミング、さらに有休の付与や管理において気を付けるべきポイントなどについて詳しく解説します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!
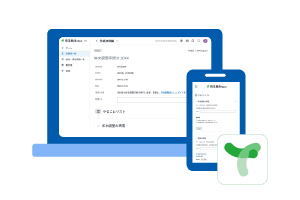
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
有給休暇が付与される要件
有給休暇が付与される要件について、労働基準法第第39条では、以下のように定められています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:e-Gov「年次有給休暇」
このことから、有給休暇が付与されるためには下記を満たす必要があります。
-
1.半年以上継続して雇用されていること
-
2.全労働日の8割以上出勤していること
条件を満たすすべての従業員に、雇用形態にかかわらず有給休暇の取得が認められています。フルタイムで働く従業員はもちろんのこと、パートタイムやアルバイト、派遣社員も、条件が合致すれば有休が取得できます。
ただし、労働日とみなされる日とカウントされない日があることに注意しましょう。普段どおりに勤務した日、遅刻・早退した日、有休取得日、労災(業務上の負傷)による休業日、育児・介護休業日などは労働日に該当します。その一方で、休日出勤した場合や企業の都合による休業日、そして業務を行わないストライキ期間は労働日に含まれません。
有給休暇とは賃金が支払われる休暇のこと
有給休暇とは、労働基準法に定められている、賃金が支払われる(取得しても賃金が減額されない)休暇のことです。
有給休暇制度を設置する目的は、従業員が健康を維持しながら働ける環境を用意するためです。健康な状態で働き続けることは、従業員の権利でもあります。
そして企業側には、自社で働く従業員の健康を守る責任があります。従業員の健康を守ることは、従業員だけでなく企業の側にもメリットがあります。なぜなら、適切に休暇を取らずに長時間労働を続けると、ストレスや疲労の蓄積によって業務の生産性が下がってしまうおそれがあるからです。
また、従業員の出自や嗜好、育ってきた文化はさまざまです。そうした人材や働き方の多様性の観点からも、企業には有給休暇の適切な活用が求められています。有給休暇制度は、従業員と企業が良い関係を保ち続けるために重要な制度です。
加えて、先述の労働基準法第39条の中には、「企業は従業員の望むタイミングで有給休暇を付与しなければならない」という内容が記載されています。そのため法律上、企業はいかなる事由であったとしても、有給休暇の取得を認めなければなりません。旅行や遊びといったプライベートの行事による休暇はもちろんのこと、特に理由がない場合でも、企業はそれを拒否できません。
有給休暇についてはこちらの記事でも解説しています。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇が付与される日数の計算方法
有給休暇は条件を満たしていれば誰でも取得できますが、労働契約の内容や継続勤務日数などによって付与される日数が異なります。以下の雇用形態に分けて解説します。
- フルタイム
- パート・アルバイト
- 週の所定労働日が定まっていない雇用
有給休暇を取得した日の給与計算方法についてはこちらの記事でも解説しています。
フルタイムで働く労働者の付与日数
正社員のようなフルタイム労働者の場合、雇用開始日から6か月後に10日間の有給休暇が付与されます。1年6か月後には11日、2年6か月後には12日、そして3年6か月後からは年に2日ずつ付与日数が増えます。最大付与日数は6年6か月以上の20日です。その後は勤続年数が増えても、付与日数は20日のままです。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パート・アルバイト労働者の付与日数
1週間において所定労働日数が5日以上、1週間における所定労働時間が30時間以上、1年間における所定労働日数が217日以上の3つの条件のうち、いずれかを満たす場合はフルタイム労働者と同じ条件で有給休暇が付与されます。
| 週所定労働日数 | 1年間の 所定労働日数 |
継続勤務年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | ||
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1週間の所定労働日数が4日以下で、かつ所定労働時間が30時間未満の人の場合、有給休暇がどれだけ付与されるのかは週の所定労働日数や所定労働時間に応じて異なります。上の表に示すように、例えば週1日勤務の人は、半年後に有給休暇が1日付与されます。週2日勤務の人は半年後に3日、週4日勤務だと半年後に7日付与されます。
アルバイトやパート従業員の有給休暇の計算方法について、こちらの記事で解説しています。
週の所定労働日が決まっていない労働者の付与日数
すべての労働者の働く曜日や日数が、あらかじめ決まっているわけではありません。シフト制によって週の所定労働日数が定まっていないパートタイムやアルバイトもいますし、派遣労働者のように、プロジェクトの進行状況に応じて働く日数が決まるケースも考えられます。
これらの場合、6か月間の労働日数を2倍し、それを基に有給休暇の付与日数を算出できます。例えば、6か月間の労働日数が50日であれば、1年間の所定労働日数を100日と算出します。これを先ほどの表と照らし合わせると「1年間の所定労働日数:73~120日」に該当するので、6か月後の有給休暇付与日数は3日、1年6か月後の付与日数は4日になります。
もう1つの算出方法として、前年の労働日数を基準として有給休暇の付与日数を決定することも可能です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇を付与する時期
有給休暇を「誰に・どのくらい」付与するのかを理解できたところで、次に「いつ」付与すべきかについてもぜひ押さえておきましょう。
有給休暇を付与する基準日は雇入れから半年後
労働基準法第39条によって定められた有給休暇の初回付与日は、入社日から半年後です。この基準日まで従業員が一定期間継続して勤務すれば、有給休暇を取得する権利が発生します。
2年目以降は、毎年基準日が有給休暇の付与日です。例えば、4月2日に入社した場合は10月2日が初回の有給休暇付与日となり、その後は毎年10月2日に有給休暇が付与されます。
ただし、企業が自社の裁量で法定の基準日よりも早い日に付与日を設定することは問題ありません。そのため、企業によっては自社で独自の基準日を設け、有給休暇を付与する時季を調整していることもあります。例えば、入社から半年経たない時期にも休みが取れるように、入社日に前倒しで有給休暇を付与するといったケースも存在します。
有給休暇は基準日の統一が可能
基準となる従業員の入社日がばらばらであることは珍しくありません。イレギュラーで月の途中に入社した従業員や、新入社員でも他の従業員と入社月が異なっているといったケースも考えられます。そのような場合、各従業員の基準日を把握しなければならず、管理が複雑になってしまうでしょう。
そこで、労働基準法の規定に比べて従業員にとって有利な条件であれば、従業員に有休を付与する基準日を年1回、もしくは年2回に統一することを認めています。このことを「斉一的取り扱い」といいます。これにより、全従業員の有給休暇の基準日を、年度始めである4月1日に統一することもできます。そうすれば企業側としても管理が簡素化できますし、従業員にとっても有給休暇が付与されるタイミングが明確になります。
なお、付与日を統一する際、あらかじめその旨を就業規則に記載し、労働基準監督署へ届出なければなりません。また、基準日による不公平感をなくすことも大切です。その他、「ダブルトラック」と呼ばれる年5日の取得義務期間が重複する現象にも注意が必要です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇が10日以上の従業員は最低5日取得させるのが義務
企業は従業員の健康と福祉を守るために、有給休暇の取得を促進する責任を負っています。仮に「何らかの理由によって、有給休暇が付与されているにもかかわらず従業員がそれを取得しなかった」ということがあったとします。この場合、企業はそれを従業員の責任にすることはできません。
理由としては、労働基準法第39条において、有給休暇の付与日数が年間10日以上の従業員に対しては、企業は「使用者による時季指定」か「労働者自らの請求・取得」あるいは「計画年休」のいずれかの方法で最低5日間の有給休暇を取得させる義務があることを定めているからです。
つまり、従業員が有給休暇を取得しなかった場合、罰せられるのは従業員ではなく雇用している側の企業が対象となります。このような規定があるのは、従業員が適切に休息を取る期間を確保するためです。この年5日の有給休暇取得義務は、2018年の法改正によって定められ、2019年より施行されました。注目すべきポイントは、この法律には罰則が伴うことです。企業がこの義務を怠った場合、違反者1人当たり最大30万円の罰金を支払わなければなりません。
法律違反を回避する方法としては、有休の取得を推進する環境づくりや計画年休制度の活用、勤怠管理システムの利用などがあげられます。特に、従業員が無理なく休めるような職場環境を整えることが非常に重要です。具体的には適正な人員配置や業務量の管理、業務の属人化の解消などに取り組む必要があります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇は「計画的付与」で取得日を決めることも可能
有給休暇の取得は従業員の権利です。そのため「いつ・どの時期」に取得するのかは、従業員の意思に委ねられます。その一方で、自由設定であるがゆえに、有給休暇の取得がなかなか進まないという課題があります。
そこで活用できるのが、計画的付与制度です。「計画年休」とも呼ばれる制度で、労働基準法第39条第6項でも定められているとおり、企業側が年次有給休暇のうち5日を除いた日数を事前に取得日として設定できます。従業員が有給休暇をより取得しやすくすることを目的に設定されています。
ただし、計画付与を行う場合には、企業と従業員の代表(労働組合など)が協定を結ばなければなりません。企業はこの協定に基づいて事前に有給休暇の取得日を計画し、従業員に通知します。計画的付与には、企業単位で取得する方法(一斉付与方式)とチーム単位で取得する方法(交替制付与方式)、個人単位で取得する方法(個人別付与方式)の3種類があります。
一斉付与方式は、企業の従業員全員で有休を取る方式です。この方式は社内的には有給休暇ですが、社外的にはその会社の休日になります。工場のように全従業員を一斉に休ませられる企業で多く採用されています。
交替制付与方式は、企業のなかの部署や班、チーム単位で有休を取得する方法です。流通業や小売業のように企業全体で休日を設けるのが難しい企業や、社内の組織ごとに業務の繁閑の差が大きい企業に向いています。
個人別付与方式は、従業員個人が企業と相談して有休を取得する方法です。仕事に追われてなかなか有給休暇を取得できないという従業員も、この制度を利用すれば計画的に休暇を取得できます。また、企業側も事前に休暇スケジュールを把握できるため、業務の調整がしやすくなります。
ただし、計画的付与の対象とする日数が多くなるということは、従業員自身が希望する時期に取得できる有給休暇の日数が少なくなるということです。そのため、計画的付与制度の導入が従業員の不満につながる可能性もあるので注意が必要です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇を付与する際の注意点
有給休暇の繰り越しや付与要件に係る出勤率についての考え方、さらに育児・介護休業中の取り扱いなど付与する際に把握しておくべきポイントをまとめました。
未消化の有給休暇は翌年度に繰り越しできる
労働基準法第115条にあるとおり、有給休暇が何らかの理由で取得できなかった場合、残りの日数は翌年度に繰り越せます。ただし、有給休暇の有効期限は2年間です。これを過ぎると時効となり消滅してしまいます。
例えば、2023年4月1日に付与された有給休暇が20日間と仮定します。これを2023年度中に消化しきれず「8日間(★)」残ったとすると、翌年度(2024年度)は、新たな有休「20日間(☆)」と併せて休みが「28日間(★+☆)」取得できることとなります。
しかし、2024年度中はなかなか休めず「5日間」しか取得できませんでした。そうすると、有休は★の部分が「8日間−5日間」で3日、☆はまったく取得していないので20日間残ります。この時点で★の3日分は有効期限を迎えるので消滅します。そして、2025年度の有給休暇は、☆の20日間と新たな20日間を併せて「40日間」となるのです。
ただし、企業によって有効期限を2年以上に設定するなど独自の規則を設定している場合もあるので確認しておくことが重要です。
有給休暇繰越について、こちらの記事で解説しています。
出勤率が8割未満の年も継続勤務年数に含まれる
労働基準法が定めている有給休暇の付与要件として、継続勤務年数と出勤率があります。継続勤務年数とは、従業員が同じ企業で働き続けた年数のことです。継続勤務年数に出勤率は関係ありません。仮に出勤率が8割未満の年があったとしても、その年も継続勤務年数に含まれます。
有給休暇が付与される要件には、直近1年間の出勤率が8割を超えることが求められます。例えば、初年度の出勤率が8割に満たない従業員がいた場合、企業は2年目にその従業員に有給休暇を付与する義務はありません。ただし、出勤率が8割に満たない年があっても、その年が継続勤務年数から除外されるわけではありません。2年目の出勤率が8割以上であれば、企業はその従業員に対し、3年目には「勤続年数3年以上」に相当する日数の有給を付与する必要があります。
反対のケースとして、初年度の出勤率が8割以上で、2年目の出勤率が8割未満だった場合、初年度には入社から6か月経過後に10日間の有給休暇が付与されますが、2年目は出勤率が8割未満のため、有給休暇の付与はありません。ただし、1年目に付与された有給休暇の繰り越し分は引き続き使用できます。
3年目の有休については、直近1年間の出勤率が8割以上の場合、2年目の出勤率が8割未満であっても「勤続年数3年以上」に相当する日数の有給休暇が付与されます。しかし、直近1年間の出勤率が8割未満の場合、3年目の有給休暇は付与されません。
育児・介護休業中の労働者も全日出勤したとみなす
育児・介護休業中であっても、出勤日に含まれます。これは、労働基準法第39条第8項において、育児休業や介護休業を取得した期間について、年次有給休暇の発生要件である出勤率の算定において「出勤したもの」として扱うことが規定されているからです。
これにより、育児休業や介護休業中の従業員も、出勤率の計算上では出勤しているとみなされます。育児・介護休業によって出勤率が低下することはありませんし、有休がとりづらくなるわけでもありません。育児休業や介護休業を取得していても、その期間を含めた出勤率が8割を超えていれば年次有給休暇が付与されます。
例えば、フルタイムの従業員が入社3年目で育児休業を1年間取得したと仮定します。その従業員が入社4年目で復帰したときに付与される有給休暇の日数は、入社から3年6か月後にあたる14日間です。育児休業をしていた1年間がカウントされないということはありません。
しかし、育児休業や介護休業を取得する場合、いつでも好きなタイミングで有休が付与されるわけではないため注意が必要です。例えば、育児休業や介護休業の申出後に、その期間中の日について年次有給休暇を請求することはできません。ただし、育児休業や介護休業の申出前にあらかじめ有給休暇の計画付与などが行われていた場合には、先に年次有給休暇を取得したものとみなされます。そのため、企業は育児休業や介護休業の期間中であっても該当する日に対して賃金を支払う必要があります。
有給休暇管理簿の作成が必要となる
従業員の有給休暇を記録するのが年次有給休暇管理簿です。労働基準法施行規則第24条の7に基づき、企業は従業員ごとに有給休暇管理簿を作成し、管理しなければなりません。年間で有休を10日より多く付与される従業員すべてを対象として作成される必要があります。管理簿は、紙でもエクセルや勤怠管理ソフトなどでもかまいません。
この管理簿に記載する情報は、「付与日・取得日数・取得時期」の3つです。
付与日とは、有給休暇が付与された日付を指します。従業員が有休休暇を使用する日ではないので注意しましょう。同じ年度内で有休が2回付与されるようなケースでは、それぞれの日付を個別に記載する必要があります。
取得日数は、従業員が実際に取得した有給休暇の日数です。前年度からの繰り越しがある場合には、繰越日数とその合計数も管理簿に記載します。また、従業員が有休を使用した場合には、その都度使用した日数を差し引いた残日数を管理簿に記載します。有休が半日だった場合には「0.5」と記載しても問題ありません。
また、年内に基準日が2回訪れる従業員の場合には、1回目と2回目の付与日それぞれに対して取得日数を記載する必要があります。これは、残っている有休の時効日をわかりやすくするためです。
取得時期は、有給休暇を取得した具体的な日付です。時季と呼ぶこともあります。従業員が有休を消化すると、その都度取得した日付を記載します。記載するのは従業員が希望して使用した日付だけではなく、計画的付与などで企業側が有休取得日を決定した場合の日付も書き込みます。
この有給休暇管理簿は、有給休暇の付与している期間と満了後3年間は保存することが義務付けられています。これは、労働基準法の規定により、企業が従業員の有給休暇の管理を適切に行うための措置です。書式に明確な決まりはなく、労働基準法施行規則第55条の2では労働者名簿や賃金台帳と併せて作成することも可能であるとされています。そのため、これら3つの書類をまとめて作成すると効率的です。
ちなみに、有給休暇管理簿の作成と保存は義務付けられてはいるものの、違反した場合の罰則は明確には定められていません。しかし、適切な管理を行わないと、労働基準監督署からの指導や是正勧告を受ける可能性があります。
また、有休取得に関するトラブルを予防する効果もあります。企業は適切な管理によって従業員の権利を守り、コンプライアンスを確保することが大切です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
付与した有給休暇の使用期限
労働基準法第115条により、有給休暇の使用期限は付与日より2年間と定められています。従業員がこの2年の期間内に有給休暇を消化しなかった場合、その有給休暇は消滅してしまいます。つまり、2年を過ぎるとその有給休暇は無効となり、もう取得できなくなるわけです。
ただし、先述したように、有給休暇は繰り越すことが可能です。例えば、1年目に付与された有給休暇が10日間あり、そのうち5日間を使用しなかった場合、残りの5日間は2年目に繰り越されます。しかし、繰り越された有給休暇も2年以内に消化しなければ消滅します。具体的には、2024年4月1日に10日間の有給休暇が付与された場合、その有給休暇は2026年3月31日までに使用しなければなりません。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇の最大付与日数
解説したように有給休暇の付与日数は、勤続年数や週の所定労働日数に応じて決まります。労働基準法で定められた最大付与日数は20日です。そのため、6年6か月以上継続勤務した場合でも、付与される有給休暇の日数は20日になります。
また、企業は従業員に最低5日間の有給休暇を取得させる必要があります。そのため、消化しなかった有給休暇は翌年に繰り越せるものの、実質的に繰り越せるのは最大で15日間となります。したがって、6年6か月以上継続勤務した場合の最大保有日数は、新たに発生する20日と合算して「35日間」になります。
ただし、労働基準法が定めているのは、あくまでも最低基準である点に注意が必要です。企業が自社の判断でこれよりも多くの有給日数を従業員に与えることは何の問題もありません。そのため、福利厚生の一環として企業が自社の裁量でより多くの有給休暇を従業員に付与することは可能です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
従業員の有給休暇は買取できる?
有給休暇の買い取りは労働基準法で禁止されています。これは、有給休暇をお金で買い取ることが従業員の休息の機会を奪うことになるためです。1955年(昭和30年)11月30日に示達された行政解釈でも、年次有給休暇の買上げは労働基準法第39条の違反とされています。
有給休暇は、従業員が心身のリフレッシュを図るための重要な権利です。それを金銭で代替することは、制度の趣旨に反します。また、未消化の年次有給休暇の買い取りを認めてしまうと、従業員は金銭を得るために有給休暇を取得しなくなる可能性があります。これによって、有給休暇の取得促進が阻害されるおそれがあります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇の買取が可能な例外パターン
原則として企業による有給休暇の買い取りは認められていないものの、例外的に有給休暇を買い取ることが認められるケースがあります。いくつかの例外パターンについて取り上げます。
労働基準法の最低限の付与日数を超えて付与している場合
企業によっては、有給休暇とは別に慶弔休暇やリフレッシュ休暇、誕生日休暇、夏季休暇などの名目で法定外の有給休暇を設けていることがあります。このような法定を超える日数の有給休暇の場合、企業が買い取ることが可能です。
例えば、6年6か月勤務している従業員の法定付与日数は20日ですが、その他の名目で合計25日間の有給休暇を付与している場合、企業は5日分の有給休暇を買い取れます。
理由としては、法定を超える有給休暇は企業が自主的に付与するものであり、買い取りが行われても従業員の利益を損なうことにはならないと考えられるためです。また、企業は法定を超える有給休暇を付与することで、従業員のモチベーション向上や福利厚生の充実を図っています。そのため、法定を超える部分の扱いについては、企業の裁量に任せられているというわけです。
有給休暇の使用の時効を経過した場合
労働基準法第115条により、有給休暇には付与された日を起点に2年間の使用期限があります。この期間内に消化しなかった有給休暇は、時効によって権利が消滅します。そこで、2年の使用期限を過ぎてしまった有給休暇であれば、企業による買い取りが認められています。これは、時効を迎えた有給休暇はすでに権利が消滅しており、従業員がその有給休暇を利用できないためです。利用できない有給休暇を企業が買い取ったとしても、それで従業員の権利を侵害したことにはなりません。
また、時効を迎えた有給休暇を買い取ることは、従業員の利益保護にもつながります。従業員は未消化の有給休暇に対する金銭的な補償を受けられるからです。重要なポイントは「有給休暇の買い取りが従業員にとって不利益になるか」という点です。
退職の際に未消化の有給休暇がある場合
退職の際に未消化の有給休暇がある場合、企業はその従業員の有給休暇を買い取れます。例えば、退職日までに10日間の有給休暇が残っている場合、企業はその10日分の有給休暇を金銭で買い取れます。これは、従業員が退職すると有給休暇を取得する権利を失い、行使できなくなるからです。未消化の有給休暇を買い取ることは、従業員にとっても企業にとっても合理的な選択となります。また、退職時に未消化の有給休暇を買い取ることで、従業員は企業から金銭的な補償を受けることができます。
ただし、企業には退職する従業員の有給休暇を買い取る義務があるわけではありませんし、有給休暇の買い取り請求は従業員の権利ではありません。そのため、退職時に未消化の有給休暇分の買い取りが発生しないケースもあります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇を付与しなかった場合の罰則
繰り返しになりますが、従業員が有給休暇を取得しなかった場合、その責任は雇用している企業の側が問われます。違反した場合に具体的にどのような罰則があるのかについて詳しく解説します。
従業員が年5日の年次有給休暇を取得しないと「30万円以下の罰金」
労働基準法には、10日よりも多い有給休暇が付与される従業員には、毎年5日間の有給休暇を確実に取得させなければならないということを定めています。この義務は、従業員が有給休暇を取得しやすい環境を整えるためのものです。
企業がこの義務を怠った場合、労働基準法第120条に基づいて30万円以下の罰金が科されます。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
引用:e-Gov「労働基準法」
注意すべきポイントは、罰金は取得義務の対象となる従業員一人当たりで発生するということです。例えば、10人の従業員が年5日の有給休暇を取得しなかった場合、罰金は最大で300万円(30万円×10人)になる可能性があります。
従業員に所定の有給休暇を付与しなかった場合は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
企業が従業員に対して付与すべき有給休暇の日数は、勤務日数や出勤率によってあらかじめ定められています。これにもかかわらず、有給休暇を付与する義務を怠った場合、労働基準法第119条によって企業には罰則が科されます。
次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
引用:e-Gov「労働基準法」
この罰則は、違反した従業員1人につき1罪として適用されます。そのため、複数の従業員が対象となる場合、罰金も増額します。例えば、100人の従業員に対して有給休暇を付与しなかった場合、罰金は最大で3,000万円(30万円×100人)になる可能性があります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
有給休暇の付与について理解を深めてトラブルを未然に防ごう
有給休暇は、条件を満たしていればどのような労働契約の従業員にも付与されます。ただし、付与日数は勤務日数や出勤率によって異なるため、しっかりと確認しておきましょう。また、有給休暇の確実な取得は、従業員ではなく企業の義務です。制度についてきちんと理解しておきましょう。
従業員の有給休暇の管理には、勤怠管理システムの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は、有給休暇5日以上取得義務などの法改正に無料かつ自動で対応するため、システム上で簡単に管理できます。自社にあったツールを活用して業務の効率化を目指しましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者下川めぐみ(社会保険労務士)
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ所属社労士。
医療機関、年金事務所等での勤務の後、現職にて、社会保険労務士業務に従事。







