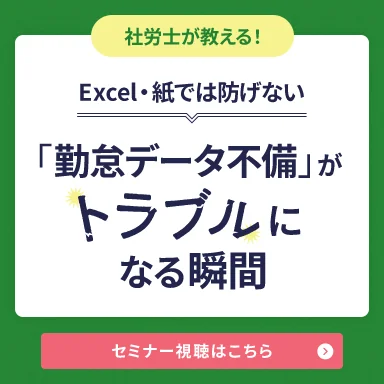勤怠管理をICカードで行うメリット・デメリット・導入時のポイント
更新

働き方の多様化が進む中、勤怠管理の方法にも柔軟性と精度が求められています。こうした背景を受け、近年ではICカードを活用した勤怠管理システムが注目を集めています。
ICカードによる打刻は、正確に勤怠データを記録するだけでなく、不正防止や業務効率化、コスト削減にもつながります。その一方で、導入や運用に際しては、いくつかの事前準備も必要です。
本記事では、ICカードで勤怠管理をするメリット・デメリット、導入時のポイントをわかりやすく解説します。給与計算と連携できるクラウド型システムもご紹介しますので、これから勤怠管理を見直したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
勤怠管理をICカードで行うメリット
ICカードによる勤怠管理を導入するには、まずどのようなメリットがあるのかを理解することが大切です。
だれでも使いやすく導入がしやすい
ICカードを活用した勤怠管理の魅力は、導入の手軽さと操作の簡便さにあります。企業は、ICカード対応の勤怠管理システムと、ICカードリーダー機能を備えたタイムレコーダーを用意するだけで、すぐに運用を開始できます。
操作も直感的で、機械の扱いに不慣れな従業員でもすぐに利用可能です。また、既に社員証や交通系ICカードを持っている場合、新たなカードの発行が不要なケースも多く、導入時の負担を軽減できます。
さらに、ICカードは勤怠打刻だけでなく、オフィスの入退室管理やプリンターの利用制限など、さまざまな社内セキュリティ機能との連携が可能です。既存のICカードの活用範囲を広げることで、社内全体の業務効率化にもつながります。
打刻ミス・不正打刻を防止しやすい
ICカードによる勤怠打刻は、従業員がそれぞれ自身のカードを使って打刻を行うため、正確かつ信頼できるデータを保持しやすいのが特徴です。
従来の手書きや手入力による勤怠管理では、「記入漏れ」「誤入力」「時間の読み間違い」など、さまざまなヒューマンエラーが発生しやすく、担当者による確認作業の負担も少なくありませんでした。ICカードを使えば、カードを専用のリーダーにかざすだけで、出退勤の記録がデジタルデータで自動保存されるだけでなく、給与計算ソフトに自動で連携できるものまであります。また、万が一カードを紛失した場合でも、設定を解除すればそのカードは使用できなくなるため、不正利用のリスクも抑えられます。
また、不正打刻や記録の改ざんは、勤怠管理だけでなく、その後の給与計算や労働時間の集計にも影響します。企業にとって、勤怠データの信頼性を高めることは、労務トラブルの予防にもつながる重要な要素です。
給与計算と連携ができる
ICカードによる勤怠管理は、給与計算や労務管理のシステムと連携できる点も大きなメリットです。
従来、タイムカードや紙の出勤簿を使用していた場合、総務・経理担当者が勤怠情報を毎月手作業で集計・転記する必要がありました。この方法では、多くの時間と労力を要するうえ、人為的なミスが発生するリスクも避けられません。
ICカードを活用すれば、打刻データはリアルタイムで給与計算や労務管理のシステムに反映され、自動で集計されます。特に給与計算では連携することで、勤怠データをそのまま活用し、正確かつ迅速に給与を算出できます。
これにより、集計ミスを防げるだけでなく、月末や締め日前の業務負担も大幅に軽減。ルーティン業務の効率化が進むことで、担当者の残業削減や、より付加価値の高い業務へのリソース配分にもつなげることができます。
コスト削減につながる
ICカードを活用した勤怠管理は、業務効率の向上に加え、コスト面でも大きなメリットがあります。紙のタイムカードや出勤簿による運用では、用紙代や印刷代、保管スペースの確保など、継続的なコストが発生していました。
ICカードに移行すれば、勤怠情報はすべてデジタルデータで一元管理され、印刷やファイリングの作業が不要になります。クラウド型システムを活用することで、リアルタイムのデータ確認や場所を問わない運用も可能となり、管理業務全体の効率化とペーパーレス化を実現できます。
また、多くの企業では、既に社員証や交通系ICカードである、SUICAやPASUMO等を従業員が保有していれば、新たに専用カードを用意する必要がない場合もあります。これにより、導入時の初期コストを抑えられるのも利点です。
さらに、打刻データは自動でシステムに蓄積されるため、担当者による集計作業の負担も大幅に軽減できます。ICカードリーダーや対応システムの導入コストも比較的安価であるため、初期投資を抑えつつ、効率的な勤怠管理が可能です。
交通費精算にも活用できる
交通系ICカードを勤怠管理に活用することで、交通費精算(会社と往復のための通勤費や業務上の外出等で移動する際の交通費)の作業が削減されます。
カードに記録された乗車履歴をそのまま使用できるため、手入力の手間や確認作業を行う必要がありません。従来は、従業員が申請書に利用区間や金額を記入し、担当者が内容を確認・承認する方法が一般的でしたが、このプロセスには、記入ミスや虚偽申請といったリスクを伴います。
交通ICカードを勤怠管理に活用すると、勤怠打刻と交通費精算が同じカードで完結するため、申請内容の整合性を保ちやすく、不正などが起きにくく、正確性と透明性の向上にもつながります。
さらに、勤怠情報と交通費データをシステム上で一元管理できるため、バックオフィス業務全体の効率化にも寄与します。
セキュリティ面でも活用できる
勤怠管理と同様に、社員のICカードをオフィスの入退室管理に連動させることで、「いつ」「だれが」出入りしたのかを正確に記録できます。ICカードは勤怠だけでなく、オフィス全体のセキュリティ向上にも活用できるツールです。
例えば、入退室履歴を基に、最初に出社した従業員や最後に退室した従業員の情報を管理者へ自動通知するしくみを導入すれば、不正アクセスや異常事態の早期発見に役立ちます。
また、ICカード連動型のセキュリティシステムの中には、ドアが一定時間開いたままの状態が続くと、警備会社に自動で通報される機能を備えたものもあります。こうした仕組みにより、従業員が安心して働ける環境を整えながら、情報漏えいや不審者の侵入といったリスクの低減も実現できます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理をICカードで行うデメリット
ICカードを活用した勤怠管理には多くのメリットがある一方で、いくつかの留意すべきデメリットも存在します。
ICカードの紛失・盗難のリスクがある
ICカードを勤怠管理に使用する場合、従業員が個別にカードを所持・管理するため、「紛失」「置き忘れ」「盗難」といったリスクは常に付きまといます。
カードを紛失すると、勤怠打刻ができなくなるだけでなく、カード情報の無効化や、新しいカードの発行・登録といった対応が必要です。システム上から設定を解除すれば不正利用のリスクはある程度抑えられますが、紛失・盗難の可能性そのものをなくすことはできません。また、こうしたトラブルが発生した際には、バックオフィス担当者の業務負担が一時的に増えるケースもあります。
このようなリスクを最小限に抑えるためには、紛失・盗難時の対応フローをあらかじめマニュアル化しておくことが重要です。例えば、「紛失時の報告ルール」や「再発行までの一時的な打刻方法」などを明確にしておくことで、スムーズな対応が可能になります。
さらに、従業員に対してカード管理の重要性を周知し、「自己管理の責任がある」という意識を持たせることも、紛失防止の観点から有効です。
ICカードの貸し借りができてしまう
ICカードを利用した勤怠管理では、基本的に個人ごとの打刻が前提です。しかし、カードが物理的に貸し借りできるものである以上、「代理打刻」などの不正が起きる可能性はゼロではありません。
代理での打刻は、勤怠記録の正確性を損ない、労務管理や給与計算に影響を及ぼします。防止策としては、ICカードの貸与・共有を禁止する明確なルールを定め、それを全従業員に周知することが重要です。
不正打刻が発覚した際の対応フローや就業規則に懲戒処分のルールを整備すると、リスク管理を徹底しやすくなります。ICカードの利便性を活かすためにも、運用面でのルールづくりと意識付けが欠かせません。
リモートワークでは不向きな場合もある
リモートワークや営業等の外回りが多い職種だと、ICカードを利用した勤怠管理との相性が悪い場合があります。ICカードをタイムカードとして利用する場合、オフィス内に専用のICカードリーダーを設置し、出社時に打刻するスタイルが一般的です。
しかし、出勤・退勤をオフィスで行う勤務形態でない場合、こうした運用方法をそのまま適用するのは困難です。オフィス内の設置はもちろん、タブレットやスマホをICカードリーダー代わりに使用できる環境を整える必要があります。
すなわちリモートワークの実施状況や勤務スタイルに応じて、モバイル対応の打刻方法や、ICカードに代わる別の打刻手段を組み合わせるなど、柔軟な運用体制が求められます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
ICカードで行う勤怠管理が企業にとって重要な理由
企業が従業員の就業状況を正確に把握することは、法令遵守の観点はもちろん、健全な組織運営を維持するうえでも不可欠です。その根拠となる代表的な法令には、以下のようなものがあります。
- 労働基準法第32条では、「法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を超えて労働させてはならない」と定められており、これを守るには日々の勤怠を正しく管理する必要があります。
- 労働基準法第108条では、使用者に対して賃金台帳の作成と、労働時間の記録が義務付けられています。管理には、客観的なデータに基づいた記録が必要です。
-
参照:厚生労働省「労働基準法について」
参照:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために」
紙の出勤簿や、Excelでの自己申告による勤怠管理だけでは、法令上の要件を満たせない可能性があります。実際に、厚生労働省もタイムカードやコンピューターのログ、ICカードなどを用いた客観的な勤怠管理を推奨しております。
ICカードを使った勤怠管理は、個人の出退勤記録がデータとして自動で残るため、改ざんや記録漏れのリスクを大幅に軽減できます。
なお、法定労働時間を超えて労働させる場合は、労使間で「36協定」を締結する必要があります。
36協定について詳しくは、以下の記事で解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理で使われるICカードの種類
勤怠管理におけるICカードの規格でよく使われるのは、「FeliCa(フェリカ)」と「Mifare(マイフェア)」です。
FeliCa(フェリカ)
FeliCa(フェリカ)は、ソニー株式会社が開発した非接触型ICカードの規格です。Suica(スイカ)やPASMO(パスモ)といった交通系ICカードを始め、おサイフケータイなどにも利用されています。
FeliCa対応のシステムであれば、既存の交通系ICカードをそのまま打刻用カードとして利用できます。暗号化技術やアクセス制御機能など、セキュリティ面で優れているのも大きな特徴です。
その一方で、Mifareなど他のICカード規格と比べると、カード単体のコストがやや高めです。
Mifare(マイフェア)
Mifare(マイフェア)は、オランダのNXPセミコンダクターズ社(旧フィリップス社半導体部門)が開発した非接触型ICカードの規格で、世界的に広く普及しています。日本国内では、Taspo(成人識別ICカード)や一部の社員証などで採用されています。
FeliCaと比較すると、カード自体の価格が安価であり、初期費用を抑えて導入しやすいのがメリットです。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
ICカードで行う勤怠管理システム導入時のポイント
システムをスムーズに導入し、より効果的に活用するには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
セキュリティ対策をする
ICカード(特に交通系ICカード)には、個人を特定できる情報やクレジット決済情報が含まれる場合があるため、セキュリティ対策は欠かせません。対策が不十分なまま運用を行うと、外部からの不正アクセスやデータ漏えいといったリスクを招く可能性があります。
こうしたリスクを低減する方法の1つが、ICカードに加えて別の認証手段を併用することです。近年では、生体認証を取り入れた打刻方式が注目されており、指紋認証・顔認証・静脈認証など、従業員本人の身体的特徴を用いた認証によって、なりすましやカードの貸し借りといった不正行為を防ぎやすくなります。
導入を検討する際は、システムにどのようなセキュリティ機能が備わっているか、またトラブル発生時の対応体制が整っているかといった点も、事前に確認しておくことが重要です。
運用ルールやマニュアルを整えておく
ICカードを使った勤怠管理は、操作がシンプルで導入しやすい一方、実運用ではルールづくりや体制整備が求められます。例えば、カードの紛失・盗難時の対応手順や、リモートワーク・外出先での打刻方法など、さまざまな状況を想定したマニュアルの整備が必要です。
また、新しいシステムを導入する際は、社内からの問い合わせが生じることも少なくありません。スムーズな運用を実現するためには、対応できる体制を整えることが重要です。社内にヘ相談窓口であるへルプデスクを設置する、またはサポート体制が充実したサービスを選定するなど、導入後の支援体制をあらかじめ検討しておくとよいでしょう。
外部システムとの連携を考える
他の業務システムとの連携も視野に入れておくことが重要です。例えば、給与計算システムと連携することで、打刻データを労働時間や残業時間として自動で反映でき、月次の集計や手入力の手間を大幅に削減できます。
弥生のクラウド給与サービスのように、勤怠データをスムーズに取り込める機能を備えたシステムであれば、バックオフィス業務全体の効率化だけでなく、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理は、客観性が大切!ICカードを活用しよう
勤怠管理は、法令を遵守し、従業員の労働状況を適切に把握するために欠かせない業務です。勤怠管理にICカードを活用すれば、客観的な記録が残るだけでなく、打刻ミスや不正の防止、業務効率化、コスト削減といった多くのメリットがあります。 しかし、ICカードの紛失や貸し借りなどの課題もあるため、導入時にはルール整備やセキュリティ対策を万全に行うのが大切です。
「弥生給与 Next」はICカードでの勤怠打刻に対応しています。各種交通系のFeliCaカード(Suica・PASMO・Edy)に加え、社員証やtaspoなどに使用されるMIFAREなども勤怠管理に使用できるため初期コストを低く抑えられます。自社の働き方や管理体制に合った方法を検討し、勤怠管理の精度向上につなげましょう。
- ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。