36協定の特別条項とは?上限時間を超えた場合の罰則や記載例も徹底解説
更新
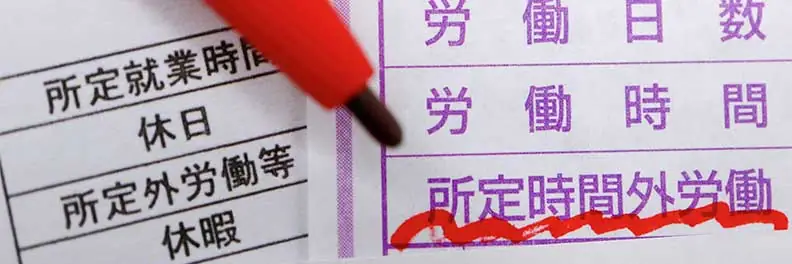
36協定を締結することで、法定労働時間を超えて業務を行うことが認められます。また、さらに「特別条項」を定めることで、繁忙期など特別な状況に応じた対応も可能となります。
本記事では、特別条項の基本的な内容や、協定の締結、従業員への周知、労働基準監督署への届け出、時間外労働時間の制限や労働者の健康確保措置について取り上げます。また、特別条項付き36協定の作成・記入方法についてもご紹介します。正しく協定を締結することで、法令を遵守しつつ、従業員の健康と労務管理のバランスを取った働き方を実現しましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
36協定の特別条項とは
36協定の特別条項とは、臨時的で特別な事情に対応するために、時間外労働の上限を一時的に超えることを認める労使間の取り決めです。
通常、法定労働時間は1日8時間・週40時間を上限としています。これを超える時間外労働を行うためには、労使間で36協定の締結が必要です。2019年4月の働き方改革関連法の施行で、時間外労働の上限が法制化されており、一般業種においては元からあった上限内容がさらに細かく制限されました。36協定では「1か月45時間・1年360時間」という上限が定められています。
そのうえで、業務量が急増するなどの臨時的な事情が生じた場合には、36協定の特別条項に基づき、時間外労働の上限を超えて労働させることが可能です。ただし、2019年4月の働き方改革関連法の施行により、時間外労働に関する規制が強化されているため、特別条項の適用には慎重な運用が求められます。特別条項を適用する際には、法律の範囲を超えないように遵守する必要があり、違反すると罰則が科されることがあります。
36協定の一般条項に基づき時間外労働を命じる場合、労働者にはその理由を明示し、業務上の必要性や臨時的な事情があることを確認する必要があります。
その一方で、特別条項は、一般条項の制限を超えて時間外労働を行う場合に適用されます。特別条項を利用するには、業務量の急増や予期せぬ事情など、特別な理由が必要であり、単なる繁忙を理由に適用することはできません。特別条項を適用する際には、その理由と条件を厳守し、法令に従って運用することが重要です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
36協定の特別条項の内容
特別条項を定める際には、以下の内容を明記する必要があります。これらは一般的な特別条項の内容であり、各会社(使用者)はより具体的に条件を明記します。
-
①1か月の時間外労働と休日労働の合計時間数|上限は月100時間未満:時間外労働と休日労働の内訳を記載することも可能です。
-
②1年の時間外労働の時間数|上限は720時間以内:休日労働の時間数は含まれません。
-
③限度時間の超過が認められる回数|年6回以内:1か月45時間を超える時間外労働は6回以内、つまり6か月までに制限します。
-
④限度時間の超過が認められる場合|個別具体的に:特別なプロジェクトによる繁忙業務など、具体的な状況を明記する必要があります。
-
⑤限度時間を超過した労働者への健康福祉確保措置|限度を超えた労働が避けられない場合、労働者の健康を守るための具体的な対策を講じる必要があります。
-
⑥限度時間を超過した労働にかかる割増賃金率|月60時間までの時間外労働の割増賃金率は25%以上、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
特別条項付き36協定を締結する流れ
協定・制度設計の段階から労働基準監督署への届け出まで、特別条項付き36協定を締結する流れについて詳しく解説します。
STEP1.協定・制度設計を行う
36協定の特別条項を導入する際には、労使間で十分な協議を行い、協定を結ぶ必要があります。
該当する事業場で働くすべての労働者(パートやアルバイトを含む)を対象に、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合は、労働組合と協定を結びます。労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と協定を結びます。その際、協定内容が労働者の健康に配慮した制度設計となるよう心がけることが重要です。
参照:厚生労働省「36協定の適正な締結」
STEP2.特別条項付き36協定を書面で締結する
次に、労働者の代表者と会社(使用者)の間で合意を形成し、書面で締結します。書面による締結は、それぞれの事業場ごとに行われ、労働者の代表者と会社の代表者が共に署名・押印することが原則です。
参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「 36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!」
STEP3.特別条項付き36協定の内容に沿って就業規則を変更する
特別条項付き36協定は、労働時間や賃金、休日など労働条件に直接影響を与えます。そのため、特別条項付き36協定を締結した場合、その内容を就業規則に反映させます(労働基準法第89条)。
常時10人以上の労働者を雇用する事業場では、就業規則を作成し労働基準監督署(以下、労基署)に提出する義務があるので、36協定締結による変更内容を反映させた就業規則を、36協定締結の届け出と共に、労基署へ提出しなければなりません。ただし、協定書の内容を網羅する就業規則である場合は、再提出は不要です。なお、変更後の就業規則の効力発生日については、特別条項付き36協定の効力発生日に併せて行うことが推奨されます。
参照:e-Gov 法令検索「労働基準法第八十九条」
STEP4.労働者に周知する
労働基準法第106条第1項に基づき、特別条項付き36協定やそれに関連する就業規則の変更は、労働者に周知する義務があります。周知の方法としては、就業規則の変更内容をだれでも閲覧することができる作業場に掲示したり、備え付けたりしておくことがあげられます。また、書面の直接交付だけでなく、電子メールや社内ポータルサイトを通じた記録媒体での通知も可能です。これらの手段を駆使し、すべての労働者に確実に変更内容を周知します。
参照:e-Gov 法令検索「労働基準法第百六条」
STEP5.労働基準監督署へ届け出る
特別条項付き36協定の届け出は、効力発生日の前日までに必ず労基署へ提出する必要があります。厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能な「様式第9号の2」を使用してください。この書類は2019年4月以降の新様式に対応しています。
常時10人以上の労働者を雇用していない場合は、就業規則の作成・労基署への届け出は義務ではありませんが、36協定については仮に労働者が1人であっても、残業をする対象である場合は届け出が必要です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
特別条項付き36協定に必要な健康福祉確保措置
新様式における36協定届の特別条項には、労働者の健康と福祉を確保するための措置を記載することが義務付けられています(指針第8条)。以下の健康福祉確保措置の項目から、1つ以上を選択して実施する必要があります。
-
①医師による面接指導:そもそも、労働安全衛生法第66条の8および労働安全衛生規則第52条の2に基づき、会社は従業員が1か月に80時間を超える法定時間外労働を行った場合、従業員の申し出により医師による面接指導を実施する義務があります。したがって、これを上回る健康福祉確保措置、例えば「従業員の申し出」がなくても実施する、80時間でなく60時間で実施する、などの施策を取る必要があります。
-
②深夜労働の回数制限:深夜労働とは22時から5時までの時間を指します(労働基準法第37条第4項 )。深夜労働は、負担が大きいことから、その頻度を制限します。
-
③終業から始業までの休息時間を確保(勤務間インターバル):労働時間等設定改善法第2条第1項により、健康・福祉のために終業から始業までの休息時間を確保することが会社の努力義務とされています。これにより労働者が次の勤務までに十分な休息を取れるようにします。
-
④代償休日・特別な休暇の付与:法定休日には割増賃金が支払われますが、その負担を軽減するために代休や特別休暇を付与します。
-
⑤健康診断:労働安全衛生法第66条に基づき、会社は従業員に対して年に1回の定期健康診断を実施する義務があります。特に勤務日数や時間外労働が多い従業員には、個別の健康診断を実施します。
-
⑥連続休暇の取得:労働者が有給休暇などの連続した休暇を取得できるように支援します。
-
⑦心とからだの相談窓口の設置:労働者が心身の問題について相談できる窓口を設置します。窓口は社内・社外どちらでも構いません。
-
⑧配置転換:労働者の健康状態に応じて、適切な配置転換を行います。
-
⑨産業医等による助言・指導や保健指導:産業医等が労働者に対して助言や指導を行い、健康保持をサポートします。
参照:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
特別条項付き36協定の上限規制を超えた罰則
36協定に違反した場合、所轄の労基署による行政指導が行われますが、場合により刑罰が科される可能性があります。また、罰則を受けるだけでなく企業名が公表され、企業のイメージが損なわれるおそれがあります。
まず、特別条項がない36協定で「月45時間・年360時間」の限度時間を超えた時間外労働を行わせた場合、労働基準法第32条違反です。この場合、行為者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条第1号)、会社には30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第121条第1項)。
また、特別条項付き36協定で定められた上限を超えて、時間外労働や休日労働を行わせた場合は、労働基準法第32条および労働基準法第35条違反です。この場合も、行為者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条第1号)、会社には30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第121条第1項)。
労働基準監督署への届け出を未提出の場合
特別条項付き36協定を締結した後、労基署への届け出が義務付けられています(労働基準法第36条第1項)。36協定を提出せずに、労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、行為者に30万円以下の罰金の対象となります(労働基準法第121条第1項)。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
特別条項付き36協定届の新様式
特別条項付き36協定届は、様式第9号の2を使用して作成し、所轄の労基署に提出します。1枚目は一般条項、2枚目は特別条項に分かれています。2枚目の特別条項には、以下の内容を主に記載します。
-
①臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合
– 業務の種類
– 労働者数(満18歳以上の者)
– 1日の時間外労働時間
– 1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数(100時間未満)+限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率
– 1年の時間外労働時間(720時間以内)+限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率
-
②限度時間を超えて労働させる場合における手続き方法
-
③限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置
参照:厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)様式第9号の2」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
特別条項付き36協定の作成・記入方法
特別条項付き36協定の作成・記入方法にはいくつかの重要なポイントがあります。
まず、臨時的に限度時間を超えて労働を課せる条件を具体的に記載することです。また、1日、1か月、1年の時間外労働時間の上限を記載する必要があります。なお、「1日当たり」の労働時間は特別条項では任意で記載されますが、一般条項では必須となっています。さらに、記入する際に労働者代表の適格性、および上限時間確認のチェックボックスに必ずチェックを入れることを忘れないでください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
特別条項付き36協定の上限規制に違反しないようにしよう
「特別条項」があるからといって、無制限に残業を要請したり休日出勤を求めたりしていいわけではなく、1か月の時間外労働と休日労働の合計時間を100時間未満とするなど、法律の定める範囲に収める必要があります。違反すれば、場合によっては企業名が公表され、深刻な企業イメージのダウンに見舞われます。法令遵守はもちろんのこと、ルールに従った健全な労使関係をつくることを心がけましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。







