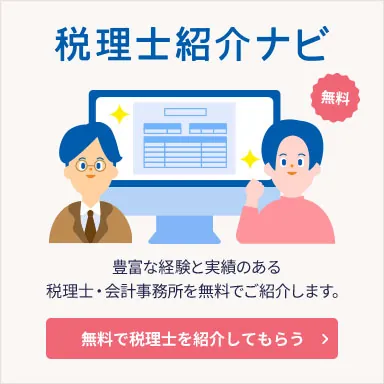給与計算は税理士に依頼する?社労士との違いと選び方を解説
監修者: 高崎 文秀
更新

従業員との労働契約に基づいて正確かつ遅滞なく給与を支払うことは、企業の基本的な責務ですが、給与計算には複雑な計算や法令遵守が求められるため、手間のかかる業務でもあります。
給与計算業務は、自社で行うほかにアウトソーシングすることも可能です。業務を遂行するにあたり特定の資格は必要ありませんが、労務や税務に関する知識が必要となるため、税理士か社労士に依頼するケースが多くなっています。
本記事では、税理士に給与計算を依頼する際の費用相場、税理士と社労士の違いとそれぞれに委託した場合のメリット・デメリットを解説します。また、依頼する税理士・社労士を選ぶポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事
税理士の主な業務とは
税理士の主な業務には、納税者に代わって税務申告をする「税務代理」や、納税者の代わりに必要な書類を作成・提出する「税務書類の作成」のほか、税に関する相談を受ける「税務相談」の3つがあります。決算申告業務や年末調整業務は、原則税理士でなければ代行できません。
社労士との違い
社労士(社会保険労務士)は、労務や社会保険に関連する業務をサポートする専門家です。社労士は、社会保険に関連した書類の「提出代行」をはじめ「社会保険関係書類の作成の代理」、行政機関の調査または処分に対して陳述を行う「事務代理」の3つが独占業務となっており、これらの業務は社労士でなければ代行できません。
給与計算は、特定の資格を必要としません。そのため、税理士と社労士のどちらに依頼することも可能です。ただし上述したように、それぞれの独占業務があります。どちらか一方に依頼先を絞る場合には、税理士と社労士の違いをしっかり把握してから考えるようにしましょう。
給与計算を税理士に依頼するメリット・デメリット
給与計算をアウトソーシングする際は、まず目的をはっきりさせたうえで、税理士と社労士、それぞれのメリットとデメリットを踏まえて検討するようにしましょう。例えば、コスト削減を目指して外部に依頼したにもかかわらず、かえって高額な費用がかかってしまったというケースもあるため注意が必要です。
税理士に依頼するメリット
税理士は税金に関するプロフェッショナルであり、節税や役員報酬など、経営に関する相談にも対応してもらえます。「節税する方法はあるか」「役員報酬の支払形態をどうするべきか」など、自社が抱えるさまざまな問題の解決が期待できます。また、従業員の給与計算から年末調整までを一括で依頼できるため、税処理に関わる負担を一気に減らせるのも大きなメリットです。
税理士に依頼するデメリット
税理士は、社会保険や雇用保険といった労務の相談に対応できません。税金だけでなく労務に関する業務も代行してほしいと考えている場合、税理士だけの依頼では難しくなります。また、年末調整などの業務も含め、税務関係のすべての業務を委託する場合、高額な費用を必要とするケースも少なくありません。
給与計算を社労士に依頼するメリット・デメリット
社労士に給与計算を依頼する際も、複数のメリットとデメリットがあります。自社の現状を考慮したうえで、適切に判断することが大切です。
社労士に依頼するメリット
社労士に給与計算を依頼した場合には、給与計算以外の労務や社会保険の業務も委任できます。具体的には、労働保険料申告・入退社の手続き・賞与支払届などの業務を依頼できます。特に、労務関係の手続きに詳しい人材が不足している企業にとっては大きなメリットです。
社労士に依頼するデメリット
社労士は、税務業務が行えません。税務書類の作成や税務相談、税務代理は税理士の独占業務に該当します。そのため、給与計算と一緒に年末調整のアウトソーシングも依頼したいと考えている場合、社労士によるアウトソーシングがデメリットになるかもしれません。
年末調整は、1年の所得が確定した時点で正確な所得税額を算定し、過不足を調整するために行う手続きであり、税金に関する業務は社労士の業務範囲に含まれていません。年末調整を別途税理士に依頼すると、コストが膨らんだり作業が煩雑になったりする可能性があります。税務に関する業務を社労士が行った場合、違法となるケースもあるため注意が必要です。
給与計算を税理士・社労士に依頼する際の費用相場
給与計算を税理士に依頼する場合と社労士に依頼する場合では、必要な費用にも違いがあります。一概にどちらへ依頼すべきとは言い切れないため、自社の状況とニーズにあわせて選択するようにしましょう。どちらへ依頼する場合でも「月額費用+単価×従業員数」で費用が決まるため、規模の大きい企業ほど費用は高くなります。
自社の人数にあわせて依頼先を選択するのも、ひとつの方法かもしれません。
税理士の費用相場
税理士に給与計算を依頼する場合の基本料は約10,000円、従業員数の単価は500円~1,000円程度が相場です。このほかに、従業員1人あたり1,000円~2,000円ほど初期設定費用がかかるケースもあります。確定申告・年末調調整・賞与の計算などはオプションになるケースが一般的であり、この場合1人あたりにかかる費用は800円~1,200円程度が相場です。多くの事務所では、依頼する業務が増えると費用が加算される仕組みを採用しています。
| 従業員数 | 費用の相場(月額) |
|---|---|
| ~10人 | 10,000円~20,000円 |
| 11人~30人 | 20,000円~35,000円 |
| 30人~50人 | 35,000円~55,000円 |
| 51人~ | 55,000円~ |
社労士の費用相場
社労士に給与計算を依頼する場合の相場は、基本料金が約10,000円~20,000円、従業員数の単価は500円~1,500円程度です。依頼する社労士によっては、給与明細の作成業務をオプションに設定しているケースもあるため注意が必要です。給与計算の依頼先として社労士を選択する際には、どこまで業務範囲に含まれているのか事前に確認しておくと安心です。なお、就業規則の作成や届出、従業員の入退社手続き、社会保険料変更の手続きなどを労務関係の業務を依頼する際は、別途費用がかかります。
| 従業員数 | 費用の相場(月額) |
|---|---|
| ~10人 | 10,000円~25,000円 |
| 11人~30人 | 25,000円~35,000円 |
| 30人~50人 | 35,000円~50,000円 |
| 51人~ | 50,000円~ |
給与計算を税理士・社労士に依頼する場合の選び方
給与計算を外部へ依頼する際は、以下のポイントを踏まえたうえでどちらを選択すべきか慎重に検討しましょう。
税理士に依頼した方が良いケース
- 年末調整の代行を依頼したいとき
- 役員報酬を決めるとき
- 会社を設立したばかりのとき
社労士に依頼した方が良いケース
- 従業員数が増えてきたとき
税理士に依頼した方が良いケース
税理士に依頼した方が良いケースは、以下の3ケースです。
- 年末調整の代行を依頼したいとき
- 役員報酬を決めるとき
- 会社を設立したばかりのとき
年末調整の代行を依頼したいとき
給与計算だけでなく、年末調整の手続きも任せたい場合は、税理士に依頼しましょう。年末調整とは、企業が年末に必ず行わなければならない手続きであり、所得税の過不足を調整するための手続きです。企業は従業員に給与を支払う際、所得税を源泉徴収しています。この源泉徴収した所得税の合計額は、必ずしも1年間に納めるべき税額と一致しません。
そのため、源泉徴収した所得税の合計額と納めるべき所得税を正確に算定し、差額を調整するための手続きが必要です。年末調整の代行は原則税理士の独占業務であり、年末調整に伴う各種法定調書の作成・提出を代行できるのは税理士のみとされています。このような理由から、年末調整の手続きも一緒に任せたい場合、税理士に依頼した方がスムーズです。
役員報酬を決めるとき
役員報酬を決める際は、税理士へ相談するのがおすすめです。従業員の給与と役員報酬は、税法上の扱いが異なります。例えば、役員報酬の金額は、起業1年目の場合、毎月決まった金額を支給することを会社の設立日から3か月以内に株主総会で決めなかった場合、税法上の損金に計上できなくなります。また、役員報酬は事業年度ごとに改定するのが一般的です。
ただし、事業年度開始(期首)から3か月以内に変更し、一度決めた役員報酬の金額を1年間(少なくとも期末まで)同額で支給しなければ一部または全部を損金に計上できなくなります。役員報酬の金額は会社の法人税に大きく影響する要素です。役員報酬の決め方が税法に則った正しいやり方かどうかを確認したいときは、税理士へ相談しましょう。
会社を設立したばかりのとき
設立間もない会社、従業員数の少ない中小企業であれば、税理士に依頼するのがおすすめです。給与計算業務は単に数字の計算を行えばいいものではなく、前提となる税務上のルールを守って遂行しなければならない複雑な業務です。特に給与や賞与、役員報酬の取り扱いは税務と切っても切り離せません。
年末調整のほかに法人税の決算申告を行う必要もあり、複雑な書類の作成や手続きを税理士のサポートがない状態でなれない業務を進めていくのは手間も時間もかかります。企業のスムーズな事業運営のためにも顧問契約を視野に入れ、税理士へ依頼することを前向きに検討してみましょう。
関連記事
社労士に依頼した方が良いケース
従業員数が増え、数十人規模になってきたら、社労士に相談するタイミングです。また、雇用形態や勤務時間に関係なく常時10人以上の従業員を雇う場合は、労働基準法によって就業規則の作成・届出義務が生じます。ミスや漏れの防止とあわせて法令を遵守するためにも、会社がある程度大きくなったタイミングで社労士に相談することが重要です。
なお、依頼する社労士を探す際は、まず税理士に相談して紹介してもらうことをおすすめします。仕事の内容が密接に関わっている税理士と社労士は、事務所同士が提携しているケースも多々あります。例えば、初めて給与計算の代行を外部に依頼する際は税理士を選択し、会社の規模が大きくなってきたら社労士に依頼する、という流れを基本に考えておくとスムーズです。
給与計算を税理士・社労士に依頼する際に注意すべきポイント
上述したように、税理士と社労士にはそれぞれの専門領域があり、その範囲を超える依頼は法律違反となる可能性があるため注意が必要です。税理士・社労士にはそれぞれ3つの独占業務があり、決められた業務領域を超えて業務を行うことは許されていません。
将来に備える意味でも、給与計算の依頼先がほかの専門家と提携しているかどうか、希望した場合には紹介してもらえるかどうかも確認しておくと安心です。異なる業務間で、スムーズにやり取りできるの環境を整えておくと、効率よく業務を進められます。
給与計算を依頼する税理士を探す方法は?
給与計算について税理士に相談したいと思っても、自力で税理士を探そうとすると手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。
「税理士紹介ナビ」は、起業全般や税、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所から、ぴったりの税理士や会計事務所を最短で翌日にご案内できます。完全無料で、会社所在地や業種に合わせた最適な税理士をご紹介します(2025年8月時点)。
「税理士紹介ナビ」には、事業者のお困りごとに沿って弥生スタッフが最適な税理士や会計事務所を紹介する「税理士紹介サービス」と、ご自身で自由に税理士を探すことのできる「税理士検索
」の2つのサービスがありますので、ご自身の状況に合ったサービスをご活用ください。
「税理士紹介ナビ」はこんな方におすすめ
「税理士紹介ナビ」は、特に次のような方におすすめです。
初めて会社を設立する方
会社を設立する際には、必要な手続きや資金調達など多くの不安や疑問が生じることがあります。「税理士紹介ナビ」なら、これから事業を始める方の悩みや困りごとに合わせて、最適な税理士探しをサポートします。個人事業主から法人成りを予定している方にもぴったりです。
起業後の会計処理や決算が不安な方
会社を運営するうえでは、法人税や地方税、消費税など、さまざまな税や固定資産の知識が必要になります。そのような場合も、会計処理や決算に関することをまとめてプロに相談できます。
できるだけ節税したい方
「節税したいが方法がわからない」という方にも「税理士紹介ナビ」はおすすめです。税理士からのアドバイスで節税方法を理解できれば、戦略的な経営にも役立つでしょう。
記帳業務を丸ごとプロに任せたい方
日々の取引を記帳するには手間や労力がかかります。売上が増えるとともに経理作業量も増え、負担が大きくなってしまうでしょう。記帳業務を税理士に丸投げできれば、その分しっかり本業に集中できるようになります。
給与計算の依頼先は会社の規模や従業員数に合わせて選ぼう
給与計算をアウトソーシングする場合は、税理士か社労士のいずれかに依頼するのが一般的です。税理士と社労士はどちらも給与計算の代行が可能ですが、独占業務と呼ばれる専門領域にそれぞれ違いがあります。税務の専門家である税理士は、給与計算のほかに年末調整や決算申告を代行できますが、社会保険の手続きはできません。
一方、社労士は、社会保険や労働保険の手続きができますが、税に関する業務には携われません。それぞれの領域を把握し、会社規模が小さいうちは税理士、従業員数が増えて社会保険の手続きが多くなったら社労士と、状況に合わせて給与計算の依頼先を選ぶことが重要です。
もし「どうやって税理士を探したら良いかわからない」という場合は、ぜひ弥生の「税理士紹介ナビ」をご活用ください。
この記事の監修者高崎 文秀
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。