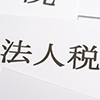追徴課税とは?種類や計算方法、対象期間、注意点を解説
更新

法人税の納付は企業の義務であり、期限内に正確な納税額を申告する必要があります。この義務が履行されなかった場合に課されるのが「追徴課税」です。
本記事では、追徴課税の種類や対象期間について解説します。追徴課税が支払えない場合の対処方法や納付する際の注意点もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
追徴課税とは過去に申告漏れなどがあった場合に追加で徴収される税金のこと
追徴課税とは、税金の申告や納付を法定期限内に正しく、あるいは全く行わなかった場合に、本来の納税額に上乗せして徴収される税金のことです。不足税額は自ら修正申告を行うか、もしくは所轄の税務署が指摘を行う更正処分によって算出されます。状況によっては、納税が遅れたことに対するペナルティとして、本来納めるべき税額以上を納付しなければならない場合もあるため、追徴課税の対象にならないようにしましょう。
追徴課税には「加算税」や「延滞税」など、ペナルティとしての附帯税が課される場合があります。納付すべき税額の計算方法や対象となる期間は、附帯税ごとに異なります。追徴課税は、通知を受け取った日を含め1か月以内に納付しなければなりません。期限内に納付しなかった場合、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることもあります。なお、追徴課税は原則として一括で納付する必要があるため、分割で納付する場合は後述する「納税の猶予」と「換価の猶予」のいずれかの猶予制度を利用しなければなりません。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
追徴課税の主な種類
法人税の申告と納付は、事業年度終了の翌日から原則2か月以内に行う必要があります。期限までに法人税を納付しなかった場合や納税額が不足していた場合は、追徴課税が課されます。追徴課税の主な種類は、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」「延滞税」「利子税」の6つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
過少申告加算税:確定申告額が不足していた場合に課される税金
過少申告加算税とは、期限内に確定申告をしたものの、申告額が本来納めるべき税金よりも少なかった場合に課される税金です。本来、納付した税金が実際に納めるべき額よりも少なかった場合には、修正申告を行わなければなりません。なお、過少申告加算税は修正申告を行った場合でも課されます。過少申告加算税の計算式は以下のとおりです。
過少申告加算税の計算式
過少申告加算税=(50万円までの税額×10%)+(50万円を超える税額×15%)
計算式に示されているとおり、不足税額が50万円以下の場合は納税額の10%、50万円を超える場合は超過分に15%の税率が適用されます。例えば、本来200万円の法人税を納付すべきだった場合の過少申告加算税は、「(50万円×10%)+(150万円×15%)=27万5,000円」となります。
無申告加算税:納税期限までに確定申告を行わなかった場合に課される税金
無申告加算税とは、納税期限までに確定申告を行わなかった場合に課される税金のことを指します。無申告加算税の計算式は以下のとおりです。
無申告加算税の計算式
無申告加算税=追加で徴収される税額×税率
税率は、不足税額50万円までが15%、50万円を超える部分が20%です。また、2024年1月1日以降に納付期限が到来する法人税に関しては、300万円を超える部分に30%の税率が適用されるようになりました。以下は追加で100万円の法人税が徴収される場合の計算例です。
無申告加算税の計算例
(50万円×15%)+(50万円×20%)=17万5,000円
上はあくまでも税務署から指摘を受けた場合の税率です。納付期限を過ぎた後に自主的に申告した場合には、無申告加算税の税率が5%軽減されます。
なお、状況によっては無申告加算税が適用されない場合もあります。具体的には、以下に該当するようなケースです。
無申告加算税が適用されないケース
- 法定申告期限から1か月以内に自ら期限後申告を行った場合
- 期限後申告にかかる納税額を法定期限内に納税している場合
- 直近5年間に期限後申告による無申告加算税または重加算税を課されていない場合
このように、無申告加算税の適用の有無や適用税率は納税者に自主的かつ誠実に納税する意思が認められたかによって異なります。そのため、申告期限を過ぎていることに気付いたときには、できるだけ早く期限後申告をすることが重要です。
不納付加算税:納税期限までに源泉徴収した所得税を納めなかった場合に課される税金
不納付加算税とは、納税期限までに源泉徴収した所得税を納めなかった場合に課される税金です。不納付加算税は、以下の計算式に基づいて算出されます。
不納付加算税の計算式
不納付加算税=期限までに納付していなかった源泉所得税×税率
税率に関しては、税務署から指摘を受けて納付した場合と、自主的に納付した場合とでは異なります。税務署の指摘後に納付した場合は10%、自主的に納付した場合は5%の税率が適用されます。ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合、不納付加算税は課されません。
不納付加算税が課されないケース
- 不納付加算税の金額が5,000円未満の場合
- 納期限から1か月以内に納付されており、かつ過去1年間に期限後納付が一度もない場合
重加算税:不正行為によって脱税した場合に課される税金
重加算税は、帳簿の改ざんや売上の隠蔽など、不正行為による脱税時に過少申告加算税や不納付加算税、無申告加算税に代えて課される税金です。重加算税は、以下の計算式に基づいて算出されます。
重加算税の計算式
重加算税=不足税額×税率
税率に関しては、過少申告加算税や不納付加算税に代えて適用される場合は35%、無申告加算税に代えて適用される場合は40%です。重加算税は他の附帯税と比べて高い税率が定められています。重いペナルティを科されないためにも、不正行為が行われないよう徹底する必要があります。
延滞税:期限内に税金を納めなかった場合に課される利息のような税金
延滞税とは、期限内に税金を納めなかった場合に課される利息のような税金のことです。原則として納付期限の翌日から納付が行われるまでの日数に基づいて自動的に課されます。延滞税は、追徴課税と共に納付することになるため、納付が遅れるほど延滞税も増えていく点に注意しましょう。延滞税は、以下の計算式に基づいて算出されます。
延滞税の計算式
延滞税=(納税額×延滞税の税率×延滞した日数)÷365日
税率に関しては、納付期限の翌日から2か月を経過するまでの期間については、「年7.3%」もしくは「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方が適用されます。また、納付期限の翌日から2か月を経過した翌日以降の期間に適用される税率は、「年14.6%」もしくは「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
利子税:延納が認められた場合に課される税金
利子税とは、延納を申請して認められた場合に課される税金のことです。前述した延滞税は納税の遅れに対して自動的に課されるのに対し、利子税はあくまでも延納を申請し、認められた場合に限り課される点が異なります。利子税は延納が認められた期間に応じて課され、以下の計算式に基づいて算出されます。
利子税の計算式
利子税=(納税額×利子税の税率×延納日数)÷365日
税率に関しては、「年7.3%」もしくは「特例基準割合」のうち、いずれか低い方が適用されます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
追徴課税の対象期間
追徴課税の対象期間は、原則過去3年です。ただし、法定申告期限後5年以内に税務署が更正処分を行った場合は5年、さらに重加算税が課されている場合は最大7年にわたり、さかのぼって税務調査される可能性があります。
前述のとおり、税務調査を通じて過少申告や無申告の指摘を受けると、納めるべき税金が増える可能性があります。そのため、申告内容に誤りがあることに気付いた場合、できるだけ早く自主的に修正申告を行うことが大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
追徴課税を支払えない場合の対処方法
追徴課税が決定すると、税務署から通知が届きます。追徴課税は、通知が届いた日の翌日から1か月以内に納付するのが原則です。ただし、さまざまな事情により納付が困難なケースも想定されます。そのような場合には「納税の猶予」もしくは「換価の猶予」といった制度を利用できます。
納税の猶予:特定の事情がある法人が納税を延長できる制度
納税の猶予は、特定の事情がある法人が最大2年間納税を延長できる制度です。特定の事情としては、自然災害や病気・ケガ、廃業などによる経済的損失があげられます。納税の猶予を申請し、承認された場合、追徴課税を1年かけて分割で納税する「分納」が可能です。猶予期間中の延滞税の全額または一部についても免除される他、正当な理由があれば最大2年まで延長することもできます。
ただし、納税の猶予を申請できるのは、あくまでもやむを得ない事情により追徴課税の納付が困難と認められる場合に限られます。どのようなケースにおいても、申請さえすれば必ず猶予されるとは限らない点に注意しましょう。例えば、単に自社のキャッシュ・フローが悪化するといった理由で納税の猶予を申請しても、認められない可能性が高いと考えられます。
換価の猶予:財産の売却や差し押さえを一時的に免れる制度
換価の猶予は、財産の売却や差し押さえを一時的に免れる制度です。追徴課税を課されている企業が納税の猶予を申請せず、かつ追徴課税の納付もしない場合、財産の差し押さえが行われる可能性があります。ただし、実際には追徴課税の納付によって事業の継続や生活の維持が困難になるケースもあるでしょう。換価の猶予は、このような場合に適用される制度です。
換価の猶予が適用されることにより、追徴課税を1年かけて分納できることに加え、猶予期間中の延滞税の全額または一部も免除されます。追徴課税を支払えない事情がある場合には、放置せず速やかに税務署に相談することが大切です。なお、換価の猶予の適用を受けるには、納付すべき国税の納付期限から6か月以内に申請書を提出する必要があります。申請の際、担保や保証人を求められる場合がありますが、追徴課税の額・猶予期間などによっては不要となる場合があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
追徴課税における注意点
追徴課税には、通常の納税とは異なる法的なルールが設けられています。追徴課税における主な注意点を確認しておきましょう。
原則、一括払いで納付する
追徴課税は、本来納めるべき税金が正しく納められていなかったために生じた税金であることから、原則として一括で納付する必要があります。納税の猶予や換価の猶予といった制度の利用によって、追徴課税を1年かけて分納することも可能です。ただし、こうした猶予を受けるには申請が必須である点に注意しましょう。納税の猶予や換価の猶予を申請することなく納付期限までに追徴課税が納められなかった場合、財産の差し押さえを受ける可能性もあります。
通知後1か月以内に納付する
追徴課税が決定した場合、税務署から通知が届きます。通知が届いた翌日から起算して1か月以内に追徴課税を納付しなければなりません。
1か月以内に納付が確認できない場合は督促状が送付され、さらに督促状にも従わない場合は財産を差し押さえる処分が執行されます。そのため、通知が届いたら速やかに納付するか、納税の猶予・換価の猶予の申請手続きを行うことが大切です。
なお、追徴課税を払えないことを理由に法人の経営者が自己破産しても、税金の支払いは免れません。税金に関しては免責の対象とならない「非免責権」が適用されるためです。
損金に計上できない
追徴課税は税務申告の際に租税公課として損金に計上できません。追徴課税は申告漏れや無申告に対するペナルティとして課される税金のため、通常の税金のように租税公課として計上し、損金に算入することは認められていない点に注意しましょう。法人税を計算するときに損金不算入の処理を行うため、摘要欄には加算税や延滞税であることを記載しておかなければなりません。なお、利子税は延納を申請して認められた場合に支払う税金であることから、ペナルティとして科される追徴課税とは性質が異なります。したがって、利子税に関しては損金算入が可能です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
法人税を正しく申告し、追徴課税を防ぐことが重要
法人税をはじめとする税金は、期限までに正確に申告し、納税するのが基本です。追徴課税は、この基本的なルールが守られていない場合に適用されるペナルティとしての意味合いで設けられている制度といえます。追徴課税の対象となった場合、納税の猶予や換価の猶予といった制度を利用できる可能性があるものの、そもそも追徴課税を徴収されることのないよう正確に税務申告を行い、期限内に納付することが最も重要です。
各事業者は決算書に基づいて法人税申告書を作成し、正しい法人税の納付額を確定させなければなりません。そのためには、日々の記帳を漏れなく正確に行うことが大切です。クラウド会計ソフト「弥生会計 Next」を活用することで、法人のお金に関するデータをまとめて管理できるため、日々の記帳から決算書の作成までをスムーズに進められます。また、インボイス制度をはじめとする各種法令にも対応しているため、最新の法令に則った会計処理が可能です。会計業務の合理化を図りたい場合は、ぜひ「弥生会計 Next」をご検討ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。