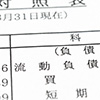賞与引当金とは?必要な理由や注意点、仕訳方法などを解説
更新
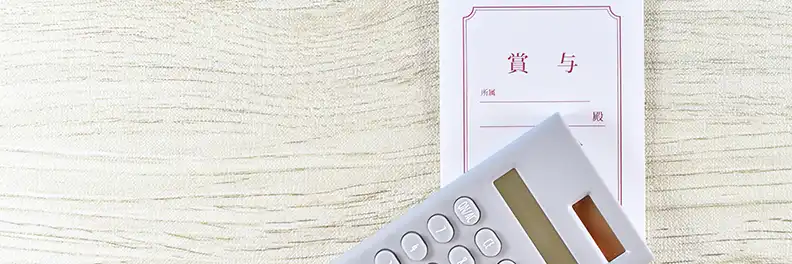
「賞与引当金」とは、翌期に従業員に支給する賞与(ボーナス)に備えて計上する勘定科目です。賞与の支給は多くの場合、査定対象期間と実際の支給日が期をまたぎます。そのため、賞与引当金を計上しておくことで、当期の費用として適切に処理でき、特定の会計期間に属する収益と費用を対応させて、その期間の正確な利益(または損失)を算出する期間損益を正しく反映する助けになります。賞与引当金の計上は会計上の義務ではありませんが、こうした処理を通じて企業の収益と費用を対応させ、財務状況の信頼性を高めることができます。
ただし、賞与引当金は日常の帳簿上では使用されない勘定科目であるため、「なぜ賞与引当金の計上が必要なのか」「賞与引当金の仕訳がよくわからない」と悩む方もいるでしょう。
なお、ここでいう「引当金」とは、将来発生が見込まれる費用や損失に備えて、あらかじめ見積もった金額を当期の費用として計上するときに使用する「負債」です。賞与引当金はその一種で、将来支払う賞与のうち、当期に対応する分だけを前もって費用処理するためのものを指します。
本記事では、賞与引当金が必要な理由や計上における注意点、仕訳方法などを解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
賞与引当金とは、翌期に支給する賞与に備えて見積もり計上するための勘定科目
賞与引当金とは、翌期に支給される賞与のうち、当期に対応する分を見積もって計上する勘定科目を指します。
賞与は、支給日ではなく、その対象となる労働期間に対応する費用です。例えば、夏季賞与であればその査定対象期間は、前年の年末から当年の夏ごろまでに設定されるのが一般的であり、支給日が翌期にずれ込むこともあります。このように、査定対象期間が当期に属しており、支給日が翌期となる場合に期間損益を正しく反映するためには、その賞与額のうち当期に対応する部分を決算時に賞与引当金として計上する必要があります。
例として、3月決算の企業で、賞与の支給が6月と12月の年2回というケースを考えてみましょう。6月の賞与の査定対象期間を12月から5月、12月の賞与の査定対象期間を6月から11月と仮定します。この場合は、3月末の決算時に、翌期の6月に支給される賞与額のうち、当期に対応する12月から3月分を賞与引当金として計上します。
賞与引当金を計上するときに使用する勘定科目は、「賞与引当金繰入額」です。翌期の賞与支給見込額のうち当期に対応する分の金額を計算し、賞与引当金として計上します。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
賞与引当金を計上するときの一例
- 決算月:3月
- 賞与の支給時期: 6月・12月(年2回)
- 6月賞与の査定対象期間:前年12月〜当年5月
- 12月賞与の査定対象期間:6月〜11月
- 6月支給予定の賞与額:150万円(見積)
この場合、3月末の決算では、6月支給予定の賞与のうち当期(12月〜3月)に対応する部分を賞与引当金として計上する必要があります。仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:賞与引当金を決算時に計上する場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 賞与引当金繰入額 | 1,000,000円 | 賞与引当金 | 1,000,000円 |
賞与引当金を決算時に計上する場合は、6月の賞与支給見込額150万円のうち、当期に対応する12月から3月の4か月分に相当する金額を計上します。半年ごとの支給なので、この場合、賞与引当金の額は、「150万円÷6か月×4か月分」で、100万円となります。
なお、このような期をまたぐケースは賞与引当金を計上する一例にすぎません。実務上は、賞与の発生が見込まれる期間に応じて、月次で一定額を計上する方法も推奨されており、これにより正確な期間損益の把握が可能となります。企業の会計方針や運用実態に応じて、柔軟に対応することが求められます。月次で計上する際の仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:賞与引当金を月次で計上する場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 賞与引当金繰入額 | 250,000円 | 賞与引当金 | 250,000円 |
賞与引当金を毎月計上する場合、月ごとの計上額は、「150万円÷6か月」で250,000円となります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
賞与引当金の算出方法
賞与引当金の計上額を算出するには、「支給見込額基準」と「旧税法基準」という2つの代表的な考え方があります。これらは企業の実務や会計方針に応じて使い分けられますが、どちらか一方に限定されているわけではありません。支給見込額基準と旧税法基準の主な違いは、算定方法の柔軟性と実務への適合性にあります。
支給見込額基準では、過去の支給実績や企業の業績、社内規定などから翌期に支給が見込まれる賞与額を見積もり、そのうち当期に対応する金額を賞与引当金として計上します。そのため、柔軟で実態に近い処理ができる一方、見積もりの精度や根拠が大切です。支給見込額基準により賞与引当金を算出するのが一般的とされています。
その一方で、旧税法基準とは、1998年度改正前の旧法人税法で用いられていた、賞与の支給対象期間を基準に賞与引当金を計算する方法になります。過去の実績や定型的な要素に基づいた計算式で算出されるため、客観性・一貫性はあるものの、現在の実務にはそぐわないケースもあり実務ではほぼ用いられません。以前は法人税の計算上以下の計算式で算定した金額が合理的である場合に限り、賞与引当金として計上していました。後述の通り、現在の税法上は賞与引当金の損金算入は認められていません。
旧税法基準による賞与引当金の計算式
賞与引当金の計上額={前1年間の1人あたりの従業員に対する賞与支給額×(当期の月数÷12)-当期末に在職している従業員に支給した賞与のうち、当期に対応する1人当たりの支給額}×期末に在職している従業員数
また、賞与引当金を計上する際には、賞与にかかる社会保険料についても考慮することが必要です。
賞与には、給与と同じように、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険料がかかります。賞与引当金の計上にあたっては、これらの社会保険料が賞与から控除されることを踏まえて手取り額ではなく額面ベースで支給額を見積もることが重要です。なお、賞与にかかる社会保険料は、賞与引当金の計上時ではなく、実際に賞与を支給するときの保険料率によって算出されます。保険料率は頻繁に改訂されるうえ、自治体によっても異なることがあるため、注意が必要です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
賞与引当金が必要な理由
賞与引当金を計上する理由は、会計上の「発生主義」の原則に基づき、費用を適切な期間に対応させるためです。発生主義とは、取引が発生したタイミングで費用や収益を計上する会計処理方法を指します。企業会計原則では、すべての費用および収益は、その発生した期間に正しく割り当てることが求められています。6月支給の賞与の査定対象期間が12月から5月であるなら、12月から3月分は当期に計上すべき費用です。
特に、賞与はまとまった金額が支給されることが多いため、賞与引当金計上の有無が利益に与える影響は大きくなります。賞与引当金を計上しなければ、支給時期を調整し、特定の期間の利益を意図的に操作するような状況が生じかねません。また、賞与引当金の計上は、翌期に支払う賞与をあらかじめ見積もり、資金を準備するという意味でも大切です。
さらに、実務上は賞与の支給が6月、12月など特定の月に偏る企業が多いため、毎月の会計処理の中で一定額ずつ賞与引当金を積み立てていくことも一般的といえます。これにより、賞与支給月に一時的な費用の急増を避け、月次の損益が大きくぶれるのを防ぐことができます。財務状況の平準化や資金繰りの見通しを安定させるうえでも、月次での賞与引当金の計上は有効な手段といえるでしょう。
なお、賞与引当金は貸借対照表にも記載されるため、ステークホルダーに対して、将来の支出見込みや人事評価方針を可視化する情報としても機能します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
引当金は将来の支出に備えて先に計上される見積金額
引当金とは、将来発生する可能性が高い支出に備えて、事前に計上される見積金額のことです。引当金を計上する目的は、企業会計原則に含まれる発生主義や保守主義に基づき、財務諸表の正確性を高めることにあります。保守主義とは、企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合に備えて、健全な会計処理を求める会計上の原則です。
財務諸表に引当金を記載しないと、負債が過少に表示されることになり、その結果として純資産が実際より多く見えてしまいます。また、実際に将来支出が発生した際、企業の利益が急激に減少したように見える可能性があります。そのため、企業の財務状況を正しく示すためには、引当金を適切に計上することが大切です。
引当金についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
賞与引当金と賞与引当金繰入額の違い
「賞与引当金」とよく混同される勘定科目に「賞与引当金繰入額」があります。賞与引当金と賞与引当金繰入額では、財務諸表上の扱いが異なります。賞与引当金繰入額は、賞与引当金を計上する際に使用する費用の勘定科目です。「賞与引当金の繰入額=賞与引当金として計上する額」と考えるとわかりやすいでしょう。
決算時に賞与引当金を計上する際には、翌期の賞与支給見込額のうち当期に対応する金額を、賞与引当金繰入額の勘定科目で借方に計上します。このとき、貸方の勘定科目は賞与引当金です。財務諸表においては、賞与引当金は貸借対照表の負債、賞与引当金繰入額は損益計算書の費用として分類されます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
賞与引当金の計上における注意点
賞与引当金の計上にあたっては、確認しておくべき注意点がいくつかあります。賞与引当金を計上する際には、会計上と税務上で処理方法が異なる点に注意しましょう。
税務上では損金算入が認められない
賞与引当金の計上における注意点は、税務上では損金算入が認められないことです。
賞与引当金は、会計上の発生主義の考え方に基づき、将来支払う予定の賞与を、実際の支給日よりも前の事業年度に計上するものを指します。この会計処理によって、期間損益を正確に把握することが可能になります。しかし、税務上では、賞与引当金は原則として損金算入が認められていません。
その理由は、賞与の支給にあたり、「金額」「支給日」「対象者」がすべて確定していることが、損金算入の前提条件とされているためです。つまり、会計上は賞与引当金を計上できても、税務上は「債務が未確定」であるため損金にはなりません。そのため、会計上で賞与引当金を計上した場合、法人税の申告では、賞与引当金繰入額を加算調整(税務上の所得を増やすための調整)し、実際の支給時の損金となるように処理する必要があります。
賞与引当金を仕訳する際は毎月計上する
賞与引当金を仕訳する際は、毎月計上することも、注意点としてあげられます。
賞与引当金は、決算時にまとめて計上も可能ですが、財務の透明性の観点からは、毎月継続的に計上することが推奨されます。賞与は、半年間など一定期間を対象にした査定に基づき支給されるのが一般的です。決算時のみの計上とするよりも、その期間に対応する費用を月ごとに按分して計上するほうが、より実態に即した人件費の把握につながります。
また、賞与引当金を決算時にまとめて計上すると、金額が大きくなり、その月の利益が大きく減少します。賞与引当金を毎月計上しておけば、月次の損益が平準化され、企業の業績や財務状況をより適切に反映できるでしょう。
賞与の支払時に届出が必要になる
賞与の支払時に届出が必要になることも、賞与引当金の計上における注意点の1つです。
実際に賞与を支給した際には、賞与支給日から5日以内に、「被保険者賞与支払届(賞与支払届)」を提出する必要があります。賞与支払届は、賞与の支給額を届出して、社会保険料を正しく計算・納付するための書類です。
賞与支払届は、事業所の所在地を管轄する年金事務所、または日本年金機構の広域事務センターに提出します。健康保険組合に加入している場合は、厚生年金に関する届出は年金事務所などへ、健康保険に関する届出は健康保険組合へ提出する必要があります。なお、あらかじめ届け出ている 賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」を提出しなければなりません。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
賞与を支払ったときの仕訳例
ここからは、賞与を支給したときの仕訳例を見ていきましょう。
実際に賞与を支払った際には、計上していた賞与引当金を戻し入れる(取り消す)仕訳を行います。賞与支給時の仕訳は、実際に支払った賞与の額によって変わってきます。
6月になり従業員に賞与を支払い、前期に賞与支給見込額を150万円と見積もり、賞与引当金として50万円を計上している場合の仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:実際の賞与支給額が賞与引当金よりも多い場合(前期に見積もったとおり、賞与150万円を支給した)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 500,000円 | 普通預金 | 1,500,000円 |
| 賞与 | 1,000,000円 | ||
賞与の支給額150万円のうち50万円は、すでに賞与引当金として処理されています。そのため、差額の100万円を「賞与」の勘定科目で追加計上します。
仕訳例:実際の賞与支給額が賞与引当金よりも多い場合(賞与の支給見込額を150万円と見積もっていたが、実際には170万円を支給した)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 500,000円 | 普通預金 | 1,700,000円 |
| 賞与 | 1,200,000円 | ||
実際の賞与支給額が当初の見積もりよりも多い場合も、基本的な仕訳方法は同じです。
仕訳例:実際の賞与支給額が賞与引当金よりも少ない場合(賞与の支給見込額を150万円と見積もり、賞与引当金50万円を計上していたが、実際の支給額は40万円だった)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 500,000円 | 普通預金 | 400,000円 |
| 賞与引当金戻入益 | 100,000円 | ||
前期に計上していた賞与引当金よりも、実際に支給した賞与の額が少なかったときは、費用計上していた賞与引当金が過剰となるため、差額分を収益として計上します。この場合は、差額分を「賞与引当金戻入益」として計上し、賞与引当金戻入益は、会計上、収益として認識されます(戻入益)。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
賞与の支払に備えて、賞与引当金を正確に計上しよう
賞与引当金は、翌期に従業員に支給する賞与のうち、当期に対応する金額を前もって計上する勘定科目を指します。発生主義の原則に基づき、費用を適切な期間に対応させるには、賞与引当金を正確に計上することが大切です。賞与引当金は決算時にまとめて計上もできますが、企業の財務状況をより正確に把握するには、月ごとの計上が推奨されます。「弥生会計 Next」などの会計ソフトを活用すれば、手間やミスを軽減し、効率良く仕訳を行うことができます。正しい期間損益の計算のためにも、賞与引当金について正確に理解しておきましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。