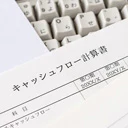間接法とは?直接法との違いやキャッシュ・フロー計算書について解説
更新

事業年度ごとに企業の財政状態や経営成績をまとめた財務三表の1つであるキャッシュ・フロー計算書には、「間接法」と「直接法」という2つの作成方法があります。キャッシュ・フロー計算書は、中小企業に作成義務はありませんが、企業の経営状況を客観的に判断するうえで非常に有効なツールです。そのため、中小企業にとっても、キャッシュ・フロー計算書の作り方や見方を知っておくことはとても大切です。
本記事では、キャッシュ・フロー計算書作成における間接法とは何か、直接法との違いや、間接法によるキャッシュ・フロー計算書の作成方法などについて解説します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
間接法とはキャッシュ・フロー計算書の作成方法の1つ
間接法とは、キャッシュ・フロー計算書を作成する方法の1つです。キャッシュ・フロー計算書の作成・表示方法には、税引前当期純利益を基準に、項目ごとに現金の増減を表す間接法と、実際の現金の流れを主要な項目ごとに集計する直接法の2種類があります。キャッシュ・フロー計算書では、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローを、区別して表示するのが特徴です。このうち、投資活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローについては、直接法で表すことが決められています。その一方で、営業活動によるキャッシュ・フローについては、各社が任意で作成方法を選択できることになっており、国内企業の多くが間接法を選んでいます。なお、間接法と直接法のどちらを選んでも、最終的な営業活動によるキャッシュ・フローの額は同じです。
キャッシュ・フロー計算書は、一定の会計期間における企業の資金の流れを示す書類
キャッシュ・フロー計算書とは、その名前のとおりキャッシュ(資金)のフロー(流れ)を表した会計書類のことです。会計期間中に、どのような理由でいくらのお金が入ってきて、出ていったのかを表します。
キャッシュ・フロー計算書は、貸借対照表や損益計算書と並んで財務三表と呼ばれる主要な書類で、上場企業は決算時に必ず作成しなければいけないものです。中小企業にはキャッシュ・フロー計算書の作成義務はありませんが、その意味や読み方については知っておいた方がよいでしょう。キャッシュ・フロー計算書を読み解くことで、損益計算書・貸借対照表だけで会計処理を行う場合より、より詳細に経営実績や財政状況を把握できるようになります。
なお、キャッシュ・フロー計算書では、以下のとおり「営業活動によるキャッシュ・フロー」「投資活動によるキャッシュ・フロー」「財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つの区分ごとに、資金の増減が表示されます。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、本業である事業でどれだけのキャッシュが生み出されているのかを表すものです。例えば、現金による売上や、売上債権の回収または仕入債務の支払い、従業員への給与の支払い、現金で支払った経費などが該当します。また、製造業であれば、原材料費とそれを販売した場合の収入も含まれます。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動におけるキャッシュの動きを表すものです。固定資産の購入・売却、有価証券や投資有価証券の取得・売却など、将来に向けた投資などで現金がどれくらい増減したのかを示します。
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達や返済などの財務活動によるキャッシュの動きを表すものです。金融機関からの借り入れや返済、株式・社債の発行、配当金の支払いなどによる現金の増減を示します。
キャッシュ・フロー計算書の作成方法
では、キャッシュ・フロー計算書における間接法と直接法とは、どのような作成方法なのでしょうか。それぞれの特徴を確認していきましょう。
間接法
キャッシュ・フロー計算書作成における間接法は、税引前当期純利益をスタートラインとして、項目ごとに現金の増減を表していく方法です。間接法は、本業である事業でどれだけのキャッシュが生み出されているかを求めるため、損益計算書を基に作成します。損益計算書の税引前当期純利益から、資金の収支とは関係のない減価償却費の金額や、投資活動や財務活動にかかわる受取利息・固定資産売却益などの金額を加減して、営業活動によるキャッシュ・フローを求めます。
間接法を用いた場合、損益計算書と貸借対照表があれば作成可能なので、実際の現金の流れを主要な項目ごとに集計する直接法に比べて手間がかかりません。そのため、間接法はキャッシュ・フロー計算書の作成義務がない中小企業や、経理の知識が十分ではない個人事業主などにも適した方法といえるでしょう。
直接法
キャッシュ・フロー計算書作成における直接法は、実際の現金の流れを主要な項目ごとに集計して表す方法です。直接法では、資金の収入額と支出額を積み上げて、営業活動によるキャッシュ・フローを求めます。営業収入、原材料または商品の仕入れなどの支出、人件費支出、経費の支払いなど、主要な取引ごとにキャッシュ・フローの総額が表示されるのが直接法の特徴です。
直接法を用いると、営業活動の項目ごとに資金の増減を把握できますが、作成にあたっては、貸借対照表と損益計算書以外に取引ごとのキャッシュ・フローに関するデータが必要になるため、間接法に比べて手間がかかります。
間接法と直接法の表示の違い
キャッシュ・フロー計算書作成における間接法と直接法では、営業活動によるキャッシュ・フローの表示に違いがあります。間接法と直説法の表示の違いについては以下のとおりです。
| 間接法 | 直接法 |
|---|---|
| 税引前当期純利益(損失) | 営業収入 |
| 減価償却費 | 原材料または商品の仕入れによる支出 |
| 貸倒引当金の増加額 | 人件費の支出 |
| 退職給付引当金の増加額 | その他の営業収入 |
| 受取利息及び受取配当金 | その他の営業支出 |
| 支払利息 | 未払消費税等の増加(減少)額 |
| 手形売却損 | |
| 為替差損 | |
| 有価証券売却益 | |
| 有価証券売却損 | |
| 投資有価証券売却益 | |
| 投資有価証券売却損 | |
| 有形固定資産売却益 | |
| 有形固定資産売却損 | |
| 有形固定資産除却損 | |
| 前期損益修正 | |
| 損害賠償損失 | |
| その他非資金損益項目の増加(減少)額 | |
| 売上債権の増加(減少)額 | |
| 棚卸資産の増加(減少)額 | |
| 仕入債務の減少(増加)額 | |
| 割引手形の増加(減少)額 | |
| 未払消費税等の増加(減少)額 | |
| 役員賞与の支払額 | |
| その他資産の増加(減少)額 | |
| その他負債の減少(増加)額 | |
| その他 | その他 |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 損害賠償金の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
間接法のメリット
間接法のメリットは、直接法に比べてキャッシュ・フロー計算書の作成に手間がかからないことです。間接法では、損益計算書の税引前当期純利益から、現金の動きに関する点だけを計算して、営業活動によるキャッシュ・フローを求めます。直接法とは異なり、損益計算書と貸借対照表があればキャッシュ・フロー計算書が作成可能なので、それほど大きな手間が必要ありません。
間接法のデメリット
間接法のデメリットは、直接法に比べて項目ごとの現金の流れを把握しにくいことです。間接法では、直接法のように、主要な取引ごとのキャッシュ・フローの計算は行いません。そのため、「どの商品をいくらで仕入れたか」「経費に占める人件費の割合はどのくらいか」といった細かい項目の把握には不向きです。
間接法を用いたキャッシュ・フロー計算書の作成方法
ここからは、間接法を用いたキャッシュ・フロー計算書の作成方法を紹介します。キャッシュ・フロー計算書の作成に間接法を用いるには、まず当期の損益計算書と前期および当期の貸借対照表を用意することが必要です。そのうえで、以下の手順で進めていきます。
1. 損益計算書より税引前当期純利益を参照する
間接法では、損益計算書の税引前当期純利益をスタートラインとして、キャッシュ・フロー計算書を作成します。まずは、キャッシュ・フロー計算書の「税金等調整前当期純利益」の項目に、損益計算書の税引前当期純利益の金額を転記します。
2. 非資金損益項目を調整する
非資金損益項目とは、現金の増加や減少を伴わない項目のことです。具体的には、減価償却費やのれん償却額、減損損失、貸倒引当金などが該当します。これらの項目は、損益計算書の税引前当期純利益の計算には含まれますが、キャッシュの動きはありません。そのため、キャッシュ・フロー計算書の作成にあたり、非資金損益項目を加算または減算して調整することが必要です。
例えば、減価償却費は損益計算書では費用計上されていますが、実際に現金を支出するわけではないので、キャッシュ・フロー計算書では加算します。また、貸倒引当金は、前期分と当期分の貸借対照表を参照し、前期から増加していれば加算を、減少していれば減算を行います。
3. 営業外損益・特別損益を調整する
営業外損益とは、本業以外の活動によって経常的に生じる収益(営業外収益)や費用(営業外費用)のことです。営業外収益には配当金や保有している不動産の家賃収入などが、営業外費用は借入金にかかる支払利息などが該当します。また、特別損益とは、例外的な出来事によって一時的に発生した利益や損失のことです。例えば、特別利益には固定資産の売却益などが、特別損失には災害による損失などが該当します。
営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失は、営業活動とは関係のない項目です。そのため、営業外損益や特別損益が税引前当期純利益に含まれていた場合は、それぞれ加算または減算を行います。
4. 営業活動によるキャッシュの増減を計算する
最後に、営業活動にかかわるキャッシュの増減を計算します。損益計算書に記載される売上高や売上原価には、売掛金や買掛金のように、現金以外の項目も含まれています。そのため、貸借対照表の売上債権(売掛金や受取手形)、棚卸資産(商品など)、仕入債務(買掛金や支払手形)の項目を参照し、キャッシュの増減の調整が必要です。
前期と当期の貸借対照表を比較して、各項目の増減を確認しましょう。例えば、売上債権や棚卸資産が前期比で増加している場合は、キャッシュを回収できていないことになるため、キャッシュ・フローはマイナスになります。反対に、前期比で減少していれば、キャッシュを回収できているため、プラスとして計上します。
また、仕入債務が前期比で増加しているなら支払いを行っていないためプラス、減少していれば現金が出ていったことになるためマイナスとして、それぞれ調整が必要です。
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
間接法を用いてキャッシュ・フロー計算書の作成し、経営状況の把握に役立てよう
間接法とは、キャッシュ・フロー計算書を作成する方法の1つです。
キャッシュ・フロー計算書を作成するには、損益計算書の税引前当期純利益からキャッシュ・フローを算出する間接法と、主要な項目ごとにキャッシュの増減を計算する直接法の2つの方法があります。間接法は直接法に比べて手間がかかりませんが、貸借対照表や損益計算書がなければキャッシュ・フロー計算書を作成できません。
貸借対照表や損益計算書の基になるのが、日々の取引を記録した帳簿です。記帳にミスや漏れがあると、貸借対照表や損益計算書の内容も誤ったものになってしまいます。「弥生会計 Next」を利用すれば、記帳の手間を大幅に軽減できるうえ、貸借対照表や損益計算書も自動で作成が可能です。業務効率化と正しい経営分析のために、自社に合った会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。