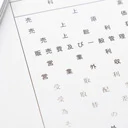損金とは?費用・経費との違い、損金算入・不算入の基準を解説
監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)
更新

損金とは、法人税の計算をするときに、益金から差し引くことができる費用や損失を指します。損金は、経費や会計上の費用に近い概念ですが、法人税法上の損金とは異なるため、混同しないよう注意しましょう。
法人税の計算をする際には、損金が何を指すのかを理解し、「損金算入」「損金不算入」の範囲を正確に把握することが大切です。
本記事では、損金と費用・経費との違い、損金算入できる勘定科目と損金不算入の勘定科目などについて解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金とは、税法上で損金算入が認められる費用や損失のこと
損金とは、法人の事業活動に伴って発生する費用や損失のうち、税法上で損金算入が認められるものを指します。
法人税の課税所得は、益金からこの損金を差し引いて求められます。益金とは、商品・製品などの販売による売上高や土地・建物の売却収入など、法人の資産を増加させる収益のうち、資本等取引などを除いた金額のことです。
税法上では、「益金-損金」で課税所得を求めますが、会計上は「収益-費用」で利益を計算します。益金と収益、損金と費用は一見似ていますが、定義が異なるため、税法上の所得と会計上の利益は必ずしも一致しません。所得と利益を求める計算式は、以下のとおりです。
税法上の所得の計算式
所得(税法上の儲け)=益金-損金
会計上の利益の計算式
利益(会計上の儲け)=収益-費用
決算の際には、当期の利益を算出して貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成し、その後、税務申告のために所得を計算します。基本的には、会計上の利益を先に算出してから税法の規定に合わせて調整し、税法上の所得を計算する流れです。
会計上では収益・費用として処理されていても、税法上では益金や損金として認められないものがあります。反対に、会計上は計上されていないにもかかわらず、税法上では益金や損金に算入されるものもあり、これらは「別段の定め」として法人税法に規定されています。この別段の定めにより、会計上の利益と税法上の所得には、ずれが生じることが一般的です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金と費用の違い
損金も費用も、「事業を営むうえで発生するお金」という意味では同じですが、費用は会計上の考え方であるのに対し、損金は税法上の考え方であるという点に違いがあります。
税金を計算する際は、法人税法に従って算出しなければならないため、費用になるかどうかではなく、損金になるかどうかが重要です。例えば、取引先を接待するためにお金を使った場合、会計上は、実際に支払った交際費が全額費用になります。しかし、税法上は、法人の交際費は原則として損金にできません。交際費が法人税法上、原則として損金算入できない理由の1つとして、無駄な経費を過度に使用すると、企業の内部留保が困難になるためとされています。
また、ある設備の耐用年数について、A社は頻繁に使うため3年、B社はそれほど使わないため6年と考えた場合、これは各企業の実態に基づくため、会計上は問題ありません。しかし、税金の計算をするときに各企業が異なる耐用年数を設定すると、課税の公平性が損なわれるおそれがあります。そのため、税法上は、資産ごとに定められた耐用年数に応じて減価償却費を計上する必要があります。
このように、会計上は費用にできても、税法上は損金と認められないものがあり、法人税を正しく計算するためには、損金として認められる範囲を正確に把握することが大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金と経費の違い
損金と経費の違いは、それぞれに基づく基準があります。
損金は税法上の考え方であり、課税所得を計算する際に益金から差し引くことができる支出を指します。それに対して、経費は会計上の考え方に基づき、事業活動のために発生した費用です。つまり、会計上の費用のうち、収益を得るためや事業を継続するために必要な支出が、経費として分類されます。具体的には、仕入代や家賃、人件費、広告宣伝費などが経費に該当します。
ただし、経費も費用と同様に、すべてが損金として認められるとは限りません。課税所得の計算にあたって益金から差し引けるのは、経費のうち税法上、損金とされるものだけです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
法人税の計算に不可欠な損金算入・損金不算入
法人税の計算をするときに欠かせないのが「損金算入」と「損金不算入」です。損金算入と損金不算入とは、簡単に言えば、損金に該当するか否かを示す考え方を指します。法人税の計算をするうえでは、損金算入と損金不算入について、正しく理解することが必要です。ここでは、損金算入と損金不算入についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
損金算入
損金算入とは、言葉どおり、損金に算入することです。
つまり、税法上の損金として認められ、課税所得を計算する際に益金から差し引ける金額であることを意味します。また、会計上は費用と認識されないものの、税法上は損金として扱われることも、損金算入と呼びます。例えば、前年度以前の赤字を繰り越した繰越欠損金などは、会計上の費用にはなりませんが、一定の要件を満たせば損金算入が可能です。
損金不算入
損金不算入とは、税法上の損金として認められないことを指します。
会計上の費用のうち、損金と認められないものは損金不算入となり、実際に支出していても益金から差し引くことはできません。損金不算入の例としては、前述した交際費の他、役員報酬や寄附金などがあげられます。役員報酬は企業が支払う費用ですが、「定期同額給与」など一定の要件を満たさなければ、損金としては認められません。また、寄附金は税法上、原則として一定額を超える部分は損金不算入となります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金経理とは、企業の支出を会計上の費用として処理すること
損金経理とは、税務上の損金に算入するために、あらかじめ企業の決算書に費用または損失として処理することを指します。
法人税法では、損金経理を「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること」と定義しており、例えば、減価償却費や貸倒引当金などは、損金経理が損金算入の前提条件とされています。これらの損金は、株主総会等で承認を得た決算書において、費用または損失として計上されていなければ、損金算入は認められません。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金算入となる勘定科目
企業が支払った費用の中には、損金算入できる項目と損金不算入の項目が存在します。損金算入が可能な主な項目は、以下のとおりです。
損金算入できる項目
| 会計上の勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 法人事業税、固定資産税、印紙税、事業所税、償却資産税、自動車税など |
| 減価償却費 | 減価償却費として損金経理した金額のうち、法人税法に定められた償却限度額の範囲内の金額 |
| 保険料 | 損害保険料や生命保険料のうち、法人税法によって損金算入が認められている金額 |
| 修繕費 | 資産の維持管理や原状回復に必要と認められた部分の金額 |
| 水道光熱費 | 電気代やガス代、水道代、灯油代など |
| 消耗品費 | 文房具や事務用品などの消耗品の購入費用 |
| 雑費 | その他の費用として分類される、発生頻度が少なく金額が小さい支出 |
| 支払利息 | 借入金に対する利息の支出額 |
| 給与 | 各種手当を含めた従業員に対する給与 |
| 福利厚生費 | 従業員への慶弔見舞金、健康診断費用、社員旅行の費用など、給与や賞与以外で従業員の福利のために支出した金額 |
| 法定福利費 | 労働保険料や企業負担分の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金不算入となる勘定科目
会計上の費用の中には、損金不算入となる費用も含まれます。損金不算入となる費用は以下のとおりです。例えば、同じ「租税公課」でも、損金算入が認められる税金と認められない税金があるため、注意しましょう。
損金不算入の項目
| 会計上の勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 法人税および地方法人税、法人住民税、延滞税、加算税、延滞金など税務上の附帯税 |
| 役員報酬 | 「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与(一定の要件を満たすもの)」に該当しない場合、または「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」に該当する場合であっても過大な部分 |
| 交際費等 | 交際費等の損金算入の特例が適用されない接待飲食費や贈答品費など |
| 減価償却超過額 | 減価償却限度額(税法上の損金として認められる償却額)を超えて費用計上した金額 |
| 寄附金 | 寄附金のうち、法人税法上、損金に算入できないもの |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金算入・損金不算入における注意点
ここまで解説してきたように、税法上の損金は、会計上の費用とは内容が異なります。損金算入と損金不算入の取り扱いも、会計上の処理とは異なる点があるため注意しましょう。税法上のルールに従わずに損金処理を行った場合、税務調査で否認され、追徴課税の対象となる可能性があります。特に注意すべきポイントは、以下の3つです。
役員報酬
企業が役員に支払う役員報酬は、原則として損金不算入とされます。
ただし、役員報酬が、以下の「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当する場合に限り、損金算入が認められます。なお、このいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金に算入されません。
定期同額給与
定期同額給与は、1か月以内の一定期間ごとに同額で支払われる役員報酬です。いわば役員の月収に相当しますが、従業員の残業代や出張手当のような加算はなく、月々の支給額が変動することはありません。なお、税務署への届出は不要ですが、報酬額を変更できるのは、原則として事業年度開始(期首)から3か月以内の時期のみです。
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、指定した日にまとめて支払われる報酬のことで、役員賞与に相当するものです。事前確定届出給与を損金とするには、所定の期限までに税務署に届出書を提出し、届出どおりの支給日に記載した金額を支払う必要があります。
業績連動給与
業績連動給与とは、企業の業績を示す指標に応じて支払われる役員報酬を指します。業績連動給与を損金算入するには、所定の指標を基に報酬額を算定するなど一定の要件があります。また、算定方法の内容などを有価証券報告書に記載・開示する必要があるため、株式を公開していない非上場企業には適用されません。
交際費
税法上、法人の交際費等は、原則として全額が損金不算入とされています。
ただし、企業規模によって、交際費等を一定額まで損金算入できる特例があります。期末の資本金が1億円以下の法人(ただし、資本金または出資金が5億円以上の法人の100%子会社等を除く)の場合は、「支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額」または「支出した接待交際費のうち800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額」のいずれかの金額を損金に算入することが可能です。
また、資本金が1億円超かつ100億円以下の法人は、接待飲食費の50%相当額を上限として損金算入が認められます。なお、資本金が100億円を超える法人は、接待費等の全額が損金不算入とされます。
租税公課
租税公課とは、国税や地方税などの「租税」と、国・地方公共団体またはその他公共団体に納める会費や罰金等に該当する「公課」を示す費用の勘定科目です。
租税公課の勘定科目で計上した金額は、損金算入ができます。ただし、勘定科目である租税公課に計上できるのは、事業主や法人が支払った租税・公課のうち、事業との関連性が認められるものに限られます。租税と公課にあたるものでも、事業そのものに関連しない税金や負担金は、租税公課として計上できません。
例えば、「法人税等」と呼ばれる法人税・法人住民税・法人事業税のうち、法人事業税は損金算入が可能ですが、法人税と法人住民税は損金不算入です。また、所得に課される税金や法令違反に伴う制裁的課税も、税法上は損金不算入とされます。損金算入・損金不算入の租税公課は、それぞれ以下のとおりです。
損金算入できる租税公課
- 固定資産税
- 利子税
- 地方税の延滞金(納期限延長によるもの)
- 不動産取得税
- 事業に使用するための自動車にかかる税金(自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税など)
- 登録免許税
- 法人税額から控除されない所得税、外国法人税
- 印紙税(収入印紙)
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
- 軽油引取税
- 酒税
- ゴルフ場利用税
損金不算入の租税公課
- 法人税、法人地方税
- 都道府県民税や市町村民税の本税
- 延滞税
- 延滞金(地方税の納期限の延長にかかる延滞金は除く)
- 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税をはじめとした各種加算税
- 過少申告加算金、不申告加算金をはじめとした各種加算金
- 過怠税
- 交通反則金などの罰金や科料、過料
- 法人税額から控除する所得税および外国法人税
- 復興特別所得税
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
損金の定義と範囲を知って、税金を正しく計算しよう
損金とは、事業活動に伴う支出のうち、課税所得の計算において益金から差し引くことが認められる金額を指します。法人税の税額は課税所得に応じて決まるため、損金が大きいほど法人税額は抑えられます。ただし、企業が支払ったお金がすべて損金になるとは限りません。税法上の損金と会計上の費用は異なるため、誤って損金不算入の費用を損金として計上しないように、十分注意しましょう。
また、税務処理を適切に行うためには、日々の帳簿付けが不可欠です。弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」などを活用し、手間をかけずに正確な帳簿付けを行うことをおすすめします。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)
東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員
お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。