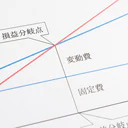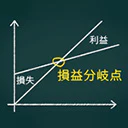福利厚生費とは?経費を計上する要件や具体例などを解説
更新

企業が給与・賞与以外で従業員のために支出するお金は、基本的に福利厚生費として計上します。ただし、福利厚生費を経費として計上するためには、一定の要件を満たさなければなりません。福利厚生費は要件をきちんと理解したうえで活用していくことが重要です。
本記事では、福利厚生費を経費として計上する要件や具体例などについてわかりやすく解説します。福利厚生費と消耗品費、交際費との違いにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
福利厚生費とは企業が従業員のために支出した給与以外の費用のこと
福利厚生費は、企業が従業員に対して給与・賞与とは別に提供する保障やサービスにかかる費用です。近年の働き方改革の浸透に伴い、働き方の見直しやワークライフバランスに対する意識も高まりつつあります。こうした社会情勢の変化から、福利厚生制度は従業員の離職防止に寄与する効果も期待されています。福利厚生制度は、従業員の生活の安定・仕事のモチベーション向上を目的とした施策や取り組みの総称です。
なお、福利厚生費を経費として計上するためには一定の要件を満たす必要があります。要件を満たしていれば全額損金計上でき、従業員にとっても所得税の非課税対象となるため、節税対策としても有効になります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
福利厚生費の分類
福利厚生費には、大きく分けて「法定福利費」と「法定外福利費」があります。それぞれに該当する費用を整理して確認しておきましょう。
法定福利費
法定福利費とは、法律で企業に義務付けられている保険などにかかる費用のことです。法定福利費の一例として、以下のうちの事業主負担分が該当します。
法定福利費の一例
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
これらの費用は、会計上では法定福利費として計上します。
法定福利費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
法定外福利費
法定外福利費は、法律上の規定はなく、各企業が独自に取り組む福利厚生制度にかかる費用です。法定外福利費の一例としては、以下のものがあげられます。
法定外福利費の一例
- 健康診断費用
- 慶弔見舞金
- 従業員の親睦や慰安を目的としたお花見や運動会の費用
- 社員旅行の移動・宿泊費用
- 給湯室や休憩室に置くお茶やコーヒー代
法定外福利費はあくまでも「従業員のために支出した費用」です。したがって、個人事業主自身や個人事業主や従業員の家族のための支出は法定外福利費には該当しません。ただし、個人事業主で家族以外の従業員がいる場合、その従業員のために支出した費用は、法定外福利費として計上できます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
福利厚生費として認められる要件
福利厚生費として認められる要件には、「機会の平等性」「金額の妥当性」「現物以外の支給」の3点があります。それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。
機会の平等性
機会の平等性とは、すべての従業員が公平に福利厚生制度を利用できることを指します。一部の従業員しか利用できない食堂や保養地、健康診断費用などは福利厚生費として認められません。例えば、役職や部門によって福利厚生制度を利用できる人とできない人がいる場合、機会の平等性が保たれていないことになります。通常、福利厚生費は所得税の課税対象外ですが、このようなケースでは、メリットを受ける従業員にとっての現物給与として扱われ、給与所得の課税対象となる点に注意しましょう。
金額の妥当性
金額の妥当性とは、福利厚生費として支出する金額が企業の規模や業界の平均、さらに一般的な常識に照らして妥当な範囲であることを指します。例えば、ごく少人数の従業員での1泊2日の慰安旅行に何百万円も支出したような場合は、福利厚生費として金額の妥当性がありません。福利厚生費の金額が妥当かどうかは、福利厚生制度の目的や企業の財務状況、従業員数などを総合的に鑑みて税務署が判断します。
現物以外での支給
福利厚生制度は原則として現物支給ではなく、サービスや機会の提供として行われる必要があります。現金の他、金券など換金性の高いものを支給した場合、従業員の給与として扱われ課税対象となる点に注意しましょう。
例えば、食事代の支給や借上げ社宅の貸与なども現物支給に含まれます。食事の場合、従業員の食事代を現金で支払う食事手当などは原則として課税対象です。その一方で、食事代の半分以上を従業員が負担、かつ企業負担が従業員1人当たり月額3,500円以下の場合は非課税となります。また、借上げ社宅に関しても、住宅手当として現金で支給した場合は従業員に課税されますが、従業員から1か月当たり一定額の家賃(基本的に賃貸料相当額の50%以上)を受け取っていれば非課税です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
福利厚生費の具体例
ここでは、福利厚生費に該当するものとそうでないものについて紹介します。具体例と共にそれぞれ詳しく見ていきましょう。
福利厚生費に該当するもの
| 名称 | 条件など |
|---|---|
| 健康診断費用 | 従業員・役員が健康診断を受診する際の費用。以下の3つの条件を満たせば、福利厚生費として認められる。
|
| 慶弔見舞金 | 従業員や役員に対し、慶事・弔事の際に一定の基準に従って支払うもの。 結婚祝い、出産祝い、香典、災害や傷病などの見舞金の他、祝いまたは見舞いの品、結婚式場・斎場に飾る花にかかった費用も含まれる。 |
| 通勤手当 | 従業員の通勤にかかる電車代・ガソリン代などのすべて、または一部を企業が負担するもの。電車やバスの場合は月額15万円以内など、一定の限度額内なら一般的には旅費交通費にすることが多いが、福利厚生費として計上する事業者もいる。 |
| 社宅の提供 | 企業が物件を借り上げ、従業員に社宅として貸し出している場合、従業員から受け取る家賃と物件のオーナーに支払う賃料の差額を福利厚生費として計上できる。 ただし、その年度の家屋や敷地の固定資産税の課税標準額から算出された賃貸相当額を差し引いている場合には、給与所得として課税しなくていいとされている。 |
| 社員旅行の費用 | 旅行期間が4泊5日以内、かつ全従業員の50%以上が参加している、金額が社会通念上妥当であることを条件として、福利厚生費として認められる。 |
| 忘年会や新年会の費用 | 全従業員を対象に行うこと、企業の負担が一律であること、常識的な範囲の金額であることなどを条件として、福利厚生費として認められる。 その一方で、「二次会の経費を企業で精算」というケースは福利厚生費で処理することは難しいケースがある。通常、二次会は「有志のみ」であり、その場合、特定の従業員が対象、という判断になる。 |
| 育児・介護支援費用 | 病児保育利用時の補助金や保育園料の補助、介護保険対象サービス利用料の補助などは、すべての従業員・役員が利用できるものであれば、福利厚生費として認められる。 |
| 残業時の食事代 | 勤務時間外の業務に対する食事代であること、内容が常識の範囲内であることを条件として、福利厚生費として認められる。ただし、アルコールが含まれている場合は、認められない可能性がある。 |
| 外部の福利厚生サービスの利用費 | 外部の福利厚生サービスを利用するために支出した費用は、福利厚生費として計上できる。ただし、社内で機会均等を担保する一定の規定を設けていることが必要。 |
| 従業員の食事補助 | 役員・従業員が食事代の半分以上を負担し、かつ企業の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として認められる。 |
福利厚生費に当たらないもの
| 名称 | 条件など |
|---|---|
| 現金や商品券の支給 | 現金や商品券など換金性の高いものを支給した場合、福利厚生費ではなく、給与扱いになる。 |
| 研修旅行 | 企業の業務遂行に必要なものである場合は、研修費や旅費交通費として計上できる。ただし、業務遂行に直接関係のない、観光などが主目的の場合は、旅費交通費として計上できない。 ただし、社員旅行に該当する場合は福利厚生費として費用を計上できる。 |
| 従業員に対する無利息や低利息での貸付金の利息 | 基本的に従業員への貸付金は、福利厚生費ではなく給与として扱われる。ただし、従業員が災害や病気などで臨時に生活資金を必要としている場合、企業が合理的な利率を定めて貸付けを行っている場合、企業は従業員に対し、無利息や低利息での貸付けが可能。 |
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
福利厚生費とその他の勘定科目との違い
福利厚生費と間違いやすい勘定科目として「消耗品費」と「交際費」があります。福利厚生費との違いについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
福利厚生費と消耗品費との違い
福利厚生費と消耗品費の違いは、業務上必要なものに使用する費用であるかどうかです。
消耗品費は、業務に必要な物品のうち、繰り返し使用すると使えなくなる事務用品や備品を購入した際の費用を指します。消耗品費として計上するには、「耐用年数が1年以内」「取得価額が10万円未満」の条件のうち、いずれかを満たすことが必要です。例えば、業務で使用するボールペンや作業服などの購入費は消耗品費に該当します。
これに対して、福利厚生費は業務に直接関係のない支出であっても、条件を満たせば計上が可能です。例えば、企業の周年記念などに全従業員へ配布する記念品などは、業務に使用する物品ではなかったとしても福利厚生費として計上して差し支えありません。消耗品費として計上できるのは業務に必要なものに限られる点が、福利厚生費とは大きく異なります。
福利厚生費と交際費との違い
福利厚生費と交際費では、費用の使途が異なります。
交際費とは、取引先や得意先など事業に関係のある者に対する接待・供応のほか、お歳暮・祝い品を贈る際にかかる費用のことです。つまり、あくまでも対外的にかかる費用のことを指します。
これに対して、福利厚生費は自社の従業員のための制度や設備、報酬にかかる費用です。よって、費用の使途が社外との交流を目的としたものであれば、福利厚生費ではなく交際費として計上する必要があります。例えば、忘年会や新年会を催す際、自社の全従業員が参加するのであれば福利厚生費に計上できますが、取引先の従業員も参加する場合は交際費として処理しなければなりません。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
弥生のあんしん保守サポート加入で福利厚生を活用しよう
企業が従業員のために支出した費用は、すべてが福利厚生費として認められるわけではありません。福利厚生費として認められるには、機会の平等性、金額の妥当性、現物以外での支給、といった3つの要件を満たす必要があります。条件を満たさない場合は給与扱いとなり、従業員の税負担を増やすことがあるため、福利厚生費として認められるかどうかはしっかり検討することが大切です。
また、福利厚生制度の充実は、人材の確保や社員のモチベーション維持のために欠かせません。特に、社員1人が果たす役割の大きい中小企業にとっては、より重要な課題といえます。ところが、中小企業における福利厚生費は、大企業と比較するとかなり少ないのが現状です。福利厚生制度のコストに悩む経営者も、数多くいると考えられます。
そこで、おすすめなのが弥生の福利厚生サービスです。弥生では、「あんしん保守サポート」に加入されている企業の方やそのご家族に「弥生の福利厚生サービス クラブオフ」を提供しています。クラブオフは、入会金・月会費などは一切不要で、会員登録するだけで、さまざまな優待メニューが利用可能です。クラブオフで提供しているメニューは、グルメ・レジャー・旅行など種類豊富で、さまざまな場面でお得にご利用いただけます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
福利厚生費を計上する要件を正確に理解したうえで活用しよう
福利厚生費は、企業が従業員に対して給与・賞与とは別に提供する保障やサービスにかかる費用です。福利厚生費として認められるには、機会の平等性・金額の妥当性・現物以外での支給といった要件を満たしていなければなりません。また、福利厚生費と明確に区別するべき勘定科目として、消耗品費と交際費があり、しっかり該当する費用の違いを把握することが大切です。こうした会計処理を効率的に進めるには、会計ソフトの活用をおすすめします。会計ソフトを利用することで、福利厚生費などの処理をスムーズに行うことができます。弥生の会計ソフトを活用して、会計処理をより手軽に進め、従業員のための福利厚生にも積極的な取り組みを行いましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
よくあるご質問
福利厚生費の具体例は?
福利厚生費の具体例は、「健康診断費用」「慶弔見舞金」「通勤手当」「社宅の提供」「社員旅行の費用」などです。機会の平等性・金額の妥当性・現物以外の支給の3つの要件を満たしたものが福利厚生費として認められます。 詳しくはこちらをご確認ください。
福利厚生費にならないものは何ですか?
福利厚生費にならないものは、「換金性の高い現金や商品券の支給」「業務遂行に直接関係のない、観光などが主目的の場合の研修旅行」「従業員に対する無利息や低利息での貸付金の利息」などがあげられます。 詳しくはこちらをご確認ください。
福利厚生費と消耗品費の違いは?
福利厚生費と消耗品費の違いは、業務上必要なものに使用する費用であるかどうかです。消耗品費は、業務に必要な物品のうち、繰り返し使用すると使えなくなる事務用品や備品を購入した際の費用を指します。これに対して、福利厚生費は業務に直接関係のない支出であっても、条件を満たせば計上が可能です。 詳しくはこちらをご確認ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。