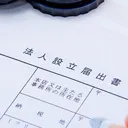会社設立日の決め方は?事業開始日との違いや注意点を解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

会社を設立する場合、設立日にこだわりを持って、縁起の良い日などを希望する人もいます。会社設立日は、どのような方法で決まるのか、自分の好きな日に設定することはできるのか、知りたい人も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、会社設立日を決める方法や、設立日を決めるときのポイント、設立日を決める際の注意点などを解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立日とは、法人登記を法務局へ申請した日のこと
会社設立日とは、法人登記を法務局へ申請した日のことです。
すべての会社には、設立にあたって法人登記を行うことが義務付けられています。法人登記とは、社名(商号)や本店所在地、事業の目的といった会社に関する情報を法務局に登録することです。管轄の法務局に対して法人登記の申請を行い、受理された日が、会社設立日となります。そのため、会社設立日を選びたいのであれば、会社設立日としたい日に法人登記を申請するといいでしょう。
なお、法人登記は、申請が受理されてから登記が完了するまでに、一般的に1週間~10日程かかります。会社設立日は、「登記を申請した日」であり、「登記が完了した日」ではありません。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立日と混同されやすい言葉
会社の設立日はあくまで登記を申請した日で、会社が事業を始めた日などではありません。以下の2つの言葉は会社設立日と混同されやすいため、正確に使い分けられるようにしておきましょう。
会社設立日と混同されやすい言葉と意味
- 創立日とは、組織や団体を初めてつくり、事業を開始した日
- 事業開始日とは、会社として実質的に事業活動を始めた日
創立日とは、組織や団体を初めてつくり、事業を開始した日
創立日とは、組織や団体を初めてつくり、事業を開始した日のことです。組織や団体であることが前提となるため、1人だけで行っている個人事業には創立日はありません。また、設立日と異なり、法人登記の有無も無関係です。例えば、会社だけではなく、学校や非営利組織などでも、創立日という言葉を使います。
事業開始日とは、会社として実質的に事業活動を始めた日
事業開始日とは、会社として実質的に事業活動を始めた日を指します。会社の存在が法的に認められるのは登記完了時ですが、実際に取引を開始するためには、登記が完了してからも準備が必要です。
例えば、法人口座は登記が完了してからでなければ作れません。場合によっては、事業開始日は会社設立日よりも後になります。事業開始日と会社設立日を、混同しないようにしましょう。
- ※創業、設立、創立などの違いについては以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
登記申請の方法によって会社設立日が変わる
法人登記の申請には、窓口で申請、郵送で申請、オンラインで申請の3つの方法があります。どの方法で申請するかによって、受理される日、つまり会社設立日の扱いが変わります。なお、いずれの方法でも、法務局の休業日(土日祝日や年末年始)を会社設立日とすることはできません。もし会社設立日にしたい日が法務局の休業日にあたる場合は、再検討が必要です。
登記の申請方法によって、会社設立日は以下のように変わります。
登記申請の方法と会社設立日
- 窓口申請の場合は、窓口で提出して受理された日が会社設立日
- 郵送申請の場合は、書類が到着して受理された日が会社設立日
- オンライン申請の場合は、申請データが受理された日が会社設立日
窓口申請の場合は、窓口で提出して受理された日が会社設立日
窓口申請の場合は、登記申請書類一式を管轄の法務局の窓口で提出して受理された日が会社設立日となります。法務局の窓口対応時間は、土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)を除く9時~17時です。希望する設立日を設定したい場合は、窓口の対応時間内に申請書類を提出できるように、しっかりと準備しましょう。
郵送申請の場合は、書類が到着して受理された日が会社設立日
管轄の法務局宛に登記申請書類を郵送した場合、書類が到着して受理された日が会社設立日になります。書類を発送した日ではありません。
また、郵送した登記申請書類は、法務局に届くだけではなく、受理される必要があります。法務局の業務時間は土日祝日と年末年始を除く8時30分~17時15分までです。郵送した書類が業務時間外に到着した場合、受理されるのは翌業務日になるため、希望の日付がある場合は特に注意しましょう。
オンライン申請の場合は、申請データが受理された日が会社設立日
オンラインで法人登記の申請を行う場合は、申請データが受理された日が会社設立日となります。法人登記のオンライン申請には、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用する方法と、デジタル庁の「法人設立ワンストップサービス
」を使って手続きする方法があります。
それぞれの利用可能時間は、「登記・供託オンライン申請システム」は土日祝日と年末年始を除く8時30分~21時で、「法人設立ワンストップサービス」はメンテナンス時間を除き24時間365日です。ただし、いずれの場合でも登記申請データを17時15分より後に送信すると法務局の業務時間外となるため、受理されるのは翌業務日になります。
なお、申請時に不備があったりエラーが発生したりすると、申請日がずれる可能性があるため、希望する設立日がある場合は窓口で直接申請することを検討しましょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立日は土日祝日と年末年始を除き自由に決められる
土日祝日と年末年始を除けば、会社設立日は自由に決めることが可能です。もし特定の日にちを会社設立日にしたい場合は、登記申請書類がその日に受理されるように手続きを行う必要があります。
会社設立日を検討する際には、主に以下の観点で考えることができます。自身にとって最も重視したいポイントを検討しましょう。
会社設立日を決める際の考え方
- 消費税の免税期間を考慮する
- 住民税の月割計算を考慮する
- 所得税と法人税の税率差を考慮する
- 縁起が良いとされる日を選ぶ
- メモリアルデーを選ぶ
消費税の免税期間を考慮する
会社の設立日を検討する際に、消費税の免税期間を考慮する考え方があります。
資本金が1,000万円未満で設立された会社は、原則として設立1期目と2期目の消費税の納税義務が免除されます。法人は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が発生しますが、新設法人には前年や前々年の売上が存在しないため、原則として消費税を収める必要はありません。ただし、1期目の前半6か月の売上と給与支払額が1,000万円を超えた場合は、2期目から課税事業者となります。
設立1期目の課税売上高が1,000万円を超えそうな場合、消費税の免税期間を最大限活用したいのであれば、会社設立日は事業開始日とできるだけ近い日に設定するとよいでしょう。会社設立後、実際に取引をしたかどうかにかかわらず、1期目の課税期間は設立日から決算日までです。会社設立日から事業開始日までが長くなると、その期間は売上がないので、消費税の免税メリットも受けることができません。
例えば、会社設立日から事業開始日までに6か月の期間が空いた場合は、消費税の免税期間は、実質的には1年半程度になってしまいます。法人口座の開設や許認可申請など、会社設立後でなければできない手続きもありますが、できるだけ事業開始の準備を整えてから登記申請を行って早めに事業を始めると、消費税の免税メリットを最大化することが可能です。
ただし、インボイス制度に対応して会社設立と同時に適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上高の金額にかかわらず課税事業者になるため、消費税の免税期間はないことを留意しておきしょう。
- ※会社設立時の消費税の納税義務については以下の記事を併せてご覧ください
住民税の月割計算を考慮する
会社設立日を検討する際に、住民税の月割計算を考慮する考え方もあります。会社設立日を2日以降の日付にすると、法人住民税の負担を軽減できます。
法人住民税は、法人税の税額をベースにして算出される法人税割と、資本金の金額や従業者数などに応じて税額が決まる均等割によって構成されています。均等割は課税所得に関係なく計算されるため、赤字でも原則として納税義務しなければなりません。
この均等割は、会社の事務所がその自治体にあった月数に応じて年間の税額を月割計算しますが、1か月のうち1日でも欠けている月は切り捨てとなります。少しでも節税したい場合は、設立日を1日ではなく2日以降の日付に設定するのも1つの方法です。
所得税と法人税の税率差を考慮する
所得税と法人税の税率差を考慮して、会社設立日を決める考え方もあります。個人事業主が法人化する場合は、会社設立日をいつにするかによって、最終的な納税額を節税することも可能です。
個人事業主と会社では課税される税金の種類が異なり、個人事業主は所得税、会社では法人税がかかります。個人事業主の所得税は、所得が高くなるほど段階的に税率が上がる累進課税で、税率は5~45%です。対して法人税の税率は、資本金1億円以下の会社であれば、年間所得のうち800万円以下の部分に対して15%、800万円超の部分に対して23.2%です。
個人事業主の事業年度は1月1日~12月31日と決まっていますが、会社の事業年度は1年以内の任意の期間で自由に設定することができるため、個人事業主の事業年度の途中で法人化すれば、所得税の適用税率を調整できます。例えば、事業年度の途中で所得税の税額と法人税の税額を検討し、所得税のほうが有利な課税所得までは個人事業主として活動し、有利不利が逆転しそうなタイミングで法人化するのも1つの方法です。
法人化による節税効果は、課税所得や個人で適用できる所得控除、役員報酬などによって異なります。法人化で節税につなげたい場合は、会社設立前に税理士に相談し、アドバイスを受けましょう。
縁起が良いとされる日を選ぶ
会社設立日にこだわるなら、一般的に縁起が良いとされる日を選ぶのも1つの考え方です。日本で縁起が良いといわれている日としては、以下があげられます。
大安または先勝
六曜の中で最も縁起が良いとされる日が大安です。大安は、事業の開始の他、旅行、結婚など、何をするにも吉とされる日です。また、同じく六曜の先勝では、「先んずればすなわち勝つ」といった意味があるため、会社設立日には適した日といえます。
先勝では、早めに行動すると良い結果に結びつくと考えられているため、先勝を選ぶ場合は午前中に申請手続きを行いましょう。
一粒万倍日
一粒万倍日は、「一粒のもみが万倍にもなって実る」といった意味から、この日に始めたことは大きな成果を上げると考えられている縁起の良い日です。一粒万倍日は、立春、夏至、冬至などの二十四節気と、干支の組み合わせによって決まりますが、その決まり方は複雑です。カレンダーなどには記載されていないケースもあるため、知りたい場合はWeb検索などで調べましょう。
天赦日
天赦日(てんしゃび・てんしゃにち)は、あらゆる障害が取り除かれるとされる、縁起の良い日です。二十四節気に基づく季節の区切りと干支によって決まり、年に数回しか訪れません。暦のうえでは最上の吉日とされています。気になる場合は、Web検索などで調べるとよいでしょう。
寅の日
寅の日は、お金に関して縁起の良い日といわれています。十二支の寅にあたる吉日で、12日ごとに巡ってきます。寅の色が黄金を連想させることから、金運が上がる日と考えられているため、それにあやかりたい場合は寅の日を設立日として検討してみてはいかがでしょうか。
8のつく日
8のつく日は、漢字の「八」が外に向かって広がっていることから、末広がりを連想させる縁起が良い日です。長期的な繁栄や発展、拡大といったイメージにつながるため、会社設立日にも選ばれることも少なくありません。
メモリアルデーを選ぶ
会社設立日を決める際、個人的に思い入れのあるメモリアルデーを選ぶ方法もあります。メモリアルデーを会社設立日にすれば、大切な日なので忘れにくい点もメリットです。例えば、自分や家族の誕生日、事業を始めるきっかけとなる出来事があった日、会社の設立を決めた日など、自分の人生や判断に大きな影響のあった日を設立日に設定するのは、1つの選択肢といえます。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立日を決める際には注意点もある
会社設立日を考える際には、注意しなければならないポイントもあります。設立登記申請をスムーズに行うためにも、以下の2点を意識して設立日を決めましょう。
会社設立日を決める際の注意点
- 会社設立日は後から変更ができない
- 登記申請は会社の本店所在地を管轄する法務局で行う必要がある
会社設立日は後から変更ができない
一度決まった会社設立日は、後から変更することができません。会社設立日は、登記の申請日で決まります。例えば、登記申請をしてから「やっぱり他の日にしたい」と登記の申請日を変更することは、認められません。
また、郵送申請やオンライン申請の場合、郵便事情やシステムトラブルなどによって、申請の受理が想定していた日とずれてしまう可能性があります。会社設立日にこだわりたいなら、法務局の窓口で直接登記申請を行う方が確実です。
登記申請は会社の本店所在地を管轄する法務局で行う必要がある
法人設立登記の申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。管轄外の法務局に申請しないように注意しましょう。登記を申請する法務局を間違えると、改めて正しい法務局に書類を提出しなければならず、希望する日に登記申請ができなくなるかもしれません。
法務局ごとの管轄区域は、法務局のWebページ「管轄のご案内」で確認できます。なお、中には各種証明書の交付のみを取り扱い、法人登記申請には対応していない窓口もあるため、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。
- ※会社設立の流れについては以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
「弥生のかんたん会社設立」なら会社設立を手軽に行える
ここまで見てきたように、希望する会社設立日を決めていても準備が間に合わなかったり、不備があったりすると、思い通りに進められないケースもあるでしょう。そんなときは、「弥生のかんたん会社設立」を利用すると安心です。
「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。なお、会社設立で一定の基準を満たすと特定創業支援等事業の支援対象となり、会社設立登記時に登録免許税が軽減される特例措置を受けることができますが、「弥生のかんたん会社設立」でも軽減された登録免許税の支払いに対応しています。
- ※特定創業支援等事業の詳細については以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
希望どおりの会社設立日にするために、入念に準備しよう
会社設立日は、法務局へ法人設立登記の申請を行った日です。もし会社設立日にこだわりがある場合は、希望する日に確実に登記申請ができるように、しっかりと準備をしておかなければなりません。せっかく設立日を決めても、当日までに必要書類が揃わなければ、登記申請を行うことができなくなってしまいます。
また、会社設立のタイミングが、設立後の税金に影響することもあります。自分だけで設立日を決めるのが難しい場合や、準備に不安がある場合は、前もって税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
会社設立の手続きをスムーズに進めたい場合は、「弥生のかんたん会社設立」といったクラウドサービスを活用することで、会社設立にかかる手間とコストを抑えることが可能です。便利なクラウドサービスを上手に活用して、スムーズな会社設立を行ってください。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。