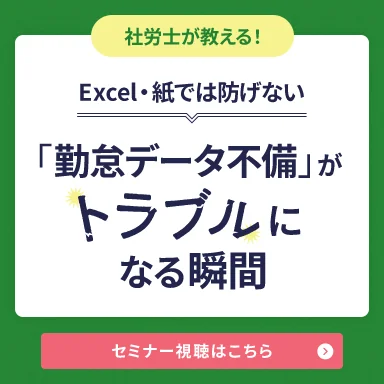勤怠管理とは?目的や方法別のメリット・デメリットを解説
監修者: 下川めぐみ(社会保険労務士)
更新

勤怠管理とは、法律に従って従業員の労働時間を記録し、管理を適正に行うことです。専用のシステムやエクセル、タイムカードを使用して労働時間を記録し、担当部署が集計して労働時間の管理、給与計算などに利用します。
本記事では、勤怠管理をする際に知っておきたい基本知識や管理方法ごとのメリット・デメリット、管理上の必須項目などを解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
勤怠管理とは
勤怠管理とは、労働基準法に従って企業が従業員の労働時間を適正に記録し管理することです。労働基準法においては労働時間や休日についての規定があるため、企業は規定通りに管理する義務があります。
勤怠管理の手段は企業によって異なります。大規模な企業の場合はタイムカードやICカード、パソコンを使って記録できる勤怠管理システムで管理することが多いでしょう。その一方で、中小規模の企業の場合は管理が必要な従業員数が少ないため、紙の出勤簿やエクセルなどで管理することも珍しくありません。
なお、勤怠管理は労務管理業務の1つであり、労務部が担当するケースが多く見られます。しかし、組織によって担当部署が異なる場合もあり、総務部や人事部などの別の部署が担当することもあります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理を求められる企業・事業所
労働基準法第4章の「労働時間に関する規定」が適用される全事業場は、勤怠管理が必要です。原則として規模や業種を問わず、ほとんどの企業に勤怠管理の義務があります。
例外として、農業や水産業は一部の規定が適用されない業種です。天候や自然条件に労働時間が左右されるという業務の性質上、労働・休憩の時間、休日の規定が適用されません。ただし、加工や販売をする場合は、労働の実態に応じて労働時間の規定が適用されることがあります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理が求められる従業員
労働基準法の定めでは、管理監督者や裁量労働制の従業員を除く、全従業員が勤怠管理の対象です。ここでいう管理監督者とは、部長や工場長などが挙げられます。ただし、役職名ではなく職務内容の実態で判断されるため、経営者と同じように労働条件や労務管理を決定・管理する立場にある者が管理監督者の地位にあるものとみなされます。
労働安全衛生法が改正されてからは、健康管理の観点から管理監督者や裁量労働制の従業員も労働時間の把握が必要になりました。そのため、実際は高度プロフェッショナル制度によって働く従業員を除く、全従業員の就業時間の記録と管理が求められます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
従業員の勤怠管理を行う目的
企業が勤怠情報を管理する目的および法的な理由について解説します。
労働基準法・労働条件を遵守するため
労働基準法において、法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間以内と定められています。休日については、従業員に対して最低でも週1回は付与しなければならない法定休日の定めがあります。変形休日制を導入している場合は、4週間のうち4日以上の付与が必要です。
法定労働時間以上の労働は時間外労働として扱われます。時間外労働が発生する場合、企業は従業員と36協定を締結したうえで、労働基準監督署への届出が必要です。時間外労働にも制限があり、月に45時間、年間で360時間以内の上限が設定されています。
繁忙期やその他の特別な事情があって、さらに上限を超過せざるを得ない場合は、特別条項付き36協定を締結します。その場合、時間外労働の上限は2~6か月の複数月平均が80時間以内、単月で100時間未満、年間で720時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで(※)です。
- ※年間720時間以内・月45時間超え年6回までの場合は「時間外労働」、2~6か月の複数月平均が80時間以内・単月100時間未満の場合は「時間外労働+休日労働」となります。
もし違反した場合は罰則が科される恐れがあります。こうした法令上の定めを遵守する前提として、正確な勤怠管理が欠かせません。
参照:e-GOV「労働基準法」
参照:e-GOV「労働基準法施行規則」
給与計算を正確に行うため
給与を計算する際は勤怠情報を利用するため、労働時間の把握は正確な給与額を算出するためにも必要です。給与の計算では通常の労働時間の他に、残業や休日労働の時間も確認して金額を算出します。
もし労働時間が正しく記録されていない場合、従業員に支払う給与額を間違えてしまう可能性があり、従業員に大きな迷惑がかかります。また、未払い賃金が発生する原因にもなり、労基法違反となってしまいます。そこで、ミスを起こさないためにも適切な勤怠管理をする必要があります。
なお、労働基準法でも、賃金台帳に労働の時間や日数などを適正に記録しておくことが義務付けられています。
従業員が健康的に働けるようにするため
長時間労働は深刻な問題として認知されています。政府はこの問題への対策の1つとして、働き方改革関連法で、企業に労働時間の客観的な把握を義務付けています。これは労働安全衛生法で定められている義務である、長時間労働した従業員に対する医師の面接指導の実施を果たすためにも必要な取り組みです。
従業員の健康を守ることは、企業の生産性を保つことにもつながります。適切な勤怠管理は健康的に働ける職場作りにも欠かせません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理によって管理する項目
勤怠を管理する際の項目について解説します。給与計算や労働時間の調整にも関係するため、漏れのない記録と管理が必要です。
従業員の始業・終業時刻、労働・休憩時間
労働時間の管理のために、始業・終業時刻、労働時間、休憩時間の項目を記録する必要があります。始業・終業時刻は会社に到着したときや退社した時刻ではなく、仕事を始めた時刻と終わった時刻を記録します。8時に到着して9時から仕事を始めたなら、9時が始業時刻です。
労働時間として扱うのは、始業~終業時刻の勤務時間から休憩時間を引いた時間です。8時間勤務して休憩時間が1時間なら労働時間は7時間となります。給与計算でも確認するため、始業と終業時間は1分単位での管理が原則です。
時間外労働・休日労働・深夜労働の時間
所定労働時間以外に時間外労働(所定外・法定外残業)が何時間発生したのか、休日(法定・所定)労働や深夜労働が何時間あったのかの管理も必要です。深夜労働は22時~翌朝5時に働いた場合のことを指します。
もし法定外の残業や休日、深夜に従業員が勤務していた場合、企業は割増賃金を支払わなければなりません。正確に給与を計算するためにも、これら3つの労働時間の把握が必要です。
割増賃金の金額は通常の給与の25~50%以上の範囲で計算します。割増率は法定外残業・休日勤務・深夜勤務のうち何が発生したのかによって変動します。
割増賃金についてはこちらの記事で解説しています。
出勤日・欠勤日・休日の日数管理
従業員の労働時間以外に、出勤・欠勤・休日の日数管理もする必要があります。休日に関しては労働基準法において法定休日が定められているため、休日出勤をした従業員がいたら振替休日や代休を取得しているかを管理します。
休日取得状況の管理は、企業にとって従業員の健康管理や生産性の維持に役立ちます。また、出勤と欠勤の日数は給与計算にも影響する、重要な管理項目の1つです。
有休を取得した日数と残日数
企業は要件を満たす従業員に有給休暇を付与する義務があります。また、年10日以上の年次有給休暇を付与する労働者に対しては、最低でも年5日有給休暇を取得させることも企業の義務です。この場合、労働者から取得時季の希望を聞き取ったうえで付与します。
義務を果たすにあたっては、従業員が有給休暇を適切に取得しているかどうかの記録と確認が必要になるため、有給休暇の取得日数、残日数は必須管理項目です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
勤怠管理の主な方法4つとそれぞれのメリット・デメリット
勤怠の主な管理方法は、次の4つに大きく分けられます。それぞれの特徴や良い面と悪い面について、以下で詳しく解説します。
-
1.紙の出勤簿
-
2.エクセル
-
3.タイムカード
-
4.勤怠管理システム
1. 紙の出勤簿で勤怠管理する方法
紙に印刷したカレンダー形式の出勤簿に、一定の記載項目を記入します。決まったフォーマットはないため記載項目は任意で決められますが、一般的にはその日の始業・終業時刻、労働時間や残業時間、休日・深夜労働の時刻と時間、休憩時間、遅刻・早退、休暇取得などを記載します。
記入された出勤簿は月の締め日に担当者が回収し、総労働時間や有給休暇取得の有無などの集計や給与計算システムに反映させる作業を行います。
紙の出勤簿で勤怠管理するメリット
導入に必要なものが紙と筆記用具だけのため、ITツールの導入と比べて低コストで始められる点がメリットです。出勤簿のフォーマットはインターネット上でテンプレートを入手すれば、すぐにでも社内に導入できます。
アナログな手段のため、コンピューターやITツールが苦手な従業員が多い職場でも使いやすいというメリットがあります。また、紙の出勤簿は、勤怠管理のために新しいITツールを導入するほどではないケースにも適した管理方法です。特に小規模の企業の場合は、手書きでもそれほど負担なく勤怠管理できます。
紙の出勤簿で勤怠管理するデメリット
紙の出勤簿で勤怠管理する場合、手書きしたときに記入ミスが発生する可能性があります。アナログな方法のため管理が社内に縛られてしまい、テレワークや社外での管理ができない点もデメリットです。ITツールでは当たり前となっているデータのリアルタイム反映や集計作業、記録検索の効率化もできません。そのうえ、紙媒体のため保管スペースも必要になります。
デジタルデータの場合はバックアップを容易に取れますが、紙媒体は紛失すると復元できない点も不便です。さらに、紙の出勤簿は自己申告となるため客観性に欠ける手段であり、不正申告のリスクもあります。
厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために、始業・終業時刻の記録はタイムカードやICカードなどの客観的な記録を基礎とすると定めています。紙の出勤簿は客観的な記録とみなされない場合がありますが、ガイドラインにある措置の条件を満たすことで紙の出勤簿での勤怠管理が認められます。
参照:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 」
2. エクセル(Excel)で勤怠管理する方法
従業員がエクセルに出退勤時刻や残業時間などの情報を手入力し、勤怠管理を行う方法です。従業員が直接書き込む点は出勤簿と変わりませんが、エクセルなら表計算で一括管理できます。
なお、この方法は自己申告制扱いになるため、上述した厚生労働省が示すガイドラインに記載されている措置の条件を満たす必要があります。
エクセルで勤怠管理するメリット
エクセルは後述する勤怠システムと比べ、低コストで導入できる点がメリットです。また、同じ自己申告制の紙の出勤簿と比べても少ない労力で効率的に管理できます。
セルに数式を設定することで計算や集計を自動化できるため、計算ミスも減らせます。企業でよく導入されている表計算ソフトであり、従業員が操作方法に慣れていれば使い方を覚える負担が少ない点もメリットです。
知識さえあれば柔軟にカスタマイズできて、会社独自のフォーマットも作成が容易です。知識がない場合でも、勤怠管理用のテンプレートが無料でインターネット上に多く公開されており、ダウンロードすることですぐに導入できます。
エクセルで勤怠管理するデメリット
従業員が勤怠情報を手入力するため、入力ミスや改ざん、不正申告が発生する恐れがあります。また、エクセルの集計や転記作業、数式設定といった手作業が多いため、人的ミスのリスクが残る点もデメリットです。
さらに、変形労働時間制やフレックスタイム制などの複雑な勤務形態の管理も、エクセルでは難しい面があります。理由は、関数が複雑化して人的ミスが起きやすいうえに、担当者が異動や退職で担当を外れると、他者には数式などが理解できない可能性があるためです。そうなると、法改正に合わせた内容に変更できなくなる可能性もあります。
勤怠管理のテンプレートを利用すると自作する手間を省けますが、テンプレートが自社の就業形態とマッチするとは限らない点に注意しましょう。
3. タイムカードの打刻で勤怠管理する方法
従業員が紙のタイムカードをタイムレコーダーに差し込んで打刻し、始業・終業時刻を記録する方法です。タイムカードは1人につき1枚使用して1か月分の勤怠情報を記録します。集計作業は出勤簿やエクセルと同様で手作業が基本ですが、機種によっては自動集計やコンピューターとのデータ共有に対応するものもあります。
なお、タイムカードを使う方法は、厚生労働省のガイドラインでも客観的な記録として扱われます。
タイムカードで勤怠管理するメリット
手書きの出勤簿ほど手間がかからず、機器に差し込むだけで簡単に打刻できる点がわかりやすいメリットです。使い方がシンプルなので、だれでも覚えやすく、教育コストもかかりません。また、導入はタイムレコーダー1台とタイムカード代のみで済むため初期費用を抑えられます。ランニングコストも従業員分の用紙代やインク代、電気代だけで済むものがほとんどです。
タイムカードで勤怠管理するデメリット
始業・終業時刻の打刻は簡単にできますが、その他の機能の少なさがデメリットとして目立ちます。例えば、休日や残業時間の打刻はできないタイムレコーダーが多いため、時間外労働時間の記録は別の方法を考える必要があります。そして、打刻方法がタイムレコーダーへの差し込みだけの場合、直行・直帰や在宅勤務、テレワークの従業員が打刻できない点も不便です。
また、打刻ミスの修正に手間がかかるというデメリットも見られます。その他にも、紙で記録するため出勤簿と同様に保管スペースが必要になります。
複数拠点に導入する場合は、タイムカードを集めるのに手間がかかる点もデメリットです。多くのタイムレコーダーは集計機能が備わっていないため別のツールが必要になり、集計作業も時間がかかります。いつでもだれでも打刻できることを利用した不正打刻が発生するリスクもあります。
使用方法が簡単で導入も安価に済むメリットはありますが、適正な勤怠管理が求められる現代では使いづらさも目立つ方法です。
4. 勤怠管理システムで勤怠管理する方法
勤怠管理システムとは、従業員の始業・終業時刻の打刻と記録、時間外労働時間の記録、休暇申請などの勤怠情報を総合的に管理できるシステムを指します。
タイムレコーダーやデジタル端末との連携、集計・分析機能などがあり、他の方法よりも勤怠管理に便利な機能を豊富に利用できます。打刻方法も複数ある中から選択可能です。
勤怠管理システムで勤怠管理するメリット
勤怠管理システムの打刻方法はさまざまな種類があり、ICカードやスマートフォン、コンピューター経由の打刻、生体認証などに対応し、併用もできます。打刻の仕方も簡単で、ワンタッチで記録できるものも多いでしょう。テレワークや在宅勤務にも対応できます。スマートフォンの場合は、直行・直帰にも対応可能です。
休日や残業などの承認・申請作業もシステム上で完結できるため、管理者と従業員双方の手間も軽減可能です。給与システムと連携すれば、転記の手間がなくなるため、計算ミスも抑えることができます。
他の方法では不正申告のリスクや法改正対応の難しさといった課題がありますが、勤怠管理システムを使えば、課題を解決しながら勤怠管理業務を効率化できる点がメリットです。集計・分析業務の効率化、複雑な勤務形態の勤怠管理、休暇の取得状況の可視化などが可能になり、勤怠管理業務に必要な情報がシステム上に集約されます。
法改正への対応もクラウド型なら自動でアップデートされることが多いでしょう。従業員に打刻忘れの通知を出す機能や生体認証、GPS機能によって打刻忘れや不正申告も防止できるシステムもあります。勤怠情報はデータ化するため、紙の保管スペースも不要です。
勤怠管理システムで勤怠管理するデメリット
さまざまなメリットがある勤怠管理システムですが、他の方法よりも導入コストがかさみやすい点がデメリットです。初期費用は無料の場合もあれば、数万円以上かかるシステムもあります。月額料金は利用ユーザー数に応じた従量課金制が一般的で、多くの場合、1ユーザー当たり200~300円前後で利用できます。機能と価格は比例することが多いため、自社に必要な機能を考え、総合的に判断することが大切です。
また、多くのシステムがあり、自社に合うシステムを選定する手間がかかる点と運用が安定するまで試行錯誤が必要な点もデメリットです。自社の就業形態に合わないシステムを選んでしまうと期待した導入効果は得られません。失敗を避けるためには、必要な機能の洗い出しや、システムと自社の就業形態との相性を見極める必要があります。
システムを導入した後は、就業規則や勤務形態に合わせた設定作業や従業員に使い方を周知する負担が一時的に発生します。導入したら終わりではなく、組織に浸透するまでを見据えて計画を立てることが求められます。
導入から運用までが大変ですが、他の管理方法で課題となる部分を解決できて、さらに効率化され、手作業によるさまざまなリスクを回避できるメリットがあるため、導入を検討する価値は十分にあるでしょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
ケース別 勤怠管理に関して注意すべきポイント
管理する際、従業員の雇用形態や働き方によっては通常と異なる勤怠管理をしなければならないことがあります。主なケースについて詳しく解説します。
従業員が扶養控除内での就労を希望するケース
雇用形態がパートやアルバイトの場合、扶養内での就労を望んでいるケースがあります。この場合、労働の日数や時間が扶養控除の範囲内におさまるように調整が必要です。
扶養控除が適用されるか否かは年収によって変わります。よく挙げられる年収のラインとして、所得税の納付が発生する103万円や社会保険の加入が必要になる130万円(企業規模によっては106万円)などがあります。扶養から外れない年収の範囲で働きたい従業員もいるため、シフトを調整する際には相手の希望を聞き、よく話し合うようにしましょう。
扶養の種類や条件について、こちらの記事で解説しています。
従業員が契約社員であるケース
契約社員の待遇は、契約期間以外は正社員とほとんど変わらない場合があります。そのようなケースでは、正社員と異なる勤怠管理をする必要はありません。正社員と同じように残業や有給休暇などの勤怠情報を記録し、労働時間を管理しましょう。
派遣社員のケース
派遣社員の勤怠管理は、派遣元と派遣先でそれぞれ異なる項目を管理するため、他の雇用形態よりやや複雑です。
派遣社員は派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結んでいます。有給休暇の付与や給与支払は、勤怠情報を基に派遣元から派遣社員に対して行うしくみです。その一方で、労働時間や休日取得などの管理に関しては派遣先が担当するため、正確な給与が従業員に支払われるには派遣先から派遣元に正しい勤怠情報を報告しなければなりません。また、派遣を受け入れる企業(派遣先)は派遣先管理台帳を派遣社員ごとに作成する必要もあります。
その他については、勤怠情報の記録や管理は派遣先の従業員と同じ方法で行うのが一般的です。派遣先と派遣元で情報共有を円滑化するためには、打刻や承認の人的ミスが発生しにくい勤怠管理の徹底と、その手段を確立することも重要なポイントです。
テレワークや在宅勤務を行うケース
従業員がテレワークや在宅勤務をする場合、タイムカードやICカードを使った打刻ができません。その場合は、勤怠情報の記録はスマートフォンやコンピューターなどの端末からアプリや勤怠管理システムを使って打刻するか、自己申告するのが一般的です。
もし自己申告制を採用する場合は、従業員へルール説明をしたり、状況に応じて実態調査したりするなど、厚生労働省のガイドラインに沿った対応が必要になります。また、テレワークや在宅勤務は、実際の労働時間を把握しにくい点や労働時間が長時間化する課題が発生しやすいため、労働時間を正確に把握するしくみが重要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
効率的な勤怠管理を実現するならシステムの導入がおすすめ
勤怠管理とは、従業員の労働時間や休日取得日数などの勤怠情報を管理することです。法律の遵守や従業員の給与計算、健康管理、長時間労働の防止といった目的で行われます。管理方法は、厚生労働省のガイドラインにおいて「客観的に記録できる方法」が推奨されています。
給与計算業務を効率化するなら、弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」が便利です。他社の勤怠管理システムとの連携に対応しており、勤怠データを取り込むことでデータ入力の手間を削減できます。自社にあったシステムを導入して業務を効率化しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者下川めぐみ(社会保険労務士)
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ所属社労士。
医療機関、年金事務所等での勤務の後、現職にて、社会保険労務士業務に従事。