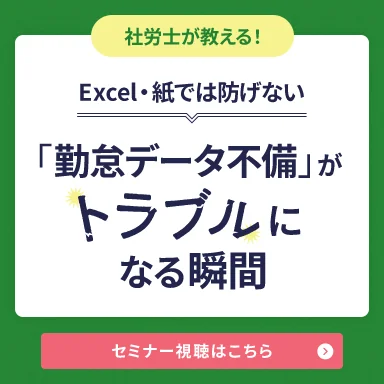勤怠管理をスマホで行うメリットは? 導入時のポイント
更新
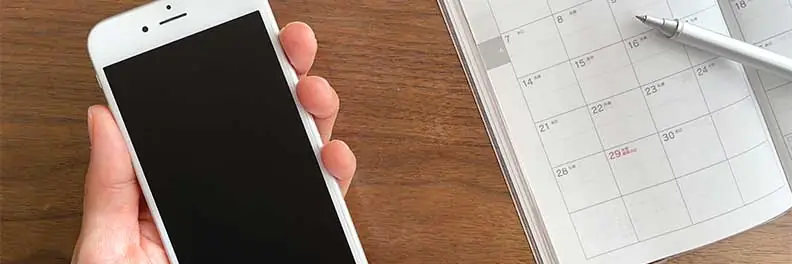
働き方の多様化に対応するため、スマホで勤怠管理を行えるシステムが注目を集めています。スマホは多くの人が日常的に所有しているため、勤怠管理の導入ツールとしてはハードルが低く、手書きやExcelでの管理に比べて、法令に則った勤怠管理を簡単に実現できる点が大きなメリットです。従業員を抱える企業や事業者にとって、スマホ勤怠管理システムは今後ますます活用が期待されるツールといえるでしょう。
本記事では、スマホで行う勤怠管理のメリットや、企業にとって重要な理由、導入時のポイント、勤怠管理システムの選び方などを解説します。「勤怠管理の務が多くて面倒」「正確な勤怠管理を行いたい」「外回りの多い従業員や、テレワーク勤務の従業員の勤怠管理に困っている」といった企業の担当者・事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
勤怠管理をスマホで行うメリット
スマホで利用できる勤怠管理システムには、業務を効率化する多彩な機能が搭載されており、企業と従業員の双方にとって便利で役立つツールです。ここでは、勤怠管理システムを活用することで得られる具体的なメリットを詳しく解説します。
場所を選ばず打刻ができる
スマホ対応の勤怠管理システムを導入すれば、従業員がどこにいても簡単に打刻できる環境を整えられます。営業や出張が多い従業員でも、スマホがあれば外出先からスムーズに勤務時間の記録が可能です。仮に打刻を忘れた場合でも、会社や店舗に戻る必要がなく、その場で対応できるため、勤怠管理の柔軟性が大きく向上します。
リモート勤務をしている従業員も、勤務場所からそのまま打刻できるため、場所を問わず働くスタイルにも適しています。
不正打刻対策になる
スマホ対応の勤怠管理システムを導入することで、「不正打刻」の防止にもつながります。
従来のタイムカードでは、本人が出勤していなくても同僚が代わりに打刻できるため、遅刻や欠勤の隠ぺいが可能です。また、Excelで勤怠情報を管理している場合も、従業員自身が出退勤時間を入力・修正できることから、正確性の担保が難しいという課題があります。
その点、スマホで行う勤怠管理なら、リアルタイムでの打刻が基本となるため、勤務情報の改ざんリスクを抑えられます。
さらに、スマホに備わっているGPSによる位置情報を活用すれば、打刻場所の把握も可能になり、外回りやテレワーク中の従業員が、適切な場所で勤務しているかどうかを確認する手段としても有効です。
位置情報が個人情報であることから、その履歴をとることは強制できないと思われるかもしれませんが、労働時間中に業務命令で営業活動等を行わせていることから、原則的に労働者はこの業務命令に従う義務があります。
勤怠管理のミスを減らせる
人為的なミスを防げる点もメリットです。
タイムカードを使用している場合、担当者が打刻情報を集計・計算する必要があり、その過程で転記ミスや計算ミスが発生するリスクが伴います。これにより、バックオフィスの作業負担が大きくなるだけでなく、勤怠データの正確性にも影響を及ぼしかねません。
その点、スマホで行う勤怠管理では、従業員が直接打刻を行い、そのデータが自動で集計されるため、手作業によるミスのリスクが大幅に軽減されます。
正確な勤怠管理が実現できることで、管理業務の効率化にもつながります。
法令遵守に役立つ
スマホで使える勤怠管理システムを活用すれば、オーバーワークの規制といった法令に則したアラート機能などを設定でき、コンプライアンスを順守し適切な対応が可能になります。
勤務時間や有給休暇に関する管理は、労働基準法によって厳格なルールが定められており、企業はその遵守が求められます。時間外労働の上限や有給休暇の取得義務など、対応すべき項目は多岐にわたり、人手による管理ではミスが起きやすいのが実情です。
さらに、労働基準法は定期的に見直しや改正が行われるため、最新の法改正に対応できる勤怠管理システムの存在は、企業にとって大きな安心材料となります。
従業員自身が勤怠を把握できる
スマホで打刻できる勤怠管理システムを導入すると、従業員は打刻データから自身の労働時間と残業時間をリアルタイムに把握できるため、自己管理が容易になりオーバーワークの防止に役立ちます。特に、日々の労働時間が変動しやすい人や残業が多い人に効果的です。
さらに、打刻漏れを検知してアラートを通知する機能を備えたシステムなら、上司や担当者が直接注意しなくても、従業員が自ら気付きやすい環境を整えられます。
正確な給与計算・労務管理につながる
スマホで利用できる勤怠管理システムの中には、給与計算機能を備えたものや、外部の給与計算ソフトと連携できるものもあり、勤怠データをスムーズに連携し活用することができます。
従業員の勤務時間を正確に把握しておくことは、給与規程に沿った正しい給与計算を行うための前提であり、残業時間の把握や人員配置の適正化といった労務管理の観点からも欠かせません。
勤怠管理システムを活用すれば、集計された勤怠データを基に残業代や社会保険料等を自動で算出でき、正確かつスピーディーな給与計算が実現します。
コスト削減ができる
打刻データの転記や集計を自動化すれば、バックオフィスの工数と人的ミスを同時に削減でき、人件費の抑制にもつながります。さらに、紙のタイムカードや帳票を使わないデジタル管理に切り替えることでペーパーレス化が進み、備品・消耗品コストも削減できます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
スマホで行う勤怠管理が企業にとって重要な理由
正確な勤怠管理は、法的に定められた企業の義務です。
労働基準法第108条では、使用者(雇用者)が労働時間などの記録を適切に管理することが義務付けられており、第32条で定められた法定労働時間を遵守するためにも、勤怠情報を正確に把握・管理する体制が不可欠です。
-
※
参照:e-Gov法令検索「労働基準法」
なお、法定労働時間を超えて労働する従業員がいる場合は、企業はあらかじめ「36協定」を結んでおかなければならないため注意しましょう。
36協定については、以下の記事で詳しく解説しています。
2019年4月に施行された改正労働安全衛生法により、企業には従業員の労働時間を客観的に把握することが義務付けられました。これにより、打刻記録の正確性や客観性がより重視されるようになり、スマホで行う勤怠管理の重要性も高まっています。
労働時間の客観的な把握について、以下の2点の改正点が大きく関連しています。
・労働安全衛生法第66条8の3
「事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。」
引用:e-Gov法令検索「労働安全衛生法
」
・労働安全衛生規則第52条の7の3
「第1項 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
第2項 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。(法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等)」
引用:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則
」
手書きやExcelによる自己申告制で勤怠を記録している場合、方法によっては労働関係法令に抵触する可能性があります。これらの方法をやむを得ず採用する場合でも、使用者には従業員の労働時間を適正に把握するための客観的な措置を講じることが求められます。
原則として、勤怠記録はタイムカードやコンピューターのログ、システム上の打刻記録など、客観的に確認可能な手段で行う必要があります。その点、スマホで使える勤怠管理システムであれば、外出先からでもリアルタイムで打刻できるため、労働時間を正確に把握・記録することが可能です。
-
※
参照:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
スマホで行う勤怠管理システム導入時のポイント
スマホで行う勤怠管理の導入は、企業・従業員の双方にとって多くのメリットがあります。
その一方で、注意すべき点も存在するため、導入前にしっかりと確認しておくことが重要です。
それぞれの従業員への対応など考える
スマホを持っていない従業員への代替手段を考えておくことが必要です。また、個人のスマホを使いたくないという従業員がいる可能性もあります。そうした場合は、会社でスマホやタブレットなどの端末を貸与するなどの対策をとり、すべての従業員に対応できるようにしておくことが求められます。実際にスマホやタブレット等の端末を会社側から貸与しているケースは少なくありません。
加えて、スマホで行う勤怠管理システムにすぐ順応できる従業員もいれば、慣れるまで時間のかかる従業員もいます。新システムをスムーズに導入するためには、あらかじめマニュアルの作成やヘルプデスクの設置をしておくことが理想です。
従業員に対して十分な説明ができるのか、きちんと導入・管理・運営ができるのかを考え、事前の準備を欠かさないようにしましょう。
緊急時の対策を考える
スマホで勤怠管理をする場合、バッテリー切れや不安定な通信環境などによって、従業員が打刻できないケースが発生することも考えられます。外出が多い従業員にはモバイルバッテリーを支給したり、オフラインでも打刻できる代替案を用意したりするなど、緊急時の対策を考えておくことが大事です。
セキュリティ・プライバシー対策が重要である
スマホを使った勤怠管理は、各自の端末から手軽に打刻できるという利便性がある一方で、情報漏えいや不正操作といったリスクも伴います。特に、従業員のGPS情報を取得する場合には、位置情報の不正利用を防ぐための十分なセキュリティ対策が欠かせません。
対策として、あらかじめ運用ルールを明確に設定し、従業員へ周知・同意を得ることが基本です。さらに、指紋認証や顔認証などの本人認証機能を採り入れることで、第三者によるなりすましや不正打刻のリスクを軽減できます。
不正打刻のリスクを知っておく
スマホを活用した勤怠管理システムであっても不正打刻が起きる可能性はゼロではありません。
例えば、位置情報の取得を行わない場合、外出先で出勤を開始したかのように装って、自宅で打刻することも可能です。外出が多い従業員や、在宅で勤務している従業員など、会社での把握が難しい場合は、GPS機能がある勤怠管理システムを利用することで不正打刻を防ぎやすくなります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
スマホで行う勤怠管理システムの選び方
勤怠管理システムにはさまざまな種類があり、搭載されている機能やサポート体制もサービスごとに異なります。特にスマホでの勤怠管理を想定する場合は、操作性や連携機能などを慎重に見極めることが重要です。ここでは、自社に最適な勤怠管理システムを選定する際に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
自社に必要な機能を備えているか
企業規模や働く環境によって、必要な勤怠管理システムの機能は異なります。例えば、多様な雇用形態の従業員が在籍したり、フレックス制や変形労働制を導入したりしている企業では、就業規則に柔軟に対応できるシステムを選び、必要に応じて、時差出勤・フレックス・シフトの設定等、カスタマイズを検討することが重要です。
近年では、残業時間の超過を自動でアラート通知する機能や、シフト管理に対応した機能、有給休暇の自動管理機能など、多機能な勤怠管理システムが登場しています。さらに、外国人従業員の増加を受けて、英語をはじめとする多言語に対応したインターフェースを備えたシステムも増えており、グローバルな職場環境にも対応可能です。
こうした機能を最大限に活用するためには、自社の就業規則や勤務形態(時差出勤・シフト制・フレックス制など)、雇用形態、勤務地の実情に応じて必要な機能を洗い出し、それらを網羅するシステムを選定することが重要です。
充実したサポート体制があるか
サポート体制が充実しているかどうかも重要なポイントです。初期設定時やトラブル時などに相談できる窓口があると、安心して利用できます。また、相談受付は24時間対応しているか、電話・メールなど幅広い連絡手段に対応しているか、運用に関するトレーニングが提供されているかなども確認しておくと、より安心です。
特に、従業員のスマホを使用する場合は、個々の端末によって操作性が異なったり、OSによって仕様が違ったりするケースも考えられます。従業員に正しい使用方法を周知するためにも、サポート体制が整っている勤怠システムを選んでおきましょう。
外部システムとの連携があるか
人事管理システムや給与計算システムなど、他のシステムと連携できるかどうかをあらかじめ確認しておくことも大切です。現在使用している労務管理のシステムと連携できれば、転記ミスや工数の削減につながります。また、勤怠管理と他の労務業務が同一システム内で完結するものであれば、情報を一元管理できるため、さらなる業務効率化が図れます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
正確な勤怠管理にはスマホの活用がおすすめ
正確な勤怠管理を行うためには、従業員が携帯しやすいスマホの活用がおすすめです。スマホの勤怠管理システムなら、外出・出張の多い従業員やテレワークの従業員であっても、手軽かつリアルタイムに打刻を行えます。また、勤怠情報の集計の工数削減や、不正打刻対策や法令遵守につながるなどのメリットもあります。
「弥生給与 Next」では、スマホを使った勤怠管理を始め、給与計算、年末調整、労務管理などを一元管理できます。多様な就業規則や雇用形態などに合った勤怠管理を簡単かつ、正確に行いたい場合は、ぜひご検討ください。
- ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。