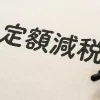定額減税はふるさと納税に影響する?限度額や注意点を解説
監修者: 中川 美佐子(税理士)
更新

2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」で、2024年(令和6年)6月より、所得税と住民税をあわせて1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。
本記事では、定額減税の実施によるふるさと納税への影響について解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
定額減税はふるさと納税に影響なし
2024年度(令和6年度)の税制改正で所得税と住民税の定額減税が実施されることになりました。
結論から述べると、定額減税によるふるさと納税への影響は発生しません。その理由を見ていきましょう。
2023年(令和5年)12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、次の記載が確認できます。
「(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額」
引用文中で述べられている「特別控除」とは、定額減税を指しています。文章の内容をわかりやすく言い換えると、「ふるさと納税の上限額は、定額減税の額を控除する前の所得割額で決まる」となります。そのため、2024年(令和6年)6月に実施される定額減税が、ふるさと納税の上限額に影響を及ぼすことはありません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
定額減税実施後のふるさと納税の上限額
先述のとおり、定額減税の実施によるふるさと納税への影響はありません。ここでは、ふるさと納税のしくみと、ふるさと納税の上限額(控除上限額)の概念について、基本的な内容を解説します。
そもそもふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の生まれ育った地元や応援したい自治体などに、納税を通じて寄附ができる制度です。
地方で生まれた子どもは、その自治体の税収によって営まれる、教育や福祉など各種公共サービスの恩恵を受け成長します。しかしその後進学や就職を機に都会へ移動すると、以後は居住地で税金を納めることになります。
特に日本は東京など都心部に人口が一極集中する傾向にあるため、都会の税収は増える傾向にあり、地方の税収は減少しつつあります。このまま地方自治体の税収が減少していくと、その自治体で運営される各種公共サービスの維持が難しくなってしまいます。そこで少しでも地方に税収を還元するため、任意の自治体に納税できる制度として設けられたのが、ふるさと納税です。
ふるさと納税は地方自治体への寄附金として扱われ、原則として確定申告を行うことで、自己負担分の2,000円を除いた金額が所得税および住民税から控除されます。ただし、控除される金額は無制限ではなく、所得や家族構成などに応じた上限額があります。また、ふるさと納税を行うと、寄附した自治体から寄附額に対して仕入れ値の最大30%の金額に相当する返礼品を受け取ることができます。
ふるさと納税の対象は、1つの自治体のみであっても、複数の自治体を選んで寄附をしても構いません。複数の自治体を選んでふるさと納税を行った場合、それぞれの自治体から返礼品を受け取れます。
なお、ふるさと納税には「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度があります。会社員の方など普段確定申告を行わない人は、ふるさと納税をした自治体に対して「ワンストップ特例」の申請書を送付することでこの特例を適用でき、確定申告が不要となります。ただし本来確定申告が不要な方であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行っている場合は、この特例の適用を受けられません。その場合は確定申告をすることで寄付金控除の適用を受けることができます。
ふるさと納税の詳細な内容については、総務省のふるさと納税のサイトを参照してください。
ふるさと納税の上限額(目安)
ふるさと納税の上限額は、定額減税が実施されても従来と変わりません。先述のとおり、上限額は、定額減税を実施する「前」の所得割額を基に算定するためです。
ふるさと納税を行う本人の給与収入と、ふるさと納税の上限額の目安は以下のようになります。
-
1. 給与収入が300万円の単身者又は共働きの夫婦(※)の場合:28,000円程度
-
2. 給与収入が500万円の単身者又は共働きの夫婦(※)の場合:61,000円程度
-
3. 給与収入が500万円で配偶者と高校生の子どもが1人いる場合:40,000円程度
-
4. 給与収入が1,000万円で、単身者又は共働きの夫婦(※)の場合:180,000円程度
(※)配偶者(特別)控除の適用を受けていない場合
この上限額を超えた金額を、ふるさと納税により寄附することは可能です。ただし、年間上限額を超えた金額については、所得税と住民税の控除の対象とはなりません。
ご自身の家庭の所得状況に基づいた上限金額を把握したい場合は、総務省が公開しているシミュレーション用のExcelなどを利用して算出してください。
参照:総務省「ふるさと納税のしくみ」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
定額減税のよくある質問
定額減税とは何ですか?
定額減税とは、2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年(令和6年)の税金から控除される施策です。
定額減税について、こちらの記事で詳しく解説しています。
定額減税と定率減税はどのように違いますか?
定額減税とは、納税者に対し所得金額(収入から経費を差し引いた金額)の大小に関わらず一定の金額を減税する制度です。定率減税は、納税者の課税所得分に対し一定の割合に基づいて減税する制度です。
定額減税と定率減税の違いについて、こちらの記事で詳しく解説しています。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
定額減税はふるさと納税に影響しない
2024年(令和6年)の定額減税実施後も、ふるさと納税の上限額への影響はありません。控除上限額は所得に基づいて設定されますが、その計算の際もこれまでどおりの方法で対応可能です。
ふるさと納税は従業員個人の判断で行うため会社が直接関与することはありませんが、従業員から質問を受けた際に説明できるとよいでしょう。ただし給与計算業務全体に関しては、定額減税の実施によって計算プロセスや源泉徴収税額などに影響がでる可能性があります。
定額減税にかかわる業務の効率化には、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は定額減税への対応はもちろんのこと、給与計算業務に必要な機能を網羅しているうえ、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信機能もあります。自社にあったサービスを活用して、業務の効率化を目指しましょう。
- ※本記事は2024年4月1日時点の情報を基に執筆しています
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者中川 美佐子(税理士)
税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「たまらん坂税理士法人」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。