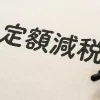【2024】定額減税とは?対象者や減税額をわかりやすく解説(シミュレーションあり)
監修者: 中川 美佐子(税理士)
更新

近年の記録的な物価高を背景に、納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除が2024年(令和6年)6月から実施されています。定額減税は、実施方法や減税額が納税者の働き方や家族構成で変わることもあり、少し複雑な制度です。
本記事では、定額減税の詳細やメリット、対象者などについて、実際のシミュレーションを交えて詳しく解説します。また、定額減税の対象にならない住民税非課税世帯や、住民税均等割のみ課税される世帯の給付措置も紹介します。懸念される給与計算業務の負担増加と対応するためのポイントについても取り上げます。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
定額減税とは?わかりやすく解説
近年、急激な物価の上昇が続いており、日本政府は賃上げの支援や定額減税を含めたさまざまな政策を打ち出しています。どれも物価高に耐え得る所得増加を目指すための重要な施策ですが、なかでも定額減税は直接、個人の可処分所得の増加につながるという理由から注目されています。
定額減税とは、2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に盛り込まれた制度であり、納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されるものです。
配偶者がいる場合でも扶養親族ではなければ、当然のことながら本人も配偶者も両方が納税者として扱われます。ただし、定額減税には所得制限が設けられています。所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超える納税者(給与所得のみの場合は2,000万円を超える人)は減税対象から外れます。
詳しくは後述しますが、定額減税の主な対象者は給与所得者、個人事業主、公的年金等取得者です。
会社員をはじめ、扶養に入っていないパートやアルバイトなどの給与所得者の場合は、所得税(源泉所得税)が2024年6月から、また住民税は6月分を徴収せず、住民税額から1万円の特別控除を引いた残額を11分割し、11分の1ずつを2024年7月から2025年(令和7年)5月までで納付することになっています。
個人事業主やフリーランスなどの事業所得者は、2024年分の確定申告時に、給与所得者と同様の定額減税が適用されます。公的年金等受給者は、2024年6月1日以降、はじめて受け取る公的年金から徴収される源泉所得税額から定額減税額が控除されます。
その一方で、定額減税の対象とならない住民税非課税世帯や、住民税均等割のみ課税される世帯に対しては給付金が支給されます。
参照:国税庁「定額減税特設サイト」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
定額減税の対象者
定額減税の対象者の範囲は所得税と住民税とで異なります。ここでは、それぞれの対象者について解説します。
所得税の減税対象者
所得税の定額減税の対象者は、次に挙げる条件をすべて満たしている人です。
- 2024年分所得税の納税者である
- 日本国内に居住している
- 2024年の合計所得金額が1,805万円以下である(給与収入のみの場合は、2024年の給与収入が2,000万円以下、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2,015万円以下)
住民税の減税対象者
住民税の定額減税の対象者は、次に挙げる条件をすべて満たしている人です。
- 2024年分住民税の納税者である
- 日本国内に居住している
- 2023年(令和5年)の合計所得金額が1,805万円以下である(給与収入のみの場合は2024年の給与収入が2,000万円以下、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けている場合は給与収入が2,015万円以下)
個人住民税均等割のみが課税される納税者は定額減税の対象とはなりません。
参照:内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
定額減税の減税額
定額減税では、納税者本人の家族構成によっても減税額が変わってきます。ここでは所得税、住民税ぞれぞれの減税額について解説します。
所得税の減税額
所得税の減税額は以下のとおりです。
- 納税者本人(日本国内の居住者に限る):30,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも日本国内の居住者に限る):1人につき30,000円
この合計額が世帯当たりの所得税の減税額です。例えば、納税者本人、同一生計配偶者、子ども(扶養親族)1人の3人家族の場合には、所得税から減税される額は90,000円です。
30,000円(納税者本人)+30,000円×2人(同一生計配偶者と扶養親族)=90,000円
住民税の減税額
住民税の減税額は以下のとおりです。
- 納税者本人(日本国内の居住者に限る):10,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも日本国内の居住者に限る):1人につき10,000円
この合計額が世帯当たりの住民税の減税額です。例えば、納税者本人、同一生計配偶者、子ども(扶養親族)1人の3人家族の場合には、住民税から減税される額は30,000円です。
10,000円(納税者本人)+10,000円×2人(同一生計配偶者と扶養親族)=30,000円
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
定額減税の実施方法
定額減税は、給与所得者、個人事業主、公的年金等受給者によって実施方法が異なります。ここでは、アルバイトや副業をしている給与所得者も含めて、どのように定額減税が実施されるのかを解説します。
給与所得者の場合
給与所得者は、所得税は源泉徴収され、住民税は特別徴収されますが、定額減税の実施方法は所得税と住民税とでは異なります。ここでは、それぞれの実施方法について解説します。
所得税
2024年6月1日以降、最初に支払われる給与等(賞与を含む)の源泉徴収から、上述した定額減税額が控除されます。源泉徴収から控除しきれない分は、2024年中に支払われる給与等において、源泉徴収されるべき所得税等の額から順次、控除されます。
住民税(特別徴収)
まず、2024年6月分の住民税は特別徴収されません。本来の年税額から定額減税額を控除した金額を11分割し、2024年7月から2025年5月までの11か月間で特別徴収されることになっています。
個人事業主の場合
個人事業主や不動産所得者は、所得税は確定申告で、また住民税は普通徴収で納めることになっており、定額減税の実施方法が給与所得者とは異なります。ここでは、所得税と住民税とのそれぞれについて解説します。
所得税
2024年分の所得税を確定申告する際に、所得税額から定額減税額が控除されます。また、予定納税の対象者は、2024年7月の第1期分予定納税額において、本人分の定額減税額に相当する金額が控除されます。同一生計配偶者または扶養親族の分は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を経ることで控除することが可能です。
なお、第1期分予定納税額から減税額を控除しきれなかった場合には、当該金額を2024年11月の第2期分予定納税額から順次、控除されます。
住民税(普通徴収)
定額減税前の税額によって算出された2024年6月の第1期分の税額から定額減税額が控除されます。控除しきれなかった場合には、2024年8月の第2期分以降の税額から順次、控除されます。
公的年金等受給者の場合
給与所得者の場合に企業が事務手続きを行うのと同様、公的年金等受給者の定額減税の事務手続きは公的年金等の支払者(共済組合や厚生労働省など)が行うため、給与等の所得がある場合を除いて、公的年金等受給者自身が特別な手続きを行う必要はありません。ここでは、所得税と住民税それぞれについて解説します。
所得税
2024年6月1日以降、はじめて厚生労働大臣等から支払われる公的年金等の源泉徴収から定額減税額が控除されます。源泉徴収から控除しきれない部分は、2024年中に支払われる公的年金等において、源泉徴収されるべき所得税等の額から順次、控除されます。公的年金等に加えて給与等の所得がある場合には、確定申告で精算します。
住民税(特別徴収)
定額減税前の税額によって算出された2024年10月分の税額から定額減税額が控除されます。控除しきれなかった場合には、2024年12月分以降の税額から順次、控除されます。
アルバイトの場合
税法上の扶養親族であるかどうかで定額減税の実施方法は異なります。年間の収入が103万円以下で扶養親族である場合には、扶養している世帯主(納税者)がアルバイトをしている本人の分も含めて所得税の定額減税が行われるため、本人が特別に手続きを行う必要はありません。
年間収入が103万円を超えると税法上の扶養親族に該当しないため、一般の給与所得者と同じ扱いになります。所得税が源泉徴収されていれば、定額減税額が控除されます。アルバイトを複数掛け持ちするなどの理由によって所得税が源泉徴収されていない場合には、確定申告で定額減税額が控除されます。
副業の場合
副業などで複数箇所から支払われる給与や報酬があっても、納税者本人が特別に手続きを行う必要はありません。主たる給与から定額減税額が控除されているためです。ただし、所得税の確定申告は必要となります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
定額減税のシミュレーション例(扶養控除等申書を提出している場合)
会社員などの給与所得者について、定額減税が実施された場合の納税額をシミュレーションしてみましょう。
①毎月の源泉徴収税額が定額減税の金額に比べ十分多いケース
まずは、減税分を期間内に引ききることができる納税額を想定したケースです。単身世帯の会社員で、年収400万円と想定すると、大まかな月給と各種控除額は以下のとおりです。
月給:33万円、社会保険料:72,000円、所得税:9,000円、住民税:18,000円
(1)所得税の3万円
毎月の所得税が9,000円のため、2024年(令和6年)6月から8月の3か月間が0円になります。残りの3,000円については2024(令和6年)年9月分の徴収分から控除されることで、合計3万円が所得税から減額されます。
(2)住民税の1万円
毎月の住民税が18,000円の場合、年額は216,000円です。2024年(令和6年)6月の徴収額は0円になり、年額から1万円を引いた額を11分割し、2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月までの11か月間で均します。計算は(216,000円-10,000円)÷11か月=18,727円/月となります(7月19,000円、8月以降は18,000円)。
これらの計算から、本来の所得税(30,000円)と住民税(10,000円)が控除されます。手取りで考えた場合、2024年(令和6年)6月は27,000円(所得税9,000円、住民税18,000円)増、7・8月は8,300円増、9月は2,700円増、その後は、700円減となります。
②毎月の源泉徴収税額が定額減税の金額に比べ①ほどは多くないケース
次に、所得税の減税分を毎月の源泉徴収額からの減額では控除しきれないケースを2つの事例で解説します。
-
1.年末調整時に6月までの源泉徴収税額の一部を還付する形で定額減税を行うケース
-
2.年末調整による還付によっても、なお定額減税の全額を控除しきれないケース
1. 年末調整時に6月までの源泉徴収税額の一部を精算する形で定額減税を行うケース
扶養家族のいない単身世帯で満額の減税が受けられないと考えられる場合の例として、年収240万円(賞与なし、月額200,000円の固定給与)と想定し、大まかな各種控除額を以下のとおりとします。
月給:200,000円、社会保険料:35,000円、所得税:4,000円、住民税:8,000円
(1)所得税の3万円
このケースでは毎月の所得税が4,000円のため、2024年(令和6年)6月から2024年(令和6年)12月の7か月間を0円としても、4,000円×7か月=28,000円となり、3万円にとどきません。
差額の2,000円は、5月までに源泉徴収された所得税額20,000円(=4,000円×5か月)のうち、2,000円分が年末調整によって精算されます。
(2)住民税の1万円
前提条件の8,000円から年額を算出すると、96,000円です。2024年(令和6年)6月の徴収額は0円になり、年額から1万円を引いた額を11分割し、2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月までの11か月間で均します。
計算は(96,000円-10,000円)÷11か月=7,818円/月となるため、7月に8,000円、8月から5月まで7,800円が毎月差し引かれることとなります。
2. 年末調整による還付によっても、なお定額減税の全額を受け取ることができないケース
本人と扶養親族3人の4人家族の場合を例として、年収は504万円(賞与なし、月額420,000円の固定給与)と想定し、大まかな各種控除額を以下のとおりとします。
月給:420,000円、社会保険料:72,000円、所得税:5,470円、住民税:24,000円
(1)所得税の3万円
給与所得者の所得税の減税は本人と扶養の親族1人につき3万円ずつ行われるため、3万円×4人=12万円の減税となります。このケースでは毎月の所得税は5,470円のため、2024年(令和6年)6月から2024年(令和6年)12月の7か月間を0円としても、5,470円×7か月=38,290円となり、まだ、控除しきれない額があります。
控除しきれない81,710円は、5月までに源泉徴収された所得税額27,350円(=5,470円×5か月)の全額が年末調整によって精算されます。
まだ12万円には54,360円控除しきれません。控除しきれないおおよその金額は、市区町村から給付される予定です。
(2)住民税の1万円
このケースでは毎月の住民税が24,000円で、年額は288,000円です。住民税についても、4人分の減税が適用されるため、減税額は1万円×4人=4万円です。2024年(令和6年)6月の徴収額は0円になり、年額から4万円引いた額を11分割し、2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月までの11か月間で支払います。
計算は(288,000円-40,000円)÷11か月=22,545円/月となります。住民税は、各自治体から通知される納税額が減税後の金額となります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
【定額減税の対象外】住民税非課税世帯・低所得層の給付措置
定額減税は納税額を減額する制度であるため、所得が基準以下で、納税していない世帯は対象とはなりません。その代わり住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯には、給付金が支給されます。それぞれの給付金額について解説します。
住民税非課税世帯
2023年度分の住民税非課税世帯には、1世帯当たり7万円が給付されます。したがって、2023年夏以降に給付された「住民税非課税世帯等価格高騰給付金」3万円と併せて、1世帯当たり計10万円が給付されることになります。さらに同世帯に対しては、18歳以下の児童1人当たり5万円が給付されます。
2024年度分の住民税において、新たに住民税非課税世帯となる場合には、1世帯当たり10万円が給付されます。
同世帯の世帯主には、各市区町村から給付の案内が送付されます。要件や申請期間、手続き方法、給付方法は各市区町村によって異なります。
住民税均等割のみ課税される世帯
2023年度分の住民税均等割のみ課税される世帯には、1世帯当たり10万円が給付されます。さらに同世帯に対しては、18歳以下の児童1人当たり5万円が給付されます。
2024年度分の住民税において、新たに住民税均等割のみ課税される世帯となる場合には、1世帯当たり10万円が給付されます。
同世帯の世帯主には、各市区町村から給付の案内が送付されます。要件や申請期間、手続き方法、給付方法は各市区町村によって異なります。
参照:内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
定額減税の実施で懸念される企業の負担
定額減税は、低所得世帯にも高所得世帯にも該当しない、いわば中間層への恩恵が最も大きいといわれている制度ですが、事務処理を行う企業から見た場合には、給与計算担当者の業務負担増加が懸念されます。
企業に勤務している会社員のほとんどは源泉徴収によって所得税が天引きされていますが、給与計算担当者は従業員一人ひとりの扶養親族の情報などを把握したうえで、減税額を算出しなければなりません。当然のことながら、必要な書類を提出するよう、従業員に告知することは欠かせません。減税額が控除しきれない場合には、何か月にもわたって計算し続ける必要があるうえ、終了時期は従業員によって異なります。
さらに年末調整では、減税額にもとづいて精算を行う年調減税事務も必要です。特に2024年6月2日以降に中途入社した従業員や、同日以降に扶養親族の人数が変更になった従業員の年末調整事務では、減税額に応じた処理を行わなければなりません。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
定額減税における給与計算のポイント
企業は定額減税の実施について、以下のポイントをおさらいしましょう。
-
1.定額減税について従業員への説明を実施する
-
2.従業員が扶養家族などの情報を正確に申請しているか確認する
-
3.所得制限に該当する従業員の確認を行う
-
4.定額減税の事務処理を適切に行えるか、給与計算ソフトやシステムの対応状況を確認する
-
5.定額減税を反映した源泉徴収額の管理方法を検討する
-
6.定額減税開始後の業務効率化について検討する
定額減税における給与計算の対応方法について詳しくは、以下の関連記事で解説しています。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
【Q&A】定額減税に関するよくある質問
定額減税が実施された目的は?
定額減税を含む令和6年度税制改正が施行された背景として、世界的な物価高があげられます。
2020年(令和2年)の生活費を基準とした2023年(令和5年)の「消費者物価指数」では、総合指数が前年比3.2%の上昇、生鮮商品とエネルギーを除いた場合は前年比4.0%もの上昇がありました。
短期間にこれほどの物価上昇が起こると、賃上げによる所得の増加だけでは間に合わず、生活が苦しくなる世帯が増加します。そのため、政府は一時的な手段として、税金の一部還元を決定しました。
定額減税と定率減税はどのように違う?
定額減税とは、納税者の所得金額(収入から経費を差し引いた金額)の多寡にかかわらず、一定の金額を減税する制度です。定率減税は、納税者の課税所得分に対して一定の割合を減税する制度です。定額減税と定率減税の違いについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
定額減税のメリットは?
定額減税による最大のメリットは、低所得世帯から中間所得世帯までへの恩恵が大きいことです。急激な物価高で、多くの低所得世帯から中間所得世帯までが家計を圧迫されています。所得が低い世帯ほど、収入に対する生活費の割合が大きくなるため、一律4万円の減税で得られる効果も大きくなります。
また、減税でもたらされる手取りの増加によって、低所得世帯から中間所得世帯までの消費や購買力の向上も期待されています。
定額減税の対象になるのは本人だけ?
本人に加えて、同一生計配偶者および扶養親族も対象となります。控除対象扶養親族とは異なり、扶養親族には本人と生計を一にしている16歳未満の子どもも含まれます。
定額減税は育休中の人も対象になる?
育休中であっても定額減税の対象です。所得税に関しては、育休中でも従業員であり、扶養控除等申告書を勤務先企業に提出していれば、復職後に支払われる給料等の源泉徴収から定額減税額が控除されます。ただし、2024年中に給料等が支払われることが条件です。住民税に関しては前年の所得額に応じて課税されるため、2023年に所得があれば対象となります。
定額減税を受けるために手続きが必要?
給与所得者や公的年金等受給者の場合には、所得税・住民税ともに特別な手続きは必要ありません。給与所得者は勤務先の企業が、また公的年金等受給者は支払者(共済組合や厚生労働省)が定額減税の手続きを行います。
事業所得者も住民税については手続きが不要ですが、所得税は確定申告を行う必要があります(確定申告で定額減税が受けられます)。予定納税の対象者の場合には、同一生計配偶者や扶養親族の特別減税を受ける場合には「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」が必要です。
定額減税は住宅ローン控除に影響する?
定額減税は住宅ローン控除には影響しません。定額減税は、住宅ローン控除適用後の所得税額に適用されます。したがって、定額減税の有無によって住宅ローンの控除額が左右されることはありません。定額減税と住宅ローン控除について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
定額減税はふるさと納税に影響する?
定額減税はふるさと納税に影響しません。定額減税は、ふるさと納税等の寄附金税額控除適用後の住民税額に適用されます。定額減税の有無により、寄附金税額控除の上限額が左右されることはありません。
定額減税とふるさと納税について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
定額減税が一度で控除しきれない場合はどうなる?
給与所得者は、2024年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます)の源泉徴収から定額減税額が控除されます。控除しきれなかった場合には、翌月の給与等から順次、控除されます。それでも控除しきれなかった場合には、年末調整で控除されます。
個人事業主で予定納税の対象者は、2024年7月の第1期分予定納税額で、本人分の定額減税額に相当する金額が控除されます。控除しきれなかった場合は、当該金額が2024年11月の第2期分予定納税額から順次、控除されます。減税前の税額が少なく、定額減税しきれかった場合には、控除しきれなかったおよその額が、各市区町村から1万円単位で給付されます。
複数の収入源がある場合の定額減税はどうなる?
複数の箇所から給与所得を受け取っている場合や、複数の公的年金を受け取っている場合には、それぞれの源泉徴収税額に対して定額減税が実施されます。最終的には、確定申告で精算します。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
給与計算ソフトで定額減税における給与計算業務の負担を軽減しよう
2024年(令和6年)4月1日に施行された一律4万円の定額減税は、扶養家族の有無などで減税額が異なるため、給与計算業務の負担増加が懸念されます。定額減税対象者の判定や、家族情報の登録内容を基にした定額減税額の算出・管理など、煩雑な業務が発生しているでしょう。
定額減税にかかわる業務の効率化には、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は定額減税への対応はもちろん、給与計算業務に必要な機能を網羅しているうえ、給与明細のWeb配信にも対応しています。給与計算業務の負担を軽減したい場合は、ぜひ導入をご検討ください。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者中川 美佐子(税理士)
税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「たまらん坂税理士法人」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。