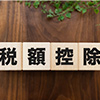配当金の確定申告は不要か必要か?配当控除による還付も解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

株式を保有していると、保有金額に応じた配当金を受け取れることがあります。配当金による収入は、所得税法では配当所得に分類されますが、配当所得については確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。では、どのような場合に確定申告が必要になるのでしょうか。
ここでは、配当金の確定申告が必要なケースや、配当控除と呼ばれる制度によって所得税の還付(払い戻し)を受けられるケースについて解説します。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

株式の配当金は原則として確定申告不要
株式から得られる配当金は、支払われる時点で所得税が源泉徴収されているため、原則として配当金による所得について確定申告をする必要はありません。株式などの取引を行う証券口座には以下の種類があり、口座の種類と株式の譲渡益に関する確定申告の要否には関係がありますが、配当金の確定申告の要否と口座の種類は無関係です。
証券口座の種類
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 一般口座
- NISA口座
株式の譲渡益については、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で譲渡益が発生した場合、金額によっては確定申告が必要になります。しかし、配当金は、取引口座の種類にかかわらず確定申告をする必要はありません。
なお、NISA口座で保有している株式で得た配当金については、そもそも所得税が非課税です。確定申告は不要で、所得税が源泉徴収されることもありません。
配当金の源泉徴収の税率は、上場株式の場合20.315%です。これは、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計です。一方、非上場株式の配当金や、発行済み株式の総数の3%を保有する大口株主の配当金などについては、源泉徴収されるのは所得税のみで、税率が20.42%になります。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
配当金の確定申告をした場合に適用が受けられる配当控除
上場株式の配当金を受け取った場合、基本的に確定申告は不要ですが、確定申告をすることで配当控除と呼ばれる制度の適用を受けられます。配当控除とは、配当金の額を基に一定の計算式で算出した金額を、所得税額から差し引ける制度です。
そもそも配当金には、株式を発行する企業から株主に分配された利益という性質があります。企業の利益には既に法人税などの税金が課せられているため、配当金にも課税してしまうと二重で税金を徴収することになります。これを防ぐために、配当控除という制度が設けられました。
ただし、配当控除の適用を受けられるのは、配当金について総合課税で確定申告した場合のみです。上場株式の配当金について確定申告をする場合は、総合課税と申告分離課税という2つの課税方法から有利な申告方法を選ぶことができます。両者の主な特徴は以下のとおりです。
総合課税と申告分離課税の主な特徴
| 課税方法 | 特徴 |
|---|---|
| 総合課税 | 配当金以外の所得と配当所得を合わせた合計額を基に税額の計算を行う。税率は、所得税については所得金額が高いほど税率が高くなる累進税率で、住民税は10%。配当控除の利用が可能で、株式の譲渡損失との損益通算は不可 |
| 申告分離課税 | 配当所得を、それ以外の所得とは分離して税額を計算する。税率は、所得税が15.315%、住民税が5%。配当控除は利用できず、株式の譲渡損失との損益通算が可能 |
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
配当控除とは?
非上場株式の配当金や大口株主として配当金を受け取る方は、基本的には確定申告をしなければなりません。この場合は、上場株式の配当金を受け取った一般的なケースとは異なり、申告分離課税を選択できないため、総合課税による確定申告が必要です。
ただし、1回に受け取る配当金の額が以下の計算式で計算した金額以下であれば、確定申告は不要です。
確定申告が不要となる金額の基準
10万円×配当計算期間の月数÷12
配当計算期間とは、前回の配当に関する基準日から今回の配当に関する基準日までの期間を指します。1年を超える場合は12か月と見なし、1か月未満の端数は1か月と見なして計算します。
また、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で配当所得を得た給与所得者も、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えていたら確定申告が必要です。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
配当金の確定申告をした方がいいケース
上場株式の配当金については確定申告が不要ですが、中には確定申告をした方がいいケースもあります。以下のケースでは、配当金の確定申告をすることで節税できる可能性があります。
課税所得が695万円以下で配当控除の適用を受ける場合
課税所得が695万円以下の方は、配当金の確定申告をすると節税につながります。課税所得とは、所得税が課税される所得のことです。収入から必要経費や所得控除を差し引いて計算し、給与所得者の場合は必要経費の代わりに給与所得控除を差し引きます。
課税所得が695万円以下の場合の所得税率は20.42%(復興特別所得税を含む)で、住民税の税率は10%です。一方、確定申告をしない場合、上場株式の配当所得に対する税率は所得税が15.315%、住民税が5%で合計20.315%です。
税率だけを比較すると、確定申告をしない方が有利にも思えますが、配当控除の適用を受けることで実質的に負担する税額が逆転し、確定申告をした方が納税額を抑えられます。
配当控除では、課税所得から配当所得を差し引いた金額が1,000万円以下なら、所得税額から「配当所得×10%」、住民税額から「配当所得×2.8%」の金額が控除されます。課税所得から配当所得を差し引いた金額が1,000万円超の場合、控除額の割合は所得税で5%、住民税で1.4%です。
この控除額に、所得税額の2.1%を上乗せする復興特別所得税を加味すれば、課税所得金額が695万円以下の場合の配当所得に対する税率は所得税が「20.42%-10.21%=10.21%」、住民税が「10%-2.8%=7.2%」となります。
両者を合計すると17.41%となり、確定申告をしない場合の源泉徴収税率20.315%を下回るのです。一方、課税所得が695万円を超えた場合、復興特別所得税を加味した所得税率は23.483%に上がります。配当控除を適用しても、所得税率は「23.483%-10.21%=13.273%」で、住民税率7.2%との合計は20.473%となり、20.315%よりも不利になります。
株式の売却損があって損益通算の適用を受けたい場合
株式などの売却で損失が出ている場合も、確定申告をすればその年に受け取った配当金と損失を損益通算できるため、節税につながる可能性があります。損益通算とは、投資などの利益から損失を差し引いて税金の計算ができる制度です。申告分離課税による確定申告をすれば、株式の売却損と配当金を損益通算できます。
例えば、上場株式Aの配当金として1万円を受け取ったとします。配当金を受け取ったのと同じ年に、別途10万円で購入していた上場株式Bを9万円で売却して1万円の損失が出ていた場合、損益通算をすれば配当所得1万円から譲渡損失1万円を差し引くことが可能です。その結果、配当所得は0円となり、配当金から源泉徴収されていた税金の還付を受けられます。
なお「源泉徴収あり」「配当受け入れあり」の特定口座で取引を行っていることなどの条件を満たした場合は、自動的にその口座内での譲渡損失と配当金の利益が損益通算されますので確定申告の必要はありません。
一方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で株式の譲渡損失と配当金収入が発生している方や、譲渡損失があった証券口座と配当金収入があった証券口座が別の方などは、損益通算のためには確定申告が必要です。
また、総合課税で確定申告をすると、損益通算はできないため注意してください。
株式の売却損があって繰越控除の適用を受けたい場合
損益通算で控除しきれない売却損が生じた場合、損失の繰越控除と呼ばれる制度で損失を3年間繰り越せますが、その適用のためにも確定申告が必要です。損失の繰越控除の適用を受けると、翌年以降に配当金や株式の譲渡益を得た場合に、利益から損失を差し引くことができます。
損失の繰越控除の適用要件には、確定申告をすることが含まれています。株式の譲渡に関する申告となるため、申告分離課税で確定申告をしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
配当金の確定申告をする場合の注意点
配当金の確定申告をする際は、必要経費の考え方について注意が必要です。所得金額は、収入から必要経費を引いて算出します。配当所得も同様ですが、このときに経費として認められるのは、借入金の利子のみです。
株式の購入にかかった費用などは配当所得の必要経費にはなりません。購入費用は株式を譲渡したときに控除することができるので、配当収入からは控除できないのです。
なお、借入金の利子とは、配当金が発生した株式を取得するために借りた金銭に対する利子を指します。株式購入以外の目的で借りた金銭にかかる利子については対象外です。株式取得時に金銭を借りていない場合、配当所得から差し引ける必要経費はありません。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
配当控除などで所得税の還付が受けられそうなら、確定申告をしよう
上場株式の配当金は、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、配当控除などの制度を利用することで、税金の還付を受けられる可能性があります。状況に応じて、節税につながるようであれば確定申告を検討しましょう。
配当所得のほかに事業所得や不動産所得がある方が確定申告をする場合は「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」が便利です。帳簿類や決算書の作成から、配当控除を含む確定申告書の作成、申告まで一貫して対応しています。ぜひご活用ください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
よくあるご質問
配当金は確定申告した方がいいですか?
上場株式得られる配当金は、支払われる時点で所得税が源泉徴収されているため、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、配当控除などの制度を利用することで、税金の還付を受けられる可能性があります。また、非上場株式の配当金や大口株主として配当金を受け取る場合は、確定申告が必要になります。
配当控除とは何ですか?
配当控除とは、上場株式の配当金について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除の1つです。課税所得が695万円以下の場合、配当金の確定申告をすると節税につながる可能性があります。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。